| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
209.1 はじめに
研究の目的
用語の定義
209.2 概要
都市化昇温量と自然昇温量
猛暑日・熱帯夜の経年変化
209.3 猛暑日・熱帯夜と自然昇温率・都市化昇温率の関係
日最高・最低気温の上昇率
猛暑日・熱帯夜の増加
209.4 猛暑日・熱帯夜の発生確率
猛暑日・熱帯夜の発生確率
発生確率の最大値(予測)
まとめ
文献
付録
付録1 43地点における各要素の一覧表
付録2 昇温率の8月と2月の比較
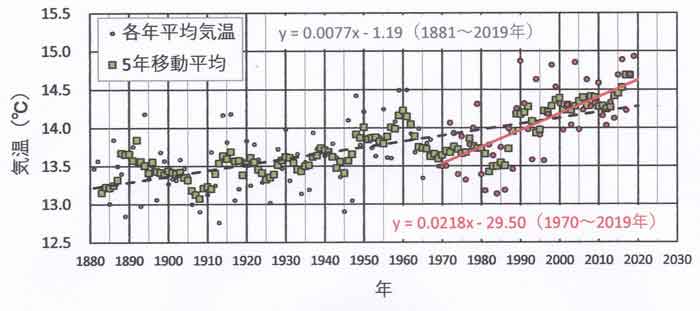


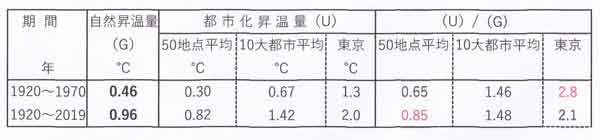
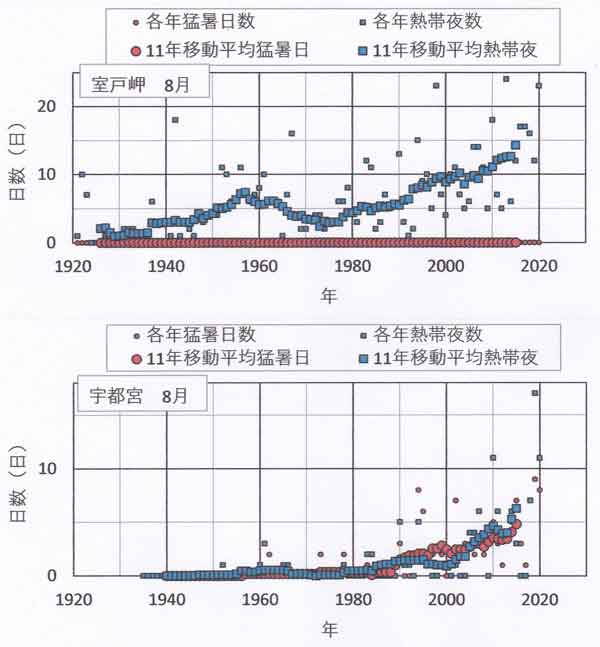
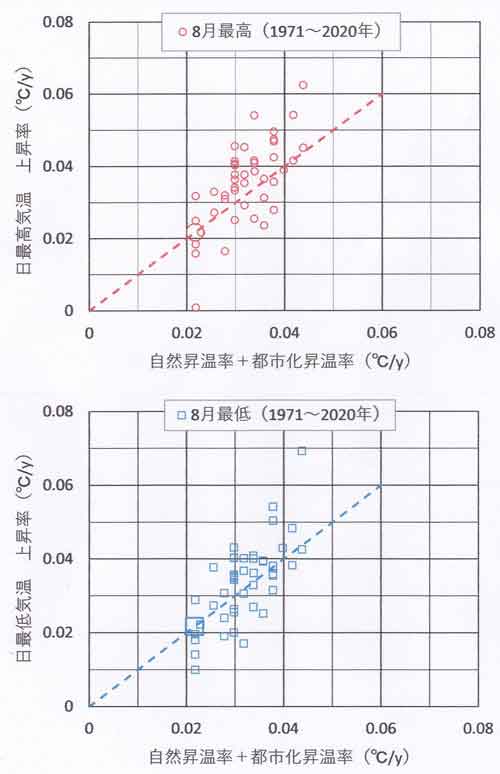
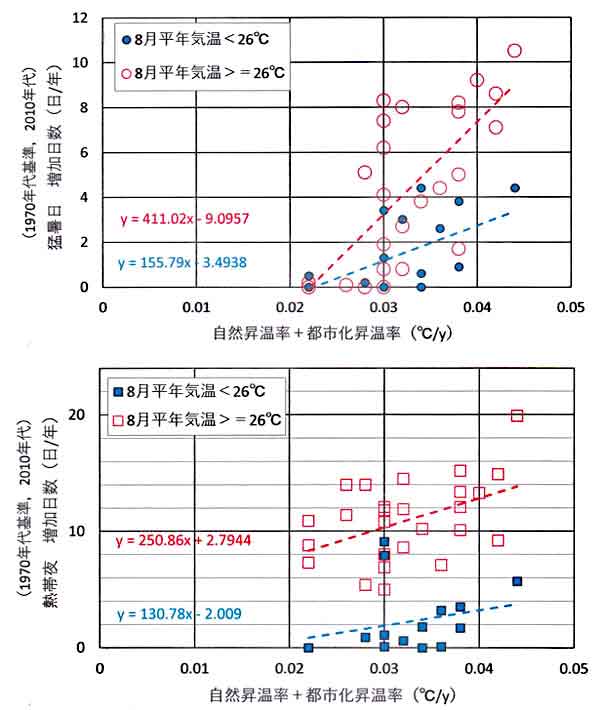
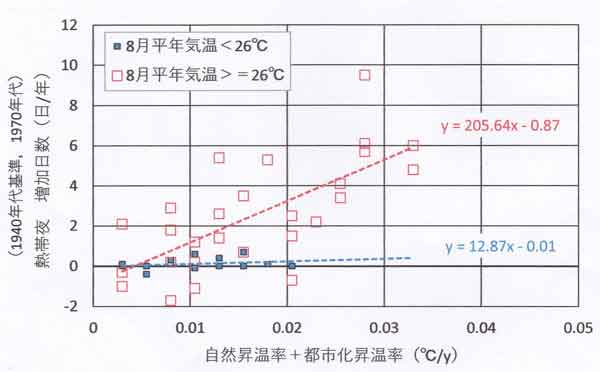
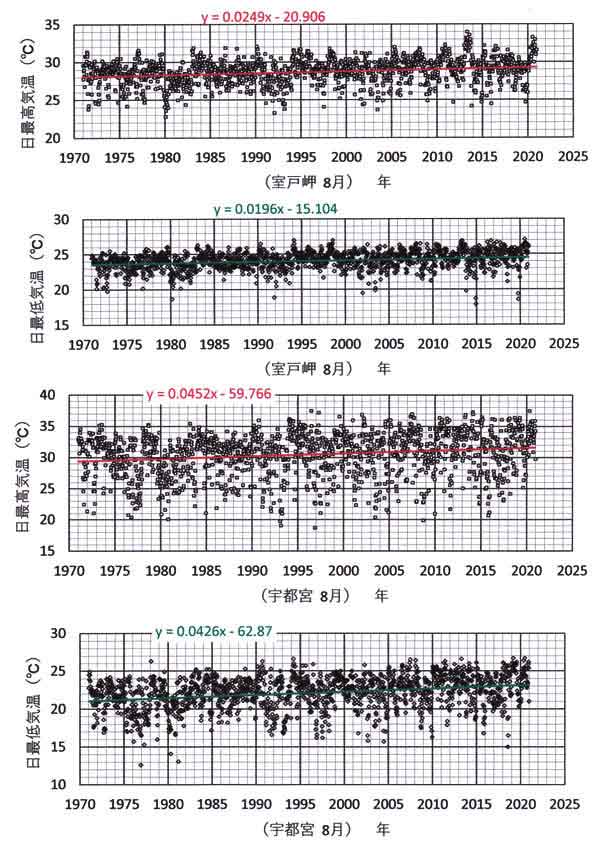
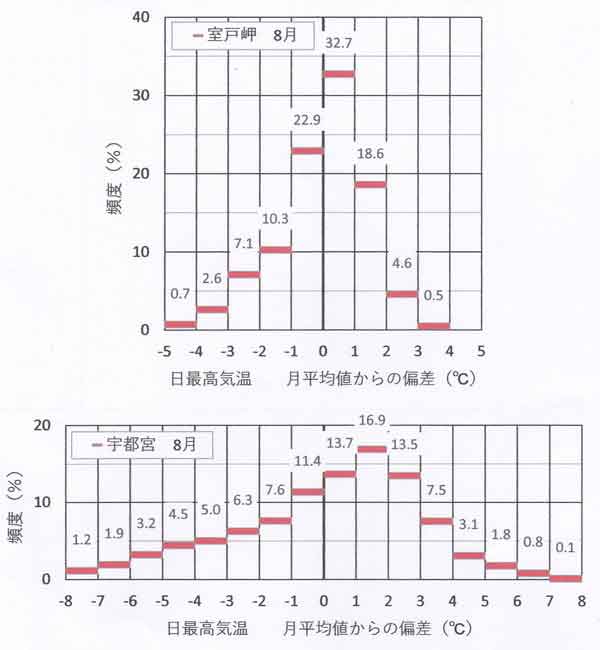
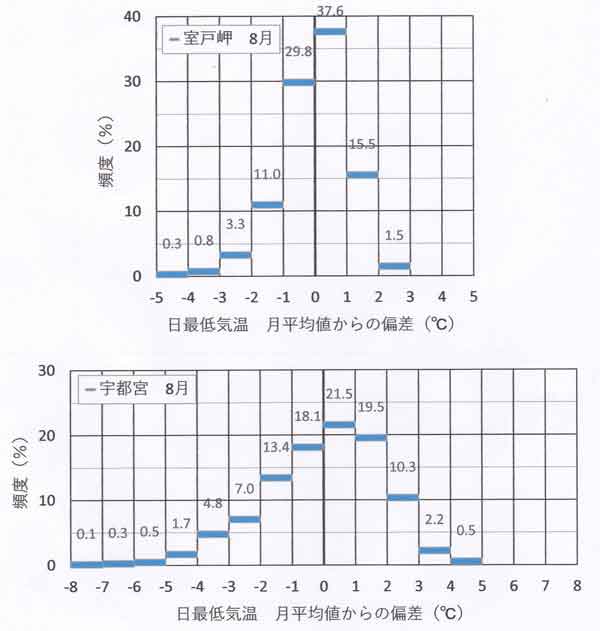
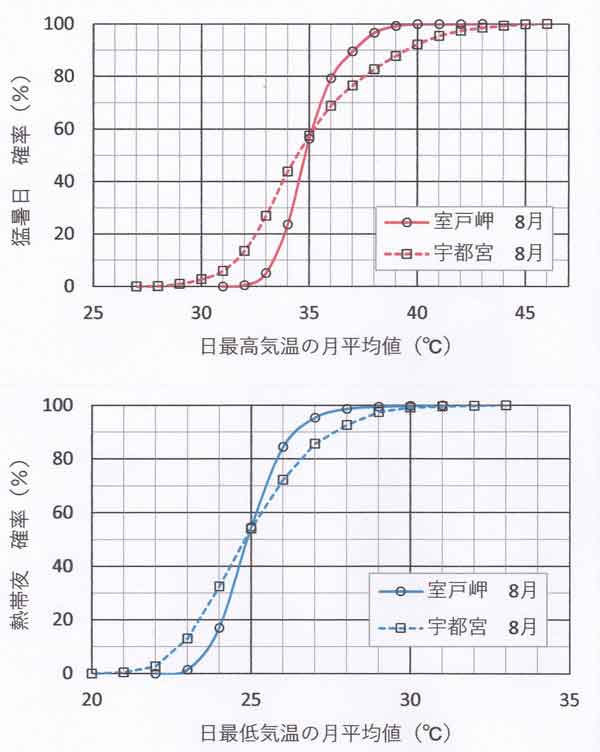
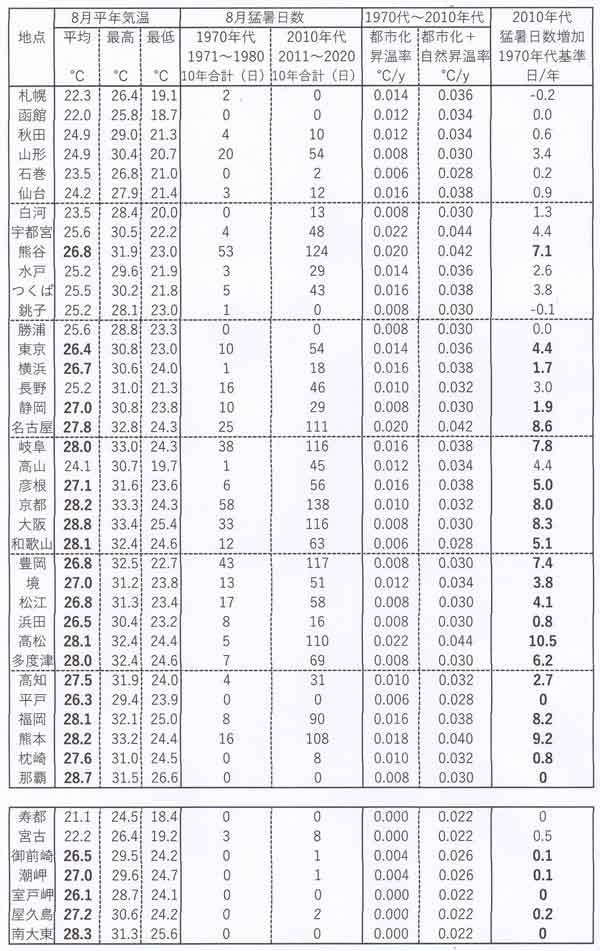
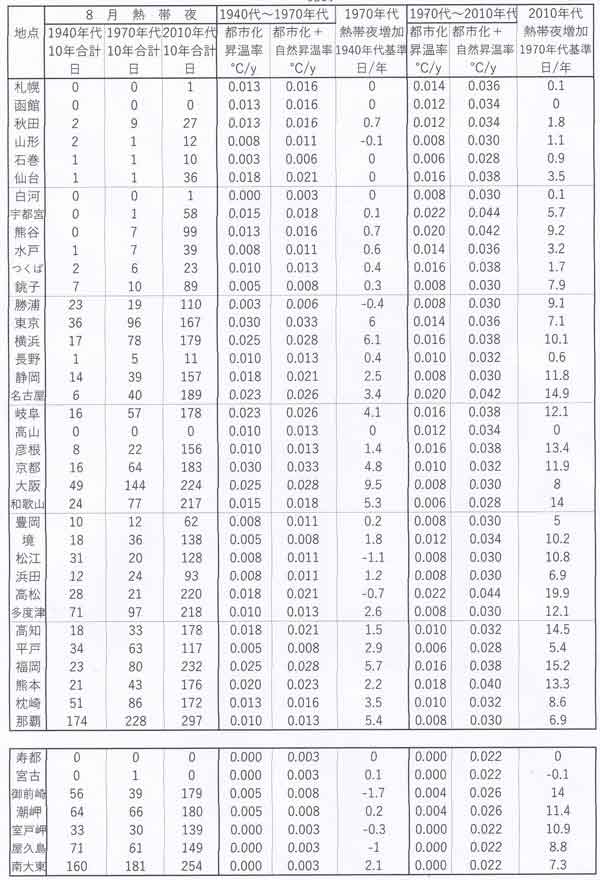
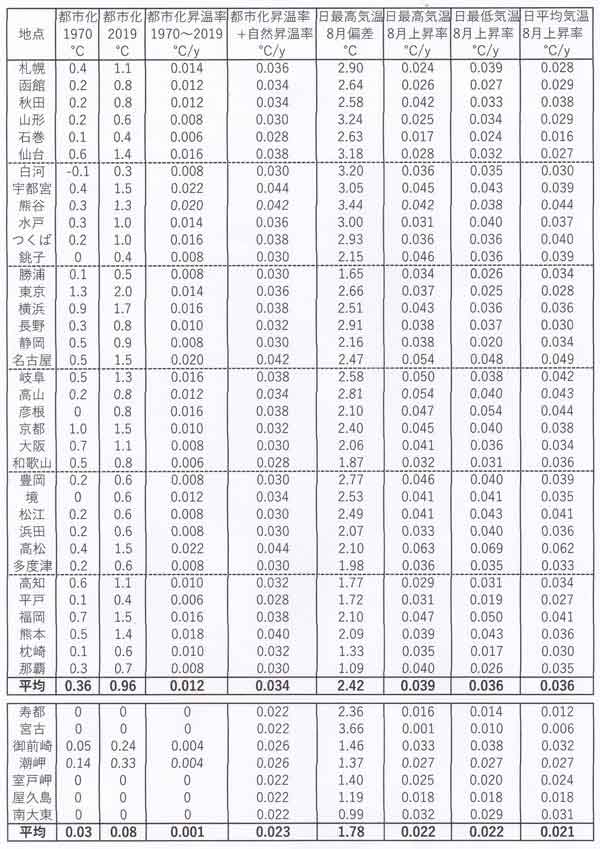
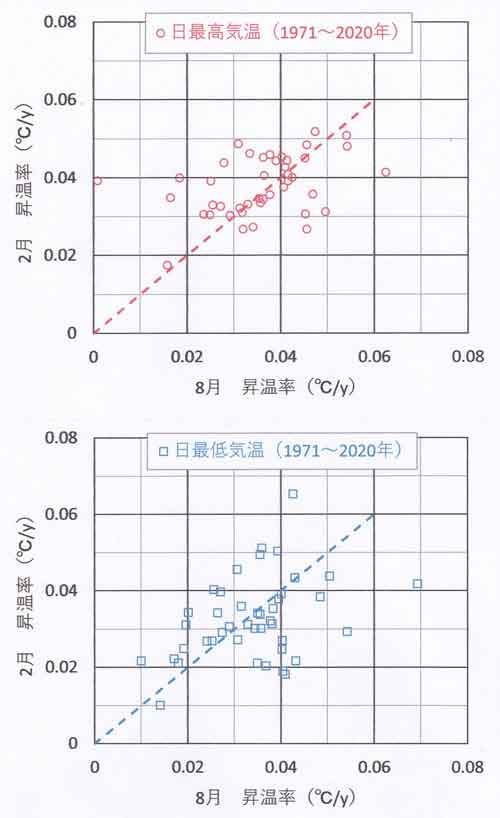
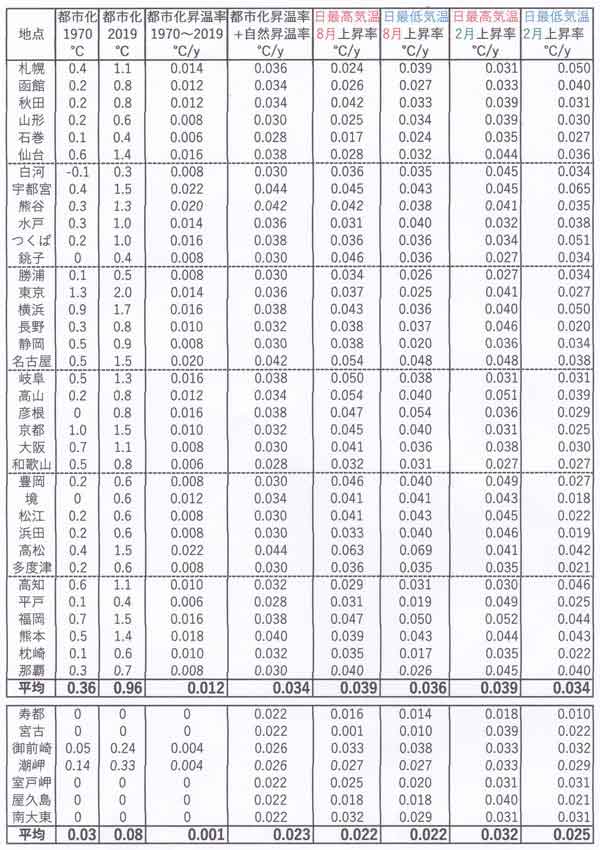
| トップページへ | 研究指針の目次 |