河内守秀宗の子。平氏出身の父は、藤原秀忠(魚名末流、秀郷の裔)の跡を継いで藤原氏を名乗ったという(尊卑分脈)。母は伊賀守源光基女。承久の乱の際大将軍となった秀康の弟。子には左兵衛尉秀範(承久の乱で戦死)、左衛門尉能茂(猶子。後鳥羽院の寵童)ほかがいる。
初め源通親に伺候し、十六歳の時後鳥羽院の北面の武士に召された。左兵衛尉・左衛門尉・河内守などを経て、検非違使大夫尉・出羽守に至る。建暦二年(1212)五月、西海の宝剣探索のため院宣御使として筑紫に下る。承久三年(1221)、承久の乱の際には官軍の大将となったが、敗れて熊野で出家、如願を号した。その後高野に真照法師を訪ねるなどしている。貞永元年(1232)秋、隠岐の院を慕って西国に下る(『如願法師集』)。嘉禎二年(1236)には院主催の遠島歌合に召されて歌を献上した。仁治元年(1240)五月二十一日、没。五十七歳。
歌人としても後鳥羽院の殊遇を受け、建仁元年(1201)の「八月十五夜撰歌合」「和歌所影供歌合」などに出詠。同年七月に設置された和歌所寄人に加えられる。この時十八歳、寄人中最年少であった。同二年(1202)五月の「仙洞影供歌合」、同三年(1203)の「影供歌合」「八幡若宮撰歌合」、元久元年(1204)の「春日社歌合」「元久詩歌合」、建永元年(1206)七月の「卿相侍臣歌合」、同二年の「賀茂別雷社歌合」「最勝四天王院和歌」、建保三年(1215)の「院四十五番歌合」、建保四年の院百首和歌など、後鳥羽院歌壇で活躍した。また建仁元年(1201)の「通親亭影供歌合」、建保五年(1217)の「右大将(源通光)家歌合」、承久二年(1220)の「道助法親王五十首」などにも出詠している。承久の乱後もたびたび小歌会に出て歌を詠んだり、百首歌を創作したりしている。飛鳥井雅経・家隆と親交があった。新古今集初出。以下勅撰集に七十九首入集。家集『如願法師集』は後世の編集とされる。新三十六歌仙。後鳥羽院の『時代不同歌合』にも撰入。
*
「秀能は身の程よりもたけありて、さまでなき歌も殊の外にいではへするやうにありき。まことによみもちたる歌どもの中にはさしのびたる物どもありき。しかあるを近年定家無下の歌のよし申すときこゆ」(後鳥羽院御口伝)。
「風体すみたるをさきとして、ふかくおもひ入りたるさまなり。地下(ぢげ)のともがらの中には昔も類なくや」(続歌仙落書)。
「近き頃は、西行法師ぞ北面の者にて、世にいみじき歌の聖なめりしが、今の代の秀能は、ほとほと古きにも立ちまさりてや侍らん」(増鏡)。
春 3首 夏 3首 秋 6首 冬 3首 恋 5首 雑 10首 計30首
春
詩をつくらせて歌にあはせ侍りしに、水郷春望といふことを
【通釈】月の出ている夕暮、難波江には潮が満ちてくるらしい。葦の若葉を越えて寄せる白波よ。
【補記】元久二年(1205)六月、漢詩と和歌を合せるという野心的な試み『元久詩歌合』、作者二十二歳の出詠歌。新古今集竟宴後の催しであったが、秀作多く、ここから新古今集に八首増補撰入されることになる。なかでも当詠は後鳥羽院「見わたせば山もとかすむ」と共に名歌中の名歌。水深の浅い難波潟に、夕月がのぼると共に潮が満ちてくる。月光にほのぼのと照らし出される蘆の葉の緑は、萌え出たばかりで丈低く、ひたひたと潮が寄せれば白い波頭に侵され水面下に没してゆく。のどかな春の夕べ、干潟を大景から小景にフォーカスして、かくも官能的にひそやかな一瞬の景趣を捉えた。
【他出】元久詩歌合、続歌仙落書、定家十体(麗様)、自讃歌、如願法師集、新三十六人撰
【参考歌】藤原範永「後拾遺集」
花ならで折らまほしきは難波江の蘆の若葉にふれる白雪
源経信「後拾遺集」
沖つ風吹きにけらしな住吉の松のしづ枝をあらふ白波
源経信「金葉集」
五月雨に玉江の水やまさるらむ蘆の下葉のかくれゆくかな
【主な派生歌】
五月雨に池の汀やまさるらむ蓮の浮葉をこゆる白波(後鳥羽院[遠島百首])
浦とほく塩みちくらしたちならぶ松の梢にかかる白波(藤原経顕[宝治百首])
夕されば塩みちくらし芦の屋の深江のはしにかかる白波(飛鳥井雅有)
春日詠百首応製和歌 春
来ぬ人をあすも待つべきさむしろに桜吹きしく夜はの山風(如願法師集)
【通釈】来なかった人を明日も待つであろう莚の上に、桜の花を吹いては敷く、夜の山風よ。
【語釈】◇さむしろ さ筵。「さ」は接頭語で特に意味は無く、粗末な敷物を言う。「さむ」に「寒」の意を響かせることが多い。
【補記】建保四年(1216)、後鳥羽院主催の百首和歌。桜の木の下に座を設け、一日待ち暮らした人は来なかった。明日こそは…と待つ夜、山から吹く風が、無情にも筵(むしろ)の上に花びらを散り敷く。初句「来ぬ人を」にはおのずと恋の風趣が薫り、次句「あすも待つべき」の実直さが微笑ましい。
花
身にかへて思ふもくるし桜花咲かぬ深山に宿もとめてむ(新拾遺123)
【通釈】我が身に代えてまで花を惜しいと思うのも辛い。いっそ、桜の咲かない深山に庵を尋ね探ろう。
【補記】嘉禎二年(1236)、配所にあった後鳥羽院が催した遠島歌合に奉った歌。初句は藤原長能「身にかへてあやなく花を惜しむかな生けらばのちの春もこそあれ」(拾遺集)などを踏まえ、我が身に代えてまで落花を惜しむことを言う。そんな思いをするのは苦しい、いっそ桜の咲かぬ深山に庵を求めてしまえ、との心である。二句切れに真情発露、院への思いを読み取るのは穿ちすぎだろうか。
【他出】遠島歌合、時代不同歌合(再撰本)、如願法師集、題林愚抄
夏
題しらず
暮れかかる篠屋の軒の雨の
【通釈】日が傾いて暗くなった篠屋の軒先に雨が降る中、濡れながら声をかけるほととぎすであるよ。
【語釈】◇篠屋 笹で葺いた粗末な住まい。
【補記】出家後の百首和歌。夕暮れて来た頃降り出した雨が、庵の軒からしたたり落ちる。その雫に濡れて、時鳥が訪ねて来た、という。「こととふ」には言葉を掛ける意もあり、鳥であれば鳴くということだが、「鳴き来る」とか「おとづるる」とか言うより、親密な感じを与える。あるいは訪れたのは声だけだったかもしれず、鳴き声が「ぬれて」いたと聞くのも一興だ。いずれにせよこの「ぬれて」には、侘び住まいする出家者に同情する涙が暗示されていよう。なだらかに詠み下した調べのうちに、孤独な暮らしの友である鳥への愛情がおのずと滲み出てくる。
春日詠百首応製和歌 夏
水な月のなかばに消えし白雪のいつしか白き富士の山風(如願法師集)
【通釈】水無月の半ばに消えた雪が、いつのまにかまた降りだして、富士の山を吹く風は白い。
【補記】「水(み)な月のなかば」は陰暦六月中旬、夏の暑い盛りである。富士山の雪がその頃消えるとは、下記本歌を踏まえて言うが、『駿河国風土記』逸文にも同様の伝説が記載されている。富士の雪は、消えたその晩のうちにまた降り出し、山風を白く染めるのだ。建保四年院百首。
【本歌】高橋虫麻呂「万葉集」巻三
不尽の嶺に降り置く雪は六月の十五日(もち)に消ぬればその夜降りけり
なごしのはらへ
夕されば麻の葉ながるみ吉野のたぎつ
【通釈】夕方になったので、麻の葉が流れている――吉野の急流の川内で禊ぎをしているらしいよ。
【補記】本歌は万葉集の人麻呂歌。下句は万葉調を写し、新古今時代(特に後期)における万葉復興の気運を窺わせる作である。題詞「なごしのはらへ」は六月祓(みなづきばらえ)のことで、夏の終わりの六月晦日、白木綿をかけた麻の葉を川に流した。吉野川と御秡の取り合わせは珍しい趣向。奔流が白木綿を巻き込みつつ波しぶきを上げ、人々の罪穢れをすばやく流し去る。優美なうちに力感こもる作。建保四年院百首。玉葉集夏巻末。
【本歌】柿本人麻呂「万葉集」
山川も依りて仕ふる神ながらたぎつ河内に船出せすかも
秋
詠百首和歌 秋
うたた寝のうすき袂に秋たちて心の色ぞまづかはりける(如願法師集)
【通釈】うたた寝をしていた薄い袂に秋がはっきりと現れて、真っ先に私の心の色が変わったのだった。
【補記】転た寝からふと目覚めると、夏衣の薄い袂に風が涼しい。万物の色変る秋と知るが、真っ先に変ったのは我が心の色であった。この「いろ」はまず、ほのかな徴候、おもむき、ほどの意であるが、当然色彩の意も含み込み、来るべき樹々の紅葉を匂わせている。「たち」が袂の縁語であることも見逃せないし、ウ音とタ音が連鎖する上句のたゆたうような調べも聞き逃したくない。出家後の百首歌。
【参考歌】式子内親王「新古今集」
うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇の秋の初風
最勝四天王院の障子に、たかさごかきたる所
吹く風の色こそ見えね高砂の尾上の松に秋は来にけり(新古290)
【通釈】風の色は目に見えないけれども、高砂の尾上の松を響かせる音によって、秋の訪れを知った。
【補記】承元元年(1207)、後鳥羽院の勅願寺である最勝四天王院の障子絵に添えた名所和歌。「高砂」は播磨国の歌枕、今の兵庫県高砂市。王朝人はこの名から海辺の小高い丘に老松の生える景を思い描いた。日本の詩情の原風景の一つであり、「高砂の尾上の松」と言うだけで、古人には心の琴線に触れるものがあったのである。その松の梢を鳴らす風の響きによって秋の到来を知った、という一見変哲もない歌だが、「色こそ見えね」は、常緑の松を詠む故にこそ生きて来る句である。晴の歌に相応しい正調の秀詠。後鳥羽院のおぼえめでたく、『時代不同歌合』改撰本に撰入された。
【他出】最勝四天王院和歌、時代不同歌合(再撰本)、如願法師集、歌枕名寄
【本歌】凡河内躬恒「新古今集」
千とせふる尾上の松は秋風のこゑこそかはれ色はかはらず
藤原敏行「古今集」
秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる
【主な派生歌】
吹く風の目にこそ見えね神々は此の天地にかむづまります(*橘曙覧)
春日詠百首応製和歌 秋
葦の葉に風秋なりと聞きしより月すさまじくすむ心かな(如願法師集)
【通釈】葦の葉のそよぐ音に、風が秋になったと聴いた――その時から、月の光は荒涼と冴えわたり、我が心も冷たく澄んでいる。
【補記】季節の移ろいに過敏なまでに反応する多感な資質を窺わせる。印象的な第四句「月すさまじく」は、作者の心のうちに照る月のさまである。建保四年院百首。
山月といふことをよみ侍りける
あしびきの山ぢの苔の露のうへに寝ざめ夜ぶかき月を見るかな(新古398)
【通釈】山中の苔に置いた露の上で、目が醒め、夜深い月を見たことよ。
【語釈】◇山ぢ 山中を漠然と指す。「山路」ではない。
【補記】家集によれば、建仁元年(1201)頃、後鳥羽院より召された歌らしい。「山ぢの苔」は高山の地面を覆う地衣類・羊歯(しだ)類を言うのであろう。それを筵代わりに旅寝するうち、ふと背に冷たさを感じ、目が覚める。と、羊歯の寝床にはいちめん露が置いていたのだ。山中の張りつめた夜の霊気、月光にきらめく露、漆黒の闇を照らす上空の月…。この上なく辛いはずの旅中の寝覚が、月によって祝福されたかのような僥倖の一瞬である。「ねざめ夜ぶかき」は、古注にあるように「粉骨」の句であろう。
【他出】自讃歌、続歌仙落書、如願法師集、新三十六人撰
【主な派生歌】
月のもるね屋の板まに露みえて寝覚夜ぶかき蓬生の宿(花山院長親)
散り初むる桐の一葉の露の上にねざめ夜深き月を見るかな(蓮月)
船中月
涙のみうきつの波のなみまくら月にひたせる袖ぞかなしき(道助法親王家五十首)
【通釈】涙ばかりが浮かぶ、浮津の波に揺られる波枕――月の光に浸している袖が切ない。
【補記】承久二年(1220)、道助法親王家で催された五十首歌。「うきつ」は「浮き」「浮津」の掛詞。浮津は万葉集巻八の歌「天の河浮津の浪音さわくなり吾が待つ君し舟出すらしも」に由り、天空に浮かぶ港と考えられたものである。船中で波に揺られつつ寝泊まりする漂泊感を「うきつの波のなみまくら」と言っている。この歌も第四句が目の付け所で、涙に濡れた袖が月の光を映しているのを「月にひたせる袖」と瀟洒に言いあらわした。「ひたせる」は言うまでもなく波の縁語である。
熊野御幸の時、秋の歌めし侍りしに
下紅葉うつろひゆけば玉ぼこの道の山風さむく吹くらむ(如願法師集)
【通釈】下葉の紅葉が散ってゆくので、山道を寒風が吹いているのだろう。
【補記】後鳥羽院の熊野御幸に供奉した時の作。「下もみぢ」は樹の低いところの紅葉で、いちはやく「うつろひ」ゆく――色を変え、落葉する――と考えられた。すなわち下葉は山道に散り敷き、梢にはまだ紅葉が残っている。そうした情景を想い浮かべた上で、道を吹き渡る風の寒さに冬の足音を聞いているのだ。枕詞「玉ぼこの」は、道とはそもそも神の通り道であると考えた古人の思想を留め、一首に重みを与えている。
【本歌】紀貫之「新古今集」
玉桙の道の山風さむからばかたみがてらにきなむとぞ思ふ
冬
嘉禄元年神無月のころ述懐歌よみ侍りし時、遠山時雨を
ひさかたの雲井ながらも逢ひ見しをしぐれにけりな天の香久山(如願法師集)
【通釈】遥かに雲を隔てながらも対面したが、また時雨れてきて隠れてしまったなあ、天の香具山よ。
【補記】嘉禄元年(1225)は出家後四年目。家集には「嘉禄元年十月前宰相中将信成連歌の次に歌よみ侍りし時、閑居時雨を」の詞書で「山ふかくなほいとへとて衣手のぬるるがうへにふる時雨かな」の歌があり、同じ時の作ではないかと思われる。冬の題詠であるが、述懐歌とことわっている点が注意される。歌会の主宰者信成も後鳥羽院の近臣だった人で、院への思いを籠めた「述懐」であることは確かなように思われる。この年春頃、都では後鳥羽院環京の巷説が流れたが、まもなく事実無根であることが明らかになった。
詠百首和歌 冬
山里の桐の落葉にすむ月のかげさだめなく吹く嵐かな(如願法師集)
【通釈】山里の桐の落葉に澄んだ光を宿す月――その光が不安定に揺れるほど吹く嵐であるよ。
【補記】出家後の百首歌。庵を結ぶ山里の初冬の景である。桐の落葉に冬の澄んだ月が宿っているが、嵐はげしく、その光は不安定に揺れている。桐は「桐一葉」などとも言うように、大きな葉が一枚ずつふわりふわりと落ちるさまが印象的。唐土では瑞木とされ、秀れた帝王が世に現れると、瑞鳥の鳳凰が出現して桐の樹に棲みつくと信じられた。わが国でもめでたい樹とされたことは、菊とともに皇室の紋章や神紋に用いられたことによって窺われる。単なる叙景歌でなく、承久の乱後の世相不安を暗喩した歌であろう。
最勝四天王院の障子に、なるみの浦かきたる所
風吹けばよそになるみのかた思ひおもはぬ波になく千鳥かな(新古649)
【通釈】風が吹くので、鳴海潟から遠く離されてしまう千鳥は、連れを片思いして、思いもしなかった沖の波に啼いている。
【語釈】◇なるみのかた 鳴海の潟。尾張国の歌枕。今の名古屋市緑区あたりにあった入江。(よそに)成る身、と掛けている。
【補記】承元元年(1207)の障子和歌。風に吹き流され、棲み処である鳴海潟から遠く離れてしまった千鳥。つがいを「片思ひ」(片・潟の掛詞)しながら、思いもしなかった沖の波に濡れて鳴いている。言語遊戯がおのずと流麗なしらべをなし、名所の風景に恋の情趣が匂いを添える。『定家十体』には幽玄様の例歌として挙げる。
【主な派生歌】
立ち返り幾たび袖をぬらすらむよそになるみの沖つ白浪(藤原雅朝[続千載])
今は又よそになるみのかたし貝我ぞしをるるあふよしをなみ(花山院長親)
【他出】最勝四天王院和歌、自讃歌、定家十体(幽玄様)、如願法師集、歌枕名寄、三五記、桐火桶
恋
夕恋といふことをよみ侍りける
藻塩やく海人の磯屋の夕煙たつ名もくるし思ひ絶えなで(新古1116)
【通釈】藻塩を焼く海人の磯辺の小屋から夕方の煙が立ちのぼる――そのように立つ我が恋の噂も辛い。思いの火が絶えることはなくて。
【補記】「藻塩(もしほ)やく」とは、藻に海水を浴びせてはそれを焼き、塩を製造した海人のなりわいで、きわめて辛い労働であったろうが、王朝歌人は風趣ある情景として眺め、またその煙を恋の「思ひ」の「火」になぞらえて歌に詠んだ。夕暮の浜辺の海人の孤影、その傍らから立つ煙。我が身にはじりじりと愛欲の炎が燻ぶり、苦しみは絶えないが、このうえ浮名が立つことも苦悩の種だ。家集の詞書によれば、建仁元年(1201)八月二十五日の北面歌合での作。歌壇登場まもなくで、作者は時に十八歳、すでに王朝和歌の技巧を自家薬籠中のものとしていた。
【他出】自讃歌、定家十体(幽玄様)、定家八代抄、続歌仙落書、時代不同歌合(初撰本・再撰本)、如願法師集、新三十六人撰、題林愚抄
(第五句を「おもひきえなで」として収録する本も少なくない。また、第二句「あまのとまやの」、第四句「たつ名もつらし」とする本もある。)
【参考歌】藤原家隆「殷富門院大輔百首」(文治三年)
藻塩やく海人の磯屋のたぐひかは波にぬれても胸こがすらむ
宇治にて、夜恋といふことを、をのこどもつかうまつりしに
袖のうへに誰ゆゑ月は宿るぞとよそになしても人のとへかし(新古1139)
【通釈】私の袖の上に、月の光が宿っている――それは誰のために流した涙なのかと、他人事のようなふりをしてでも、あの人が聞いてほしい。
【補記】「袖の上に…月は宿る」とは、袖の涙に月の光が反映することを言う。その涙は「誰ゆゑ」のものかと、「よそになしても」――自身に関係のないこととしてでもよいから、せめて訊いてほしい、との訴えである。女の立場で、つれない恋人への恨みを婉曲な上にも婉曲に詠んでいる。
【他出】自讃歌、定家十体(幽玄様)、定家八代抄、続歌仙落書、如願法師集、新三十六人撰、三五記、桐火桶、題林愚抄
和歌所歌合に、深山恋といふことを
思ひ入るふかき心のたよりまで見しはそれともなき山路かな(新古1317)
【通釈】思い込んだ私の深い恋心を譬える手立てにもなろうかと思って眺めた深山であったが、実際分け入ってみれば、それ程でもない(私の心の深さには及ばない)山路であったよ。
【補記】家集には「建永元年七月廿五日当座御歌合に、深山恋を」。作者二十三歳の作。「心のたよりまで見しは」との言い方がやや解りにくいが、「わが思ひ入りたる、深き心のほどは、たとふべき物もなきを、此み山の深きことは、我心の程をたとふべきたよりと迄、かねてみしはといふ意にて」とする本居宣長の解説(『新古今集美濃の家づと』)でじゅうぶん納得できる。実際その山に分け入ってみたら、我が心の深さには及ばず、それ程でもなかった、ということで、山よりも深い恋の思いを強調する歌になっている。古注では「無上至極の哥なるべし」とまで高く評価されていた。
【他出】自讃歌、定家十体(幽玄様)、如願法師集、三五記、東野州聞書、心敬私語、題林愚抄
【参考歌】源重之「重之集」「新古今集」
つくば山は山しげ山しげけれど思ひ入るにはさはらざりけり
題しらず
今来むとたのめしことを忘れずはこの夕暮の月や待つらむ(新古1203)
【通釈】「すぐ行こう」との約束をあの人が忘れずにいるなら、今日の夕暮の月の出を待ち遠しく思っていることだろう。
【補記】待たされる女の立場で詠んだ素性法師の名高い本歌を、待たせる男の立場で読み換えた。しかも本歌の「有明の月」は「夕暮の月」に改めている。家集によれば後鳥羽院から召された歌で、秀能の発想の冴えはさぞ嘆賞を得たことだろう。もっとも詠みぶりは素直で、思いやりがこもる。女を裏切りそうにはない男の歌だ。
【本歌】素性法師「古今集」
今こむと言ひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな
【他出】自讃歌、定家十体(幽玄様)、如願法師集
題しらず
人ぞ憂きたのめぬ月はめぐりきて昔わすれぬ
【通釈】あの人ったら無情だ。あの時、約束した月の晩に訪れてくれなかった。もはや期待もしていない月は、それでも時が経てば巡って来て、忘れたい昔を思い出させる、蓬生の宿だことよ。
【補記】家集の詞書によれば、飛鳥井雅経が少将であった頃、歌会で詠み合った歌の一つ。秀能は十代後半から二十代前半である。「よもぎふの宿」とは、人に忘れられて雑草が伸び放題の家ということで、歌の語り手である女自身の暗喩でもある。凝縮した詞遣いに物語的な情趣を籠めた作で、初句切れと言い体言止めと言い、新古今歌風の一典型である。
雑
和歌所歌合に、羇中暮といふことを
草枕ゆふべの空を人とはばなきてもつげよ初雁の声(新古960)
【通釈】旅先で野宿する私の境遇を人が尋ねたなら、夕暮の空をわびしく眺めていると、そう泣いて伝えてくれ、初雁の声よ。
【語釈】◇草枕 草を枕にすること。すなわち旅先で野宿すること。◇ゆふべの空 「ゆふ」には前句からの続きで「結ふ」の意が掛かる。「空」はいわゆる旅の空、「旅にある境遇」「旅先で眺める空」の両義。
【補記】建永元年(1206)七月、仙洞の和歌所で催された「卿相侍臣歌合」と称される歌合の出詠歌。秀能はほぼ同世代の少壮歌人源通光と合わされて鎬を削った。空を渡る雁に、都人への私信を託そうとする旅人の心情を詠む。草枕を「結(ゆ)ふ」と「夕」が掛詞。「空」は「旅の空」と言う時の空でもあり、雁の縁語ともなる。初雁は秋の風物である。
【他出】卿相侍臣歌合、自讃歌、如願法師集、新三十六人撰
羈旅の心を
わたの原八十島かけてしるべせよ遥かにかよふおきの釣舟(新拾遺764)
【通釈】海原の数多くの島を経て隠岐の島まで案内してくれ。沖を遥かに往き来する釣舟よ。
【補記】後鳥羽院の遠島歌合出詠歌。隠岐に流された篁の歌を本歌取りして、院への思いがあらわである。「しるべせよ」は沖の釣舟に呼びかけた言葉で、遥かな隠岐の島まで航路を案内してくれ、ということ。『増鏡』には結句「おきの友船」として引かれる。
【本歌】小野篁「古今集」
わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海人の釣舟
春日詠百首応製和歌 雑
うちたゆむ夢を嵐にまがへても深山さびしき夜はのむらさめ(如願法師集)
【通釈】途絶えた夢は激しい風の音に紛らせても、深山にあって寂しい夜半の叢雨よ。
【補記】建保四年(1216)の百首和歌。寝苦しい夢が途絶え、その記憶は嵐の音に紛らせてしまえばよいものの、さて目が覚めれば、独りぽっちで山にいることを思い知らせるように、庵の屋根を叩いて一団の雨が通り過ぎて行く。……出家以前の作だが、当時の歌人は山家の侘び暮らしをいつか我が身に訪れる運命として、繰り返し想像裡に描いて飽きなかったのである。
貞永元年の秋、西国にくだり侍りし時
命とは
【通釈】命をかけて約束はしなかったけれども、再び石見の沖の、隠岐の白島を見たのであったよ。
【語釈】◇おきの白島 「おき」には「沖」「隠岐」を掛ける。隠岐島後の北端、西郷町西村に白島崎があり、その沖に白島と呼ばれる小島がある。白い岩肌を見せる奇岩・群島の眺めが美しい。
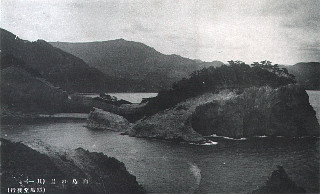 |
【補記】承久の大乱後、すでに十年以上が経った頃、秀能は隠岐の院を慕って西国に下った。乱に際し将軍として戦った人物が島へ渡ることを、幕府がやすやすと見過ごしたはずもないと思われるが、この歌を事実として受け取れば、彼は何度か渡島を果したことになる。「白島」は院の御所とは離れているが、隠岐のさらに北隅の離れ小島に、院自身を暗喩していると思える。上句は「再びの訪問を、命をかけて白島と約束はしなかったけれども」ほどの意で、結局のところ、命をかけてまで再び此処へやって来た、と言っていることになる。前例のない、あわれ深い句である。
和歌所歌合に、海辺月といふことを
明石がた色なき人の袖を見よすずろに月も宿るものかは(新古1558)
【通釈】明石潟――心に艶のない人の袖を見よ。私の袖と違って、月の光は明るく映えていない。むやみに月も人の袖に宿るものではないのだ。
【語釈】◇明石がた 明石潟。播磨国明石の遠浅の海。明るい意の形容詞「あかし」と掛詞になり、月と縁のある語。◇色なき人 心の艶のない人。物の情趣を解さない人。◇宿るものかは 宿るものだろうか、いやそんなことはない。
【補記】名所の月にあわれを誘われ、涙にびっしょり濡れた我が袖の月の光はいかに「あか」きことか、それを見よ、と言っているわけである。建永元年の卿相侍臣歌合。通光の「月やどる藻塩の袖を人とはばわぶとこたへよ須磨の浦波」と対し、勝。後鳥羽院の判詞に「右末句殊優也」と賛辞があるが、隠岐本ではなぜか削除されてしまった歌である。
【他出】卿相侍臣歌合、定家十体(有心様)、如願法師集、歌枕名寄、三五記、桐火桶
【主な派生歌】
袖の上におぼえずおつる涙にもすずろに月はやどりぬるかな(*油谷倭文子)
熊野にまうで侍りし時、たてまつりし歌の中に
月すめば
【通釈】月が澄んでいると見れば、周囲の浮雲は既に消え去って、奥山の陰に隠れて吹いてゆく嵐であるよ。
【補記】さっきまで空は激しい風が吹き寄せる浮雲に四方を塞がれていた。いま月が澄んでいると見れば、雲はすっかり消え果てて、嵐は奥山の山陰を去ってゆく。……常縁の注に「宵の程は嵐も雲も月にそふものなり。次第に更行ば雲もきえ、かぜの音しづまり、山がくれなどに小篠などの打さやぎて、山ふかく嵐の吹て行、まことに眼前の体也。熊野へ参詣の時の哥なれば、心にしみ侍り」とある。中世歌学者の鑑賞の深さも心に沁みる。
父秀宗身まかりての秋、寄風懐旧といふことをよみ侍りける
露をだに今はかたみの藤衣あだにも袖を吹く嵐かな(新古789)
【通釈】袖に置いた涙の露を、今はせめて形見と見る我が喪服――しかしはかなくも袖を吹いて露を散らしてしまう嵐であるよ。
【補記】秀宗の死の年は知られないが、『拾遺愚草』などに建永元年(1206)七月の和歌所当座歌合で「寄風懐旧」の題が出されたことが判る。おそらくこの時の歌だろう。露を形見に見る、とは、袖の涙を亡父の思い出につながる唯一のものとして慕う、ということであろう。「藤衣(ふぢごろも)」は喪服。その涙を吹き払ってしまう嵐の無情さを歎いているのである。
【他出】自讃歌、定家十体(有心様)、定家八代抄、続歌仙落書、時代不同歌合(初撰本)、如願法師集、新三十六人撰、兼載雑談
ことかはりてのち、人々にいざなはれて法輪寺にまうでてよみ侍りける
むかし見し嵐の山にさそはれて木の葉のさきに散る涙かな(続後撰1091)
【通釈】昔見た、嵐の吹く嵐山――その思い出に誘われて、木の葉よりも先に散る我が涙であるよ。
【語釈】◇ことかはり 出家したことを言う。◇法輪寺 嵐山東麓の寺。◇さそはれて 「人々に誘われて」「懐旧の情を誘われて」両義の掛詞。
【補記】家集には「嘉禎元年九月」と記されている。作者五十二歳、晩年の作である。
雑歌の中に
袖のうへにかはらぬ月のかはるかな有りし昔の影を恋ひつつ(風雅1681)
【通釈】私の袖の上で、変わらないはずの月の光が、ありさまを変えているよ。過ぎ去った幻影を恋しがっては――。
【補記】出家後の百首歌。業平の名歌「月やあらぬ」にせよ、『新勅撰集』小侍従の秀詠「幾めぐりすぎゆく秋にあひぬらむかはらぬ月のかげをながめて」にせよ、月の光は歳月を経て不変のもののシンボルであった。変らぬはずの袖の上の月が、しかし今は昔と違っている、と言う。変えたものは、過去の面影を恋いつつ流す涙であるが、また涙に濡れる袖が墨染の色であることも暗示していよう。
詠百首和歌 雑
憂へても泣きてもいはむ友もがなこたへぬ月にながめわびぬる(如願法師集)
【通釈】不平でも泣き言でもいい、何か言ってくれる友がいてくれたら。夜空の月は何も答えてはくれず、眺め続ける気持も萎えてしまった。
【補記】西行を思わせる詠みぶりである。俗名秀能如願法師は、仁治元年(1240)五月二十一日、入寂。享年五十七。後鳥羽院崩御翌年のことであった。
公開日:平成14年04月15日
最終更新日:平成21年01月16日