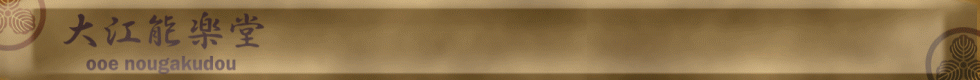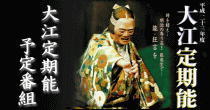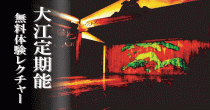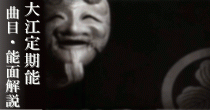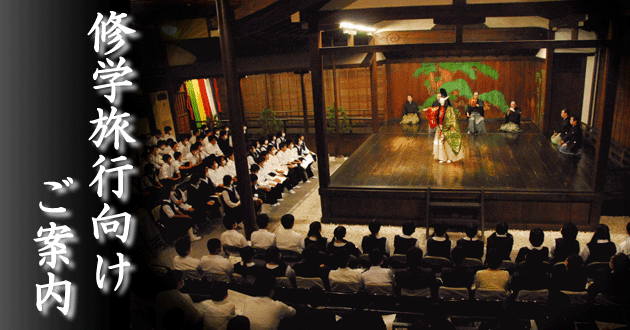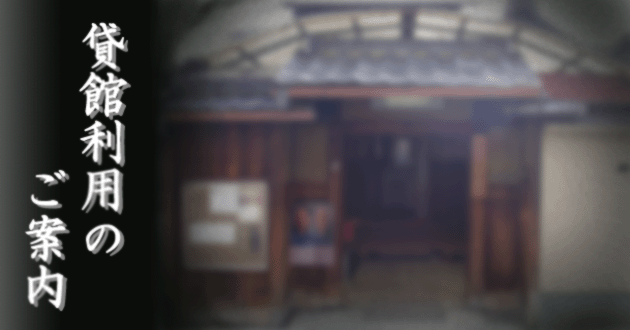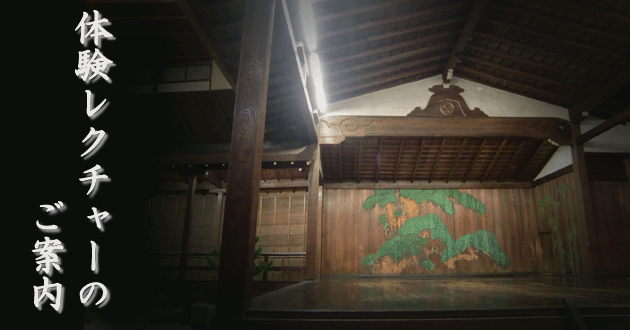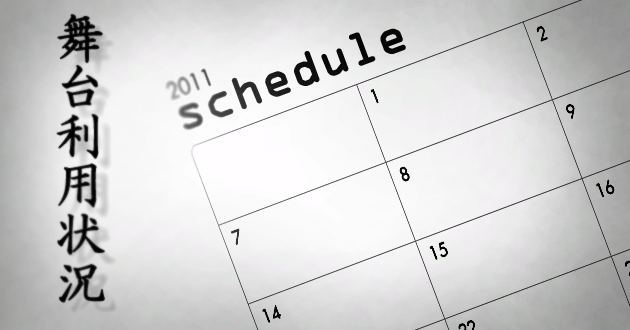能・龍田について
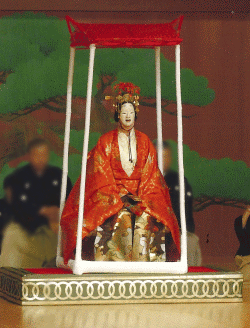
六十余州の寺社に御経を納めながら廻国している僧(ワキ)が、南都の寺社の巡拝を終え、大和国から河内国へ向かう途中に紅葉で名高い龍田川に着きます。龍田明神へ参詣するため龍田川を渡ろうとすると、そこに一人の女人(前シテ)が現れ古歌を詠み、止めます。僧は、今は紅葉の頃は過ぎて川面には薄氷が張り川波も見えないので渡ることを許してほしいと言い、川を渡ろうとします。すると女人は更に別の古歌をも詠み引きとめます。不審に思った僧は、女人に素性を尋ねます。女人は、自分は神巫(かんなぎ=巫女)であると言い、龍田明神への案内を申し出ます。社前に着くと、霜月でどの木も枯れているのに、一本だけ見事に紅葉している木があります。不思議に思い神巫に尋ねると、これこそが龍田明神のご神木であると答え、宮廻りしているうちに神巫は、自分は龍田姫の神霊であると名乗って社殿の中に消え失せます。〈中入り〉
その夜、僧が神前で通夜をしていると、神殿鳴動して龍田姫神(後シテ)が現れます。龍田姫神は瀧祭の神徳を述べ、紅葉の美を賞し、夜神楽を奏して昇天していきます。 この「龍田」は、秋の神をシテとして紅葉の美を讃えるのを目的としていますが、薄氷の張る時期に季節を於いたのは藤原家隆の歌に寄った為と、厳粛さを加える為であったか、とも言われています。 「金春の三輪、金剛の巻絹、観世の龍田、宝生の室君、四座の神楽の由なり」と古書に言われ、「龍田」は観世流に於いて大事にしている神楽とも言えるでしょう。
能面「増女(ゾウオンナ)」について
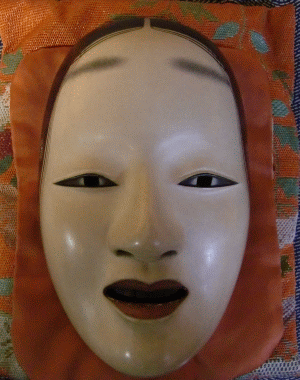
能面「増女」は小面のような若い女性と対象的に顔全体が少し年をとった女性の相貌をしています。額が長く頬の肉付きがぐっと引き締まり鼻筋も細くほそおもてです。その上目全体がくぼんで、さらに目の幅もやや細くその周囲には影を作っています。口も若い女面では両端がやや引き上げられているのに対し、増女では反対に両端がやや下がりめに作られています。このような工作が増女の相貌を生み出しているのです。小面のような若い女性の明るさや愛らしさなどが見られない代わりに、全体に清高な品位があって端正です。女神・天女・神仙女などが主人公の曲で用いられることが多い面です。これらの曲の多くは天冠を頭にいただきますので、別名「天冠下」とも呼びます。