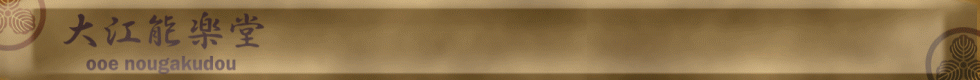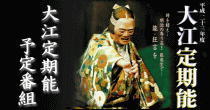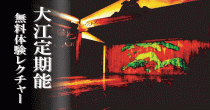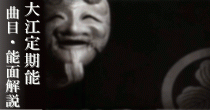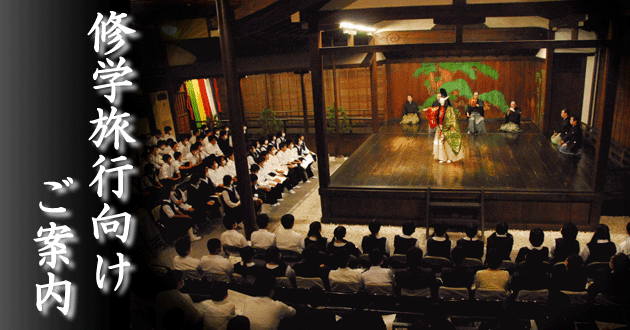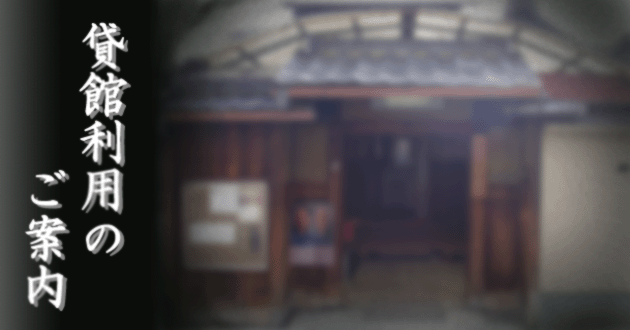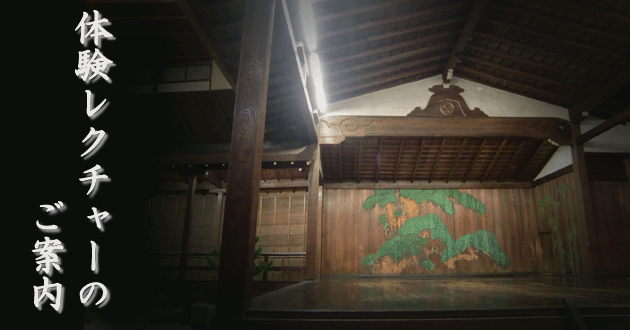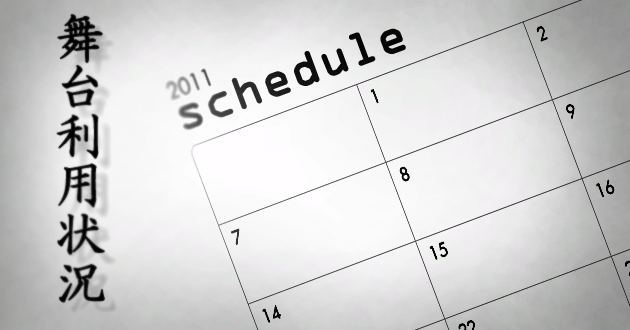能・清経恋之寝取について

平清経の家臣である淡津三郎は九州より都へ戻り、清経の妻へ主君の形見である黒髪を届けます。清経自害の報せを受けた妻は、戦死や病死ならばともかく、私を残して自害するとはと嘆き悲しみ、形見の黒髪も返してしまいます。涙ながらに床につくと、夢枕に清経の亡霊が現れます。妻は自分を残して自害したことへ恨みを言い、清経は自らの形見を返した妻を責めつつも、都落ちした平家一門のため宇佐八幡に参詣し祈念したが、神からも見放された事や、敵に怯え逃げ落ちてゆく苦しさ、追い詰められていく不安や心細さを語り、いつまでもこの苦しい思いをするくらいならと覚悟を決め、月の美しい中で船の舳板に立ち、横笛を吹き鳴らし、今様を謡い、南無阿弥陀仏と念仏を唱え入水したことを伝えます。その後、修羅道の苦しみを見せますが、十念を唱えた徳により成仏できたことを伝え消えうせます。
小書「恋之寝取」では笛の独奏に誘われるようシテが登場する特殊演出になります。
能面「中将」について
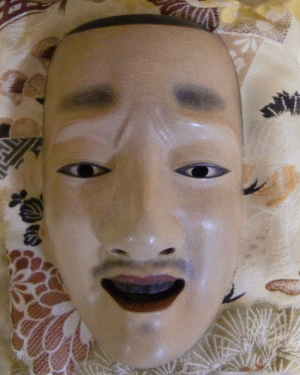
能面「中将」は在原業平の相貌を表現した面です。中将の名前は業平の官位・右近衛権中将からとられています。面を見ていただくと、下瞼は彎曲し眦にかけてつりぎみになっており、また鼻筋はどっしりと太くなっております。貴族独特の気品さもあり、殿上人が描く眉毛である殿上眉、お歯黒、鼻下にある生毛のような口髭などが特徴的です。よく見ていただくとこの面には下歯がございません。これは、やさしさ・美しさ・みやびやかさなどを表現する能面独特の方法です。眉間に深く入った2本の皺は、死後修羅道に落ちた平家の公家達の背負っている悲哀を表現しています。