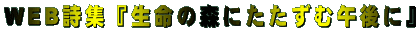第五章 追憶 青春詩編 6編
雨の日の幻想 / 花帽子の季節/ 海が残していったもの
高原の秋/ 初夏の森で / 夜のフラスコ


「雨の日の幻想」
約束の場所で待てど
待ち人は来ない
約束の場所に一つ
カタツムリの殻がぽつり
のぞいてみたなら
僕の名が聞こえた
そして、
約束の場所のどこにも
僕はもう居ない
約束の場所にあった
カタツムリの殻の中では
澄んだ笑い声だけが響いてる
明るい雨の降る菜の花色のひるさがり



「花帽子の季節」
花帽子をかぶって木立を抜けて歩く
菖蒲池の脇を抜けて
西洋館の前の森へ
いつもすれ違う自転車の少年たち
鉱滓線の貨物線路を越える陸橋で
黄色いカンナが揺れていた
さようなら さようなら
どうして手を振るのだろうと意味もわからずに
いつも最後尾の車両の機関士に
母と肩を並べて手を振った少女の日
制服を脱いで花帽子をかぶる季節になって
恋が密かにはじまった
夏が終わる頃にはまたそれぞれの学区に
戻らなくてはならないのに
夏の1日は日時計のように間延びして
溶け落ちるように過ぎていくのに
その季節だけは特別に秋は足早に訪れた
海からの帰り肩をならべて岸壁から
青く透き通る渦潮を見下ろしていたこと覚えている
何を話せばいいのかわからなかった
どんな約束があり得たのかそれさえも
去りゆく日
さようなら さようなら
流れている涙の意味もわからずに
海峡フェリーに手を振った
花帽子の季節が来ると思い出す
高貴なる白い檸檬の花の香の
遠い夏の日の備忘録



「海が残していったもの」
寄せては返す波打ち際
沖でカモメたちが群れ飛んでいる
白い翼を広げて
竜巻のようにくるくる旋回を繰り返しながら
太陽は、強く高く照っていた
遠い夏の一日
海を見つめていた
君の後ろ姿だけ覚えている
いつも、精一杯頑張ってた
悲しみを一人で耐えようとする
勝ち気な優しさに
いつも僕はため息だけついて‥
沓を脱いだ君の白い足が綺麗だって
はしゃぎながら水遊びしたのに
夢中になって小さな魚を、追い掛けたのに
いつも、波は細かい砂からさらっていく
いつも、流れ去ることのできない塊だけが残される
求め合っても、はしゃいでみても
若すぎる二人の心のなかには
いつもカラカラちいさな石ころだけが残った
季節が変わって
僕たちはもう逢わなくなった
それぞれの胸に苦いザラザラの粒を残したまま
ときおり、ふと、あの海を思い出す
青い波、君の横顔‥
流れ去った潮流は、同じ浜辺には帰らないのに
風は、いつも海から吹いていたのに
優しさの意味を知るには、まだ幼すぎた二人
<でも不思議だね。取り戻せない過去ほど美しい>
あの夏の海が残していった苦いザラザラの粒は
時の流れと涙の波に洗われて
いまでは、甘い追憶のきらめき
<もっと大人になったらもう一度だけ君に逢いたい>



「高原の秋」
高原の秋はもう色褪せて
ただ風だけが騒いでいる
ひらひらと舞い降りる淡雪を口に含んでみると
それは、失った追憶のひとかけらのように
甘くはかなく
湖は静まり返り
さざなみが流木の白い骨を洗う
木立は空を突いて梢を風に揺らし
ナナカマドと駒鳥の胸だけが血のように赤い
夢はかならず消え去るもの
虚栄の欲望をひとつ叶えるたび
人はいつもなにかを失いながら生きていく
はらはらと舞い落ちる淡雪を口に含んでみると
それは、もう逢うことのないあの人の微笑みに似て
やさしくはかなく溶けていく



「初夏の森で」
そう、あれから
僕は森の中を一人、歩くようになった
町の俯瞰図、鳥のさえずり、遠くに響く学校のチャイム
咲きほころびる白い野茨の花
ひっそりとした湧水池に木々は影を落とし
こずえの先の青空を、まだ若い夏雲が往き過ぎていく
そして、あれから
僕は泉のほとりに舟を浮かべるようになった
小花を乗せた笹舟はくるくると軽やかに水面を舞い
せせらぎに捲かれて見えなくなる
舟はやがて
小蟹や鮒たちの棲む国に辿り着く
泉水の吹き出す暗く冷たくひそやかな夢の眠る国に
かつて、僕の心を満たしていた
優しい気持ち、激しい思い、熱い衝動
受け取る人がもういない今は
流れるままの涙のように、すべて森に返してしまおう
これは、僕だけの秘密の儀式
日の暮れるのすら忘れて森の懐に抱かれる
藍色の蝙蝠傘をさして君が突然木立の間から現われた
と、思ったら薄墨の空に顔をだしたまあるい黄色い月だった


「夜のフラスコ」
僕の心は透明なフラスコ
水のしずくを溜めこんで
熱くなる自分自身の内なる感情と
冷静を保とうと外に向かう思考と
二つの温度の狭間で
いくつも水滴を生む
水はなかなか外には出てこない
いつも透明なガラスの壁を伝い
滴り落ちては底に溜まるばかり‥‥
自己嫌悪と後悔
ためらいと迷い
あてどのない旅
自分自身探して
泳ぎ続けている
でも、そんな僕でも
生きていく術がある
フラスコを空にする
とっておきのやり方
よく晴れた日の午後
気持ちよく森を歩き
鳥たちの歌声を聞き
花たち虫たちからの
メッセージを添えて
心の水滴を空に返す
フラスコは軽くなる
心はぽっかり空白に
羽が生えたかのよう
風になったかのよう
気化した水滴たちは
いつの日か雲となり
いつの日か雨となり
川となり海に流れて
水循環の一部として
深く地球に沁み透り
時に元素に姿を変え
成層圏を駈けめぐる
目には見えない歌となる‥‥‥‥
だけども僕のフラスコは
やっぱり水を溜めていく
時に一つの願いは、もう一つの夢を消去してしまう
僕はいったいどちらを選べばいい
届かぬ自分の目標と理想‥‥
哀しみは尽きせぬしずく
ガラスの壁を伝い濡らす
僕の心は、透明なフラスコ
今日もしずくを溜めこんで
月の輝き映しては
青い光を放ってる

詩集目次へ戻る
森の扉へ戻る
メニューに戻る