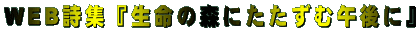第三章 森の植物誌 vol.1 5編
銀杏(いちょう) / 蔦(つた)/萩(はぎ) / 薄(すすき) / 麦


「銀杏」
夏はそこに日陰があった
凛々と深々と冷たい葉陰の翳り
突き刺す光線を遮る銀杏の枝は
緑のとんがり屋根の隠れ家
そして秋
三角の葉の一枚一枚
縁取りから
イエローからグリーンへのグラデーションに染まる
青い空の下
黄金色のその情景は
森の収穫祭のように明るいのに
なぜ とらえどころのない哀しみに
足元をすくわれるように私はここにいるのか
それはこの金色の雨が
冬へ向かう祝祭の最後の輝きだからか
人はどこから生まれどこへ向かうのだろう
銀杏、おまえは路傍の語り部のように
生命の祝祭を讃え、終焉を謳え
だれもがいつかは気付くだろう
どんな路程を辿っても
終局はその一点に帰結することを



「蔦」
からみつく
つめたいレンガに
ゆれる蔦の葉ゆれる
張り出しアーチ窓にゆれる
あの娘の愛した
あの男のこころ
奪って闇に消えた
長い栗毛の痩躯の女が
路地裏に残していった
プワゾンの残り香
一緒にあの娘と飲んだ酔えない涙酒も
石壁に蔦の絡まるカフェ
わたしもたぶん綺麗な月の晩には
忍び歩く白い猫のように
蔦のようにからみつく
愛しい男の胸
蔦は夜に似ている
そしてすでに女の一部分である



「萩」
かろやかな彩りうすむらさき
はかなくゆれる
ささやくようにゆれる
ほほをくすぐるように
記憶の束を呼び起こすように
秋になればそこにいる
ひっそりと生きることのうつくしさを
誇るはずもなく
ただ風とともにある
だからこそ月光に愛され
ほんのりと
そのひとつひとつの花びらに
蛍がやどったかのように
夜にこそ輝く
うすむらさきの恋歌
その名は萩
萩の花いとおし



「薄 」
ゆれる
草原に
ゆらゆら風に
銀の尾、ゆれる
キツネの子
しっぽを立てて走るにげる
100メートル走ったらふわり・薄の群に化けた
岬の果ての空は笑ってる
からからと
青く
晴れやかに
でも天の底があんまり高いので
水平線があんなに遠いので
地平線があんなに果てしないので
だから秋の旅路はちょっとさみしい


「麦」
天を突いてのびる
麦、その命のまま
ただ空をめざす
曇天があり
強風があり
害虫が横をかすめる
ごていねいに散布される薬品は
果たして自分を守ってくれるのか
少しずつ自分を殺していくのか考えあぐねて
ちょっと疲れたなぁ・・・ああ
私を真に必要としているのは
農薬を撒く手ではなく
刈り取る手ではなく
私を待っている食卓なのだ

詩集目次へ戻る
森の扉へ戻る
メニューに戻る