ことばをめぐるひとりごと
その6
「チョー」の先輩
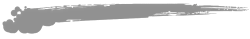 第5回で、「ちょすご」など、「超〜」のつくことばは1986年ごろから使われだしたのではないかという考えを述べました。
では、「超〜」が生まれる前には、若者は強調表現のためにどんなことばを使っていたのでしょうか。それは、平凡かもしれませんが、「すごい」ではなかったかと思います。たとえば、次のように使われました。
あの人は(略)何でもやれるすごいオールマイティーな方ですが、
(ニッポン放送 1982.4.16)
えー、でも、みんな、なんか(歌が)すごいうまい……何であんなに高い声とか低い声とか、(ニッポン放送 1982.5.14)
ペンションのオーナーでさー、(司会が)すごい好きな人がいてね、やっぱ蝶ネクタイかなんかしてさー、
(ニッポン放送 1983.4.8)
この言い方は「超〜」よりは比較的おとなしい表現として今でも使われていますが、僕の記憶では1982年ごろから出てきたと思います。
この「すごい」は、従来の用法と比べると、下のことばへ接続するしかたが違っています。これより前は、「すっごくオールマイティーな方」「すっごくうまい」「すっごく好きな人」のように、もっぱら「すごく」とか「すっごく」などと言っていたのです。
「すごく」が「すごい」になったのは、強調表現であることを目立たせるためでしょう。「すごく」は連用形で、下へ続いていきますから、意味の重心が下に移ってしまいます。でも、「すごい」はそこで終わることもできますから、強い感じを与える(陳述の役割を担わすことができる?)のでしょう。たとえば「私はこう思うんですが……」と言うより、「こう思います。」と言ったほうが印象が強いのと似ています。
〔追記、この考えは後に改め、もっと簡単に考えるようにしました。「ぼっけえ、きょうてえ」の末尾参照〕
これと同じようなことが、江戸時代の上方語「えらう(エロウ)」でも起こっています。増井典夫氏によれば、「えらう」は「ひどく」というような意味で、江戸初期に現れました。
七めが此中卯月八日にここへ来て、ゑらうさやしおつた、一日に拾七貫手放した、(洒落本「浪華色八卦」)
などと用いられ、その後、徐々に広まっていったようです。この「えらう」が、江戸後期の上方では「えらい面白い」などと、「えらい」の形で用いられるようになったといいます。「えらい面白い」などという言い方は、今でも関西で使われていますね。
(1997年記)
▼関連文章=「「チョー」の誕生」「夏目漱石の「大変」」/「おそろしい光る」「大したたまげた」「ぼっけえ、きょうてえ」「「膝栗毛」程度を表すことば」
●この文章は、大幅に加筆訂正して拙著『遊ぶ日本語 不思議な日本語』(岩波アクティブ新書 2003.06)に収録しました。そちらもどうぞご覧ください。
|