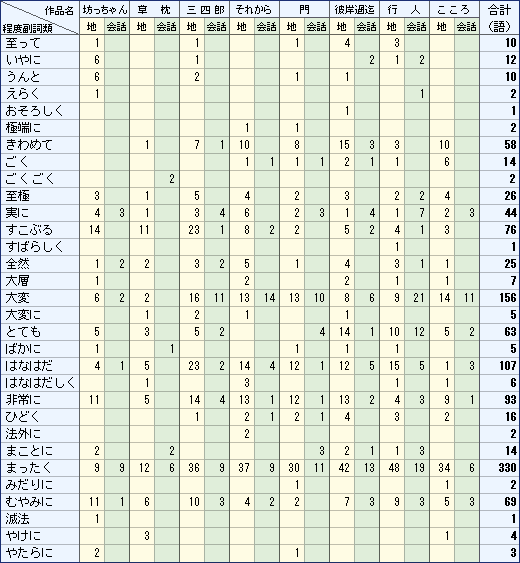02.09.28
夏目漱石の「大変」
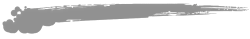
程度を表す副詞のたぐいは、日本語には多くあります。
若者が何にでも「超」をつけて言うのはけしからん、というようなことを耳にすることがありますが、必ずしも事実を表していません。小矢野哲夫氏の「けとば珍聞」1998.06に掲載されている近藤明氏の報告によれば、程度がはなはだしいことを表すことばは、方言形や強調形を除いても、「めちゃ・超・すごい・かなり・まじで・鬼のように」など40以上あります。きわめてバラエティに富んでいるといえるでしょう。
国立国語研究所の『「分類語彙表」形式による語彙分類表(増補版)』を見ると、程度がはなはだしいことを表すことばは「すこぶる」「甚だ」「大変」「非常に」などをはじめ、70語ほどが挙げられています。昔から、この種のことばは豊富でした。
もっとも、中には、その下にどのようなことばを続けてもいい、というわけにはゆかない程度副詞類もあります。たとえば、「底抜けに」「べらぼうに」「めっぽう」を使って「底抜けに悲しい」「べらぼうに固い」「めっぽうくやしい」のように言えるかというと、やや違和感が残ります。
「底抜けに」に続くのは、まず間違いなく「明るい」「楽しい」「陽気な」など、気分が浮き立っていることを表すことばです。「べらぼうに」は、「べらぼうに簡単」「べらぼうに長い顔」などと言うこともできますが、多くの人がすぐに思い浮かぶのは、「値段がべらぼうに高い・安い」という使い方ではないでしょうか。
「めっぽう」になると、かなり限定がゆるくなるかもしれません。僕の感じ方では、「めっぽう強い男」「彼女はめっぽう美しくなった」「めっぽううまい料理」のように驚きや称賛の気持ちをもって使うことが多いような気がします(追記参照)。
下に取ることばをあまり選ばない、いわば無色透明の程度副詞として、今最もふつうに使われることばは、「とても」ではないでしょうか。「とてもお世話になりました」「とてもためになりました」というふうに、口頭でも書面でも用いられます。
若い人は「超」がふつうだと言うかもしれませんが、少なくとも学校のレポートや、おおぜいの前で話すスピーチなどでは「超ためになりました」というふうには言わないでしょう。では「すごくためになりました」はどうかと言われるかもしれませんが、これも公的な言い方ではないでしょう。事務的な文書で「すごく○○」と書くことはあまりないはずです。
ところが、この「とても」も、大正時代ごろから使われだしたらしく、それ以前は「とてもできない」「とても間に合わない」など、下に不可能の表現が来るのがふつうでした。今でも、
「君は最近、授業をよく理解していますか?」
「とてもとても」
とだけ言う場合、それは「とてもよく理解しています」ではなく「とても理解できません」の意味になります。昔の意味が残っています。
「とても」「超」「すごく」「すごい」が使えなかった時代は、人々は「とても」不便な思いをしたのではないかという気がしますが、もちろん、当時は当時なりに、だれもがふつうに使っている程度副詞類がありました。それは何でしょうか。まず、クイズを出しておきます。
●次の程度を表すことばのうちで、夏目漱石の小説で最も多く使われているのはどれ?
(1)大変
(2)甚だ
(3)非常に
|
先の『語彙分類表(増補版)』に出ている程度副詞類が、夏目漱石の小説ではどれぐらい使われているかをちょっと数えてみると、以下の表のようになります。
(※注 「地」は地の文、「会話」は会話文で使われた語の出現度数を示す。)
上の表は、調べたことばを五十音順に並べてありますが、全体を多い順に列挙すると、「まったく」「大変」「はなはだ」「非常に」「すこぶる」「むやみに」「とても」「きわめて」「実に」「至極」……のように続きます。これで見るかぎり、漱石は「まったく」を最も多く使っています。
ただ、「まったく」は元来「完全ににそうである」という意味であって、程度のはなはだしいことを表すというのとはやや趣が違うようです。そのため、次の例のように、画家のターナーの名にくっつけて「全くターナーです」という言い方ができます。
「あの松を見給え、幹が真直で、上が傘の様に開いてターナーの画にありそうだね」と赤シャツが野だに云うと、野だは「全くターナーですね。どうもあの曲り具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ」と心得顔である。(「坊っちゃん」)
これは、べつに「〈ターナー度〉がはなはだしい」というわけではなくて、「松の木の様子がまるでターナーの絵のようだ」ということです。
「まったく」のほか、「実に」「まことに」も「本当にそうである」ということで、今のことばでいえば「超」よりも「まじで」に当たるでしょう。「全然」も「一体生徒が全然悪るいです」(「坊っちゃん」)というように、「完全にそうである」という意味で使われました。
また、前に触れたように、「とても」も「とても〜不可能」という言い方で使われるものですから、程度を表すことばからは除いたほうがよいでしょう。
とすると、これら以外では「大変」が最も多いということができます。さっきのクイズの答えは「大変」が正解です。
「大変」は、今ではなんとなく硬い感じのすることばです。女性が会話で使うことはあまりないでしょう。しかし、漱石の作品の中では、会話部分だけを取り出してみても、「大変」の使用度数は多いのです。
「ホホホホ大変非人情が御好きだこと」(「草枕」)
「大変込み入ってるのね。私驚いちまった」(「それから」)
「おや宗さん、少時御目に掛からないうちに、大変御老けなすった事」(「門」)
というふうに、女性の気軽な会話で、ごくふつうに使われています。
ちょうど、今でいえば「とても」ぐらいの感じではないでしょうか。「すごく」とか「すごい」とかいうほど、くだけてはいないと思いますが。
追記 俵万智さんが脚本を担当し、1994年1月に東京・両国シアターX(カイ)で公演された舞台の題名は「ずばぬけてさびしいあのひまわりのように」といいます(「週刊文春」1993.11.11 p.49「ぴーぷる」)。「ずばぬけて」の下には、ふつう「さびしい」は来ないところを、あえて持ってきたところがミソです。(2002.09.30)
▼関連文章=「「チョー」の誕生」「「チョー」の先輩」
|