
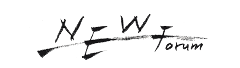
ノースウエスト・アース・フォーラム
別役劇観劇会

 |
ノースウエスト・アース・フォーラム別役劇観劇会 |
 |
2008年7月30日、NEWフォーラムの第7回目の企画として 不条理演劇作家の代表にあげられる別役実氏の音楽劇「夜と星と風の物語」(テグジュベリ原作の「星の王子さま」より)観劇会をおこなった。別役実氏は北ラス会のメンバーであるが、 中学時代のクラスメートの小笠原さんと三ツ井さんに仲立ちしてもらった。劇場は北千住駅西口千住ミルディスI番館10-12階「シアター1010」(Theater Serial No. 26)
バオバブの木のあるマダガスカル島の鳥の話しを山岸さんから聞いた後で、バオバブの木3本で破壊されてしまうような小さな星からきたサン=テグジュベリの「星の王子さま」を題材にした別役劇を観劇することになったのも何かの縁であろう。
星の王子様を主演した女優で劇作家の矢代静一氏の娘の毬谷友子さんは対談で「別役さんの『星の王子さま』ですから、かなり覚悟して台本を読んだのですが、原典で私が一番好きなところはキツネが『かんじんなことは目にみえない』 と いう有名なセリフを言う場面です。しかしそのキツネが出てこない。でも読んでいくうちに、物語の中核にあるのは、あのキツネの言葉だと思いました。サン= テグジュペリのスピリットをご自分の中にすっかり入れた上で、登場人物たちを別役さんの世界で遊ばせている。だから私も物語の中のことをすべて理解した上 で、演じなければと思っています。 別役さんが生み出す笑いはドタバタとは違う、すごく知的なもの。セリフを崩さずに、言葉の力を生かしてストレートに言うおかしさ、というのを私は野田秀樹 さんの作品を通して理解しましたが、考えてみれば、別役さんは野田さんやKERAさんといった現実ではありえない、ユニークな世界を作り出す方たちの元祖 のような存在ですね。あのぶっ飛んだ世界を40年以上作り続けているのは本当にすごい。観たことがない人にとっては、この作品が今の演劇の流れを作った別 役実の世界に触れるきっかけになると思います」と語っている。
私は「当世悪魔の辞典」、「別役実戯曲集 マッチ売りの少女/象」、「道具づくし」 、「日々の暮し方」しか読んだことはないが別役氏は劇作のほかにも沢山本を書いている。
伯父が海軍のパイロットだったこともあって北高生の頃はパイロット志願だった。近眼になって断念したため、パイロットだったサン=テグジュペリには共感をもって「人間の土地」とか「夜間飛行」を読んだ。「星の王子様」はサン=テグジュペリの代表作だが、スイス人からフランス語を習うときの教科書だった 。途中で挫折したままになっていたため、いまさらフランス語では読めない。手元にあった英訳でようやく通読した。別役氏はサン=テグジュペリの他の著作も読んでこの戯曲を発想したのだろう。
サン=テグジュペリは44才になった1944年、フランス解放戦争に従軍中、偵察を目的に単身ライトニング機に搭乗、飛び立ったまま、地中海で行くへ不明 となった。2008年3月15日の仏紙プロバンスに元ドイツ空軍のパイロットホルスト・リッペルト氏(88才)が1944年7月31日、任地の南仏で敵機 がレーダーに映ったため出撃、マルセイユ方面に向かう戦闘機をみつけて撃墜したと告白。リッペルト氏はサン=テグジュペリの愛読者だったため、撃墜の数日 後、コルシカ島の連合軍基地から独占領下の仏本土に偵察にでたサン=テグジュペリだったと知って慙愧の念にさいなまれたという。
不条理演劇と聞くとアイルランド出身のサミュエル・ベケットがフランス語で書いた「ゴドーを待ちながら」という戯曲を連想する。「ゴドーを待ちながら」ではなにも分からないがフランス語で”En attendant Godot”と知ればGodotとGodの類似からなにやら分かった気になる。今回の別役氏の作品はサミュエル・ベケットや今はリュベロン山塊のルールマラン村に眠るアルベール・カミユの「異邦人」から連想する難解さはなく、楽しめた。
観劇後、別役氏との懇談会を 「手作り居酒屋 甘太郎 北千住店」 (Restaurant Serial No.325)で持った。
別役氏は「自分は不条理作家と言われているが、年をとると思い出が大切になり、恋愛について書きたいと思うようになった。夏休み向けの企画として親子連れで楽しめるようにと『星の王子様』を選んだ が、テーマは自ずと思い出と恋愛を描くということになった。作曲家稲本響と組んでミュージカルを何回かつくったが、今回は曲も良くてそれなりに仕上がったと自負している」と挨拶があった。

別役氏を囲む懇談会
観劇者からは主演女優の毬谷友子さんが指摘した原作者のサン=テグジュベリの『かんじんなことは目にみえない 』という原作のテーマはどこに表現されているのかとの質問があった。砂漠に墜落したパイロットと両親の関係など多少不条理ポイところもあるにはあったが作 者の意図はむしろ、星の王子様の舞台を借りて「思い出」と「愛」について語りたかったということなのだろう。観劇者の大部分が女性ということで別役氏がこ の劇を奨めてくれた理由もそこにある。
バンドのリーダーだというボイスパッカーショニストのMalのワザに賛辞を送る言葉があった。 マイクをもつだけで息を打楽器とするヒューマンビートボックスというのだそうだ。
観劇者の一人から「青蛇の毒で『星の王子さま』が自殺するのは子供に悪い影響を与えるので好ましくない」との意見もあった。別役氏は「原典にあるのでそのまま引用しただけだ」という。
手元にある英訳本を再読すると「星の王子様」が自分の星に帰るために、今様の言葉で言えば時空をワープするために、砂漠にいた猛毒をもつYellow Snakeに頼んで、蛇との約束の地点で足首に噛み付いてもらって一旦死に、自分の星で再生するということになっている。
原作では自殺を忌避するキリスト教国の作品として自殺という暗いイメージを本人からの委託殺人と偶発性で薄めるというテクニックを駆使して品よくしている。原作通りに演じるには蛇に自律的に動いてもらわねばならず、舞台上でなに が生じたのかを観客に分からせるには黒子を使うか、遠隔操作のヘビを開発するかしなければなるまい。藤原演出では経済性を追求して王子様が毒々しい蛍光色を持つ毒蛇を袋に入れて持ち歩いていて、そのとき 、蛇を自分の首筋に持っていって咬んでもらうというということに変えた。かってハラキリが美徳とされた我が国の伝統の作法にのとった演出だろうが、この演出を好ましくないと感じた人がいることは日本も変りつつあるということかもしれない。
観劇者の一人から細部はどのように構想するのかという質問があった。別役氏は「書き出せば細部はおのずから湧いてくるものだ」とつぶやく。
August 3, 2008
Rev. August 15, 2008