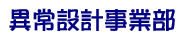
|
近接格闘戦、つまり押し合いとひっくり返し合いを主とする
かわさきロボットコンテストに、
全く新しい方法で相手を押し出す方法を提案したのが
「らぴすらずりIX」(以下LIXU)です。
2001年の 「保守的らぴすらずり」に 続いて、新コンセプトで大会に参加することとなりました。
|

|
そこで相手マシンを押し出すためには相手より摩擦係数の大きな足機構が必要となり、 相手マシンをひっくり返すためには相手よりも安定したマシンの構成が必要となります。
それにはフィールド上でマシンが触れている二つ目の素材、空気を利用することです。 空気を利用することで、足の摩擦係数が少なくとも相手を押し出すことができ、 あるいは自分のマシンの安定性を増すことができます。
きっと。
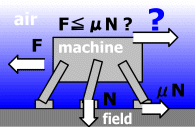
図1:マシンに働く力
しかし現在のフィールドは凹凸起伏が非常に激しいので、 このような方式では床に十分に吸着することができず、 効果を発揮できません。 また「人間の自主規制」の攻撃アームのレンジは短いので、 相手を追いかけて移動するためには吸着を切る必要がありました。
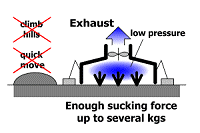
しかし、近接格闘戦を行うマシンに高速回転するプロペラをつけると、 相手のアームがプロペラ回転面に入ってしまうかも知れず、 いわゆるバードストライクによる事故の危険性が非常に高くなります。
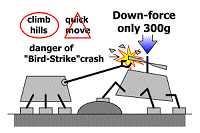
しかし「らぴすらずり」シリーズはロングレンジアームで相手を攻撃するので、 よく考えるとそもそも機動性が必要ありません。 そのためマシンの総合性能を下げることなく、 プロペラ推進や吸着機構を取り付けることができるのです。
また危険性を考えて、 バードストライクのない位置にプロペラ推進機構を追加することと、 プロペラ推進機構の追加に伴う重量増加は足機構の軽量化によって補償することを 主眼としてマシン構成を行いました。 そのため足機構についてはミラーチェビシェフ2 にこだわらず最適なものを検討することとしました。 自社技術を放棄する羽目になる時もあります。
そこで「LIXU」ではアームを3本として、 そのうち2本には高速に展開して相手を挟み込む役目を負わせました。 このアームは相手に対する攻撃能力を持たず、 心理的障害にしかならないため「心理障壁(Psyco-barrier)」と名前をつけました。 これならばカーボンファイバーのパイプで軽く簡単に作ることができます。
残る1本は「スローアーム(slowarm)」です。 構成はストラトリンク(StratoLINK)とほぼ同一ですが、 ICBEの姿勢を決定するために取り付けていた寄生並行リンクは ありません。
ここにプロペラ推進機構を取り付ければ、 早く移動する必要のあるのは軽い物のみとなり、 質量のあるものはゆっくり移動すればよいことになって力学的には有利です。
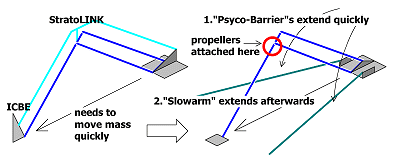
図4:心理障壁とスローアーム
これならば特注品のパイプは使用しないので低コストで、 1000mm近い遠距離から相手を押すのでバードストライクの危険も少ないはずです。
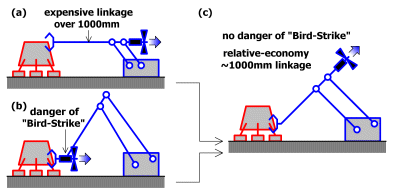
図5:プロペラ推進機構の位置
- 胴体上下動の完全0化
- 180度対向クランクでの補正足先機構実現
- スライダクランク機構利用により軽量・単純
斜めの弧状の線は足先の補正曲線で、 原動節の回転180度以上にわたって、 原動節から地面(y=0の線)までの距離がまったく変わっていないことがわかります。
ただし補正足先のみではピッチング方向の姿勢を決定できないので、 実際に使用する際にはアウトリガーを前後に出して安定を図りました。
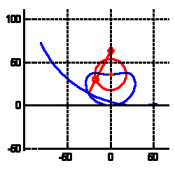
図6:補正足先機構のグラフ
(クリックするとアニメーションします)
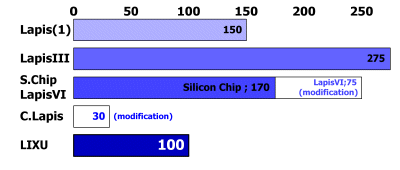
図7:歴代らぴすらずりシリーズの作成部品点数
| 全長(スタート時) | 345mm |
| 全高(スタート時) |
約1700mm
「るびぃNT5」を抜いて参加時歴代1位 |
| 全長(展開終了時) | 約2170mm(歴代6位) |
| 全幅 | 展開前245mm/展開後610mm |
| 重量(バッテリー含む) | 3450g |
| 電源 |
単3アルカリ乾電池4本(制御電源用)
ニッカドバッテリー2本(1700mAh,6セル 主電源用) |
| 動力 |
コンスタントフォーススプリング×2(アーム展開用)
実委支給ギヤ・アーム展開用サーボモータ 380モータ×2(プロペラ用) |
| 所要展開時間 |
約0.5秒(心理障壁)
1秒強(スローアーム) |
| 歩行形式 | 補正足先機構を持った180°対向脚2対による4足歩行 |
| 歩行速度 | 約150mm/s |
- プロペラ推力が800gでは十分ではなかったこと
- 心理障壁とスローアームの展開が同一のトリガーで行われており、 戦術的に時間差をおくことができなかったこと
- スローアームの先端が相手を捕まえやすい構造になっていなかったため、 相手に命中したあとで「跳ね返り」が発生し相手に逃げられたこと
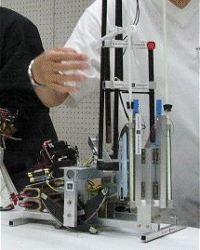
図8:LIXU
(2002年10月26日 工大祭)
しかし旧式な機構の実装と動力源の不十分さにより、 好成績を収めることができず、 例年のように大会関係者にインパクトを与えることはできませんでした。 勝利しないマシンのアイデアは、他者には無意味なアイデアに見えるのです。
プロペラ推進の効果を関係者に認識してもらうためには、2003年の 「らぴすらずりIXx」を待たねばなりませんでした。
| 2001年10月 | 構想設計開始 |
| 2002年2月 | プロペラ推進の実験機作成および実験 |
| 2002年3月 | 心理障壁の実験機作成および実験 |
| 2002年4月 | 設計製作開始 |
| 2002年8月 | 第9回かわさきロボットコンテストに出場。2戦2敗 |
| 2002年10月 | 工大祭で展示 |
| 2003年5月 | 足回りブロックを 「らぴすらずりIXx」で再利用するためマシン解体 |