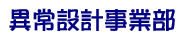
|
近接格闘戦を得意とするマシンが多く参加するかわさきロボット競技大会で、
最初に展開による超遠距離攻撃を実現させ、「異質」なマシンとして
着目されてきたのが「らぴすらずり」シリーズです。
このシリーズは1997年の 「らぴすらずり(初代)」から 2000年の「らぴすらずりVI」まで、 フィールドの端から端まで届く細く長いアームを特徴としてきました。 しかし今回は全く新しいコンセプトのマシンで大会に参加することになりました。 それが「保守的らぴすらずり」です。 |
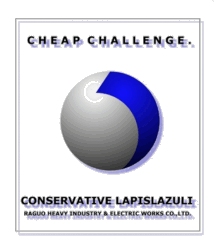
|
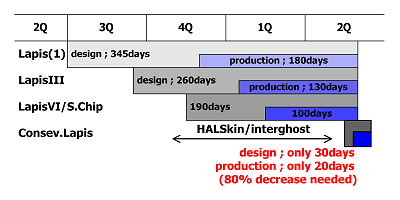
図1:らぴすらずりシリーズの設計製作期間の比較
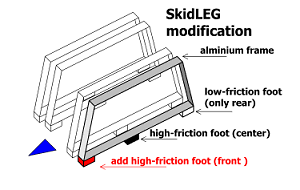
図2:SkidLEGの改造内容
また今まではチーム内で自作していたモータドライバも、 今回は実行委員会が支給して来るものをそのまま利用することで 製作にかかる時間を減らしました。 自作のモータドライバは軽量でカスタマイズも効くのですが、 デバッグにかかる時間がバカにならないこと、 今回の「保守的らぴすらずり」は自由度が少なく、 支給モータドライバで十分制御できる事を考慮に入れた判断です。
選んだのは「ファランクス」と言うアイデアです。 これは2000年大会終了直後にMeister君と一緒に考えたアイデアで、 幅1m程度に展開したマシン前面に槍を多数備え、 そのまま前進して相手の機構に槍を突き刺し、押し出すと言うものです。
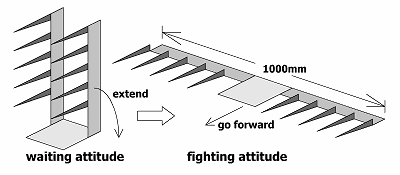
図3:「ファランクス」(オリジナルアイデア)
このアイデア実現のためには機動性が必要ではないため、 「らぴすらずりIII/VI」で使用した古い足回りでも十分であると考えました。 しかし、マシン全体を巨大に展開するのは機構が複雑になるので、 槍のみを斜めに展開することとしました。
また独自の展開機構は積まず、 マシンを前後させることでアームに振動を与えて展開することとして、 簡素化と軽量化を図りました。
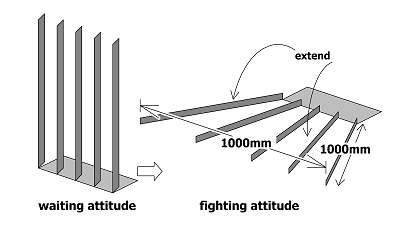
図4:「ファランクス」(修正版)
この「ファランクス」は長さが1000mm近くあるため、 ほとんどのマシンに対してアウトレンジ攻撃ができ、 また展開した槍の範囲が同じく幅1000mm程度あるため、 相手マシンが側面に回ることがほぼ不可能となりました。 また、材料は軽量化と強度確保のためにカーボンファイバーと グラスファイバーを交互に使い、白黒の槍ぶすまがマシンの外見上の特徴となりました。
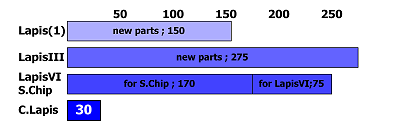
図5:新規製作部品数の比較
完成したマシンは以下のようなものになりました。
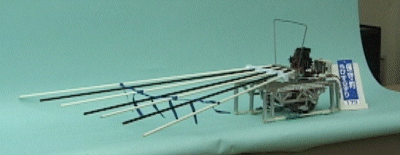
図6:保守的らぴすらずり(2001年9月14日撮影)
試合結果は以下のとおりです。
| 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 予選第1回戦 | LightBreakerII | 正面から押し合ったものの軽すぎて押し負ける。押さえ込み一本負け |
| 敗者復活1回戦 | なし | 不戦勝 |
| 敗者復活2回戦 | クレマチス | 相手とスタック30秒により水入り。 相手電装品が破壊されており修理できず。一本勝ち |
| 敗者復活3回戦 | 風鈴 | 相手とスタック30秒により水入り。水入り後押さえ込み一本負け |
| 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 第一試合 | ハチミツボーイ | 押さえ込み一本負け |
| 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 第一試合 | LightBreakerII | 相手と正面から押し合い押さえ込み一本負け |
一方で、ファランクスが相手の機構に入った場合は、 容易に相手を行動不能に陥れることが可能であるとも判明しました。 また広い正面は相手に対して側面を突く戦略を取らせませんでした。 これらの試合では全て正面で相手と戦闘を行なっています。
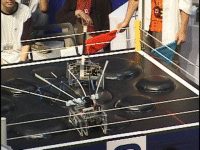 |
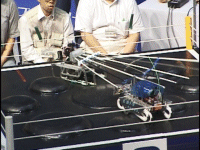 |
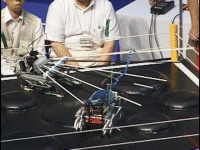 |
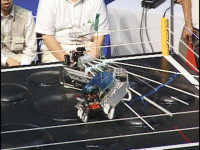 |
| 図7:試合風景(第8回かわさきロボット競技大会) | |
しかし、当初の目的であった 「(1)確実に出場できて(2)今まで誰もやったことがなくて(3)面白いマシン」の製作と、 「(a)出場し(b)ファランクスの効果を検証し(c)格闘戦の経験を積む」事は十分に達成できました。 また(b)ファランクスはその後 「らぴすらずりIX」 「らぴすらずりIXx」でも 応用され、 「らぴすらずりIXx」のベスト16入賞の原動力ともなりました。
更に結果が未知数のアイデアの検証は、 既存のアイデアの再検証と異なり、 設計製作が非常に楽しいことも判明しました。
趣味のマシン製作においては作っていて楽しい事が重要です。 作っていて楽しいことが、 結果としてマシンの設計製作を早く進めることにつながるからで、 また早く完成したマシンはデバッグに時間を長くかけることができ、 結果として強いマシンとなるからです。
今までの勝利・理念最優先のマシン設計を改め、 マシン設計製作の速さと製作時の楽しさに着目して 強いマシンを作るアプローチを 「Faster, Cheaper, Yukaier(より速く、より安く、より愉快に)」 方式と名づけ、今後のマシン製作の指針としていきます。
| 2000年10月 | 「保守的らぴすらずり(原型)」の開発決定 |
| 2000年11月 | 攻撃用アームを2+1の3本とする事を決定 |
| 2001年3月 | かわさき技術交流会に参加のため開発中断 |
| 2001年4月〜7月 | 「何か。(仮)」用シェル「HAL9000分の1」「interghost」作成のため開発中断 |
| 2001年8月上旬 | 「保守的らぴすらずり(原型)」の開発中止
「確実に参加できて、今まで誰もやったことがなくて、 面白いマシンを作る」をコンセプトにマシン設計をやり直し |
| 2001年8月下旬 | 「保守的アーム」の設計・製作完了 |
| 2001年9月15日 | 第8回かわさきロボット競技大会に参加 |
| 2001年11月中旬 | 神奈川工科大学バトルロボットトーナメントに参加 |
| 2001年11月下旬 | 東京理科大学ロボットウォーズに参加 |
| 2002年6月 | NHK取材時の運転で足機構を破損。以降保管状態 |