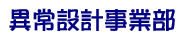
| 節の名称 | 節の長さ | 機構の動作 |
| 原動節DA | 1 |
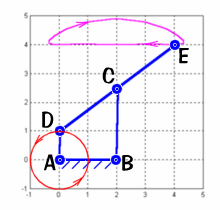
|
| 固定節AB | 2 | |
| 従動節BC | 2.5 | |
| 中間節CD | 2.5 | |
| 中間節の延長CE | 2.5 | |
| 図1:チェビシェフ機構 |
しかしこの時問題となるのは、 リンクを配置していくと5レイヤ以上の多層構造となる点でした。
青・水色・緑・ピンク・赤がそれぞれのレイヤを示しています。 図を見ると分かるように、 ピンク色で示されている原動節ADと緑色の固定節ABを同じ平面内に置く事は出来ません。 またADと赤色で示されている中間節CDEを同じ平面内に置く事も、 CDEとABを同じ平面内に置く事もできないため、 1つのチェビシェフリンクだけで3レイヤが必要である事がわかります。 左右のチェビシェフリンクでABだけは共有できるので、全体で5レイヤが必要です。
(クリックすると動きをアニメGIF-85Kbで見る事ができます。)
このような多層構造は通常、機械的なガタ・ゆるみを招き、 多くのスペースも必要とします。 これに対する従来の解決策はリンクを薄くし、 軸をしっかり止めるというものでした。
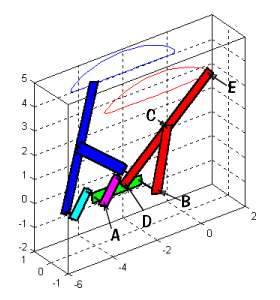
図2:一般的なチェビシェフリンクの使用法
原動節が360度回転する4節リンクを3レイヤ未満で構成する事は不可能なので、 これが最もレイヤ数の少ないチェビシェフリンク2個の配置方法のうちの一つとなります。
ではミラーチェビシェフ2(IIIc)を紹介しましょう。
レイヤ数の増加は、360°回転する原動節と固定節、
中間節を同一平面状に配置できないために発生するので、
このような配置をとるとレイヤ数の増加を招くことなく、
機構を配置する事が出来るのです。
異常設計事業部ではこの機構について検討した結果、
ミラーチェビシェフ2機構はわずか3レイヤで実現できる事が判明しました。
これが「ミラーチェビシェフ2(IIIc)機構」です。
またCDEやBC、あるいはABとBCのように互いに重なり合う事のないリンクは 同一平面内に配置する事ができることを考慮に入れました。 こうすると原動節周辺以外でのレイヤ数増加を抑える事ができます。 ミラーチェビシェフ2ではこれをリンクCDEとリンクBCで採用した結果、 3レイヤに2つのチェビシェフリンクを収めるという機構が実現したのです。
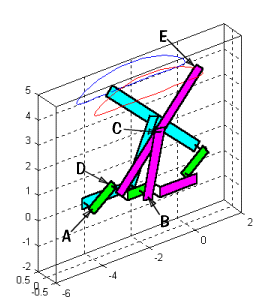
図3:ミラーチェビシェフ2機構
図3をクリックするとミラーチェビシェフ2機構のアニメGIF(85kb)を見る事ができます。
今回の「らぴすらずりIII」「しりこん・ちっぷ」ではミラーチェビシェフ2機構に、 それとは独立な平行リンクを付加して支持しました。 こうすると部品点数の増加を招くので、実際には頭の良い方法とは言えないのですが、 ミラーチェビシェフ2機構の動作を確認するためにこの形としています。
また2001年には「しろやぎ01」チームが本ページの資料をもとに、 ロボット技術研究会関係者以外として初めて本機構を採用しました。 異常設計事業部は今後もミラーチェビシェフ2の技術をオープンソースとすることで、 かわさきロボット競技大会の技術向上に努めます。