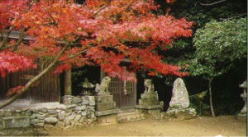|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中山王子~山口王子跡~川辺王子(和歌山始まり) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
<中山王子跡> 熊野古道の大阪と和歌山の境は、新旧の交通手段が並行して走っている。大阪から見て左が阪和高速道路で、中央が古道、そして右がJR阪和線である。現代の古道は、裏道であるにもかかわらず、交通量はかなり多い。 そんな古道の、大阪から和歌山に入って最初の王子は中山王子である。 和歌山市滝畑集落にあるこの王子は、看板だけが残る。 王子権現社と紀伊風土記に記されているが、JR阪和線路により消え、その痕跡すらない。 阪和線の山手を走る電車はほぼ熊野古道に沿って走っている。 古道を分断して走る線路を見ると、もっと別なルートはなかったかと、少し残念な気もする。 中山王子社前の掲示板 (熊野古道 中山王子社跡) 平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて、京都の貴族のあいだで熊野信仰が熱烈に広まり、熊野三山への参詣が盛んにおこなわれた。 中山王子社は、春日神社に合祀され、さらに明治42年山口の日吉神社に合併された。 熊野道行きの人々が、この雄ノ山峠を越えるのは大変であったことは想像に難くない。 現在は車の行き来が絶えず、道幅も狭いので歩いての峠越えは気をつける必要がある。道が狭いので、カメラを持って歩くと車と接触しそうになり、危険である。 古道は、ここからかなり険しい山坂を上っていくことになる。 四季に応じて、周辺の景色は美しく、いにしえの人々もしばし足をとめたであろう。 和泉山脈である。 車で布施屋貝塚線を和歌山へ進むと、阪和高速道路の下を並行して通る。 そして数分間登ると、雄の山峠頂上となる。 この付近から湯屋谷に至るまでの間、『ゴミを捨てるな』と書かれた看板が至る所で目に入る。 以前は粗大ゴミが捨てられて本当にひどかったのが、地元の方々の熱心なボランティアできれいになった。 住民運動の勝利である。 峠を下ってすぐに、峠の不動明王がある。お不動さんは、高さ30センチくらいで、大きくはないが精悍な顔立ちで、いかにも道行きの人々を守ってくれそうな感じである。 <春日神社> 滝畑は、昔をとどめるしっとりとしたいい佇まいの家が多い。日本人として、残しておきたい風景が続いている。 周囲の田畑にはトタンの囲いがしてある。何かと通りかかった人に聞くと、イノシシの被害がひどいのでそうしているとのこと。 それでもイノシシは乗り越え、作物を食いにやってくると言う。 そうした集落の奥に、氏神である春日神社が鎮座する。 その古い氏神は、何となく人の祈りを込めたらしい神々しさを感じる。 社の奥には、日本全国の「音無しの滝」の発祥といわれる小さな滝があり、役の行者もここで修行をしたと伝わる。 帝たちも熊野参詣の道すがらここにも立ち寄ったであろう。 平清盛も、熊野との縁を大切にしたらしく、紀伊名所図会には、 泉と紀伊の国のさかひなる雄の中山にて、 あしげなる馬に乗りたる者、 早馬とおぼしくて、 もみにもん出て来れり と清盛へ都よりの早馬がきた様子が記されている。 <峠の不動明王> 和歌山への坂の途中に不動明王を祀った小さな祠がある。 はるばる京都から熊野に詣でる人は、このお不動さんを見て和歌山が近いことを知っただろう。 お不動さんは祠の左端に着物を着せられていた。
<山口王子跡> 中山王子から、雄の山峠を越えると、紀伊路に入る。このあたりに関があった。白鳥の関という紀州民話の中にこの白鳥伝説が残されている。かなり古くからあるらしく、万葉集に、こんな歌が残されている。  吾が背子が あとふみもとめ 追いゆかば 紀の関守い 留めてむかも (あの方の後を追っかけて真土山まで行ったなら、紀伊の関所の番人は、引き留めるでしょうね) 神亀元年(724年)10月聖武天皇の玉津島行幸の際、お伴の中にある女性の恋人がいて、その人に送るために金村が女性から依頼されて作った歌である。 山口王子社前の掲示板 平安時代の終わりから鎌倉時代のはじめにかけて、京都の貴族のあいだで熊野信仰が非常に流行し、熊野三山への参詣が盛んにおこなわれた。 小野小町の墓は和歌山にあった 山口王子社は別名三橋王子とも呼ばれ、雄の山峠を越えて紀伊に向かってはじめの集落、湯屋谷の峠道にある。 明治時代まで社殿があり、明治末期に山口神社に合祀され、現在は社地跡が残るのみというが、場所の確定はできなかった。 戦時中に社地跡の松を伐採したことにより急速に荒廃したとのことである。 案内の看板があるあたりは、工場や店が並び昔日の面影はない。 この山口の集落は近世は宿駅として栄え、カギ状に続く道は独特の町並みを作っている。 宿泊して、博打に手を出し負けて帰れなくなり、この地に居着いた人もたくさんいるという。 裏道にはいると、時代劇の舞台のような古い屋敷に出会う。 また、ここには小野小町の墓がある。 小野小町は、熊野詣での帰りにこの里で病に倒れた。 小野寺というのがあったが今はなく、廃寺跡として史跡となっている。 小町のものといわれる墓が王子跡の近く、集落最初の家の上の墓地にあり、「小町堂」と書かれている。 さらに小野小町像が遍照寺にあるが、小町88歳の老いさらばえた姿のものである。 絶世の美女をこんな無様な木造とした意図をはかりかねる。 いくら美人でも老いてはこうなるという戒めにも思えるが・・・・・。 遍照寺の住職さんに聞くと、小野小町の墓はあちこちにあり、実在していたのは確かだが、資料が乏しく没年も定かでないとのことである。 これとよく似た小町像が、京都方面にあると聞く。その小町像 は100歳の時のものであるという。????
<川辺王子>  川辺王子と言われている所は2カ所あり、山口王子跡から南下して、県道粉河加太線を右折してJR紀伊駅方向に進む。紀伊上野バス停留所付近に山田商店が左側に見えてくるが、ここを左折する。 この道を南に降ると小さな社が見えてくる。 もう一つは、力侍神社(大正15年県委員の調査は、ここを川辺王子跡としている)であるが、和歌山市方面からだと国道24号線を川奈が団地方面に左折し、川永団地中央付近の、二澤病院とグラウンドに挟まれた道を行く。(国道から行くと右に二澤医院が見えてくる。その前の道を右折) 細い道を道なりに進むと、力侍神社に至るが、その途中に中村王子社跡がある。 川辺王子社跡の掲示板 (熊野古道 川辺王子社跡) この川辺王子社跡は、現在、和歌山市上野二三番地にあたる。  八王子社として祀られており、和歌山市内にある王子社跡のなかでは比較的古いおもかげを残しているところである。 京都の貴族による熊野詣は、平安時代の終わりから鎌倉時代のはじめごろ(十一世紀終~十三世紀初)に最も盛んにおこなわれたが、そのなかで建仁元年(一二〇一)の後鳥羽上皇熊野詣に随行した藤原定家の旅行日記である『御幸記』の十月八日の頃には「次に川辺 王子に参る」と誌されている。 川辺王子の位置については、いくつかの異なった考証があるが、この付近では熊野参詣道の道筋が時代によって多少変わったり、王子社の後身である神社が後世に移転したりしたためと考えられる。 次の王子社は、神波を経て南東約一.二キロの楠本にある中村王子である。 平成五年八月二日 和歌山市教育委員会 力侍神社の前の掲示板 (力侍神社本殿 摂社八王子神社本殿) 力侍神社はもと天手力男命(あめのたちからおのみこと)を祭神とし、力侍神社の  名前も手力男に由来している南から参道を通って社地に入るとと、向かって左側の社殿が本殿で、右側が摂社(合祀されて客分となった神社)八王子の社殿である。 名前も手力男に由来している南から参道を通って社地に入るとと、向かって左側の社殿が本殿で、右側が摂社(合祀されて客分となった神社)八王子の社殿である。両社ともはじめからこの場所に建てられていたのではなく、力侍神社はもと神波に(現社地の北西約700メートル)にあり、その後上野(現社地の北西約1キロ)の八王子社境内に移り、更に江戸時代のはじめ[寛永3年(1626)]に両社ともにこの地に移されたと伝えられる。 社殿は流造、一間社、檜皮葺きで正面と両側面には緑をめぐらし、擬宝珠高欄をおき、背面の見切に脇障子を構えている。身舎正面には引違いの格子戸を入れ、側面と背面には板張りの壁とする通常の形式である。 両社殿とも建立年代を示す史料はないが、各部分の様式や技法からみて一六世紀終わり頃に建立されたものと考えられる。 木鼻やかえる股などの彫刻も優れており、全体に建立の形態が良く保たれ、和歌山県内における桃山時代の神社建築の代表例のひとつとして貴重な資料である。 平成五年三月三十一日 和歌山県教育委員会 ▲ページトップに戻る
|
||||||||||||||||||||||||||||