
Vinyl Magic
VNMP 01
La terra dei grandi occhi/Calliope
新興ネオプログ・レーベル、ヴィニル・マジックの栄えあるデビュー楽団でもあったカリオペの1st。アルティ・エ・メスティエリ(Arti e Mestieri)の鍵盤奏者クロベラ(Beppe Crovella)を仕掛人とする90年代イタリアのマイナー・ブームはカリオペをもって始ったわけだが、本体は2作目であっさりコケタ。気を取り直して3作目は上出来だったがそこまで。その後は消息すら聞かない。
タイトルの『大きな目の大地』というのが何を指すか? などということは考えたくもないし興味もないが、若干暑苦しいものの重厚で華麗、クロベラ所有のヴィンテージ鍵盤類の音色も相まって、新しい息吹が感じられるセンスと品質を誇っている。テクニックも上々、専任歌手も野太いが歌は上手い部類だろう。歌詞はイタリア語。90年代風のギターが音圧たっぷりでメタルっぽいのは仕方がないが、曲展開もそれなりに複雑でポリリズムと変拍子を多用した息もつかせぬ展開の連続が醍醐味。それでいて、そこはかとなく香る叙情性あたりはイタリアの伝統か。中心人物は全曲を作る鍵盤のドロ(Rinaldo Doro)と思われ、微妙な転調を多用する巧みで斬新な鍵盤捌きを聞かせている。ラストは「Mellotronmania」なる小曲で幕を閉じるが、鍵盤奏者の思い入れがよく伝わるデビュー・アルバムだろう。

ReR
SHCD LC-02677
Acnalbasac noom/Slapp Happy
タイトル『Acnalbasac noom』を反転すると『Casablanca moon』になるように、遥かな昔、音源その弐でご案内したスラップ・ハピーの1stの原盤にあたる原曲集。英ヴァージンからのリリースが決まっていたが、シャッチョーサンの鶴の一声「もちっとポップにせんかい」でお蔵入りになった曰くつきの音源である。中身は曲順に至るまで構成はほぼ同じだが、トリオのバックで器楽演奏をこなしているのはドイツのファウストということで、アレンジがかなり異なるというか、アヴァン・ガルド。微妙にチープで素っ気なく、そしてもちろん、“壊れている”。どちらが良いかといえば、個人的には完成度高く、こなれてロマンティック、聴き易い『Casablanca moon』をとるが、ファウストとヘンリー・カウの間で揺れ動いた儚い蜃気楼にしてヤサグレポップは、30年以上の時空を越えてやはり味わい深いものを持っている。ダグマー・クラウゼの声もいやに生っぽい。
録音は73年、ファウスト(Faust)の拠点ヴュンメ(Wumme)、製作はやはりファウストのウヴェ・ネッテルベック(Uwe Nettelbeck)。原盤CDはリコメンディッドの発展解消系ReRからのリリースで、ボーナス4曲入り。
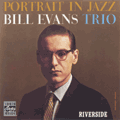
Riverside
OJCCD-088-2
Portrait in jazz/Bill Evans Trio
初出は1959年、1987年のリマスター。トリオ第一作。まぁ、敢えて語る必要のない超著名盤であり、古典であり歴史であり、ついでに遠い遠い我が青春時代の思ひ出(笑)。いろいろな意味で戦後日本社会の分岐点になった混沌かつ激動の世情のなかで、闘争と挫折の狭間でふと聞こえてきたピアノの音色は今も記憶の底に深く刻み込まれている。あまりにもクールで品行方正な音色は、仏の手の平でいきがっていた猿には多少高尚過ぎた部分も無きにしも非ずではあったが。分厚い盤厚のLPレコードの重さと珈琲の薫り。もうもうと紫煙が立ち込める地下のアジト(agitpunkt)。今振り返ってみれば、滑稽なほど直情径行な時代背景には既に虚妄と頽廃の兆しがひっそりと忍び寄っていた。
全9曲+ボーナス2曲。最も有名なのは「枯葉(Autumn Leaves)」だが、個人的にラストの「Blue in Green」が気に入っている。木漏れ日を透かし見た空の青? 鈍緑の氷河に貫入したセルリアンブルー? 未熟のなかのエロス? 新鮮な生気のなかの憂鬱? クレジットはマイルズ・デイヴィズ(Miles Davis)となっているが、マイルズがモード・スタイルを完成させたといわれる名盤『Kind of Blue』にも同曲が含まれている。後にクレジットで揉めた(結果的には負けたのだろう)らしいが、共作あるいはエヴァンズの作曲といわれている。
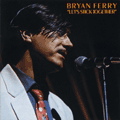
東芝EMI
VJCP-3335
Let's stick together/Ferry, Bryan
三作目のソロアルバム。ロクシー・ミュージック中断期のソロというせいか、本作は1stアルバムの録り直しが半分ほどを占め、残りはシングルB面、及びEPからの収録となっている。全11曲。73年から76年にかけてのバラバラ録音のため、キャストは一定しない。非常に濃厚な趣味性を漂わせながらも、フェリィの個性際立つ歌曲はあくまでもポップであろうとするあたりは潔い。歌唱力やアレンジの才もプロとして申し分ないだろう。
佳曲がぎっしりと詰まった1stからの引用もより簡潔にこなれ、リアレンジ、演奏力の向上も含め、エッセンスが華麗に抽出されたものになっている。「Sea Breezes」の「But even angels there make the same mistakes in love」のくだりに込められた生々しくも切ない情感、あるいは、ロクシーの曲でも最も気に入っているものの一つである「2HB(=To Humphrey Bogart)」で語られる名台詞「Here's looking at you, kid」の儚げさ。これを「君の瞳に乾杯」と訳したのは、映画「カサブランカ(Casablanca:1942、米)」の翻訳者であるが、まさに世紀の名訳だな。映画を見たのは遥かな昔だが、そのシーンは非常に印象深く記憶に刻まれていて、「2HB」とセットで再生される。

Mute 9 61460-2
Suspiria/Miranda Sex Garden
古楽声楽ユニット、ミランダ・セックス・ガーデン93年の三作目。古声楽と弦楽器を奏でる5人の女性とインダストリアル・ノイズ風、男5人のバンドのカップリング。全11曲はその10人から適宜選抜された数名によって演じられるという形をとっているようだ。路線的にはア・カペラからバンド・サウンドへの遷移期である前作の『Iris』を更に発展させたもの。バンド・サウンドとアンビエント声楽、プログ風の曲構成、展開と挿入、あるいは弦楽重奏を交互に、あるいは重層に組み合わせ、静謐な空間に潜む深遠な闇をおぼろげに照らすかの如く幽玄を垣間見せる手法は完成の域にあるだろう。器楽演奏部分のリズムがワンパターンに陥る気配は感じられるが、弦楽の緊迫感やしなやかさ、天上の声楽は補って余りある。
カバーが2曲。そのうち、ジャズ・スタンダードとしても名演が目白押しの、ミュージカル『Babes in Arms』(1937)の曲「My Funny Valentine」を歌うあまり悩ましくないすっきりとした声には印象を新たにさせられた。ちなみにタイトルは他の曲目や歌詞から類推するに、ダリオ・アルジェントのイタリア映画『Suspiria(邦題:サスペリア)』のことだろう。

Repertoire
PMS 7044-WP
Here we are/Jane
北ドイツ、ハノーファー出、4拍子系のブルーズ・ロックとして1970年デビューのジェインの2ndアルバム。前作に比して遥かに鍵盤の比重が上がり、ストリング・シンセ、オルガンの音圧も重厚さを増した。前作にクレジットされていた歌手の名が消え、ドラムのペーター・パンカがボーカル兼任ということでどうしても歌が弱いが、構成力も弱いからまぁ良いバランスか。湿度の高いズブズブの叙情ど演歌になってしまうあたりはどう足掻いても持って生まれた出自だろうが、野暮ったさが若干薄れ、曲調にすっきりとした透明感が感じられるようになったり、ゲストで女性コーラスを入れたりと工夫の跡は見て取れる。B級扱いされることが多いが、ご当地では日本で評価が高いアングラ系より高評価で人気もあったらしい。メロディの泣きが勘所だな。個人的にも本作に収録の「Out in the rain」が気に入っている。全英詩。
レペルトアールの再発盤にはボーナスとして、前作に収められていた「Daytime」「Hangman」のシングル・ヴァージョン他計4曲付。

Apache
2292-44214-2
Le tour de France 88/Gall, France
88年の自国公演実況録音盤。企画・衣装はベルジェ(Michel Berger)、音楽コーディネイトはトップ(Jannick Top)という布陣で仕切られたようだ。かなり広い会場での録音のようで、音像が拡散気味だがちょっとクールな空気感みたいな雰囲気が良く出ていて、実は狙っていたのかもしれない。全11曲、CD限界のトータル73:54とヴォリュームもたっぷり。
日本では60年代のアイドル歌手としてしか評価されていないが、ベルジェと組んで新機軸を打ち出せた80年代こそがそのキャリアの真骨頂だろう。ジャズ・スタンダードなんぞも取り入れたりするが、やっぱり「Résiste」「Babacar」「Ella, elle l'a」あたりのアップテンポな曲が決まるし上手い。しっとりと歌う「Evidemment」なんぞも良いが、基本はアンサンブルで歌う人だと考える。曲はアレンジを変えてかなりの長尺ヴァージョンになっているが、やはり特筆すべきはお姉ちゃんポップスにはありえないベースだろう。Topの開放弦弾きまくるゴリゴリ・ビンビン・ドロドロの地鳴りベースが響くこと。普通に考えればかなり異様な音の組み立てなわけだが、もう耳に慣れてしまったな。ガルの声にはTopのベースが必要だ。

Decca
475 465-2
Concertos, Tone Poems, Organ Symphony/Saint-Saëns //Pascal Rogé, Charles Dutoit etc
フランス近代音楽の中で印象主義の台頭に組せず、あくまでロマン主義を貫いた孤高の知性にして、新進のドビュッシーやミヨーと対立した嫌味なオヤジ、シャルル・カミーユ・サン=サーンス(Charles Camille Saint-Saëns:1835-1921)の協奏曲を中心に管弦楽曲を集めた5枚組CD。一応、敬愛するフォーレの師というわけで、ドイツ的な構築主義の範疇にありながらもフランス的な流麗なメロディや花やかさは捨てがたい魅力を放っているだろう。場合によっては流れすぎてしまうフォーレとは明らかに異なる確固たる基盤が垣間見えてしまうことが古く固い頑固親父ではあるが、情感に流れない安定した気持ちの良さは品格ある心地良さを醸成している。教会オルガン奏者としても卓越した腕を発揮したようで、「交響曲3番」の第二楽章後半でも圧倒的なオルガンが響き渡る。
ピアノ・コンチェルトは1から5まで全曲。3は初期版と完成版の両方を収録。ピアノはパスカル・ロジェ(Pascal Rogé)と申し分ない。ヴァイオリン・コンチェルトはチョン・キョンファ(Chung Kyung-wha)の演奏で1と3、チェロ・コンが1と2、交響曲の3にロンド・カプリチョーソ、著名な「動物の謝肉祭」全曲、「ダンス・マカブル(死の舞踏:原曲は交響詩)」、「ヘラクレスの青年時代」「オンフェールの糸車」「英雄行進曲」と主だった管弦楽曲が収録されている。オケはばらばらだがデュトワを筆頭にメジャーどころ。演奏の質は極めて良い。70年代から80年代に掛けての録音だが音質も申し分ない。
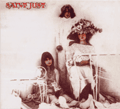
Akarma AK1045
Saint Just/Saint Just
73年初出、80年代末に一度CD化されていたと思ったが、長らく絶版状態が続いて一時は法外なプレミアムが付いていたサン・ジュストの1stアルバム。もちろん定価以上の中古なんぞ馬鹿馬鹿しくて検討の余地すらないが、欧州盤の場合は商業的価値以外の“価値”が確立されているせいか、サプライ側も(再発専門レーベルが乱立するくらい)再発には積極的で、市場からモノが消えた頃にはリマスターのおまけが付いて復刻するものである。
バンド編成になった2nd『湖畔の家』に比べると遥かにサイケ・フォーク寄りで繊細にしてメランコリック。曲調も複雑で斬新かつ前衛的に展開する一方、ピアノバックの詠嘆に近いソプラノ歌唱は叙情と耽美を余すところなく表現し切る。ソレンティのカントは声量のあるタイプではないが、独特の節回しであくまで透明に、清冽に、そして若干のエキセントリックさをもって迫ってくる。原則はソレンティに加え、弦楽器+管楽器のトリオ編成だが、ゲストでところどころ鍵盤+パーカッションも入ってボコボコした70年代イタリア独特のタイトなリズムから祭り太鼓まで、平板にならない多様な工夫を聞くことができる。
タイトル『サン・ジュスト』は本作ラストの曲名であり、歌詞を読む限り、フランス革命の革命家を指すようだ。虚妄の残影のような儚さを湛えた秀逸なスリーヴ・デザインは今見ても溜息が出るほど素晴らしい。

MCA
MCD 77000
Libera/Ruggiero, Antonella
70年代~80年代、その超絶歌唱力で一世を風靡したマティア・バザールの初代歌姫アントネッラ・ルッジェーロ。ベースのあんちゃんと駆け落ちしたと聞いていたが、実はロベルト・コロンボ(Roberto Colombo:一時期PFMにして業界の重鎮)とできていた? 駆け落ちしたベースのあんちゃんが病死して乗り換えた? のかどうかはよく知らないが、コロンボのサポートで要は独立したらしい。コロンボとの共作ともいえるその1stソロ・アルバム。
マティア・バザール(MB)も時代の変遷に合わせて器用に音楽性を変えてきた楽団だが、基本はロック+歌ものにあったのはそれなりの構成員から見ても理解し易い。そこを出てデビュー作として新たに提示されたものは、MBではできなかった、どちらかというとエスニック色が強いワールド・ミュージックになっている。しかし、まぁ、なんというべきか。歌唱はもちろん、曲、歌詞、アレンジからスリーヴ・デザイン、総天然色の内絵の数々に至るまで、極めて高質にして文句の付け所はない。完璧。素晴らしい。参った。平伏します。強いて言えばふっくらとした優しさが際立ち、ちょっと大人しいが欠点ではない。プロデュース、作曲はコロンボ、『Libera』はイタリア人が大好きな「自由な、暇な」を意味する形容詞女性形。
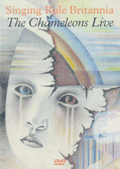
cherryred
CRDVD47
Singing Rules Britannia/The Chameleons
1985年のライブとPVの2本立てDVD。計95分。カメレオンズは80年代初頭、北部マンチェスター出のポストパンク・ギター・ポップ、あるいはネオ・サイケ。いつごろまで続いたのかは知らない(2000年代に復活した模様)が、質に反比例して終始マイナーであり続けた、評価に恵まれない楽団であった。鬱々、あるいは黙々とアクション皆無で弾き続ける二人のギターと、エモーショナルでメロディアスなベース+歌の組み合わせが妙に構築的で透明感溢れるリリシズムを発散していたものだ。大雑把な印象としては同時代のフェルト(Felt)や一時期のコクトー・ツインズ(Cocteau Twins)と被るものが感じられるが、彼らは中期のビートルズっぽい知的で偏屈なリリシズムを狙っていたのかもしれない。決して上手いとはいえない歌のあんちゃんであるが、歌詞はナイーブで繊細、閉塞的な時代状況の中での孤独な労働者階級の悲哀と諦観に満ちている。
よくあるパターンなのだろうが、聴衆はあまりノリがよくない。あんちゃんの前だけぴょんぴょんしているが、他はいたって冷静である。あんちゃんは歌の合間に500mlくらいの紙パックの葡萄ジュース(中身は知らん)で喉を潤す。ステージ真正面でステージの框に方杖をついて聴いている女の子に「飲むかい?」とジュースをあげるんだが、女の子は困った顔をして隣の友達に紙パックを手渡してその子に飲ませるんだわ。飲み終わった子からパックを受け取って、歌のあんちゃんに「ありがとう」って残りを返すのだが、なんか受けた(笑)。
DVDはNTSC、リージョン・フリー。
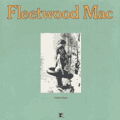
Reprise
7599-27458-2
Future games/Fleetwood Mac
遷移期の佳作。イギリスの重厚ブルーズ楽団だったFMが、前作から加わったクリスティン・マックヴィーにアメリカ人ボブ・ウェルチを加え、生き残りにしてこの時点では頭一つ抜け出ていたフロント・マン、ダニエル・カーワンのフォーク色と相まって、地味ではあるが繊細で、軽妙かつ透明感溢れるポップに生まれ変わった。次作『枯木』のジャケの世界から彷徨い出たかのような、冒頭カーワン作の夢見る儚いフォークソングにはぶっ飛んだものだ。カーワン、ウェルチ、女マックヴィーの三者三様の曲作りは、アルバムとしての統一感よりも敢えて趣に富んだものを並べ変化を際立たせる狙いがあったように思える。ウェルチのタイトル作のメロディアスな可憐さや、マクヴィーの渋く決めたコーラスワークに顕著なように、この時期のFMは青みがかった浅葱色のイメージなのだな。
しかし、何故カーワンの写真だけがペンギンに差し替えられているのだろう?

LaserLight
15 688
Meditation, Classical Relaxation Vol.3/Various
LaserLightはアメリカの廉価盤メーカー。300円くらいで買ったよくあるクラシック・オムニバス。タイトルを見ればわかる通り、権利切れの耳に馴染んだ音源を適当に組み合わせただけの、素面なら絶対に食指を惹かれない内容である。中身もアルビノーニの「アダージョ」、ドヴォルザーク(ドヴォジャク)の「ロマンス」、グリークの「ペール・ギュント」にベートーフェンのやっぱり「ロマンス」、シューベルトは「ロザムンド」の抜粋、ラストはマーラーは交響曲5番の一部抜粋「アダージェット」と、あまりにも“如何にもセレブ”で御座いまっせ的な編集盤である。
が、しかし…というのがお約束。ジュエルケースをひっくり返して、どこのイージー・リスニング楽団が演奏してんのかいな? と、しょぼつく目を凝らすとぎょっとする。寄せ集めだから演者は曲ごとに違うのだが、冒頭の「アダージョ」で目が点になった。およよ。演者はドレスデン・フィル、指揮はヘルベルト・ケーゲル(Herbert Kegel:1920-1990)。ケーゲルは旧D.D.R.の指揮者。冷厳実直、ぴりぴりと張り詰めたような空気感で古典から現代音楽までをこなした極めてドイツ的な名匠であるも、D.D.R.崩壊後の混乱期にピストル自殺を遂げた人であった。
本来、アルビノーニ(正確には別人の手が入っている)の「アダージョ」は明るいイタリアの陽光のもとで奏でられることが最も似合う優美で心地良い楽曲であるが、そこはそれ、やっぱりケーゲルである。彼による悲痛で絶望感に満ちた、暗い透明感に身の置き所がないような、レクイエムさながらの深刻な「アダージョ」はこれまた類例を見ない白眉の出来である。夏本番の陽光に目が眩みながら聴くケーゲルは情動の二律背反を際立たせ、これまた鮮烈にして魅惑的である。
ちなみに他の曲もそれなりの音源でけっこう聴ける。

4AD
DAD 2513 CD
Lullabies to Violaine Volume 1/Cocteau Twins
既に長きに渡って入手不可能だった待望のシングル・12吋EP集リマスター版。2005年に1万部限定リリースされた4枚組を2分割したもの。第一集ということで初期から中期、1982~1990年の全17+15曲が2CDに収められている。インディ系であったCTは基本的にミニ・アルバム風のマキシ・シングルやEPをアルバム・リリースに先駆けて(1stだけアルバムが先)多発しており、そのすべてがことごとくアルバム収録ヴァージョンと異なる内容で、かつ優れてCTらしさが彷彿しているという難儀なことをしでかしてくれていたわけだが、これと第二集を揃えれば一気に片が付くという内容になっている。タイトル通り、「Lullabies」が82年のデビュー・シングル、「Violaine」が96年の最後のシングル。曲目は完全に発売順に並べられ、暗鬱にたなびくモノクロームがやがて煌びやかな光彩を加え、鮮やかに、花やかに匂い立つように開花する様を余すところなく描いている。
やはり個人的には最初のピーク、84年の「The Spangle Maker」や85年の「Aikea-Guinea」あたりが非常に思い出深い。前者は深い霧の夜の海から打ち上げられた人魚のぬめり、後者は薄闇に弾け踊る光彩と至高の高揚をイメージさせる極めて視覚的な楽曲である。歌も演奏も技量的にはお世辞にも評価し難いが、機材的、音響的アプローチを駆使し、素人っぽさを逆手に取ったようなセンスで構築された音楽は一つの時代を風靡したといってもよいだろう。

EMI Classics
7243 5 75437 2 9
2002
L'œuvre pour piano seul/Ravel //François, Samson
大御所サンソン・フランソワが弾くラヴェル・ソロ・ピアノ曲の2CD作品集。初期作品と連弾曲である「マ・メール・ロワ」を除くほぼ全てのピアノ曲が収められている。67年の録音と古いが、元の録音が良かったのだろう。リマスタリングが施された音質は現代ものと比べても遜色はない。重く閉ざされた鎧戸の隙間から回折する光のように優雅で繊細な小品「亡き王女のためのパヴァーヌ」、師フォーレに献呈され、印象主義の幕開けとなった「水の戯れ」、ベルトラン(Louis Aloysius Bertrand:1807-1841)の散文詩をモチーフにした「夜のガスパール」の超絶技巧、組曲「クープランの墓」の複雑な多様性、斬新で諧謔的な「古風なメヌエット」まで、同国人フランソワの解釈と情感が見事に嵌った定番中の定番のリマスター再発盤。
安直な比喩だが、ドビュッシーをマネやゴッホに例えるならば、ラヴェルはスーラや後のクレーを思わせる。量子的なまでの解析と精緻に組み上げられた洗練の美学は予定調和を遥かに超えた幻惑を構築する。正確に効果を計算して狙って作っているが、その狙いが聞く側の容量をことごとく超えてしまうのがラヴェルのラヴェルたる所以である。
鬱蒼と繁ったひんやりとした木陰から、炎天下の夏の庭で踊る溢れんばかりの光と色彩を垣間見るような鮮烈、一歩引いた隔絶感と静謐な空気感、艶やかさと予断を許さないカット・バック、もはや抜け出すことのできない、くらくらするような盛夏の陶酔。惹かれることの不可逆的な幸せ。

Manikin
MRCD 7048
Friendship/Ash Ra Tempel
テンペル名義、30年ぶりくらいの復活作。テンペルが意味するものはマヌエル・グトシンク(Manuel Göttsching)+クラウス・シュルツェ(Klaus Schulze)で残念ながらエンケ(Hartmut Enke)の名はないようだ。「Reunion 30:40」、次作ライブで拡大演奏される「Pikant 21:40」、「Friendship 26:30」の計80分近い全3曲。マシンとギターによる滔々たるエレクトロ・アンビエント・テクノ。もちろん全曲インスト。
元太鼓奏者のシュルツェらしくリズム・パターンがかなり前に出ているので今風の趣が強いが、迎合や媚のないシンプルなコンセプトに忠実で、クールで冷やっこい。あるいは極めてドイツ的で禁欲的な構築と実践。珍しいことに曲調はほぼ通しで短調で、さながら現代のレクイエムのように沈痛で哀切だ。通奏低音のように全体を包み柔らかく響くシンセの音も青一色の透き通った深い水底を思わせる。過去の延長というよりはノイのローター(Michael Rother)の近作に近いものを感ずる。