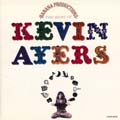
東芝EMI
TOCP-6739
Banana productions/Kevin Ayers
1969~1978年の初期のコンピレイション盤。ケヴィン・エヤーズ(Kevin Ayers)は当時から鬼才だの天才だのといった称号が貼り付いており、70年代前半、レコードを欲しいなと思っても既に時期遅く廃盤だったり、とんでもないプレミアが付いた輸入盤しか出回っておらず、初期の名作群を聴くことができたのは70年代末期になってからだったと記憶している。現在は、正規スタジオ盤以外にも、ライブや未発表テイクやら、ありとあらゆる音源が怒濤のようにリリースされている。しかし、ソフト・マシン(Soft Machine)にしても、ホール・ワールド(Whole World)にしてもこの頃は凄いメンバーだ。後のカンタベリィ系の元祖(まぁ、本人にとっちゃ迷惑以外の何物でもないだろうが)でありながら、はみ出し組としての片鱗を感じさせる。マイク・オールドフィールドもホール・ワールドでベースなりギター弾いてるけど子供の頃からなんて上手いのだろう。

Statik CDST22
What does anything mean? basically/Chameleons
スコットランド・インヴァネスで録音されたカメレオンズの2ndアルバムであるが、構成員は北イングランドの工業都市マンチェスター出身の四人組。一般的には80年代ネオ・サイケ/ギター・ポップとしての評価が高いが、一曲目「Silence, Sea and sky」の怒濤のメロトロン風ストリング・シンセとそれに続く「Perfume Garden」のギターのリフに打ちのめされた。柔らか目の奥行きのあるボーカルと静と動を司る繊細でクールなツイン・ギターが印象的で、滴るほどの抒情性に富んだ透明感のある音作りに惚れた。色の薄いスコッチ・ウイスキーに氷河の氷を浮べて飲むような……白と青と緑の世界。前作に比して遥かにダイナミックに、より複雑な展開を内包しながらも構築的で、尚且つ抒情的に迫るメロディ・センスが秀逸この上ない。
趣が異なる最後の2曲は81年録音の古い未発表ボーナス。ガチャガチャ・ドコドコしていてまるでU2のようだな、と思ったらプロデューサが同じリリーホワイトだった。さも在りなん。

Beggars Banquet
Bega 45 CD
Burning from the inside/Bauhaus
バウハウスはワイマールからナチスの時代のドイツの美術・建築学校で、近代デザイン関連においてはそれなりの功績をあげたところ。学校は新古典主義を標榜するナチス台頭後、退廃芸術の烙印を押され閉鎖に追込まれるが、こちらのバウハウスもスタジオ盤4作目である本作を最後に一旦崩壊(2008年に正式にラスト・アルバムをリリース)した。既にフロントであるピーター・マーフィ(Peter Murphy)が一部にしか参加しておらず、歌の比重が下がった分、より虚無的ではあるが民俗色やエスニック色などさまざまな要素が乱入し、掠れていくロック色とは裏腹に、無機的なポスト・パンクの残影とどうしようもない刹那感が渾然一体となったごった煮の様相を呈している。全10曲にシングル等のボーナスが4曲追加。クールで端正な構造主義への道半端、結晶になり損ねたポスト・パンクのひとつの終焉。

Permanent/Joy Division
アルバム未収録のシングル曲に、95年ヴァージョンの「Love Will Tear Us Apart」他、微妙に明るめの曲を加えた追悼アルバムなのか、あるいはアメリカ用のベスト盤か? 既に88年の『Substance』がシングル集であるが、音源は新たにリマスターされている模様。没後15年も経ってこんなものを出すと私みたいなのが引っ掛るという思惑もあったことだろう。 。根暗の権化のようなポストパンクの中でも殊更這い蹲るように暗かったのがジョイ・ディヴィジョン(以下JD)。神経症間違いなしというべきか、真面目に“病院いった方がいいよ”と言ってあげたくなるほど それにしても相変わらずの影響力というか、すっかり神格化された存在になってしまいました。
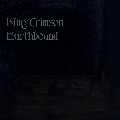
Earthbound/King Crimson
イギリス本国では繋ぎとはいえ正規のLPとしてリリースされたものたが、CD化はされていない(後注;2002年にとうとう出た)。カセットで隠し録りされたライブでブートレグ並に音が悪いし、ほとんどの曲がその場でできちゃったような、やたら重量感に溢れた即興演奏だからフリップ御大としては躊躇したのだろう。実際適当にブルーズ(!)しておるわけで、ブルーズが弾けない(といわれている)御大はステージ上で困り果てていたとか。逆に個人的にはその重量感溢れるブルーズとLP B面の未発表曲が面白い。「Groon」で聴ける、こういう病的なVCS3シンセサイズド・ドラムをその後やった、あるいはやってる人はいない(後注;伊デリリウムがやっていた)から荒っぽいけどおもしろいです。フリップ御大のディストーション掛けまくりの鳴りだしたら止らないギターも凄い。そしてやはり「ペオリア(Peoria;地名)」に「アースバウンド」でしょう。何の衒いもなくサックスをブイブイ吹くメル・コリンズの芸人根性とどん臭くて重いボズ・バレルのベースが絶品。
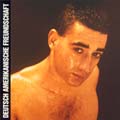
Alles ist gut/Deutsch Amerikanische Freundschaft
う~む、独米友好の『万事良好』です。汗と激しい息遣いと吐息でいっぱいの肉弾ミニマル・エレポップ(っていうのかな? こういうの)。これは英ヴァージンに移籍した3作目。新ドイツ波の立役者にして黒子:コニー・プランクが最も期待を賭けたユニットでもあるわけだが、既にディジタルというものの誤謬には気づいていたにちがいない。初期の二作に比べ結構かわいいし、中身は顰蹙ものだが外面はお花畑風テクノポップで聴き易いかもしれない。「盗賊と王子様」とか「拝ムッソリーニ」とか好みですが、飛び散る汗と男くさい臭いでムンムンしております。
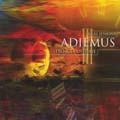
Dances of time/Adiemus3・Karl Jenkins
ようやく3と4を手に入れました。テーマも少し変って随分と明るめになってきました。今回は世界各地の舞踏がテーマです。しかし、アディエマスの日本盤ってなんでデザイン違うんだろ。イルカ(2だから2匹いるのね)の水中写真になってるんだなぁ、これが。さすがに面倒なのかこの3作目は同じジャケになってますが(後注;実は相変わらず違うバージョンが存在する。おまけにやっぱりイルカ。)、イルカ3匹みたいなデザインだったら絶対手を出さないだろうみたいな感じ。危ない危ない。

Vers demain/Mona Lisa
これはオリジナルの五作目。その直後ぽしゃったが、90年代後半に復活したらしい。98年に新作が出て、2000年のプログフェストにもバンコやケンソーと共に出演した模様。前作に比して若干明るめのビート感が目立つ曲が増えて、フランス語のポンポン跳ねまわるような感じが楽しい。前作に比べ軽いとかポップとか、過去のシリアスなテアトラルを期待した人には評判が悪かったが、個人的には非常に気に入っている一枚。(要するにポップなのが好きなのだろう) ドミニク・ル・グネ(Dominique Le Guennec;復活版モナ・リザでは復活)は前作をもって既にリタイアしているのだが、シニカルな中身と妙なドライブ感が絶妙に楽しい。「Rétrospective」などおっかないものもあるし。タイトルは『明日に向かって』という意味ですが明日は無かったんだねぇ。
「Rétrospective(邂逅)」
四方を壁に囲まれた
女中部屋
とても安全とはいえない隠れ場所
手に入れたガスボンベの
ずっしりとした重さが怖い
誰のために? 自分のために! 何のために?
私に残されているのは……
四面の壁に囲まれた
女中部屋
たったひとつののぞき窓から
片目だけを覗かせると
涙が流れるのに気づく
誰のために? 自分のために! 何のために?
私に残されているのは一丁のピストル
いつも同じように
その部屋で愛欲に耽る
母とその愛人
僕の父を殺した
本当に魅力的なカップル
姦通者へ一撃だ
手にピストルを握り締め
弾倉には一発の弾丸
四面の壁に囲まれた
女中部屋
……
さあ、マリア様とはもうお別れだ
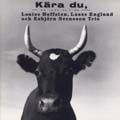
Kära du,/L.L.E Trio
Louise Hoffsten,Lasse Englund och Esbjörn Svensson Trioが正式な名前。(かな? 読めねぇよ)3人の名前を並べて(後注;並べたわけではなさそう)最後にトリオだそうで、まぁ、わかりやすいこと。でも5人じゃん。というのは当たらずとも遠からずでもなくて、エスビョルン・スヴェンソン・トリオ(Esbjörn Svensson Trio;略してE.S.Tという新進著名ジャズトリオらしい)に頭の二名が加わった形ということらしい。ディスカウントのワゴンセールで目つぶって買ってるんで勘弁してくださいな。中身は星の数ほどある北欧系コンテンポラリ・トラッド+ジャズの一つのように思えるが、今一つ正体不明です。民謡のようだしフォークのようだしポップの気もあるし、ロックっぽいのもあるし、なんでもありだなこりゃ。牧場の牛追い唄か。女の人がかすれた高い声で歌っています。

Merci/Magma
一応、マグマ名義正規スタジオ盤としては20世紀ラストにあたるもの。2000年ぐらいに復活していますが、まだ新盤は出ていないように記憶している。昔のような呪術的な要素が薄れて英語やフランス語で歌っている曲もあってびっくりです。もちろんコバイア語のものもありますが、この時点で既に以前のマグマとは異なった、むしろ以降の『奉納』シリーズに近い感触を受けます。喇叭が復活したけれど、部厚い音で強迫的にずんずん迫って来るようなところは感じません。大人になったのかな? かつての奇声歌手クラウス・ブラスキーズが一曲だけ歌ってますが、張りのなさがちょっと寂しい。
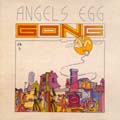
Angel's egg/Gong
最初期ソフトマシンのギター奏者、オーストラリア人ヒッピーのデヴィッド・アレンがフランスで主宰するゴングの絶頂期、「Radio gnome invisible part 2」と銘打たれた“見えない電波妖精”三部作の第二部『天使の卵』。タイトルからもわかるように、まぁ、内容を詮索し理解しようとすることは空しい。とにかく“電波”だから。めちゃめちゃ勝手に自分達だけで楽しくやってます。前作のコミック・ロック色に、いかれまくったアイディアとスーパーテクによる浮遊感が加わり、 はすばらしい。三部作の中でもちょっとエレガントな雰囲気と儚げな空気感が優しいのですが、フランス語のほわんとした語感と場末風のワルツがいいなぁ。
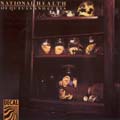
Of queues and cures/National Health
イングランドの中産階級ジャズ・ロックであるカンタベリィ音楽を代表するナショナル・ヘルスの2作目。ベースがニール・マレイ()からジョン・グリーヴズ(John Greaves:Henry Cow ⇒ Gilgamesh)に交代。相変わらず出入りが激しい。“National Health”はイングランドの医療制度の総称で狭義には国民健康保険という意味にして、恐らくは極めて冷笑的で皮肉たっぷりのウィットとユーモア、或いは鼻持ちならない嫌味。回顧的な新保守主義と吹き荒れるパンクの嵐の中で、階級としての選択肢は限られていただろうが、精一杯の矜持を保ちながら更なる高みに登り詰めた王道の最高傑作といっても過言ではないアルバム。
中身は所謂カンタベリィ系の正道そのもの。驚異的な演奏技術と作曲能力に支えられた、軽やかにスピード感のある超絶変拍子、意外や意外に磨きぬかれたメロディ、くるくると跳ね回る摩訶不思議な転調、緩急と動静がぎりぎりの限界でせめぎ合うアヴァン・ガルドからポップまで変幻自在にして軽妙洒脱。キャラヴァン(Jimmy Hastings)のフルート、カウ(Georgie Bornちゃん)のチェロ等ゲストの管弦楽器も、カンタベリィとしては格段に多彩にして変化に富んだアンサンブルに花を添えている。
しかしながら今作の最大の特徴は、スチュワート(Dave Stewart)、ミラー(Phil Miller)、パイル(Pip Pyle)といういつものケント・カンタベリィ人脈に、異質にして唯一のグリーヴズ@ケンブリッジの自由で創意に溢れたベースが、演奏のみならず作曲でも特段の貢献を成していることだろう。饒舌な即興に走りがちなベース演奏は浮き上り気味の部分も含めスリリングに異質で極めて興味深い。グリーヴズが歌うボーカル・ナンバーも枯れた男臭さを漂わせながらもcrooningに相応しい黄昏た感傷が聴きどころ。ヘタウマなグリーヴズならではの旨味が横溢している。

Brotherhood/New Order
合金のサンプル帳みたいなあまりにも素っ気無いスリーブデザイン。いぶし銀ではなくてチタンジンクの輝き、というか半光沢なのか。この鼠青はドイツのラインツィンクが特許を持っている合金で、高純度亜鉛に微量のチタンや銅、アルミニウムを加えたチタン亜鉛合金で、パティナ層という防蝕を兼ねた表面酸化皮膜はブルーグレーに発色する。主として屋根材に用いられるが、それなりに高価。 で、それが『少年時代』とどう関わるのかは至って不詳だが、新生ニュー・オーダーの2作目。ニュー・オーダーが星の数ほどある単なる踊り音楽にならなかったのは、やっぱりジョイ・ディビジョン(Joy Division)の重くて暗い影を背負っているからだと思うけど、この頃からはハイテクも板についてこなれた熟練を漂わせております。前作で少しだけ見られたシーケンサによるダンス・ビートも自然で味のあるものになって来た。

Platetectonic
AHAON-077
Electrique plummagram/Poi Dog Pondering
知らぬ間に、あるいはいつの間にかダンス・ミュージックになってしまう“タロイモ思考”のアルバムである。ハワイアン・ローカルからシカゴ・テクノのミニマル・ダンスへという変遷は唐突にして唖然という他はない。正直言って追っかけているわけではなく、しがない場末のディスカウント電器店(既に倒産)の隅っこで埃を被って叩き売られているものをジャケ買いしていたので、とにかく当たり外れの振幅が激しい。不思議な所で不思議なものが入手できたあの頃(1990年代後半を指す)。国内ではまったく知名度がなく(本国ではそれなりに人気で評価も高く、尚かつ現役)、これっぽっちも人気がないようですが、売ってるほうも売ってるほうだよなぁ。いったい、どこから仕入れてきたのだろう?
パワフルで陽性の歌入りミニマル・テクノ・ダンス。微妙に哀感が漂う民俗色とファンキィな乗りが絶妙にマッチしているあたりは不思議極まりない。フルートやヴァイオリン(フィドルかな?)などの生楽器と超絶エレクトロニクスのバランスも面白い。要素がごった煮のように無分別にグツグツしている全7曲。
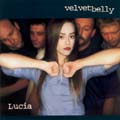 BMG
BMG74321 722282
Lucia/Velvet Belly
ノルウェイの詳細不詳な中年掃溜めに鶴キンテット。国籍不明風のプログ色が濃かった前作に比して、大きくポップに舵を切った全11曲の5作目(ラスト?)のアルバム。2曲目「Easy」は映画の主題歌に採用されている。歌詞はすべて英語。ラストはケイト・ブッシュのカヴァー。ダーク・アンビエント・ノイズ風の引き締まったタイトな音像を基調にしながらも、ブルーズやポップスに対するアプローチで脱皮を計ろうとするも結果は中途半端に終わっている。
紅一点のお姉さん(アンヌ‐マリ・アルメダル)はけっこう見映え麗しく、細いながらもクリアで少女趣味的な憂いを含んだ声質。現在は独立してソロ歌手に転向した模様。段々コクトー・ツインズに似てきたぞ。もっとも華やかさのかけらもなく、どうしようもなく地味ですが。あんまり洗練され過ぎない方が良いと思うが、硬くてスコンと抜けるリズムはいいぞ。高くはないけど結構情感のあるよく伸びる声。
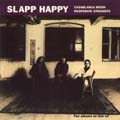
1975
Casablanca moon + Desperate straight/Slapp Happy
『カサブランカ・ムーン』と『絶望一直線』の2作のLPを1枚のCDにまとめたカップリングCD。2作の傾向がかなり違うので曲が続くとかなり違和感があるが、お得なので許す。いきなり奇怪な殺人者を歌うタンゴで始まるが、一様に面妖なポップスを繰り広げている。昔はやたらとっぱずれた躁鬱な声だなと思ったダグマー・クラウゼの声も、最近ではむしろうっとりするほど柔かく耳に聞こえる。少女歌謡のような紛い物臭い、キッチュで甘い砂糖菓子のように聞こえたりもするか。2000年に日本でライブをしたのはそれなりに話題になっていたが、98年、2000年と新作が出ている。一方、後半『絶望一直線』はヘンリィ・カウ(Henry Cow)とのジョイント・アルバムという体裁。共に転機となったSlapp Happyの2作目とCowの3作目は合体による相互協同製作で、やっぱりドツボでズボズボと底無し沼に嵌っている。元が即興に秀でた現代音楽系なので内容は非常に斬新だが、そう思わせないポップなセンスは素晴らしい。アヴァンギャルド・ポップと云うのだねぇ。
「猶予の月(Slow moon's rose)」
猶予の月が今昇り
北極の川が凍りついたような
銀色の格子が成長していく
ゆるゆると海が凍りついていく様は
まるで雪の朝が来たようだ
翼をもった鳥たちは
さえずりも残さずに
氷の上を走る帆船のように
蒼いガラスの中を飛び去った
つついた川の上に
猶予の月が昇った
その宵が鼻の頭で
一雫の宝石になって消えたとき
昇りはじめた朝日の下で
告げ口をした蝸牛は
足跡を残したまま
狩人の黒い大筒から
逃れようと逃げ惑う
銀の格子とか川というのは蝸牛の這った跡なのだろう。それに月の光があたって光って見えるということなのだろうが、随分と(意外にも)繊細な感覚だ。