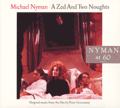
Virgin
7243 5 98444 2 8
2004
A Zed and Two Noughts/Nyman, Michael
久々のナイマン、1985年のグリーナウェイ作品『ZOO』のサウンドトラック。還暦記念のリマスター再発・デジパック。白鳥と衝突して交通事故死した妻達の夫である元シャム双生児の動物学者が辿るシンメトリーと腐敗の物語。腐敗は純粋に腐敗菌による生化学的な腐敗を指す。九相詩絵巻の近代版といったところか。
乙一というライトノベルズ作家がオマージュ(本来はhommageで敬意だが、日本人ならhomageと書いてハミッジと言うべきだろう)して、それを更に映画化したらしいが、オリジナルを見ればこれ以上のものが作れるとは思えないのだが。せっかくだからそのサウンドトラックも聴いてみると面白いかなぁ。主題歌があったりしてねぇ。こういったありがちな構図には、やはりどこかに儲かりまっせとタイアップ企画を考え、対象に合わせたレベル設定をして、プロデュースなりコーディネイトしている仕掛人がいるのだろうか。
6/4と4/4の変拍子ポリリズムによる強迫感が耽美で変態な映像を髣髴とさせる。曲を聴くとシーンを思い出すくらい強烈でかつ美しい。映像も楽曲も偏執狂的なこだわりが審美的な新鮮さと相まって、グロテスクなまでの美醜の逆転を引き起こす。プロデュースはデヴィッド・カニンガム、演奏はどういう編成だか資料がないズー・オーケストラ。バイオリン三本くらいの小編成。クラビネットとピアノはナイマン自身だろう。

DENON
COCO-70596
L'Arlésienne Suite, Carmen Suite/Bizet //Emmanuel Krivine
おや、今回はまともじゃないか? という期待を二枚目にして多分裏切る方向にあっさり翻意しよう。実際、今やポップ・ロックよりも遥かに少ない人しか聴かないという意味では逆説的に取り上げるには相応しい内容と質だし、実は好き。
「ラルレジェンヌ・スイート」に「カルメン」の抜粋を加えた廉価版CD。一面のラベンダーの向こうの黄色は麦秋でしょうか。縁取るような萌える若葉が鮮烈なアクセントに見えてしまいます。今でも3年に一度、アルルの女王コンテストなる催しが開かれているそうで、「アルルの女王」になるには、1;プロバンス語が話せる、2;馬に乗れる、3;黒目黒髪、4;髪結、民族衣裳の着付が自力でできる、5;アルル生れのアルル育ち、6;公式には独身、もちろん容姿端麗その他諸々だそうでジェンダーフリーを踏み躙る前近代さが売り。
体系的に追っかけているわけではないので、ジョルジュ・ビゼー(Georges Bizet:1838-1875)がどういう立場にあって、どういう功績を残したのかについては知らないが、時代を鑑みれば前期印象派といったところでしょうか。
「アルルの女組曲」は劇伴音楽、「カルメン」はオペラ。どちらも広く(かどうかは知らないが)知られた印象的なメロディとアンサンブルが華麗なロマンティックかつエキセントリックな楽曲です。発表当時は芳しくない評価で、失意のうちに37歳で故人になるビゼーだが、後にオーストリアでの評価がきっかけになって再評価に至ったらしい。
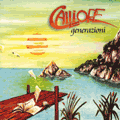
Electromantic
ART405
Generazioni/Calliope
90年代初頭にミラノで勃興したネオ・プログの先陣であったが、ブームの失速とともに没落も早かったカリオペ四作目、といいたいところだがこれは少し困った。
最初の4曲は1st、2ndの人員による1993年のライブ、後半3曲はまったく別の構成員による2002年のスタジオ録音で楽曲は1stの冒頭3曲、すべて1stから3rdにおいて主導的な役割を果たしたリナルド・ドロによるものだが、肝心のドロはいないというわけ。プロデュースはアルティ+メスティエリのベッペ・クロベラであるところは全作共通。以前取り上げた3rdとは異なって1st、2ndはドロのビンテージ・キーボード大会にメタル・ギターと極めてリリカルな曲調の謳い上げる男声ヴォチェがこてこてのプログを演出する。3rdの方々は何処へ? と思ったら、家庭の事情でドロが引退したことにより実質的に終わったというのが真相だったようだ。
新生カリオペについてはともかく、93年のライブはなかなか。ほぼ原曲のアレンジ通りですが質の良いテクニカルでかつ、情感のこもった演奏が聴けます。曲の出来は元々とても正統的で良いので、節度あるテクニックに裏打ちされたライブも質の高い内容になっている。ちなみに、まったく同名の楽団があるので要注意。普通に検索をかけるとそっちがヒットします。ここで取り上げているイタリアのカリオペはCD四作、すべてイタリア語タイトルです。

PDI 80.0931
L'oucomballa/Companyia Elèctrica Dharma
バルセロナの民芸ジャズロック・アンサンブル、というと聞こえがよいが、平たく云えば大道チャルメラ・チンドン、CEDの2ndアルバム。チャルメラ(charamela)は元はポルトガルの木管楽器だったそうだが、かつて流しの中華ソバ屋が吹いていた日本でいうチャルメラは中国伝来の唐人笛というらしい。
どちらかといえば正統的なジャズ・ロックにほんのりと民芸風味が加味されだしたという過渡期ではあるが、そこはやはりカタルーニャもの、独特の地中海ラテン滋味と能天気でありながらも切ない独特の哀歓がテンコ盛です。特徴的なチャルメラ・サックスもギターとユニゾンしまくっておるし、転げ回るようなリズムも達者だ。ちなみに現役。今でも新作が出ています。
全曲インスト。タイトルは“L'Ou com Balla(ルコンバージャ)”で、バルセロナ市内で最も古く伝統的な名所で、聖堂カーサ・デ・ラルディアサの噴水を指しているようだ。葺き上がった水の天辺に卵が載っているらしい。タイトル、曲名、クレジットがほぼカタルーニャ語で、伊語と仏語と西語の辞書から類推するのも辛くなってきた。
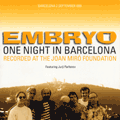
disconforme sl
DISC 1938 CD
One night at Barcelona/Embryo
ドイツ出身の民族音楽団、エンブリョによる実況録音盤2CD。『バルセロナの一夜』ということで、バルセロナ出身の画家、ホアン・ミロ(Joan Miró:1893-1983)財団主宰の1999年9月2日のお祭り出演時の一回こっきりの実況生録音のようだ。
かなり中央アジア民族色の濃い伝統音楽から、ロシア人、ユーリ・パルフェノフ(Jurji Parfenov)の喇叭を売りにしたジャズ寄りのものまで、枯れた味わいの民芸ジャズ。初期の陶酔幻覚色はまったくないですが、乾燥した空気にまったりと響きながらも、それなりのぞくぞくするような即興が円熟を醸し出している。今のご時世に鍵盤楽器なしという構成もなかなか珍しい。その代わりを担うのはブルクハルトを中心にした鉄琴木琴というかたち。ブルクハルト自身による概観と詳細な曲目解説付き。まぁ、大量伝達媒体受けとは無縁そうだから、書いてくれる人がいないとも云う。
結組時の構成員は実質的な首領であるブルクハルトのみですが、まぁ、30年以上経っているから良しとしよう。
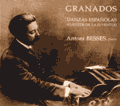
Mandala Man
5013
Danzas Españolas/Granados, Enrique //Besses, Antoni
こちらはカタルーニャ人のエンリケ・グラナドス(1867-1916)。ファリャ(Manuel de Falla:1876-1946)、アルベニス(Isaac Albéniz:1860-1909)と共に国民学派と云われる近代エスパニョルのピアノ弾き兼作曲家のおそらく最も著名な『エスパニョラス舞曲集』全12曲。後半は『青春物語(Cuentos de la juventud)』全10曲。
比較的初期の作品で、概ね簡潔でロマンティック。ショパンやドゥビュッシーを範にカタルーニャ独自の地中海民族色にほんのりと染まったピアノ曲集。
舞曲といえばダンス・ミュージック。スペインに限っても古くは、3/4拍子のシャコンヌ、3/2のサラバンドから、3/4、2/4のボレロ、2/4のタンゴ(アルゼンチンだけど)と歴史参照には事欠かない。だが、近代に入ると舞踏とは独立して、より抽象性の高い形式として一つのジャンルを形成するようになる。なかでも19世紀は各地の風土と結びついた民族色豊かな舞曲が流行だったらしい。
さて、この人は悲劇の主人公でもある。諸説紛々(まぁ、脚色だろう)だが、アメリカでの演奏旅行の帰途?、第一次大戦中の英仏海峡を英船籍フェリー「Sussex」号で横断中、機雷敷設船に誤認されU-ボートに雷撃されたらしい。船は別に沈没せずフランスの港に曳航されたが、325人の乗客乗員のうち数十人の死者が出たそうだ。グラナドスはその混乱のなかで妻が甲板から転落したのを見て、助けるために3月の海に飛び込んで、救命ボートに妻を助け上げたが自身は低体温症で死亡したらしい。凄い話になると大西洋航路の豪華客船をU-ボートが撃沈、妻もろとも悲劇の水死というのもあるようだ。一応、当時の米大統領ウィルソンがドイツ外相に宛てた書簡で、このSussex号事件で中立国であるアメリカ人に数人の怪我人が出たとして怒っておるので事実はそんなところだったのだろう。でもそうだとするならば、こっちのほうがよっぽど悲劇ですね。

Celtica Napoletana
CN001
Medieval Zone/Sorrenti, Jenny
ナポリの出、カンタウトーレ、アラン・ソレンティの妹であるジェニー・ソレンティの三作目? のソロアルバム。70年代のサン・ジュスト(Saint-Just)時代に二枚のアルバムで歌っているのがいちばん著名なあたりだろうか。オザンナの30周年ライブにも出ておりましたが、歌はともかくとしても時の流れは残酷なものだ。
イタリアは横へ倣え的一枚岩の国ではないので出身地がわかると大抵傾向もわかるので便利だ。あまりの引ったくりの多さに旧市街でのスクーター類乗り入れ禁止措置が発動されるなど、北イタリア人が鼻で笑い分離独立を目指す、相変わらず“どうしようもねぇ”南イタリアのようですが、カプリ湾を望む風景は風光明媚。
一応、楽団形態による電化フォークのようなもの。南欧トラッド、作者不詳の民謡のリアレンジが半分ほどと、どちらかといえば濃厚なカンタウトリーチェ(カンタウトーレの女性形)というよりは涼しげで繊細な感触が強い。歌詞もイタリア語のみならず、英語、(南)仏語混じり。エンハンスド仕様でビデオクリップ一曲付き。

King record
KICC 8729
Es war einmar...Spieldosen-& Drehorgel-& Klänge/-
純機械式の自動演奏装置とオルゴールによる音源を集録したコンピ盤。スイス人? ハインリッヒ・ブレヒビュールのコレクションの演奏が収録されている。個人的には20世紀前半の、映画等でよく見ることができる、普通のピアノに自動演奏装置を取り付けて透明人間が弾いているように鍵盤までが動くシステム(ピアノプレイヤー)が興味深いが、ここはそれ以前の時計と組み合わされたバレル・オルガンやクランクを廻す手回しオルガンのちょっとくぐもったノスタルジックな音色が主体。どの装置もせいぜい多くても10曲程度しか再生できないので、レコードの発明以後は完全に過去の遺物ですが、筐体に施された意匠も凝っていて面白い。
幼少のみぎり、机に座ってぱこっと蓋を開いてオルゴールで一家団欒などという記憶が微かに残っているのだが、捏造された記憶だろうか。回転が段々遅くなって、ついには曲の途中でコテっと止まってしまったときの無常感みたいなものが好きではなかった。
ジャケットの鳥かごには剥製のルリビタキ? がとまっていて、ぜんまい仕掛けで実物と同じように動きながら鳴く。その可愛らしい音が収録されていますが、なんとも西洋的で悪趣味な逸品。
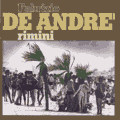
BMG/Ricordi
74321 974472
Rimini/de Andrè, Fabrizio
P.F.M.とのジョイント・ライブの前年にリリースされた9作目。アドリア海に面した高級リゾート地リミニを題材にして、地中海音楽に大きく傾倒した転回点。内スリーブには各曲に対応した何とも味のあるモノクロ写真の数々。扉の外は海なのだろうか、薄暗い部屋にビデのかたちが艶めかしい。渚を行く老人二人。乳母車(これはベビーカーとは云い難い)は孫だろうか? パラソルが畳まれて閑散とした曇天の海岸に商売上がったりの物売り婆さん。金持ちと貧乏人、光と影の織り成す誇張されたこの世の縮図のようだが、持てる者も持たざる者も、矜持を持って生きていけた最後の時代かもしれない。
ボブ・ディランのカバー(歌詞はイタリア語)が一曲含まれる以外はかなり作り込まれた電化トラッドで、ロック色の強いリズムが弾けるような陽光と影を表しているようだ。非常に効果的な鍵盤と弦楽アレンジは四人目のオルメ、ジャン・ピエロ・レヴェルベリ、女声ヴォチェは後に妻になるドリ・ゲッツィ(Dori Ghezzi)。24bitディジタル・リマスターの再発盤。
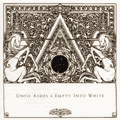
Projekt
147
Empty into white/Unto Ashes
『無は白に帰す』というタイトルが表象する白い闇。作を重ねるごとに視界が利かなくなる闇の透明感が鮮烈だ。三作目にしてダーク・ゴシック・アンビエントの装いでありながらも本質的な宗教色が透けてみえる。前作ほどの隙のないネオ・クラシカルではなく、トラッドを基調にしたエスニックで暗鬱な曲調と凍り付きそうなインスト・アンビエントで構成されて、かなりポップ寄り。歌詞も大半が英語に戻っている。ちなみにタイトル曲は Tatsuya Nakatani (誰?)によるアンビエント。冥界の鉄扉が引き開けられるような虚空の軋み。ラスト(と思ったら次に19曲目があるのだがクレジットがない)はドナルド・ローザー(Donald Rother)のDon't fear(the Reaper)のカバー。ここに同郷とはいえBÖCが来るのか、と感慨深い。
Webのビデオも気に入っています。最近はこの「パレスティナリート」とフルールのビデオを起き抜けに視聴するのがすっかり日課になっておりますが、見聴きすればするほど現世に未練がなくなっていくのは良いことなのか悪いことなのか。まぁ、この世の摂理の受け入れ方は対照的であるにせよ、その美意識には共感しよう。
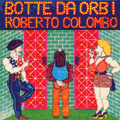
['mju:zik]
C3 P8
Botte da orbi/Colombo, Roberto
『Passpartù』のころ、P.F.M.でフラヴィオ・プレモリ(Flavio Premoli)と共にタスティエーレ担当だった、ロベルト・コロンボ77年の2ndソロ・アルバム。デ・アンドレとのジョイント・ライブにも顔を出しておりましたが、どちらかというと80年代以降のブレイクしたマティア・バザールの辣腕プロデューサー、及び業界の黒子としての方が有名かもしれない。
金管をかなり意識的に使った、かなり変てこりんなジャズ・ロックのようなもの、ですが非常に垢抜けた、人を喰ったようなコミカルなセンスが際立つ。音の切れが70年代のイタリアものとは完全に隔絶されて、先鋭的とでも云おうか。80年代のエレクトロ・ダンスを髣髴とさせるアプローチを既に聴くことができる。
タイトルは慣用句で『メッタ打ち』の意。左翼風刺漫画風のジャケ絵は『Passpartù』と同じ路線でしょう。ヴィオリーノでマウロ・パガーニ、ルーチョ・ファブリあたりのクレジットが見える。

CLD001
O sete/Projeto Caleidoscópio
タイトルは『7』の意。全7曲。ブラジルの男女デュオ、プロジェト・カレイドスコピオの1stアルバム。万華鏡企画とはなかなか良い銘です。女性の方は若干メスティーソの血が入っているように見える何とも言い難い魅力的な美人です。もっともどう見てもデキているとしか思えないツーショットばかりで鼻白むことは請け合い。まぁ、そのアナルー・パレデス(Analu Paredes)ちゃんが頼りないけど可愛らしい声でそこはかとなく歌うのが聴き処。バカマルテやカテルナ・レクイエムの人員も参加しているようだが、楽曲は総じてゆったりとした草原の陽だまり調で優しい。ジャケットはプトレマイオスの宇宙とウロボロスかな。水金地火木土+太陽でやっぱりここにも7がある。
歌詞は南米ポルトガル語。声量はないが柔らかい発音と透明な清涼感で、素人っぽい甘さは散見されるが、ほんのりと、のほほんと暖かく愛らしいミナス風トラッド・プログ。ちょっと前に二作目が出ております。英語ライナーと歌詞の一部英訳、アニー・ハズラムとマルクス・ビアナの献辞付。
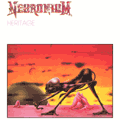
Huygen Corporation
HCCD-001
Heritage/Neuronium
カタルーニャの2人ユニット、ミケーレ・ウイゲン主宰のニューロニウムの何作目かは既によくわからん。と、思ったら裏ジャケに親切にも“7作目だよん”と書かれておった。個人的にはそのラテン趣味とエレクトロニクスが上手く同調しておらず、叙情に流れ過ぎる部分が不満でそれほど入れ込んではいなかったのだが、これを聴いてその評価は一変しました。
起承転結のある構成とよく練られた楽曲、類い稀なラテン・メロディーの作る泡沫の夢のような音場は感動的ですらある。シーケンス・パターンなども積極的に使った楽曲もある一方で、狂いそうなまでの切ないメロディは究極の美意識の為せる技に他ならない。インドかバリの寺院で撮ったと思われるウイゲン氏は、ちょっと神経質で生真面目そうな人でした。一部に相方サンティ・ピコ(Santi Pico)によるギター入り、全曲インスト。
タイトルは『遺産』。なんとも端麗で叙情的な流れは当り障りのない過去探方紀行か歴史遺産賛美に思えるが、曲名をみると
1: 秘密の聴聞(9:18)
2: 報復(11:43)
3: トルケマーダ(5:54)
4: 死の服毒(14:16)
と、トルケマーダ(Tomás de Torquemada:1420-1498)は中世スペインの異端審問所において残虐の限りを尽くした最初の異端審問官であることから、宗教裁判を扱った内容のようだ。

ECM 1525
Officium/Garbarek, Jan/The Hilliard Ensemble
ECMのベスト・セラーだから富に著名な『オフィチウム』。タイトルは現代英語の“Office”の語源でもあるラテン語にして『聖務日課』の意。身近に例えるならば『勤行』。平たく云えば『お勉め』。
実際のところは、時間別に分ければこんな感じらしい。
朝課 (マトゥティヌム)
賛課 (ラウデス)
一時課 (プリマ)
三時課 (テルツィア)
六時課 (セクスタ)
九時課 (ノナ)
晩課 (ヴェスペルス)
終課 (コンプレトリウム)
晩課はイタリア語でヴェスプロ(晩祷)といって、音楽的には最も華麗で荘重な勤行らしい。其七拾七で扱ったモンテヴェルディはこれに当たる。
ノルウェイのサックス奏者、ヤン・ガルバレクとイギリスの古楽声楽アンサンブル、ヒリアード・アンサンブルのコラボレイト。中世古楽たる宗教歌曲の上をガルバレクの冷たい透明感に満ちたサックスが漂い駆けるという趣向。ある意味、邪道であることは間違いないが、呈示される静謐な幽玄はまさに他に類をみない。半信半疑でパソコンで聴きはじめて、30秒後にはトレイを開けてオーディオのCDプレーヤーに入れなおした憶えがあります。
魚を食う鳥、その糞が人間が生き延びることができるオアシスの最初をかたち造る。次の溶岩の流れがすべてを蒸し焼きにするまで。
独英仏伊語版各ライナーの巻頭辞。キリスト教的宗教観とは無縁な上に、正直、心の底から何かを祈ったという経験すら生れてこのかたタダの一度もない人間にとって、この音楽は自らの罪状を告発するかのように先鋭に、鋭角的に前頭葉に切り込んでくる。だから、普段は滅多に聴かない。
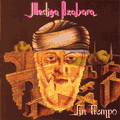
Avispa ACD-004
Sin tiempo/Medina Azahara
朗たけた堂々のアンダルシア浪花節、メディナ・アサアラ7作目。メタルとしての評価が高い(というか面白がられているだけだろうが)らしいが、メタルそのものに関心はない。とは云えども世の中変わったものだ。確かに後ろの方でメタルなリフが鳴っておるが煩いというほどではない。とにかく目立つのはデビューから一貫している若干線の細い甲高くリリカルなボス(Voz=Voice)と、ヘナチョコで思い入れたっぷりのフレーズをさり気なく入れまくるシンセ・キーボード。なんだかこぶしの振り方がトリアナの故人ヘスス・デ・ラ・ロッサに似てきたマヌエル・マルティネス(Manuel Martinez)のボスも結局はアンダルシアの牛(羊かな)追い歌なのだなぁ。匂うくらいリリカルで恥ずかしくなるぐらい哀愁ぶりぶり。歌詞はもちろんエスパニョル。
タイトル『Sin tiempo』は「Sin tiempo ni sitio(時間もなく場所もなく)」の略と思われる。

Musea
FGBG 9012.AR
Le jardin hors du temps/Vital Duo
『季節はずれの庭』とでもいおうか。現代楽器、古楽器を駆使して中世ラテン歌舞曲をモチーフにした現代の歌舞曲を創演するヴィタル・デュオのDVD。後半はヴィタル・デュオがコアとして機能するミニモム・ヴィタルのスタジオ・ライブ。その他に若干の中世関連の資料など。このところそれなりに画像にも興味があって適度に安価ならば躊躇いなく購入しておりますが、大抵期待を外してくれるのが大部分を占めるなかで、これは映像、音声、そしてなによりも内容の充実したきちんとした作りに好感が持てました。
前回の『La source』から『Esprit d'amor』あたりの曲を現シャントゥーズのソーニャ・ネドゥレ(Sonía Nedelec)が歌うという、なかなか興味深いバージョンになっております。聴くのと見るのとは大違いな部分も確かにあるが、出来はスタジオ盤よりも良いのではなかろうか。基本的にとても上手いので、かなり複雑で難しい曲でも破綻なく見聞きできる。もちろん、いちばんの見どころは、ロングスカートに厚手のセーターというおよそ“アーティスト”には相応しくないネドゥレ嬢の上品でエレガントな美貌(1,2,3,4)。どアップで堪能できます。シャントのほうはアルトで情感がこもるタイプながらも、かなりスピーディな曲調にも乗るというちょっと珍しい歌手。民謡語呂合わせのような歌詞をころころ表情を変えながら歌うのがとてもかわいらしい。
NTSC、リージョン0。