
Island
IMCD 147
Ha! ha! ha!/Ultravox
ウルトラヴォクスの過渡期にして二作目。パンクなA面とポストパンク・アンビエントなB面が同居する不思議なアルバム。
「イロシマ・モナムール(Hiroshima mon amour)」
どういうわけか僕等は遠すぎる位置に流されて
遠く隔たった星のように伝えあう
バラバラに砕け落ちた電話の声
陽光が塵にきらめいて、バラの香りが漂う、いや
扉の影に誰かいる
広島、わが愛
都市間鉄道に乗って
欧州の灰色を装う
波音が木霊する砂浜に乗り出して
木々と砂に宿る百万の記憶
如何にしてその記憶を放置せしめるのか
広島、わが愛
秋の湖で出会う
木霊だけが湖面を渡る
過去のポラロイドのなかを歩く
未来はガラスを砕くように溶融し、陽はかすめるように低く
僕等の影は金色に輝く
広島、わが愛
原作はマルグリット・デュラス(Marguerite Duras)、アラン・レネ+ロブ・グリエの映画(同題:1959)としても著名で、1961年の『去年マリエンバートで(L'année dernière à Marienbad)』の原型ともいえる。「わたしは広島を見て聞いて理解したわ」「いや、きみにはわかっていない」 遡る過去と滑りゆく記憶の条理と不条理。明滅する彼岸の白昼夢。あぁ、フォクスの消失感の原型は『マリエンバート』にあるのか。延々と輪廻する会話。形而上学の庭。手を取り合って現実(夢か?)から逃れる二人と、結果的に手を取ればどちらかが自己を喪失するという相反するアイデンティティ。消失する(創造される)記憶は白一色の画面に焼き付けられた。
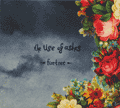
Mellow Records
MMP 292
Firetree/Use of Ashes, The
オランダのユニット、ユーズ・オブ・アッシーズの二作目のアルバム『火炎樹(鳳凰木)』のようだ。人数すらよくわからない集団は原型をメカニーク・コマンドー(Mekanik Kommando)といったらしいが、名前を変えて中身も大きく変わったらしい。そりゃ、正解だろう。ユニット名のUoAはキリスト教のある種の典礼儀式を示しているようだ。
ネオ・サイケとアンビエント・ノイズ、ときおりギター・ポップ風の展開が挟まれて取り留めの無さで売るタイプ。ときどきはっとするような新鮮な切り口は感じられるものの、冷たく湿度のある沼地をとぼとぼ歩いているような薄ら寒さと暗さにどっぷりと浸かっている。公式Webらしきものも一応あるようですが、知りたい情報がことごとくオミットされておるというありがちなタイプ。
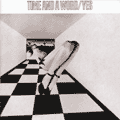
Elektra/Rhino
R2 73787
Time and a word/Yes
イエスの最初の飛躍はタイトル曲「Time and a word」だろう。まだ千差万別、多種多様のごった煮のようなアルバムで、方向性が確立されるのは次作『The Yes Album』なのだろうが、タイトル曲の微妙にギクシャクしたポリリズミックな曲構成と堅苦しいばかりに隙のない完璧なアレンジ、それがもたらす高揚感と硬質な透明感は異論のないところ。オーケストレーションを多用しているあたりも新機軸なのだろうが、そのあたりはさすがに時代を感じさせるものがある。まぁ、個人的に好きなのは「Then」とか「Sweet dreams」なのですが、うっかりするとメロディ・ラインが逆転しているようなスクワイアのリードベースとブルフォードのジャズ・ドラムなども非常に個性的、独創的で面白い。
音源は定番、2003年のライノ・リマスター、ボーナスで+4曲。
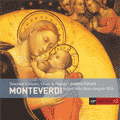
Virgin
7243 5 61662 2 6
Vespro della Beata Vergine/Monteverdi
昨今、頻聴かつ傾聴かつ拝聴しているモンテヴェルディ中期の作。深遠にして豊饒、幽情にして明晰、げに恐ろしきは、男女混声ヴォチェと部分的にヴィオリーノ他の伴奏が奏でる至福の法悦にして禁断の領域にある。歌ものにして、器楽。歌詞はラテン語。簡潔な発声の妙、美しくも厳かなメロディも心を打つものがあるし、作りこまれた精緻でプロフェショナルな構成、展開はまさに敬服に値する。また、コンポーザとしてのモンテヴェルディはルネサンス時代は使用禁止だった「三全音」なる和音を使用したり、平均律を細分した微分音程を用いるなど楽理においてもプログレッシブな理論家であったようです。
確かにデッド・カン・ダンスなりお耽美ものの神秘も色褪せる内容と質だろう。比較する必要はないだろうが、結局、西洋音楽は歴史の蓄積の上に成り立っているというか、その基本原理の継承に時代なりの味付けを施したに過ぎないということをつくづく思い出させてくれた。
105分越えのタイトル曲『聖処女マリアの晩祷(1610年作)』と晩年の『ヴェネツイアの晩祷曲集(1640年作)』が6曲計40分越え、計150分の2CD。晩祷とは夕方の(その日、最後から二番目の)お祈りを指すようです。録音は1982-1984年。指揮はアンドリュー・パロット(Andrew Parrott)。ヴォチェはソプラノx4、メゾ・ソプラノx1、テノールx7、バリトンx1、バスx4という編成。モンテヴェルディ(Claudio Monteverdi:1567-1643)はバロック期のイタリア(というかベネチア共和国か)を代表するコンポーザ。
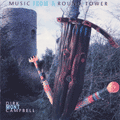
ESD 81212
Music from a round tower/Campbell, Dirk Mont
エッグ→ヘルスと足跡を残したカンタベリィを代表する人と思っているが、意外に地味な扱いのベース兼フレンチ・ホルン奏者兼コンポーザ。モント・キャンベルの現段階では唯一のソロ・アルバム。エッグやヘルスを期待すると完璧に外す現代音楽寄りの内容であるところに意気を感ずる。イングランド・トラッドやクラシックはもとよりギリシャ、アルメニア、アフリカ、トルコ、東欧、あるいは雅楽などの雑多なエッセンスを背景にした管楽器のアンサンブルとMidiシーケンスを用いたアンビエント寄りの楽曲が主体になっている。
背景の円塔は早春のイースト・サセックス、ブライトリング・タワー、オブジェはマーカス・ボルト(Marcus Bolt)の彫刻「怒れる王」。共同プロデュースはデイブ・スチュワート、バーバラ・ガスキンの声も聞こえる。版元は“Broken Records”のGnome Dustレーベル。販売はESDですが販売手数料を除く全額が演者と作曲者に入るそうで、“あなたの支持に感謝する(買ってくれてありがとう)”と書かれております。
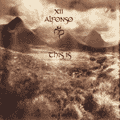
Musea
FGBG 4502.AR
This is/XII Alfonso
ドゥーズ・アルフォンソの近作。80年代後半のスタートでこれが四作目にあたるライブ。フランス南西部、ボルドー近郊メリニャックの出らしいので若干のケルト色も頷けるところか。同郷のミニモム・ヴィタルとの関係は不詳だがサポートにペイッサン兄弟の名が見えるし、ヴィタル・デュオの曲を取り入れていたりするあたりは同郷のよしみなのだろう。 ユニット名アルフォンソはブルボン家スペイン王の名。有名なのはAlfonso X el Sabio(アルフォンソ・デスィモ・エル・サビオ:賢王アルフォンソ十世:1221-1284)で、王としては不遇だったが、ミニモム・ヴィタルも取り上げている「聖母マリア頌歌集(Las cantigas de Santa Maria)」の作曲者として著名である等、芸術の面ではエル・サビオの称号を法王から付与されるくらい優れた才を誇った。アルフォンソ十二世(1857生、在位1874-1885)は現国王の三代前で比較的穏健な時代だったようですが、語順の逆転を含めて呼称の意図は不詳です。
アンビエント風味とケルト民族調を主調にした大人向けのゆったりしたポップスであるが、今ひとつ乗り切れないもどかしさを感じてしまうのは、スタンスがはっきりしないところ。ライブということもあるのだろうが、AOR風の何の取柄もない英語歌があったり、ケルト・シンフォだったり、アンビエント・プログだったりとスタジオ盤に比すると取り止めが無い。テクは今一つだがエンジニアリングが上手いのでよい雰囲気は出ているでしょう。本来はエレクトロニクスを駆使した淡々と素朴な美しさを前面に出したインスト曲がメインで、若干女性ボーカルが入るといった趣。
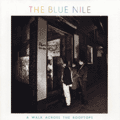
Linn Records
LKHCD1
A walk across the rooftops/Blue Nile, The
寡作で知られるスコットランドはグラスゴーのブルー・ナイル、1stアルバム。この時点ではブキャナン(Paul Buchanan)、ムーア(Paul Moore)、ベル(Robert Bell)によるトリオ編成。サポート・キーボードにプリファブ・スプラウトの『Andromeda heights』のエンジニア、カラム・マルコムあたりが目を惹くところか。特有の悩ましくも奥深い空間の滋味は、なにものにも替えがたい魅力を放っていることは衆目の一致するところだろう。
エレクトロニクスを基盤にした極めてメロウで黄昏た大人の奥ゆかしさが気持ち良いほどに爽快だ。1stにしてこの完成度、玄人受けする内容と貶しようがない隙のなさ、特異でありながらもリリカルで気持ちの良いメロディ・ラインと派手ではないがぴったりとツボに嵌る手触りが艶かしい。漸く2004年に四作目の新作が出たようです。
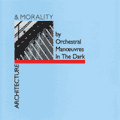
Virgin
7243 8 39795 2 3
Architecture & Morality/O.M.D
同じく80年代の幕開き、三作目にして一皮剥けた。それなりにヒットしたことも頷ける出来であることは確かだろう。いきなりギターの音が聞こえたりして引きますが、初期特有の黄昏た浮遊感と優しく湿った仄かに香る空気にたなびくメロトロン(サンプリングかと思ったら本物らしい)の硬質な響きが心地良い。悲観的で気持ちの良いメロディとそれを支える心細く音数が少ないリズムのアンサンブルは既に極上の環境音を成している。 しかし「Joan of arc」や「Joan of arc(Maid of Orleans)」がシングルカットされるとはなかなか面白い。シングルのジャケを見ればわかる通り、ジャンヌダルク(というか、オルレアン市庁舎前の銅像というべきか)を指している。
タイトルはイギリスの建築史家ワトキン(David Watkin)の著作から採られたもののようだが、具体的な意図は不明。最近のものはCCCDらしいので、UK国内盤かUSA盤が良いようです。
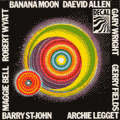
DECAL
CD LIK 63
Banana moon/Daevid Allen
盤起しと思われるゴングの名主、デビッド・アレン名義のソロ一作目。クレジットが極めていい加減なのだが、Calyxで確認する限りにおいては、トリッシュ(Christian Tritsch)が2曲を提供し、ホッパーが一曲提供。ドラムはワイアット(一曲、ブルーズを歌う)、ベースは後のホールワールドのレゲット(Archie Legget)にキーボード、バッキング・ボーカルが加わった構成のようだ。曲調はパンクからブルーズ、いかれ音頭、スペース・ジャズ・ロックまで。ケヴィン・エヤーズの“物真似”をして遊んでいる曲や『Angel's Egg』の原曲を思わせるものまで、変幻自在にして無節操な絢爛豪華ごった煮。なんともいえない乾いたユーモアと、微妙にリリカルなアンバランスが特質です。
リリース年次を考えるとこの時点で不可視電波妖精三部作のアイディアはほぼ完成していたと思わせる。

BMG/ARISTA
251 183
Time is the key/Pierre Moerlen's Gong
こちらはゴング一族の末裔。旦那が不在で番頭というよりは手代格、モワルランが頭目を務めていた時期の二作目。つまらないスリーブのオブジェクトはおそらく今風に言えば“マレット”というらしいが、私の年代はやはり太鼓を叩くのは撥と相場が決まっておりやす。撥とかいてバチと読む。火の用心が打ち鳴らすのは拍子木、火の見櫓で叩くのは半鐘、坊主が撞くのは梵鐘と。
全曲インストのパーカッション・フュージョン。特に頭から四曲目までのきらきら輝くような、それでいて柔らかく撓るような鉄琴の音色と控え目なモワルランの達観した境地に至るパーカッションは聴きものというか、虜になるものを持っている。民族調のものは可愛らしくて面白いが、後半は種切れ。特に、最後3曲のぱっとしないギターはホールズワースか。日本では人気が高いらしいホールズワースだがどこへいっても浮いている人だ。

Cuneiform
Rune 107
Certitudes/Présent
プレザンの中でもかなり躍動感の強い五作目。リズム隊はドゥニ+セジュールというユニヴェール・ゼロそのもの。重量級の変則ポリリズムの饗宴と壮絶な、あるいは偏執狂的なとことん、延々、執拗に繰り返されるピアノのリフが作り出す狂気に染まった楽曲には言葉がない。タイトルは自信たっぷり『確信』の意。赤と黒のふつふつと増殖する結晶格子のようなスリーブは冒涜的な歌詞と共に煉獄を象徴しているのだろう。
2曲目「May Day」のすべてを拒絶し、心の底をすくわれるような静謐で冷酷なシンセ・アンサンブルと、ロックとは完璧に無縁でありながらそれ以上のさかしまの躍動感を叩きつけるパーカッションは底なしの無窮に引き摺り込まれるような絶望と諦観を与えてくれるだろう。凶暴に暴れまわるピアノとギター、呪術まがいのボイスがすとんと一点に収束して非情なまでのシンメトリィを構成すれば地獄の蓋が口を開けて待っている。
ケースからCDを外すと一言。「この世におまえとおまえの守護天使の居場所はない」
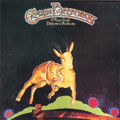
Virgin
0777 7 67138 2 1
Bluejeans and moonbeams/Captain Beefheart and the Magic Band
取敢えず毛色が変わったものから。首領はキャプテン・ビーフハート。嘘臭い本名? はドン・ファン・フリート(Don van Vliet)というらしいのでオランダ系でしょうか? 根拠はない。そのあまりにも奇想な変態さ加減が常に取り沙汰される変人ですが、これはそのなかでも異色なほど世間に接近したもの。螺子が外れたような変拍子も突破ずれた奇矯な歌声もそれほど気にならずに聞ける大人の一枚といったところでしょう。珍しくカバー曲まで含まれています。ゆったりとしたスティール・ギターにメロトロンまで、どっぷりとリズム・アンド・ブルーズに浸かりながらもリリカルだったりして正直美しい。
一般的にはザッパとの関連や米西海岸の風土から語られるものなのだろうが、わたしのアプローチはあくまで、ZNRやユニヴェール・ゼロからの遡上であってまがいものあるいは邪道です。いろいろと紆余曲折のある人だが、個人的には80年前後(82年に音楽からは引退して専業画家に転進)がつぼに嵌るかなぁ。
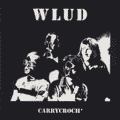
Musea
FGBG 4166.AR
Carrycroch'/Wlud
自主制作1000枚プレスの1st『Carrycroch'』にボーナスを加えた再発復刻CD。今ひとつ上昇志向に欠けるアルザスのコルマール出身のカルテット。WLUDは四人の名前の頭文字を組み合わせたもので他意はないらしい。録音の悪さは如何ともし難いが、曲構成や展開にはそれなりの冴えと新鮮さを感じさせる。テクニックは可もなく不可もないが、作りこまれた華麗なメロディで聴かせるタイプだろう。アンジュ風のオルガンが聞かれる部分もあるが、エレピを中心にしたジャズ・ロック風のアプローチと、リリカルでそれなりに盛り上がっていくきちんとした展開の妙がさり気なく並存しているところが面白い。全曲インストだが、だれずに聴かせる。翌年2ndを出して消息を絶つ。
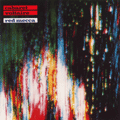
Mute 9174-2
Red Mecca/Cabaret Voltaire
トリオだった初期インダストリアル期の3rdアルバム。何故に『赤いメッカ』なのか? と問われても答えようがないのだが、1st『三真言』でも感じられたエスニック趣味の一環なのだろう。『三真言』のようにLP片面一曲づつという暴挙(心意気ともいう)は遠慮したのか、全9曲の比較的コンパクトな楽曲が並んでおります。荒涼とした虚ろな基底音に乗るチープで薄ら寒いノイズが織り成す即興美学。テストデプトやノイエ・ドイッチェ・ヴェレあたりの影響もあるだろう、金属的な質感が前面に押し出されている。一方で、生音やボーカル、楽器音が目立ち始めたあたりは聴き易さには貢献しているのだろうが、コンセプトとしては後退している。この後はよりメロディアスに、ダンサブルな方向に舵を切る。
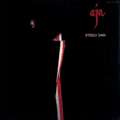
日本コロムビア
YX-8114-AB
Aja/Steely Dan
後にも先にも唯一のSD体験ということで、中身に関してはあまり書けることがない。しかしながら、完全に一世を風靡した美麗にしてメロウな完成度、磨き上げられた硬質な楽曲はあまねく万人が認める(認めた)ところでもある。まぁ、英語風に発音すれば「エイジャ」なのだろうが『彩』である。和服をお召しになった山口小夜子のジャケットも印象深く、かつ高質で惚れ惚れするような出来映えだった。これをきっかけに山口小夜子も随分と流行っておりましたが、個人的にはその前年ぐらいの「ゆれるまなざし」の真行寺君江の“目”にまいったなぁ。
この時点でフェイゲン(Donald Fagen)+ベッカー(Walter Becker)というデュオにして、コンポーズとアレンジに徹するという立場で、著名奏者を掻き集めてコマ録り製作された正にエンジニアリングの勝利とも云うべき逸品。最高の録音と最高のミックス、最高の職人の持てる能力をフルに引き出してと、最高尽くしで製作されたファンク・フュージョン。さすがに今聴いても何の遜色もない。まだ生きているようだし、他のも聴いてみようか。しかし“彩 aja”あたりで検索かけると面白い。
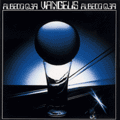
BMG/Victor
BVCP-5025
Albedo 0.39/Vangelis
タイトル『アルベド(オルビドー) 0.39』のアルベドは、ある波長域で惑星などが放出しているエネルギーを、同じ波長域で惑星が受けているエネルギーで除したもの。一般に反射能といわれる。ざっと調べた限りでは地球の反射能は0.3~0.39ぐらいで資料によって誤差がある。光源はもちろん太陽。アルベド=0は完全黒体、1なら鏡と同じ。ラストのタイトル曲ではアルベドを含めて地球のさまざまなデータを読み上げるナレーションが入っております。
基本的なアンサンブルはシンセやシーケンサーを多用した電子音楽でありながらも、曲構成や展開は頑固なまでにクラシック・ベースなので伝統音楽の範囲内にすべてが収束していることが特徴でもある。つまり、破綻がない。それを面白いとみるか詰まらないとみるかは人それぞれだが、その破綻のなさが後にサウンドトラックやBGMに多用される聴き易さと結果としての一般性と商業性を産み出しているのだろう。