
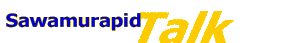
□2001 Nov.
| 2001.11.29(木) |
|
初速400km/hで角材を射出する機械。そして沢村といいます。 グッタリレイジーな毎日ですが、ようやくDVDドライブを増設したことで、買い込んでは積んだままにしてあったDVDをぼちぼち観はじめました。 チャールズ&レイ・イームズによる映像作品を編んだ「EAMES*FILMS」もそのうちの一本で、10秒ごとに10のべき乗のスケールで画面が極大へと遠のいていく(&極小へと近づいていく)ちょう有名な「パワーズ・オブ・テン」を筆頭に、ひんやりとした映像作品が数本収録されています。 自然科学未満の「理科っぽさ」が物足りない&気にくわない向きもありましょうが(パッケージデザインはgroovisionsだしね)、まあそうゆわんと機会があれば観てみることをレコメン。 このDVDに収録されてるぶんでは「パワーズ・オブ・テン」以外知らなかったのですが、個人的には「ブラックトップ」が好いたようです。黒いアスファルトの上を洗剤で泡だった水が流れていくさまを様々なカットから撮ったの10分ほどの映像で、こういうアブストラクトな映像にいったい何を喚起されているのかぜんぜんわからんのですが、くりかえし流してはいい気分になっています。むかし風邪をひいて学校を休んだとき、むいてもらったリンゴをほおばりながらNHK教育「ミクロの世界」を観ていたのを思い出します。 トップ画像をさらにろくでもないものに変更。身内チャットで萌え1行AAは可能かという話題に興じていたときのもよう。 ■結論=3行なら何とか。 |
| 2001.11.12(月) |
|
空気げんこつ? 沢村といいます。 アー、ルネッサンスジェネレーション忘れてた。つうか行くヒマねえですっての。 こないだ、こんな記事(一番下の段。「秘密のパーツ」てなんだ)とこんな記事をいちどきに知って、無関係とは了解しつつ面白いなあと思いました。ほんとに世界は動いているのだなあ(崖っぷちに方面に)とも思いました。 今回の深夜ニュースは一目見た感想はとくになしです。 |
| 2001.11.05(日) |
|
すごいオモロイ報告書。久々に香ばしいもの読みました(bbs参照)。沢村といいます。 ところでむかし荒俣宏が「東京路上博物誌」のなかで、気圧計を持って地下鉄に乗ると高低差に応じて気圧が変動するから、高低差の激しい丸の内線などはものすごいダイナミズムが感じられるだろう、みたいなことを書いてて、単線非電化の土地で高校生を営んでいた僕はそのアイデアにえらく興奮した覚えがあるのですが、今考えるとどうなんでしょうね。地下鉄は地下水が溜まらないようにするために駅以外は全部30パーミル近い勾配にしてあるという話は聞きますが、気圧計のほうはどのていど精密に測るのかしら。 ハマトリ感想のつづき。 西島さんぽくて好きかも、と言ってたユイグの作品は会場で観たら2秒で飽きました。そら浅田彰も腐すわ。展示室には人が多かったけど、みんなどうなのよ。 万里の長城を瞬間的に10キロ延長したことでゆうめいな蔡國強の作品は、期待に反してなんだこりゃって感じの電飾花火だったんですが、じつは床に並べられた松下電器のマッサージチェアがくせ者でした。寝椅子というのは頭部が固定されるんですよね。動体知覚によって成立する作品にあって、視線を固定してしまうそのアイデアはほとんど詐欺ともよべるもので、じつに気持ちよく観賞してしまったんでした。作品名は「花火大会−天から」というんですが、作品のちかくのボードに貼ってあった、横浜港の一角から観客のほうに向けて打ち上げ花火を水平発射するパフォーマンスの中止を知らせるビラが気になりました。 CABINみたいな没入型全周投射システムで繰り広げられるものとばかり思っていた束芋のビデオアートは、ぜんぜん楽しくなくてガッカリ。映像のほうも、ジャポニズムの手法で日本を内側から批評してみせる作品は木下蓮三が過去にもっと醜悪な形でやってるんだから、見せ方にこだわるしかないでしょう。だから次回は全部CGにしてCABINで上映な。 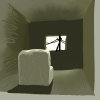 アレクサンドラー・ラナーの「電報」は、例によってへたくそな絵など描いてみるしだいでありますが、できれば写真入りのサイトをリンクしたいのです(けど、どれもまともに写ってない)。 アレクサンドラー・ラナーの「電報」は、例によってへたくそな絵など描いてみるしだいでありますが、できれば写真入りのサイトをリンクしたいのです(けど、どれもまともに写ってない)。「電報」は、窓に向かって椅子が置いてある小部屋が観客に向かって断面をさらし、その窓からはミニチュアの電柱が見えているという、いたってシンプルな作品なのですが、その模型世界が静かに切ない。ミニチュアというとカテランのエレベータもありましたが、こちらは特になんとも。階数表示灯も光るしドアも開くんだけど、別になんとも。 バッタとルアーではルアーのほうが圧勝。この服が海岸にうち捨てられてたらちょうビビる。インスタレーションで安物の液晶プロジェクタ使うのやめれ、フォーカスが甘くて萎える。会田誠にはアーティストというよりイラストレーターとしての才覚しか感じなくなってしまった。「荒川河川敷のホームレス"ヨシオさん"の遺作〈人生シリーズ)」もなんだかアリバイぽいよ。 そんな感じです。長くなってしまった。きっとこのページのレイアウトむちゃくちゃになってるだろうな。 |
| 2001.11.04(日) |
|
11月ですか。目に余るネグレクトに、すっかりお寒くなりました。沢村といいます。 そういえば、横浜トリエンナーレ行ってきたんでした。すっかり先週の話ですけど感想をいくつか。 ニセ樹木希林こと草間彌生のナルシスシリーズ、横浜港に浮かべたほうの作品は雨のせいでよくわかんなかったけど、素材が金属になるだけでこの人の描くドロドロのオブセッションは一気に親しみやすいものになってました。ミュージアムショップで売られてたTシャツのデザインにされちゃうくらい。個人的には好きなんだけど、いいのかそれで。  藤幡正樹の「フィールドワーク」はいちおうインタラクティブ作品ですが、じっと座って眺めてるだけでうれしい展示でした。ただ、これはアートかと小一時間問い詰められると、ちょっと口ごもるかもしれませんがそれはともかく。3Dグラスをかけて眺めるスクリーンには真っ暗な座標空間が広がり、GPSを手にして歩き回る人間の軌跡が白い線になってマッピングされていきます。遙か彼方には螺旋状の軌跡が描かれていて、誰かが山を登っているのが見える(というか「分かる」←このへんの感覚はビミョウです)。同時に手にしたデジカムで撮影した光景を映すウィンドウも線上を移動していく。 藤幡正樹の「フィールドワーク」はいちおうインタラクティブ作品ですが、じっと座って眺めてるだけでうれしい展示でした。ただ、これはアートかと小一時間問い詰められると、ちょっと口ごもるかもしれませんがそれはともかく。3Dグラスをかけて眺めるスクリーンには真っ暗な座標空間が広がり、GPSを手にして歩き回る人間の軌跡が白い線になってマッピングされていきます。遙か彼方には螺旋状の軌跡が描かれていて、誰かが山を登っているのが見える(というか「分かる」←このへんの感覚はビミョウです)。同時に手にしたデジカムで撮影した光景を映すウィンドウも線上を移動していく。藤幡さんのGPS作品は94年の富士山からはじまるのですが、最近のプロジェクト(しまった、絵を描く必要なかった)では移動者の視点ともリンクしてて、体験のマッピングになっているところが爽やかです。展示のほうでは、十字型の歩道橋の各端に立った4人が、同時に中心に向かって歩く始めるさまが流れていて、交差する瞬間の4人の視覚が犇めいてる感じは観てて妙にくすぐったかったりもしました。 大学で働いてたころ、都市計画の先生のお手伝いで江戸期の古地図とカメラを持って自宅周辺数キロ区画を自転車でうろうろしたことがあったんですが、一日中走り回って感じたのが、ウワモノを取り去ったあとの地形の起伏でした。バイパスの坂道で自転車を止めて振り返ると、ものすごく広い平原にでも立っているような気がして、なるほど都市論はこの実感から始まるのかと得心したんでした。認識のレイヤが一枚はがれたあの感じが、こんかいの藤幡作品でも思い出されて、しかしこちらは擬似的であるがために逆に認識というか感覚が拡張された気分になって、スコシふしぎでした。 (関係ないですが、モノトーンな空間+アイコンサイズの自然画ていうと、ここ3年くらいのコジャレ系サイトの定番デザインですナー) 長くなりました。つづきは明日。 |
■2001 Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
■SawamurapidTalk

