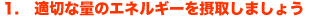
あなたにとって一日の適正な総エネルギー量は次の式から算出されます。
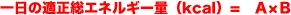
A=標準体重(kg)= 身長(m)×身長(m)×22(女性は21)(WHO方式)。
B=軽い仕事に従事の方では 25〜30(kcal)
中等度の仕事に従事の方では 30〜35(kcal)
重労働に従事の方では 35〜40(kcal)
(注)kcal(キロカロリー)とは、従来Cal(カロリー)とよんでいたものと一緒です。 |
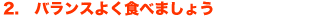
三大栄養素(糖質、たんぱく質、脂質)を適切に配分しましょう。
糖質:総エネルギーの55〜60%
たんぱく質:総エネルギーの15〜20%
脂質:総エネルギーの20〜25%
糖質1gは4kcal、たんぱく質1gも4kcalのエネルギー量に相当しますが、脂質1gからは9kcalのエネルギー量が生じます。脂質はとりすぎないように注意しましょう(特にコレステロールの多い動物性脂肪)。
このほか、ビタミンやミネラル※、食物繊維※※も不足しないように心がけて下さい。
野菜を十分とりましょう。牛乳、乳製品なども重要です。
※ ミネラル:カリウム、カルシュウム、鉄など
※※食物繊維:海藻、きのこ、こんにゃくなど 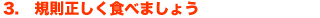
血糖値の変動をできるだけ少なくするために、一日の総エネルギー量を3回の食事にほぼ均等に配分し、決まった時間に食事をとることに心がけて下さい。
また、間食や夜食は避けましょう。
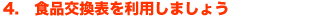
食品交換表※を利用して、適正な量で栄養バランスのよい献立をつくりましょう。食品交換表では「80kcal
= 1単位」という基準をつくり、1単位に相当するさまざまな食品の目安量が示されています。つまり、1600kcal
/ 日の食事療法を指示されたときは、「1600÷80=20」となり、一日に20単位の食品を摂取することとなります。
※食品交換表:「糖尿病食事療法のための食品交換表」日本糖尿病協会 / 文光堂

早食いの習慣を改め、一口30回箸をおいてよくかんでゆっくり食べるようにしましょう。
量が足りないと感じるときは、野菜や海藻、こんにゃくなどの低エネルギー食品でおかずにボリュームをもたせてください。
肉類の脂肪は避けましょう。赤身の肉にしましょう。調理に使う油を少なくなるよう工夫しましょう。
例えば、卵も目玉焼きより、ゆで卵に。肉は網焼きやしゃぶしゃぶにすると脂が落ちて、カロリーを減らすことができます。
外食(特に丼物や麺類等の単品)はなるべく避けましょう。
アルコールを続けるとインスリンの働きが悪くなり血糖コントロールが乱れますので、原則的に禁酒です。コーヒーや紅茶には砂糖を入れないようにしましょう。
|











