
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 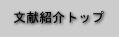    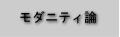 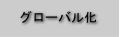
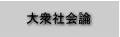  
その他
岡真理(2000)『記憶/物語』 岩波書店
以前、漫画喫茶でさるSF漫画を読んでいたとき、ちょっと不快な描写に出くわしたことがあります。政治的にさしたる意味もなく、宇宙からの攻撃に晒されたとある惑星。廃墟のなかで幼い子供が泣いています。かろうじて生き残った母親はその子供を抱きしめますが、次の攻撃によって親子もろとも消滅してしまいます。
漫画ではさして珍しくもないような描写に僕が引っかかったのは、やはり僕が父親になったからだと思います。子供を持ったことで、自分の愛しい者を失った時の悲しみを以前よりも頻繁に想像するようになりました。そして、自分が何もできないことも歯がゆさも。
たとえば、我が家に向かってミサイルが飛んできたとしましょう。僕がどれだけ体を鍛えようと、機知をめぐらそうと、僕には妻子を救うことなど到底不可能なわけです。戦争や天災といった苛酷な<出来事>の前に、一人の人間など徹底的に無力なのです。
しかし、時として人はそうした無力さを受け入れることができません。そのため、出来事がどれだけ苛酷であろうとも、人はそれに対し主体的に立ち向かうことができるのだという<物語>が必要とされることになるのです。
たとえば、第二次世界大戦。戦争というこの巨大な出来事に対して、個々人は徹底的に無力です。戦場で、または街角で、または強制収容所で、人々は何の意味もなく命を落としていくことになります。そこに理由など何もありません。けれども、残された人々はそのような無意味さに耐えることができないわけです。
そこで必要とされるのが物語です。戦場で散った兵士たちは、空襲で亡くなった民間人は、「戦争の哀れな犠牲者」であってはなりません。彼らは、そのようにして散ることを主体的に選んだのであり、戦争という巨大な出来事を前にしても、なおも主体的に「大義」に殉じたのだ、ということにされることになるわけです。
けれども、そうした物語は、一つのストーリーとして完結してしまうがゆえに、常にその外部に<語りえない>ものを残すことになります。物語のなかで、戦場で勇壮に散ったとされる兵士の描写からは、往々にしてその物語に合致しない要素が排除されてしまうのです。
この本のなかで著者は、そのように出来事を物語によって描き出すことの問題点を鋭く指摘しています。物語は一貫しているがゆえに、それを読む人に安心感を与えます。しかし、実際には物語では決して語りえないものが多数存在しているというのです。たとえば、著者は次のように述べています(p.7)。
「それが、どのような出来事なのか、自分自身にもよく分からない体験を、既成の言語、できあいの言葉で切り取っていくとき、私たちはなにか居心地の悪い思いをしないだろうか。出来事が私たちの手持ちの言葉の輪郭にあわせて切りとられるとき、私たちは、言葉で語られた出来事が、出来事そのものよりもどこか矮小化されてしまったような、どこかずれているような、そんなふうに感じはしないだろうか。」
とりわけ、戦争や天災といった出来事を物語によって語りつくすことは不可能です。にもかかわらず、物語はそれが「リアル」であればあるほど、そこで語られていないものの存在を見えなくさせてしまいます。あたかも物語が出来事の実態をそのまま表現しているかのような印象を読者に与えてしまうことになると著者は論じます。
しかし、それでも人は出来事の物語化に引きつけられてしまいます。先に述べたように、物語こそが出来事を前にした人間の行為に意味づけをしたいという欲望を叶えてくれるからです。人間の主体性なるものを一切否定するような出来事の圧倒的な力を前にして、それでもそこに主体性があったかのごとくに語るものこそが物語なのです。
ここで、ナチス・ドイツの強制収容所で生き残った女性(サヴァイバー女性)に関する本書の記述を引用しておきます(p.48)。
「(強制収容所で:津田)自分が生き残ったのは、収容所で殺された者たちに代わって、自分自身がより良く残された命を生きる使命を負っているからだと考えるようにしている、と(サヴァイバー女性は手紙に:津田)書く。と、その言葉に対しベッテルハイムは、自著において、そうした考え方を否定する。そのような『使命』などない、と彼は言う。生きのびた者が使命を負っているがゆえに生きのびたのだとしたら、死んだ者たちは、そのような使命がないがために死んだのであり、そこに死の理由があったことになる。死んだのが私ではなくほかの者たちであり、生きのびたのが彼らではなく私であったことに、いかなる理由も使命もありはしないのだ、と。」
こうしたベッテルハイムの発想に対し、著者は「その倫理的命令の厳しさに、わたしはたじろがずにはおれない」と書いています(同ページ)。しかし、少なくとも本書の後半において著者が主張しているのは、そうした厳格な「倫理的命令」の遂行であるように思われます。そして、僕がこの著作に違和感を覚えずにはいられなかったのは、まさしくその点なのです。
たとえば著者は、阪神大震災で息子を失った老婆についての『朝日新聞』の記事を引いて批判を行っています。その記事は次のようなものでした。
「葬儀を終えても、息子の死が信じられなかった。彼女は遺骨を海にまく決心をした。海に永遠の命を重ねたからだ。自然埋葬に取り組むグループに入っていて、息子も理解を示してくれていた。神戸港沖に、孫娘と散骨をしたのはその年の四月のことだった。(年末に帰郷して家事を手伝った息子が絞ってくれた:津田)雑巾は手元に残した。固く絞られて解けないその形にように、記憶が風化しないことを願った。・・・
震災の年の暮れ、医師から欝傾向にあると診断を受けた。処方してもらった薬を飲むと、すぐに晴れ晴れとした気分になった。だが彼女は薬を飲むのをやめた。このままでは息子を失った方しみまで薄れてしまうと恐れたからだ。・・・
寂しいときは、近くの海へゆき、庭に咲いた四季の花弁をまく。大阪の孫娘からも、海へ行ってきたよと連絡が入る。海と雑巾、凪く日も、荒れる日も、息子とどこかでつながっている。」(『朝日新聞』2000年1月7日)
著者が特に批判しているのは、この記事の最後の部分です(p.84)。
「息子とどこかでつながっていることを、息子は永遠の命を、海に、雑巾に、日々実感する母。物語は終わり、読者は理解し、感動する。そこには、読む者を不安に陥れたり脅かすものは何もない。なぜなら、すべては理解可能なのだから。」
要するに、著者はこの記事が描き出す「死んだ息子とつながっている」ことによって老婆が救済されたという物語を否定しているわけです。出来事の圧倒的な暴力は、そのような意味づけによって描き出されうるものでは決してないからだ、というわけです。
このような物語に対して、著者が賞揚しているのは、一言で言えば「後味の悪い」テクストです。出来事の圧倒的な力や人々の死の無意味さを読者に痛感させるようなテクストこそが、出来事は物語という枠には収まりきれないことを読者に認識させるからです。
けれども、物語が人を惹きつけるのは、それが<意味>をもたらしてくれるからに他なりません。戦争や災害によって人が死んだとき、物語はその死が決して無意味なものではないと残された人々に語ってくれるわけです。ハンナ・アーレントは、イサク・ディーネセンの「あらゆる悲しみも、それを物語にするか、それについての物語を語ることで、耐えられるものとなる。」という言葉を引いて、それが真実であることを認めています(ハンナ・アーレント、引田隆也ほか訳(1968=1994)『過去と未来の間』みすず書房、p.357)。
つまり、物語には悲しみを癒す働きがあり、それゆえに心に深い傷を負った人物ほどに物語を必要とするわけです。従って、そのような体験をしていない外部の者が、傷を抱える人物に癒しのための物語を作るな、ということは傲慢だとの謗りを免れないでしょう。上で引用したベッテルハイムの言葉にしても、強制収容所を体験したベッテルハイム自身はともかく、それを体験していない者がサバイヴァー女性の考え方を否定することは倫理的に許されることなのでしょうか。
そのような物語による救済を否定し、出来事の生々しさと常に向き合うことを著者は要求しています。そうした著者の姿勢は、内田樹さんが『ためらいの倫理学』で指摘しているように、この著作に非常な息苦しさを与えているように思います。もちろん、その息苦しさこそが、この著作に緊張感を与えており、作品として完成度を高めていることは否定できないわけですが。
けれども、出来事と可能な限り向き合った、より「ましな」物語を作ることすら拒否し、出来事の不条理さに拘泥している間に、より気持ちの良い、そしてそれだけに始末の悪い物語が増殖していくという状況を著者はどのように考えるのでしょうか。人間のささやかな幸せを描いた物語ですら、そこから排除されている「他者」がいるからという理由だけで、他のもっと質の悪い物語と同様に批判の対象とされてしまっても良いのしょうか。
戦争や強制収容所のような凶暴な出来事ほどではないにせよ、我々は日々、何らかの出来事と出くわし、その無意味さに直面しています。そのなかにあって、並外れた無意味さを痛感させるテクストを、日々、我々は新聞や読書を通じて消費しなければならないとするれば、その反動は限りなく滑稽で甘美な物語の逆襲という形をとって現れることになるのではないでしょうか。
本書の最後で、物語を否定して出来事に正面から向き合う「難民」、つまりお気楽な「国民の物語」からは排除された存在になることを著者は読者に求めています。しかし、それは本当に可能な選択肢なのでしょうか。
とまあ、いろいろと書いてきましたが、非常に刺激的な著作であることは間違いなく、おすすめの一冊です。(2005年9月)
佐藤郁哉ほか(2004)『制度と文化』日本経済新聞社
この著作は、社会学というよりも経営学に分類されうる著作で、企業文化や制度について解説されています。しかし、その視座は極めて社会学的であり、その意味でも興味深い著作です。企業の「風土」や「カラー」とも呼ばれる企業文化ですが、それが組織の運営にどのような影響を及ぼしているのかという従来の企業文化論を越えて、組織のアイデンティティの問題にまで踏み込んだ組織アイデンティティ論についても詳細な解説が行われています。たとえば、組織文化と組織アイデンティティの違いについては、次のように述べられています(p.97-98)。
「人々が価値を共有したり相互に魅力を感じていなくても、成員性の認知(同じ組織の一員だという認識:津田)という条件さえ満たされていれば、集団が形成され(成員性の認知は集団存在の十分条件)、またその反対に成員性の認知が存在しなければ、共有価値や相互の魅力があったとしても、集団は形成されない(成員性の認知は集団形成の必要条件)ということ」
このような組織アイデンティティが重要になる局面としては、たとえば企業同士の合併などがあるわけです。よく観察してみれば、両社とも似たような価値観や行動パターンを持っている。したがって、企業文化という観点から見れば、両社の合併はうまくいくはずなのですが、実際にはうまくいかない。なぜなら、組織アイデンティティの共有に失敗しているがゆえに、価値観や行動パターンの類似がむしろ「近親憎悪」のような形で噴出しているからだ、というわけです。しかし、だからといって組織の一体性を闇雲に主張したところで、組織内での生産性の向上につながるわけではない、と著者たちは述べています。では、どうすれば良いのでしょうか?それは、集団を競争のなかに置くことなのだそうです。ただしそれは集団内で成員相互を競争させるという意味での競争ではなく、他の集団と競争させることで集団としての一体感と生産性の向上とが結びつくというわけです。
…と、ここまで書いて、これは企業組織のアイデンティティ論としては目新しいのかもしれませんが、たとえばナショナル・アイデンティティという文脈に置き換えてみれば、それほど目新しくもないなぁ、ということに気づいてしまいました。ナショナル・アイデンティティの形成において、集団としての一体性を訴えるために「敵」の存在が強調されうることはしばしば指摘されることですしね…。
しかしまあ、企業のアイデンティティや、企業を取り巻く諸制度の社会的構築プロセスなど、社会学的な観点から企業を眺めた場合に何が見えてくるのかを理解するうえではなかなか役に立つ一冊ではないでしょうか。(2006年7月)
セルトー・ミシェル、山田登世子訳(1980=1990)『文化の政治学』
岩波書店
現代社会における「文化」の語られ方を学問や学校、マイノリティといった観点から論じている著作です。いかにもフランスという感じのする本で、なんとなくわかったような、わからないような、というのが正直な感想でした。ただ、ところどころに「なるほど」と思わせる指摘があり、読むのはそんなに苦痛ではありませんでした。僕が思うに、本書の中心は「権力としての知」ということであり、文化がどのように特権的に語られてきたのか、ということにあります。そこで、たとえば「民族誌的なエキゾチズムや『民衆主義的』エキゾチズムは、およそあらゆるエキゾチズムとたがわず、大人や人間やブルジョワたちに自己のイメージを提供するのを目的にしているのではないか」(本書p.77)なんていう、サイードを思わせるような指摘をするわけです。やや古めの本ですが、最近になって再販が出たので、普通の本屋さんでも手に入るでしょう。(2000年7月)
藤田弘夫(1991)『都市と権力』 創文社
食糧の生産を行っていない都市は、農村よりも飢えない。本書はこの大胆な仮説から、ユニークな権力論を通じて、都市の成立過程とその権力のメカニズムを解き明かしてゆきます。なんでこの人はこんなにいろんなことを知っているのだろう、と著者の博学さに驚かされる一方で、その論理の明快さにも舌を巻きます。都市社会学をやっている人のみならず、社会学に興味を持つ人なら(興味がなくとも)読んでまず損のない本だと思います。我々の周りにあふれているがゆえに、あることが当然だと思われてしまっている食糧。実はそれは全然当たり前のことではなく、世界中のあらゆるところに飢餓は存在します。人間にとって最も基本的かつ重要である食糧という問題を、本書を通じて一度考えてみてはいかがでしょうか。 (1998年)
真木悠介(1997)『時間の比較社会学』 岩波同時代ライブラリー
見田宗介さんが、多くの人に読んでもらうことを前提としない本を執筆するさいに使うのが真木悠介という名前だそうです。が、本書はそれでも結構読まれたらしく、1981年に出版されたのが、去年、岩波の同時代ライブラリーから再び出版されました。本書は、現在、過去、未来という直線的な時間感覚が他の時間感覚とどのように異なり、それが近代の社会編成とどのように結びついてきたのかを論じています。特に時間と貨幣との結びつきに関する議論には唸らされました。それ以外にも多くの興味深い議論がなされています。が、少々苦言を呈するなら、独特の文体で、少々意味が取りづらいところが結構あることでしょうか。 (1998年)
メルッチ・アルベルト、山之内靖ほか訳(1989=1997)『現在に生きる遊牧民』岩波書店
現代の社会運動の特質について論じた著作なのですが、社会運動という現象のみならず、権力や民主主義など現代社会の様々な側面について勉強になる本です。これまでの社会運動論の問題点や、環境保護運動や平和運動といった「新しい社会運動」の何が一体新しいのかということを明らかにしています。また、解説が非常に充実しており、批判的な研究の流れを知る上でも便利な本だということが出来るでしょう。 (1999年)
森島恒雄(1970)『魔女狩り』
岩波新書
15世紀から17世紀にかけて、西欧を席巻した魔女狩り。華やかなルネサンスの陰にあって、数多くの罪なき人々が魔女と呼ばれ、拷問され、殺されました。本書は、魔女狩りがどのような背景のもとで生じ、いかにして人々が「魔女」に仕立て上げられていったのかを明らかにしてゆきます。そして、そこからは「正義」の名のもとでこそ、人間は最も残酷に悪をなしうるのだということが見えてきます。このような魔女狩りは迷信の支配する社会でのみ生じうるものであって、現代社会では絶対にありえないことだとは言いきれません。魔女狩りの歴史から我々が学びうることもまた多いのではないでしょうか。 (1999年)
ロサルド・レナード、椎名美智訳(1989=1998)『文化と真実』
日本エディタースクール出版部
この本は社会学というよりは文化人類学の本に属するのかもしれませんが、今日の社会科学の非常に重要なテーマである、他者の文化をいかにして表象するかという問題を考えるうえで参考になると思います。つまり、文化はこれまでしばしば、一枚岩的で本質的なもの、として捉えられてきました。そうした考え方はしばしば文化本質主義につながり、社会分析で説明出来ない現象を全て文化のせいにしてみたり、文化というフィルターを通してしか人間を見ることが出来なくなるといった事態を招いてきました。加えて、その文化を「客観的」に観察することが出来るという前提があり、それがサイードの言う「オリエンタリズム」をもたらしてきました。本書はそうした事態を踏まえて、他の文化を表象することの難しさと可能性とを教えてくれています。(1998年)
|

