
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 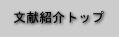    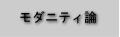 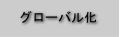
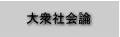  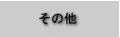
社会学入門・概論
イーグルトン・テリー、大橋洋一訳(1991=1999)『イデオロギーとは何か』 平凡社ライブラリー
これまでの思想・社会理論においてイデオロギーという用語がどのような意味で用いられてきたかを整理し、その意味を突き詰めてゆく本です。そう書くと、とてもつまらなさそうな感じがしますが、それどころか、実にスリリングかつ面白い本です。マルクス主義、ネオ・マルクス主義、ポスト・マルクス主義の流れが明快にわかりますし、イデオロギーがどのような機能を果しうるかについても、とても勉強になります。そのロジックの冴えや皮肉の面白さは特筆に値するでしょう。また、著者のイーグルトンはポスト・モダニズム的な発想には極めて批判的であり、正当なる左翼思想の継承者という感があります。なお、最近出たライブラリー版の方は改訳版に近くなっているそうなので、そちらを買った方がよいでしょう。(1999年)
ヴェーバー・マックス、尾高邦雄訳(1919=1936)『職業としての学問』 岩波文庫
大学で社会学を学ぶ人がはじめに読む(読まされる?)本として名高い本書ですが、やはりそれにはそれだけの理由があるということでしょう。教壇に立つものは「論壇上の小預言者」として自らの「政策」を学生に押し付けるべきではない、というヴェーバーの戒めは、今なお有効であるようにも思います。もっとも、ヴェーバー自身が「いかなる学問も絶対に無前提的ではない」と認めているように(本書p.68)、ヴェーバー自身は単純に価値自由なるものを信奉していたわけではないようです。『マックス・ヴェーバー入門』に書いてあるように、自らが立脚している価値を自覚していることが必要だ、ということなのでしょうか。とにかく、ちゃんと社会学を学びたいのであれば、やはり読んでおくべき本だとは思いますね。もっとも、僕はわりと最近になってようやく読んだのですが…。(2002年6月)。
ヴェーバー・マックス・清水幾太郎訳(1922=1972)『社会学の根本概念』
岩波文庫
マックス・ヴェーバーの死後に編纂された『経済と社会』の巻頭に収録された論文です。原本で30ページ、翻訳でも100ページ足らずの非常に薄い(そして安い)本なのですが、ヴェーバー社会学のエッセンスが詰まっており、非常に勉強になる本です。もちろん、初めて社会学を学ぶ人にはちょっとお勧めできませんが、いろいろと社会学の本を読んだ後に頭を整理したいとか、基本をしっかり押さえたくなったとかいう時には便利な本だと思います。最近、いろいろヴェーバーに関する「神話」の虚偽性が暴露されてきているわけですが、ヴェーバー本人がどうだったかはともかく、この本で志向されているような学問的厳密性を持って研究に取り組んでいきたいとは思います。(2003年3月)
エリアス・ノルベルト、徳安彰訳(1970=1994)『社会学とは何か』 法政大学出版局
個人や社会を、完全に孤立し相互作用をもたないモノのように捉える社会学の考え方に対し、本書はネットワークによって形成される個人・社会という観点から社会学の再構築をめざします。本書の著者であるエリアスは、晩年になってようやく認められた苦労の人で、本書も70歳を超えてからの著書です。しかし、パーソンズのシステム論批判を中心にラディカルな議論が展開されており、その権力観においても見るべきものがあると思われます。特に、エリアス独自のゲーム・モデルは非常に興味深く、ネットワークにおいて権力がいかに生み出されるかを容易に理解することが出来ます。タイトルから社会学の入門書のような感覚を受けますが(実際、入門書と本書にも書いてありますが)、一般の入門書とは一線を画しており、入門書だと思って読むと意外とてこずるかもしれません。 (1997年)
奥村隆編(1997)『社会学になにができるか』
八千代出版
若い研究者による、社会学の入門書なのですが、非常に面白い本です。特に、第1章自我論になにができるか、第7章文化装置論になにかできるか、が非常に面白いです。あと、第5章の権力論になにができるか、もなかなか面白いです。全体で見ると、この本のタイトルによくあらわれているように、社会学には一体なにができるのかという、社会学を志す者なら一度は考えたことがあるはずのテーマに正面から挑んでいます。私自身、学問をやることに意味があるのか、としばしば考えますが、そのヒントを与えてくれたように思います。少々、難を言えば、入門書の割には理解しにくい章があるのが残念だということでしょうか。 (1998年)
コリンズ・ランドル、友枝敏雄ほか訳(1994=1997)『社会学の歴史』
有斐閣
社会学の歴史を紛争理論、功利主義・合理的選択理論、デュルケム理論、ミクロ相互作用論という4つの伝統に分類し、その展開を整理している本です。社会学の入門書というにはちょっと難しすぎるかもしれませんが、自分の研究領域がどのような系譜に位置づけられうるのかを知るには最適の本だと思います。もちろん、これは「コリンズによる整理」ですから、彼独特の視点がかなり入っており、たとえばマルクスよりもエンゲルスを高く評価したりする点などは興味深く読めました。それにしても、こういう本を読むと、自分の勉強不足が改めて痛感されるところです。(2001年11月)
なだいなだ(1974)『権威と権力』
岩波新書
このホームページでも、なださんの『民族という名の宗教』を紹介しているのですが、それよりも20年ほど前に出版された本です。が、今でも再販が重ねられていることからもわかるように、とても面白い本で、名著と言ってよい本でしょう。権威や権力とはどのようなメカニズムで働くものなのか、という問題を学校や病院を舞台にして、分かりやすく解き明かしてゆきます。「父権の復活」の題目のもと、父親の権威の復活が頻繁に唱えられていますが、そうした議論がいかに一面的であるかが本書を読めばわかるでしょう。それにしても、最近の「父権の復活」なんて主張は、同じような主張が本書に登場することからもわかるように、ずーと前からなされてきた主張の焼き直しに過ぎないんだなぁと思いました。
(1998年)
バウマン・ジグムント、奥井智之訳(1990=1993)『社会学の考え方』 HBJ出版局
タイトルからもわかるように、社会学の教科書なのですが、ただの教科書ではありません。というか、著者独自の視点からこれまで社会学の議論を整理した著作、というべきものでしょう。よって、社会学の学説史などを追っているわけではなく、主に共同体のウチとソトがどのようにして決定され、それがどのように機能するのかということに議論の焦点を当てています。その意味でアウトサイダーやナショナリズムなどの問題を考える上で、よい見取り図になることでしょう。だたし、かなり大きな本屋でかろうじて手に入れたので、最近ではちょっと手に入りにくい本かもしれません。(1999年)
藤田弘夫・西原和久編(1996)『権力から読みとく 現代人の社会学・入門』 有斐閣アルマ
退屈な社会学の入門書が多いなかで、権力という観点から社会学を捉え直した刺激的な好著。単なる入門にとどまらず、入門書ではあまり扱われない時間概念やM.フーコーなどにも分かりやすい解説が加えられており、入門書とは思えない面白さ。デュルケムやマルクスといった社会学の大御所の思想には余り触れられていないのですが、通常の社会学の教科書を補うという意味で読むとよいのではないでしょうか。(1997年)
山之内靖(1997)『マックス・ヴェーバー入門』
岩波新書
マックス・ウェーバーは果たして近代を肯定していたのか。本書では、ウェーバーとニーチェとの関わりを論じながら、ウェーバーが近代という時代に内在する破壊的な衝動を見抜いていたことを論じてゆきます。ところで、ウェーバーの有名な言葉である「価値自由」。私はこの本を読むまで価値自由とは、価値自由とは目指すべき目標であると思っていたのですが、それは大いなる間違いでした。社会科学というものは、多かれ少なかれ特定の価値を前提とせざるを得ないということを自覚する必要がある、というのが価値自由なのだそうです。うーん、恥ずかしい。このように、私はウェーバーに関してはあまり知らないため、本書の位置づけに関しても確かなことは言えないのですが、面白い本であることは確かです。(1997年)
|

