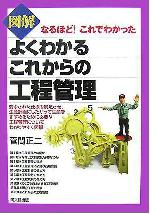トップページ‖製造業の皆様へ‖著書一覧‖すぐ使える生産設備類設計ノウハウ集‖生産現場の管理手法がよ〜くわかる本‖図解 よくわかるこれからの生産管理‖
高品質・低コスト・短納期を目指す<入門>外注管理‖モノづくり企業経営の勘どころ‖モノづくり教室‖アンケート
このホームページに関するお問い合わせは
mailto:PF2S-SGM@asahi-net.or.jpまで、
お求めの際はこちらから
お願い致します。
第1章 工程管理とは何か
| 1 |
|
わが国のモノづくりの現状はどうなっているのか |
| 2 |
|
そもそも工程とは何なのか |
| 3 |
|
工程にはどのような種類があるのか |
| 4 |
|
加工工程にはどんなものがあるのか |
| 5 |
|
組立工程にはどんなものがあるのか |
| 6 |
|
特殊工程にはどんなものがあるのか |
| 7 |
|
重要工程とは何なのか |
| 8 |
|
生産ラインにはどのような形態があるのか |
| 9 |
|
そもそも工程管理とは何なのか |
●COLUMN● 1 同じ蕎麦でも工程が異なる?
第2章 なぜ、工程管理が必要なのか
| 10 |
|
工程管理はなぜ必要なのか |
| 11 |
|
工程管理の目的は何なのか |
| 12 |
|
工程管理と生産管理の違いは何なのか |
| 13 |
|
工程管理はどこが行なうのか |
| 14 |
|
工程系列とは何なのか |
| 15 |
|
当該工程の品質信頼性を上げる |
| 16 |
|
自社に合った工程管理システムを構築する |
●COLUMN● 2 工程管理に必要な生産設備の分類記号
第3章 工程管理の現状
| 17 |
|
工程管理の内容は変化している |
| 18 |
|
工程管理システムは製品の影響を受けている |
| 19 |
|
生産ロットは小さくなっている |
| 20 |
|
工程は改善を通して進化している |
| 21 |
|
統計的手法を使って工程を管理している |
| 22 |
|
管理限界を設定して工程を管理している |
| 23 |
|
経験をベースに技術・ノウハウを蓄積している |
| 24 |
|
技術・ノウハウの流出を防止している |
●COLUMN● 3 1994年版ISO9001で要求されていた工程管理(参考)
第4章 工程管理に必要な各種知識
| 25 |
|
品質は工程でつくり込む |
| 26 |
|
工程FMEAで工程の信頼性を向上させる |
| 27 |
|
FPで工程の信頼性を向上させる |
| 28 |
|
IE手法を工程管理に活かす |
| 29 |
|
工程分析を実施して改善につなげる |
| 30 |
|
工程ばらしでラインバランスをよくする |
| 31 |
|
設備能力を把握しておく |
| 32 |
|
GT手法を使って量産効果を得る |
| 33 |
|
SLP手法を使ってヒト・モノの流れをよくする |
| 34 |
|
工場自働化の概念を把握しておく |
●COLUMN● 4 見かけの活動から実のある活動へ
第5章 工程計画の進め方
| 35 |
|
工程計画とは何をするのか |
| 36 |
|
工程計画の実施手順はどうなっているのか |
| 37 |
|
手順計画を立案する |
| 38 |
|
日程計画を立案する |
| 39 |
|
複雑な日程計画の立案にはPERTを使う |
| 40 |
|
内外製区分を決める |
| 41 |
|
工程図を作成する |
| 42 |
|
最適なライン形態を選定する |
| 43 |
|
CE、SEで立ち上げ期間を短縮する |
| 44 |
|
対象工程に柔軟性を持たせる |
| 45 |
|
異常検出装置を組み込む |
| 46 |
|
工程検査を盛り込む |
●COLUMN● 5 工程計画と工程再編
第6章 工程設計の進め方
| 47 |
|
工程設計の実施手順はどうなっているのか |
| 48 |
|
工程設計で効率的・経済的な生産を具現化させる |
| 49 |
|
QC工程表を作成、道具立てする |
| 50 |
|
設備・治工具仕様書を作成する |
| 51 |
|
設備条件などは標準化しておく |
| 52 |
|
省エネ設備を導入する |
| 53 |
|
MP情報を設備仕様に活かす |
| 54 |
|
工程数を極力減らす |
| 55 |
|
各工程のサイクルタイムを統一する |
| 56 |
|
同一工程に複数の作業を集約する |
| 57 |
|
工程間の運搬時間を短くする |
| 58 |
|
各工程の間口を最小化する |
●COLUMN● 6 初工程ネックの弊害
第7章 工程統制の進め方
| 59 |
|
工程会議で納期遅れなどのトラブルをなくす |
| 60 |
|
日常の工程管理は製品の納期確保に主眼をおく |
| 61 |
|
5Sで経済的なモノづくりを推進する |
| 62 |
|
仕掛り品を削減する |
| 63 |
|
工程編成のロスを少なくする |
| 64 |
|
不良率などの品質実績を把握し改善する |
| 65 |
|
設備故障などの実績を把握し改善する |
| 66 |
|
治具図面などは手元で管理する |
| 67 |
|
改善内容は図面にフィードバックしPDCAを回す |
| 68 |
|
初期流動管理を実施する |
| 69 |
|
生産委託先の工程を管理する |
●COLUMN● 7 “目で見る管理”のサポート役
第8章 QCDを向上させる工程管理
| 70 |
|
生産の実状を把握し改善活動につなげる |
| 71 |
|
工程を正常な状態に維持・管理する |
| 72 |
|
工数低減を推進する |
| 73 |
|
付加価値を産まない工程を減らす |
| 74 |
|
既存ラインを再編する |
| 75 |
|
一人生産方式を取り入れる |
| 76 |
|
治工具類を改良して使い勝手を良くする |
| 77 |
|
生産設備類を改造して使い勝手を良くする |
| 78 |
|
自主工程監査を実施する |
| 79 |
|
工程情報を管理に活かす |
| 80 |
|
技術・ノウハウを可視化する |
●COLUMN● 8 改善活動の効果
第9章 既存工程の改善
| 81 |
|
生産リードタイムを短縮する |
| 82 |
|
ネック工程を把握・改善する |
| 83 |
|
工程能力を向上させる |
| 84 |
|
設備総合効率を向上させる |
| 85 |
|
チョコ停を撲滅する |
| 86 |
|
設備故障の発生を防止する |
| 87 |
|
勘・コツ作業を排除する |
| 88 |
|
段取り改善を推進する |
| 89 |
|
活性示数を向上させる |
| 90 |
|
工場間の部品移動を改善する |
●COLUMN● 9 段取り貧乏
第10章 これからの工程管理
| 91 |
|
各工程で得た情報を共有化し工程管理に活かす |
| 92 |
|
POPで生産状況をリアルタイムに把握する |
| 93 |
|
LANで情報を共有する |
| 94 |
|
バーコードを工程管理に活かす |
| 95 |
|
ICタグ類を工程管理に活かす |
| 96 |
|
複合加工機をうまく使う |
| 97 |
|
重要工程には自動検査装置などを組み込む |
| 98 |
|
連続自動運転時間を延ばす |
| 99 |
|
標準化を推進する |
| 100 |
|
展示会・見本市などで最新の技術情報を入手・活用する |
●COLUMN●10 混流生産の現場で見る工程管理
<読者の皆様へ>
拙著をお読み戴き、ありがとうございました。
下記項目でミスがありました。お詫び申し上げます。
お手数おかけしてたいへん恐縮ですが、ご訂正をお願い申し上げます。
| 該当箇所 |
現状 |
訂正後 |
備考 |
| 79ページ下図 |
加工工数 |
加工個数 |
2刷以降は訂正済みです |
| 153ページ下図 |
MTTR 平均修復間隔 |
MTTR 平均修復時間 |
|
今後とも拙著をよろしくお願い申し上げます。