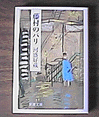|
|
|
|
|
4.藤村のパリ |
|
●「私の随想選 第一巻 私のパリ」● ★★ |
|
|
1991/03/05 |
好き時代のフランスに対する河盛さんの愛情が、みっちり詰まっている、
そんな印象を受けるエッセイ集です。 私のパリ/パリの日本人/パリの匂い /文学都市パリ/パリ物語/フランス歳時記 |
|
●「私の随想選 第二巻 私のフランス文学1」● ★★ |
|
|
1992/05/30 |
余り熟読できなかったものの、スタンダール、ユゴー(「レ・ミゼラブル」)、バルザック、これら大作家たちを描いた部分は、楽しかったです。各人の実生活における生々しい人間像が浮かび上がった、という印象です。 フランス文学との出会い/モラリスト /革命と文学/スタンダール雑記/ヴィクトル・ユゴー雑記/バルザック雑記/ゾラとモーパッサン (ゾラ他殺説・モーパッサン雑記)/アカデミー・フランセーズ |
|
●「私の随想選 第七巻 私の茶話」● ★★ |
|
|
|
一週間かけて、じっくり、楽しんだという読後感が残りました。三國一朗氏の月報に掲載された言葉が、すべてを語っていると思います。読んでいて疲れるということはまずない、途中で止めるとしたら、それは最後まで読んでしまうことが惜しいからに他ならない、という内容でした。 エスプリとユーモア /ことば・ことば・ことば/よむ・かく(本とつきあう法 他)/こしかた/くらし/喫煙室 |
|
●「藤村のパリ」● ★ 読売文学賞 |
|
|
1997年5月 2000年9月
|
3年前、本書が単行本として刊行された時、
関心があったのですが結局読み逃していました。今回文庫化されて、迷わず手が出た本です。 |