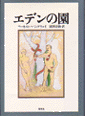|
|
|
|
|
2.ケニア 3.移動祝祭日 4.アフリカの緑の丘 5.アフリカ日記 6.危険な夏 |
|
●「エデンの園」● ★★ |
|
|
1990年11月 1989/04/04 |
作家の死後に発見された未完の長編。 ぶっきらぼうな語り口、簡素な表現は、まさしくヘミングウェイのもの。そして、その簡略された文章の中に、難解さをつくづく感じます。 退廃的、禁じられた恋愛関係を描いた作品であり、常に生と死を描いてきたヘミングウェイとしては異質なものを感じます。 |
|
●「ケニア」● ★☆ |
|
|
1999/09/02 |
本書は、ヘミングウェイの遺稿を長男パトリック氏がまとめ、生誕 100周年を記念して刊行されたものだそうです。既に発表されている「アフリカ日記」と、同一の遺稿を基にしているという経緯があります。 主なストーリィとして、妻メアリのライオン狩り物語があり、一方でヘミングウェイと現地のアフリカ娘ディバとの三角関係があります。主人公であるヘミングウェイは、ケニアにおける臨時監視員という立場らしく、白人の旦那として君臨している様子が見受けられます。 ヘミングウェイが語りたかったことは、如何にアフリカが自分の生きるに適した土地であるか、また自分が如何にアフリカに馴染んでいるか、ということだったように思います。しかし、その一方でヘミングウェイはパリの空気を愛する文化人であり、どれだけアフリカを愛しようが完全にアフリカに同化することはできない、という認識も持っていたようです。 主軸となるストーリィとして、メアリのライオン狩りの物語があることは前述した通りですが、ここでヘミングウェイはすっかり保護者の役に回っており、狩猟における駆け引き、狩りの難しさをコーチングするような具合です。狩りの楽しさを素直に描いた「アフリカの緑の丘」と比較すると、何を意図したのかがもうひとつ掴みきれない思いがします。 全体としては、かなり粗削りで、まとまりが不足している、という印象。楽しむというのには至らず、あくまで遺稿として読んだ、という気持ちです。 |
|
●「移動祝祭日(全集題名:回想のパリ)」● ★★★ |
|
|
1964年発表 1973年12月
2009年02月 1978/03/16
|
“移動祝祭日”とは、祝日のような固定的な祝祭日でなく、何時とは確定しない祝祭日、という意味だそうです。 書かれているのは1921〜26年のパリ、彼が22〜27歳の修行時代です。ジェイムズ・ジョイスも話の中に出てきますし、スコット・フィッツジェラルドとの交流も記されています。 本書は、とてもヘミングウェイらしい一冊であると同時に、素晴らしい作品です。 この作品の素晴らしさは、彼の心情が脈々と息づいており、その一方で実にさりげなく、淡々と語られているところにあります。 ヘミングウェイは生きることを限りなく愛し、それを記した。そして、それらが小説として売れた。彼の作品は売るために懸かれたものではなく、愛するが故に書かれたものであると感じます。その点において、彼は稀有な作家だったと思わざるを得ません。 |
|
●「アフリカの緑の丘」● ★★ |
|
|
1935年発表 1974年07月 1978/03/21 |
「移動祝祭日」は実に素晴らしい作品でしたが、本書も良い作品です。 生活を描いたのでなく、これが生活そのものなのです。 好い作品を読んだ後は、本当に気持ちが好いものです(ヘミングウェイの語調を真似をすると)。 |
|
●「アフリカ日記」● ★☆ |
|
|
1971年発表 1974年07月 1978/03/25 |
「アフリカの緑の丘」から
かなりの年月を経た後の話です。 本作品は遺稿の一部をまとめただけに、ヘミングウェイの意図がどこまで出ているのか判らないのですが、全体的には、人生における後輩達に人生航路の舵取りをしてやっている、という印象を受けます。 |
|
●「危険な夏」● ★★☆ |
|
|
1960年発表 1974年04月 1982/02/20 |
最初の闘牛案内書「午後の死」から約30年を経て発表された、闘牛にまつわるドラマを描いた作品。 「もう一度スペイン再訪が許されるのとは思わなかった」という文章から始まる本書は、あの青春の頃の情熱と感動に充ちた時代への回想へと私を誘い込んでいきます。 本書は、アントニオとルイス・ミゲルという二人の優れたマタドールの対決が主題になっています。二人を見るヘミングウェイの視線には、情熱よりも慈しみの気持ちが強く感じられます。 青春、人生の意義を、闘牛というドラマを通して作者と共に感じる、そんな作品であるように思います。 |
|
●「フィッツジェラルド/ヘミングウェイ往復書簡集
<日本語版>」● ★★ |
|
|
2009/06/11
|
ヘミングウェイとスコット・フィッツジェラルドの若き日におけるパリでの親交、今から35年も前にヘミングウェイ全集「回想のパリ」を読んで知って以来、ずっと記憶から消えることはありませんでした。 1925年にパリのディンゴ酒場で知り合った時、フィッツジェラルド28歳は既に「グレート・ギャッビー」により有名な作家、一方のヘミングウェイ25歳はまだ駆け出しの作家。 名作をモノにしようとお互いにハッパを掛け合い、金に困っているときは都合をつけ合い、お互いの作品の良いところ、悪いところを忌憚なく指摘し合っている様子が明らかです。 ※なお、1925年12月の手紙にある「戦争は何といっても一番いいテーマだ」というヘミングウェイの言葉、その後のヘミングウェイの代表作を思うと印象的です。 |