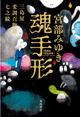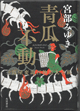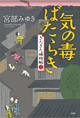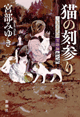|
|
41.さよならの儀式 42.黒武御神火御殿−三島屋変調百物語六之続− 43.きたきた捕物帖−きたきた捕物帖No.1− 44.魂手形−三島屋変調百物語七之続− 45.子宝船−きたきた捕物帖No.2− 46.よって件のごとし−三島屋変調百物語八之続− 47.ぼんぼん彩句(文庫改題:新しい花が咲く−ぼんぼん彩句−) 48.青瓜不動−三島屋変調百物語九之続− 49.気の毒ばたらき−きたきた捕物帖No.3− 50.猫の刻参り−三島屋変調百物語拾之続− |
【作家歴】、魔術はささやく、レベル7、龍は眠る、本所深川ふしぎ草紙、火車、とり残されて、淋しい狩人、震える岩、蒲生邸事件、鳩笛草、クロスファイア |
ぼんくら、模倣犯、ドリームバスター、あかんべえ、誰か、日暮らし、孤宿の人、名もなき毒、楽園 |
おそろし、英雄の書、小暮写眞館、あんじゅう、ばんば憑き、おまえさん、ソロモンの偽証(第1〜3部)、桜ほうさら |
泣き童子、ペテロの葬列、荒神、悲嘆の門、過ぎ去りし王国の城、希望荘、三鬼、この世の春、あやかし草紙、昨日がなければ明日もない |
| 「さよならの儀式 8 Science Fiction Stories」 ★★ | |
|
2022年10月
|
宮部さんには珍しい、本格的SF短編集。 SFアンソロジー“NOVA”に、2010〜18年に掲載された短編を集めての単行本化。 8篇が収録されていますが、各篇のSF趣向は本当に様々。それでも趣向の違いに戸惑うことがないのは、各篇の完成度が高いからでしょう。ですから、篇ごとの読み応えもたっぷり。 私としては、近未来設定ながら、非現実とは思えない「母の法律」と「戦闘員」の冒頭2篇がすこぶる面白かったです。 「わたしとワタシ」は、ごく短いタイムスリップもの。女子高生だったワタシが、現在45歳の私に対して突き付ける言葉に切れ味良いユーモアがあります。 表題作「さよならの儀式」はロボットもの。古くなり廃棄処分されることになったロボットの描き方が上手い! 「聖痕」は、宮部さんの極悪事件ものを彷彿させる篇。 「星に願いを」「海神の裔」「保安官の明日」は、そう持ってくるか、という3篇。 短編集といえども、宮部作品にハズレはないですね。 母の法律/戦闘員/わたしとワタシ/さよならの儀式/星に願いを/聖痕/海神の裔/保安官の明日 |
| 「黒武御神火御殿(くろたけごじんかごてん)−三島屋変調百物語 六之続−」 ★★ | |
|
2022年06月
|
「あやかし草紙」に続く、シリーズ第6巻。 なお、本巻から第2期とのことで、話の聞き役はおちかから、三島屋の次男坊である「小旦那」こと富次郎に変わります。 「泣きぼくろ」「姑の墓」「同行二人」はこれまで通りという印象ですが、いずれも割とあっさりした小篇。 聞き役が富次郎に変わったことから、肩慣らしという趣向なのでしょう。 事実、富次郎、おちかに較べると、覚悟も肝も未だ未だ据わっていない、という印象です。 まぁ徐々に慣れていくのでしょうけれど。 という訳で本巻の主眼はやはり、表題作である第4章の「黒武御神火御殿」。 博打にのめり込んでしまった札差の三男坊=甚三郎。ふと迷い込んだ先は見知らぬ屋敷。その屋敷で同様に入り込んでいた老人の亥之助、女中らしい女=お秋と出会いますが、それから3人、その屋敷から出られなくなってしまう。そしてさらに・・・。 いやはや何と恐ろしいことか。この屋敷の中は、異世界なのでしょうか。どこまでも逃れられないという臨場感がたっぷり。 読み応えある堂々の中編ストーリィですが、読み終わった後は、結局それだけのことだったのかと、それ以上に思いは広がらなかった感じです。 序/1.泣きぼくろ/2.姑の墓/3.同行二人/4.黒武御神火御殿 |
| 「きたきた捕物帖」 ★★☆ | |
|
2022年03月
|
久々の捕物帖。 読み始めた端からワクワクします。行間から沸々と楽しさが湧き出てくるようです。 ストーリィは、人望のあった深川元町の岡っ引き=文庫屋の千吉親分がフグの毒に当たって急死するところから始まります。 文庫(厚紙製の箱)売り稼業は、千吉の下でずっと商いに携わって来た一の子分=万作・おたま夫婦に。 千吉の代名詞だった朱房の十手は、生前に千吉も言い置いていたこととして、同心の沢井によって取り上げられることに。 おかげで下っ引きたちは散り散り。 本シリーズで主人公となる北一は、3歳の時に母親とはぐれ千吉親分の下で育てられた末の子分。千吉と昵懇だった深川の差配人=勘右衛門、通称<富勘>のおかげで、長屋に移り引き続き文庫稼業を続けられることになります。 この北一、まだ16歳。素直で真面目な性分ですが、頼りないところも多分にあります。 そんな北一が、周囲の人間に盛り立ててもらいながら、千吉親分の跡を追って文庫屋としても岡っ引きとしても成長していくシリーズになるのでしょう、そこに魅力と楽しさを感じます。 その富勘、「桜ほうさら」に登場した人物。そして北一が一人住まいを始めるのも、同作でお馴染みの富勘長屋、という次第。 周辺人物で特に光るのが、この富勘。さしづめ、あらゆる面での北一の指導役、引き回し役、というところでしょう。 本人はいずれ自立を目指し文庫屋稼業に励むつもりだったのに、様々な事件が起きる度、千吉親分の子分だったからとして岡っ引き仕事を押し付けられます。 しかし、北一の経験、実力不足は明らか。それを補うのが、幼い頃に疱瘡で視力を失ったという、千吉親分の寡婦となった松葉。この松葉が勘と洞察力に秀でていて、まさに安楽椅子探偵役。 それ以外にも、偶然親しくなった、旗本別邸の用人=青海新兵衛という気さくな武士の存在も楽しい。 そして、漸く第三話の「だんまり用心棒」にて、北一の貴重な相棒となるもうひとりの“きたさん”=喜多次が登場します。 これからのシリーズ展開がとても楽しみです。 1.ふぐと福笑い/2.双六神隠し/3.だんまり用心棒/4.冥土の花嫁 |
| 「魂手形(たまてがた)−三島屋変調百物語 七之続−」 ★★ | |
|
2023年06月
|
聞き手が三島屋の姪=おちかから、次男坊である「小旦那」こと富次郎(本作では22歳)に変わってから2作目、「黒武御神火御殿」に続くシリーズ第7弾。 今回は3篇を収録。 いつも思うのですが、その構成、物語の運び方がお見事。流石は宮部みゆきさん。元々“三島屋変調百物語”は、宮部さんの語りの上手さを存分に発揮してこその面白さ溢れるシリーズと言えますが。 「火焔太鼓」:美丈夫の若々しい侍が語り手。国許に置かれた、火事を防ぐための<火焔太鼓>に纏わる、そして実兄と嫂までが深く関わることになった藩の秘事、<ぬし様>にかかる信じ難い物語が語られます。 この篇で読み手は、三島屋変調百物語の世界にすんなり引きずり込まれます。 「一途の念」:富次郎が贔屓とする、屋台の団子売り=おみよ・16歳が語り手。5年もの間苦しみぬいてやっと死んだ母親と、兄3人に関わる不思議な、そして悲痛な出来事が語られます。 この篇にて、三島屋変調百物語が語り手を救う道になっていることを知らず知らずのうちに得心させられてしまいます。 「魂手形」:表題作の本篇は、本書頁の約半分を占める中篇。 語り手は粋な老人=吉富。55年前、木賃宿の息子だった15歳の時に出会った不思議な出来事について語り出します。 吉富を大事にしてくれた継母のお竹と共に吉富が世話した不思議な旅人=七之助。そして、その七之助が携えていたのは不思議な手形。 七之助、奇妙にも他の客人から離れた部屋が良いといい、吉富たちはその要望に応えるのですが、その泊り部屋を訪ねると何故か空気が冷たくなっている。やがてその理由は、七之助が共に旅していた○○の所為と分かるのですが・・・。 お竹という女性の個性的なキャラクターと、吉富との関わりから始まる篇。その冒頭から面白くてぐいぐいとストーリィに引っ張り込まれます。その所為か、気味が悪いとか思う暇もなく、何時の間にかどっぷりと変調百物語の世界に嵌り込んでいる、という風。 最後の顛末は、流石に仰天。まさか、そんな・・・!と。 ※なお、途中、おちかの近況も伝えられます。そこも嬉しい。 火焔太鼓/一途の念/魂手形 |
| 「子宝船−きたきた捕物帖(二)−」 ★★ | |
|
2024年08月
|
“きたきた捕物帖”第2弾。 宮部さん、本シリーズは「生涯、書き続けていきたい物語」なのだとか。 その言葉に沿うように、本作の主人公=北一は、急速に成長することはありません。むしろ、ゆっくりゆっくりと、亀の歩みの如き成長ぶりのようです。 でも生真面目でマメ、そんな北一の姿は好ましい。 だからこそ北一の周辺人物たちも、北一を支え、助力しようとするのでしょう。 そもそも北一、故・千吉親分の子分だったとはいえ、岡っ引きでも下っ引きでもなく、そうなれる当てさえもない。それなのにトラブルや事件にまみえると、その解決のため全力で走り回るのですから。 という訳で宮部さん曰く、北一は名探偵ではなく、市中で起こる大小のトラブル、もめごとを解決するトラブル・シューター(何でも屋)なのだとか。 北一を囲む、<チーム北一>による捕物帖、と言って良いのではないでしょうか。だからこそ、楽しい。 出番は少ないながら、そこに独自の存在感で加わるのが、もう一人の“きたさん”である喜多次。 前作では謎めいた存在のままでしたが、本作ではその経歴がちょっと打ち明けられます。 さらに“ぼんくら”シリーズから長い年月を得た政五郎親分、「おでこ」こと三太郎も登場してくるので、驚き。 北一が少しずつ成長していく姿を描く本シリーズ、ゆっくり味わって読み進んでいけたら、と思います。 ・「子宝船」:赤子に恵まれますようにと、小さな居酒屋の伊勢屋源右衛門が描いて配った宝船の絵が、とんだ騒動を引き起こします。 ・「おでこの中身」「人魚の毒」:北一がいつも利用していた弁当屋の一家3人が何者かに毒殺されます。その犯人を突き止めるため、北一が懸命に駆け回ります。岡っ引き仕事の苦みも語られる篇。 1.子宝船/2.おでこの中身/3.人魚の毒 |
| 「よって件のごとし−三島屋変調百物語 八之続−」 ★★ | |
|
2024年03月
|
百物語の聞き手が「小旦那」こと富次郎に変わってから3作目、「魂手形」に続くシリーズ第8弾。 なお、百物語の傍らでは、瓢箪古堂の勘一に嫁いだ従妹のおちかが懐妊、それに伴って三島屋にも変化が生じます。 また、長兄=伊一郎も度々顔を出します。 収録3篇、それぞれに趣向が異なり、その分楽しめます。 しかし、恐ろしさに震えあがったのは、表題作である「よって件のごとし」。この3作の順番が絶妙です。 ・「賽子と虻」:博打好きな土地神に虻の神? さらに賽子? 本篇は異世界のお話であります。 ・「土鍋女房」:<三笠の渡し>の船頭一家にまつわる話。日本の昔話+ちょっとオカルト的な話ですね。 ・「よって件のごとし」:さる藩におけるゾンビ話。 ただし、幾多もあるゾンビ話と同様に思ってはいけません。 よくある話だからこそ、宮部さんの語りの上手さが発揮されるというもの。 これこそ宮部さん独自の怪異譚ですし、本当に止めどもなく恐ろしく、話に強く引き込まれ、圧巻の面白さ。流石です。 ※兄の伊一郎がついに菱屋での奉公を終え、三島屋に戻ってくることになります。その経緯も語られますので、お楽しみに。 序/賽子と虻/土鍋女房/よって件のごとし |
| 「ぼんぼん彩句 bon bon saiku」 ★★ (文庫改題:新しい花が咲く−ぼんぼん彩句−) |
|
|
2025年12月
|
「あとがき」によると宮部さん、同年代の親しい人たちとBBK(ボケ防止カラオケ)なる会を設けていて、メンバーに俳句を切り出したところ全員が乗り気となり、BBKには(ボケ防止俳句会)の意味も付くことになったのだとか。 そこでBBK句会で詠まれた俳句をタイトルにして短編小説を書くという試みに挑戦、その結果生まれたのが本書だそうです。 さて、本短編集、題名となっている俳句を念頭にストーリィを味わうべきでしょうか。それともストーリィを味わったうえで、俳句と照らし合わせてみるべきでしょうか。 まぁ、どっちでも良いのでしょう。 ただし、俳句とストーリィがうまくマッチする、というのは至難のことではないかと感じます。 それでも、ストーリィテラーの宮部さんだからこそ、こうして12篇を紡ぐことができたのだろうと思います。 なお、楽しい話は極めて少ないようです。また、ろくでもない男と関わったことで味わった悲劇、という内容が割と多い。 俳句を捻るというと、そうした傾向のものが多くなってしまうのでしょうか。 12篇の中で私が楽しかったものは、次の4篇。 「プレゼントコートマフラームートンブーツ」、「山降りる旅駅ごとに花ひらき」、「薔薇落つる丑三つの刻誰ぞいぬ」、「冬晴れの遠出の先の野辺送り」。 とくに「薔薇落つる丑三つの刻誰ぞいぬ」は、絶賛したい逸品です。 一方、「鋏利し庭の鶏頭刎ね尽くす」と「月隠るついさっきまで人だった」は、本当に異常、気持ち悪いの一言に尽きます。 枯れ向日葵呼んで振り向く奴がいる(よし子)/鋏利し庭の鶏頭刎ね尽くす(薄露)/プレゼントコートマフラームートンブーツ(若好)/散ることは実るためなり桃の花(客過)/異国より訪れし婿墓洗う(衿香)/月隠るついさっきまで人だった(独言)/窓際のゴーヤカーテン実は二つ(今望)/山降りる旅駅ごとに花ひらき(灰酒)/薄闇や苔むす墓石に蜥蜴の子(石杖)/薔薇落つる丑三つの刻誰ぞいぬ(蒼心)/冬晴れの遠出の先の野辺送り(青賀)/同じ飯同じ菜を食ふ春日和(平和)/あとがき |
| 「青瓜不動(あおうりふどう)−三島屋変調百物語九之続−」 ★★ | |
|
2025年06月
|
「よって件のごとし」に続くシリーズ第9弾にして、百物語の聞き手が小旦那こと富次郎に変わってから4作目。 今回、三島屋の皆にとっての大きな出来事は、瓢箪古堂の若主人=勘一の元に嫁いだおちかがいよいよ出産間近。 無事出産できるのか、皆が心配しつつ、でも楽しみに待ちつつ、という状況。 ・そんな時に三島屋に現れたのは、かねてから懇意だという、各地を巡礼して回っているという行然坊。 そしてその行然坊の紹介により後日訪れてきたのは、いねと名乗る労働着姿の女性。そのいねの背には、不動明王像が。 その不動明王“うりんぼ様”が、おちかの出産を守ってくれる、という。 “うりんぼ様”はどのような経緯から現れた仏像なのか。その経緯を描いた「青瓜不動」の篇が、本巻では一番の読み応え、面白さ。 ・「だんだん人形」:語り手のひいひいひい祖父さんが味わった過酷な出来事が語られます。そして造られた土人形は、どのような想いが込められていたのか。 ・「自在の筆」:ちょっと後味の悪い篇。 ・「針雨の里」:捨て子だった門二郎は、12歳になった時から御劔山のふもとにある狭間村で働くことになります。その村の衆たちは皆、門二郎たちに優しかった。 しかし、その狭間村でずっと暮らすのは村の衆だけ。門二郎のように外から働き手としてやってきた子どもたちは、成長していくと村から出ていく。 その狭間村が抱えていた秘密は、一体何なのか。 そこにはファンタジー要素があるのですが、その優しさが気持ち良い、後味の良い篇です。 序/1.青瓜不動/2.だんだん人形/3.自在の筆/4.針雨の里 |
| 「気の毒ばたらき−きたきた捕り物帖(三)−」 ★★ | |
|
|
“きたきた捕物帖”第3弾。 捕物帖とはいいつつ、通常の時代版犯罪捜査とはちょいと異なります。なにしろ主人公の北一、本業は文庫売りで「親分」と言われる立場でもないし、経験・覚悟ともまだまだ半人前以下。 それでも富勘長屋の住人仲間等々から気遣われたり、励まされたりで、何とか事件解決に奮闘する。 そんな北一の、日々踏ん張る姿、周囲の人々から信用されその成長を期待される様子を見ているのが、とても楽しい。 その北一、腕っぷしもまるでお話にならず。本巻でも捕えようとした相手に昏倒させられ、自分の不足を自覚。 喜多次に乞い、身体を鍛え始めます。それもまた北一の成長の一歩というところでしょう。 本巻では2篇収録。 「気の毒ばたらき」は、放火事件。 故千吉親分の文庫商売は、その店ごと一の子分だった万作と女房のおたまが継いでいましたが、何とその店が放火に遭う。 放火犯人自体はすぐ判明しますが、何故そうした事件が生じたのか、放火によってどんなことが生じるのか。北一は身をもってそれを知ることになります。 表題にもなっている「気の毒ばたらき」とは火事場泥棒のこと。気の毒ですねぇと近づき油断させて盗みを働くという次第。 「化け物屋敷」は上記から一転、本格的な事件捜査もの。 懇意の貸本屋=村田屋治兵衛、30年近く前に新妻のおとよを殺害され、事件は未解決のまま。北一、治兵衛のために真相を解明しようと調べ始めます。 そのため、町奉行所で文書係を勤める「おでこ」こと三太郎を始め、検死の手練れである栗山与力、元同心で隠居の沢井蓮十郎にも助力を求めます。もちろん喜多次の協力も欠かせません。 そして蓮十郎の元には思いがけない協力者がいて・・・。 北一の粘りと覚悟が問われる展開。北一、見事にそれに応えたと言って良いでしょう。 本シリーズ、これからも楽しみです。 1.気の毒ばたらき/2.化け物屋敷 |
| 「猫の刻参り−三島屋変調百物語拾之続−」 ★★☆ | |
|
|
本シリーズ、元々どの巻も面白いのですが、本巻は特に面白かった! 猫神様、河童の神様、山の神様の御殿というファンタジー設定がどれも魅力である一方、最後に登場する女の生首というのは本当におどろおどろしい。 しかも、本巻の装画・挿画を担当されたこよりさんの画が本当に素晴らしい。その画だけでも十分魅了されます。 そして本巻で驚くのは、三島屋、長男・伊一郎に襲いかかった災厄とも言える出来事。またそれは、富次郎にも波及し、といった具合。 次巻の三島屋は一体どうなることやら、と興味を引き立てられます。 ・「猫の刻参り」:語り手はお文という中年女性。祖母のおぶんから聞いた話と。おぶん、嫁いだ先で夫に粗略にされ、姑・女中たちから女中同然に扱われます。しかも、実家の両親はただ我慢しろとだけ。以前に可愛がっていた猫が訪ねてきて、おぶんに代わって懲らしめてやろうか、と・・・。 ・「甲羅の伊達」:語り手は鼈甲屋の小僧である爪吉。亡くなった大旦那から聞いた話と。店で奉公していた若い女中のみぎわが水に棲むヌシ様=河童の三平太に救われた一切の出来事。 ・「百本包丁」:語り手は一膳飯屋の女房という初代。子どもの頃暮らしていた村が火事となり、母と共に逃げ出して行き着いた先は、山の神様の御殿。そこで母娘は包丁人を務めることに。 山犬の山桃、御台様というキャラクターが実に魅力です。 一方、本篇に登場する花蝶という女が本当に恐ろしい。こんな女が実際にいたとしたら、思わずぞぞっ・・・。 ・「富次郎の話−命の取引き」:三島屋、そして伊一郎に降りかかった災厄絡みの短い篇。 どんな経緯かというと、とても言葉にはできない程・・・。 本巻、ファンの方は、是非読み逃すことがありませんように。 序/1.猫の刻参り/2.甲羅の伊達/3.百本包丁/富次郎の話−命の取引き |
宮部みゆき作品ページ No.1 へ 宮部みゆき作品ページ No.2 へ
宮部みゆき作品ページ No.3 へ 宮部みゆき作品ページ No.4 へ