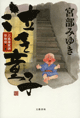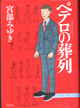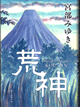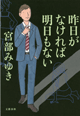|
|
31.泣き童子−三島屋変調百物語三之続− 32.ペテロの葬列−杉村三郎シリーズNo.3− 33.荒神 34.悲嘆の門 35.過ぎ去りし王国の城 36.希望荘−杉村三郎シリーズNo.4− 37.三鬼−三島屋変調百物語四之続− 38.この世の春 39.あやかし草紙−三島屋変調百物語伍之続− 40.昨日がなければ明日もない −杉村三郎シリーズNo.5− |
【作家歴】、魔術はささやく、レベル7、龍は眠る、本所深川ふしぎ草紙、火車、とり残されて、淋しい狩人、震える岩、蒲生邸事件、鳩笛草、クロスファイア |
ぼんくら、模倣犯、ドリームバスター、あかんべえ、誰か、日暮らし、孤宿の人、名もなき毒、楽園 |
おそろし、英雄の書、小暮写眞館、あんじゅう、ばんば憑き、おまえさん、ソロモンの偽証(第1〜3部)、桜ほうさら |
|
さよならの儀式、黒武御神火御殿、きたきた捕物帖、魂手形、子宝船、よって件のごとし、ぼんぼん彩句、青瓜不動、気の毒ばたらき、猫の刻参り |
| 31. | |
|
「泣き童子(わらし)−三島屋変調百物語 三之続−」 ★★ |
|
|
2016年06月
|
姪であるおちかの傷心を癒そうと三島屋伊兵衛が始めたのが、不思議な出来事を体験した人にそれを物語って貰う“百物語”。聞き手はもちろん哀しい思いを今も引きずるおちかです。 そんな百物語の「おそろし」「あんじゅう」に続く第3巻。 冒頭2篇の「魂取の池」「くりから御殿」はごく普通に不思議なあるいは恐ろしい話ですが、まだまだ序盤。 本書でいちばん恐ろしい思いをしたのは表題作の「泣き童子」。拾われて育てられた末吉が何故かある状況になると酷く泣いて泣き止まない。そこにどんな秘密があるのか。やがてその状況は明らかになりますが、それが再現されてしまうところがとても恐ろしい。特にその子供の所為でも何でもないことのために何故幼い子供が悲劇を身に受けなければならないのか。真の恐ろしさはそこにあります。そこが宮部さん、上手い! 「小雪舞う日の怪談語り」は、珍しくも有力札差が毎冬行うという怪談語りの会におちかが招待されて出向きます。おちかが唯一の聞き手ではなく、多数の聴衆の中でおちかもその一人というのが珍しい。この会で途中仕掛けもあり、計5話が語られます。 語られる話を聞く面白さという点では本怪談語りも、おちかが聞き役となる話と全く遜色は有りません。 なお、本章の最初と最後でおちかとあるものとの出会いがあります。雪の季節という中で心が温まるエピソードです。 「まぐる笛」はこうした妖し話としてはかなり異色。また「節気顔」はかなりオカルト風です。 一冊の中でいろいろな趣向の話が楽しめるとあって、今後の続刊がまだまだ楽しみです。 魂取の池/くりから御殿/泣き童子/小雪舞う日の怪談語り/まぐる笛/節気顔 |
| 32. | |
|
「ペテロの葬列」 ★★ |
|
|
2016年04月
|
「誰か」「名もなき毒」に続く、平凡なサラリーマン=杉村三郎を主人公とするシリーズ第3弾。 大企業・今田コンツェルンの総帥=今田嘉親の外腹の娘である菜穂子と結婚するにあたり、その条件としてグループ広報誌の編集部社員となったというのが主人公の現在の状況。 その杉村、女性編集長の園田と役員OBの取材に出掛けた帰り、乗ったバスが拳銃を持った一人の老人にバスジャックされてしまいます。 事件はそれなりの経緯で解決したものの、以前の事件に懲りず、またもや杉浦はバスジャック事件の余波である問題事に巻き込まれてしまいます。 単なる素人に過ぎない主人公、事件の奥底に隠された真相を明らかにすることができるのか。 前2作でも同様でしたが、素人が探偵役を務める所為か何となく緊張感を書いていてどう読めば良いのか戸惑うところもあったのですが、3作目となるとそれなりに慣れて来た気がします。 それは読む側だけでなく、本ストーリィにおいて主人公はしばしば、事件に慣れてきたという言葉を口にします。 もしや本シリーズ、素人が探偵役となるミステリという試みであったのか、と今更ながらに気付きました。 事件は、バスジャックから投資詐欺へと問題は変遷していきますが、それだけのストーリィで終ったのであればそう驚くことではありません。 驚いたのは、最後の最後で主人公に突然降りかかってきた驚愕の事実。主人公より読み手であるこちらの方が余っ程動転してしまったかもしれません。 結局、全体を俯瞰してみるとその究極のところは、多くの登場人物たちも含め、自分の居場所、生きる道探しというテーマが根底にあったのではないかと思う次第です。 さて、本シリーズの続き、まだありそうな気がします。次作品で主人公の身分は果たしてどうなっているのやら。 宮部さん、最初からこうした大きな流れを考えていたのでしょうか。もうしそうだとすると、その構想力の大きさにはただ頭を下げるばかりです。 ※ペテロは12使徒の一人で、一旦キリストを知らないと嘘を付き、その後に恥じて正直に言い殉教した人物。その題名から本書内容をどう紐解くのか。それは読んでのお楽しみです。 |
| 33. | |
|
「荒 神」 ★★ |
|
|
2017年07月
|
江戸時代の奥州、大平良山の両側にあり互いに反目し合う二つの藩が舞台。 その一方である香山藩の山中にある仁谷村を、突如“怪物”が襲い、村人たちはその怪物に喰い殺される等々して全滅。 11歳の蓑吉がただ一人逃れ、永津野藩の名賀村に暮す浪人者の榊田宗栄、村人らから“小台様”と親しまれている訳有りの女性=朱音に救われますが、その怪物は永津野藩にも現れ、人々に襲いかかります。 身の毛もよだつ巨大な怪物の正体は何なのか、果たして人間に対する山神の怒りの現れなのか。そしてその怪物を藩士たち、村人たちは果たして退治することができるのか。 まさに時代版妖獣もの、といったストーリィ。 怪物のおどろおどろしさ、パニックに陥る人々、その地獄絵の描写たるや相当なもの。その展開の上手さは流石に宮部みゆきと思わされますが、それだけなら単なる時代もの怪物譚に終わってしまうところ。 それが後半に入り、怪物の正体について糸口がつかめた辺りから俄然面白くなり、ストーリィにも奥行きが出てきます。 そこに至って初めて、それまでただバラバラに登場している観のあった主要登場人物の存在が、それぞれ意味あるものとして浮かび上がってきます。 永津野藩側からは朱音、榊田宗栄、朱音の実兄で藩主側近ながら酷薄な人物として恐れられる曽谷弾正、香山藩側からは蓑吉、藩士の小日向直弥、番方・志野家の奉公人であるやじ等々、それぞれが怪物との対決を目指して再び山に分け入ります。 一旦読み始めると、加速度的にどんどん引き込まれてしまうストーリィ。ただし、読後感を率直に言わせてもらうと、特に何かが残るということはなし。 その意味では本書、時代版エンターテインメントというに尽きます。それでも、朱音という女性の残像は実に鮮やかです。 序.夜の森/1.逃散/2.降魔/3.襲来/4.死闘/5.荒神/結.春の森 |
| 34. | |
|
「悲嘆の門」 ★★ |
|
|
2017年12月
|
ある夜、廃墟ビルの屋上に“かいぶつ”が舞い降りてくる。 屋上にあるガーゴイル像が少しずつ姿を変えているという目撃情報、姿を消した老人を探すと言ったまま消息を絶ったバイト仲間という各々の理由から、大学生の三島孝太郎と元刑事の都筑茂典が出会ったそのビルで2人が目撃したものは・・・・。 ホラーサスペンスのような気配を漂わせて開幕した本作品は、6年前刊行の「英雄の書」と対を成す物語という。 しかし、どう関係するのか、どう対になっているのか、出だしのストーリィからは皆目見当がつきません。その点が明らかになるのは中盤、“かいぶつ”が2人に語ったことと、ある人物の登場から。 それを機に本ストーリィは、異世界に跨る壮大なフィクションとして大きく膨らんでいき、読み手は圧倒されるばかりです。 読み応えたっぷりの内容に予想もつかない展開、この辺りは宮部さんが得意とするところの描きっぷりと思いますが、それは「英雄の書」の世界設定を借用したためであって、本書を通じて伝えようとしたことは、実は単純なことではないかと思うのです。 一言で言ってしまうと、現代社会で肥大化する一方の病巣。具体的には、ネット社会であるが故に悪意ある言葉が安易にばらまかれ、また身勝手なルールを振りかざし自分だけはいいんだ、という主張する輩も目につきます。 最近発生している凶悪犯罪を思い起こすと、それは絵空事とは言えないとリアルに恐ろしくなってきます。 一旦口にした言葉は決して消え去ることなく、自分の身に跳ね返り蓄積されていく。言葉とはそんなもの。 言葉を大切に扱うか粗末にするかによって、そこから紡ぎだされる物語も変わってゆく、そんな小説家らしい現代社会への警告が本ストーリィの中から聞こえてくるような気がします。 「英雄の書」までは行かずとも本作品にて繰り広げられる世界観は理解するのに少々難解なところがあります。それでも“かいぶつ”の存在によってもたらされる迫力は中々のもの。 宮部さんならではの異世界ファンタジー、どうぞご賞味あれ。 ブロローグ/1.砂漠のなかの一粒の砂/2.死神/3.<輪>と戦士/4.狩猟/終章.悲嘆の門 |
| 35. | |
|
「過ぎ去りし王国の城 The Castle Kingdom Gone」 ★★ |
|
|
2018年06月
|
中学3年生の尾垣真が拾った西欧風古城のデッサン絵、真はその画の中に引きこまれそうになり愕然とします。 しかし、小さな絵の中に自分が入れる訳がない。 クラスで目立たず、友達もいない真が勇気を奮ってその不思議な絵のことを打ち明けた相手は、ハブられ女子の城田珠美。美術部に所属し県のコンクールで入賞したこともある実力者である城田に、絵の中に自身のアバターを描き込んでもらい、それによって絵の中に入り込もうとしたもの。 その絵の中で真が見たものは、塔に閉じ込められているらしい女の子の姿。しかも、絵の中で知り合ったパクさんから、その女の子は10年前に失踪した子だと知らされ・・・・。 絵の中に引き込まれかけ・・・というと「ナルニア物語」を連想しますが、本書は真や珠美らが絵の中の世界に入り込んで閉じ込められていた少女を救う、といった単純な冒険ファンタジー物語ではありません。 絵が漂わせる不穏な雰囲気、一体この絵は何故?という疑問。そのうえ絵の中に入り込む度にエネルギーを絵に吸い取られ、危険な状態に陥ることもしばしば。 最初こそ冒険ファンタジー物語かと思ったのですが、絵の中での冒険は少しも広がりません。むしろ少女失踪の謎、絵自体の謎の方が深まっていき、趣向としてはミステリ小説のようです。 しかし、謎解きは究極の冒険へと繋がって行きます。その辺りの展開が宮部さんらしく実に上手い、奇想天外なもの。 本ストーリィから伝わって来るものは何なのか。それはやはり人は人と結びつくことによって救われる、ということなのではないかと思います。そしてそれを踏み台として人は先へと進むことが出来るのではないか。 古城の絵の中という不思議な世界観に加え、間もなく卒業の時を迎える中学生2人の旅立ちの清々しさを味わえるという、不思議さ&爽快さという達成感あるストーリィ。満足です。 1.古城のデッサン/2.塔のなかの姫君/3.探索仲間/4.城主 |
| 「希望荘」 ★★ | |
|
2018年11月
|
「誰か」「名もなき毒」「ペテロの葬列」に続く“杉村三郎”シリーズ第4弾。 前作で菜穂子と離婚し今多コンツェルンと決別した杉村三郎は、本書で<杉村探偵事務所>を開業、私立探偵となっています。 元は編集者と言いつつ、難事件の渦中に巻き込まれることの多かった主人公の三郎、私立探偵を稼業とすることについて何ら違和感はありません。 本書で杉村は、依頼を受け4つの事件解明に挑みます。 「聖域」:依頼人は近所に住む老婦人の盛田さん。亡くなったと知らされていた同じアパートで独り暮らしだった三雲勝枝そっくりの、裕福そうな老婦人を見かけた。本人かどうか確認して欲しいとの依頼。 「希望荘」:老人ホームで死去した実父=武藤寛二が、死ぬ前に「人を殺したことがある」と洩らしていた。その真偽を調べてほしいという息子の相沢幸司氏からの依頼。 「砂男」:離婚後故郷に戻って農業市場で臨時働きしていた三郎は、探偵事務所<オフィス蠣殻>の2代目社長=蠣殻昴から、評判になっていた蕎麦屋の店主=巻田広樹が駆け落ちして失踪したという事件の調査を手伝ってほしいと頼まれます。 「二重身」:母子家庭の女子高校生=伊知明日菜から、母親が交際していた雑貨店の店主=昭見豊が東日本大震災時に失踪したまま。その行方を捜して欲しいとの依頼。 私立探偵ですから、いきなり殺人事件とか緊迫するストーリィにはなりません。 むしろ、素人探偵的だからこそ、関係者へ丁寧な聞き取りをすることによって調査を進める三郎に読み手が一体感を抱き、一緒になって事件を調べていくという面白さを感じることができます。 三郎の聞き取り調査によって浮かび上がってくるのは、登場人物たちそれぞれの多様な人生模様。彼らの人生を知ることこそ、本書の読み応えと言って過言ではないでしょう。 語りの上手さ、登場人物の多さ、その多彩さも本書の魅力。 各篇ストーリィには、ハッピーエンドも、すっきりとした解決もありません。 むしろ哀感が残る結末ですが、残った人たちは頑張って人生を歩んで行って欲しいという願いにも似た想いが残ります。 それはちょうど、主人公の杉村三郎も言えること。 聖域/希望荘/砂男/二重身(ドッペルゲンガー) |
|
「三 鬼−三島屋変調百物語 四之続−」 ★★ |
|
|
2019年06月
|
“三島屋変調百物語”シリーズ、「泣き童子」に続く第4巻。今回は日本経済新聞社系出版社からの刊行です。 相変わらず 560頁余という大部な一冊。読み終えるのには時間がかかるだろうなぁと思っていたのですが、日経新聞朝刊に連載されていた時に読んでいましたので再読となり、すんなり読めました。 このシリーズは、川崎の実家にいた頃起きた事件で心に傷を負ったおちかが、叔父の伊兵衛が営む江戸は神田にある袋物店「三島屋」に身を移して“百物語”を聞きながら再生の道を探っていくという長編としての魅力が一つ。そしてもう一つの魅力は、“物語る”という方法で味わえる読み切り物語の面白さ。 それは本シリーズのスタート以来、変わるところはありません。 「迷いの旅籠」は、江戸近郊の小森村、小作人の娘である13歳のおつぎが語り手。村にやってきた絵師の白杖先生が、今は無人の離れ屋にある種の絵を描いたことから信じ難いことが起きる、という話。それはいったい・・・・。 「食客ひだる神」は、人気仕出し弁当屋<だるま屋>の亭主、房五郎が語り手。何故か夏場休業してしまうこのだるま屋、その隠された事情とは・・・・。 「三鬼」は、改易されたばかりの栗山藩、その江戸家老だった村井清左衛門が語り手。若い頃、故郷で山番士を命じられて赴任したその洞ヶ森村で経験した怪しげな出来事とは・・・・。 「おくらさま」は、痩せ衰えた老女でありながら振り袖姿で現れたお梅が語り手。お梅が語り終えた直後、その姿は煙のように消えていた。そこにどんな謎があったのか・・・。 4篇それぞれの味わいですが、その中で「食客ひだる神」はコミカルな面白さをもった篇。 最後の「おくらさま」で新しい登場人物が顔を出します。 一人は、他店に奉公へ出ていた従兄の富次郎がある事情から養生をしに三島屋へ戻ってきます。もう一人は、貸本屋「瓢箪古堂」店主の倅である勘一。その2人がお梅をめぐるおちかの探索を手伝います。 一方、寺子屋の先生だった浪人、青野利一郎がさる事情で故郷に戻ることになり、本シリーズから退場です。 このシリーズ、一歩一歩進みつつ、まだまだ続きそうです。 宮部さんのライフワークと言うべき作品になるのかも。 序/1.迷いの旅籠/2.食客ひだる神/3.三鬼/4.おくらさま |
|
「この世の春」 ★★☆ |
|
|
2019年12月
|
いやー、面白かったです。 上下巻併せて 800頁という大部な作品ですが、頭からシッポの先まで常に面白く、頁を繰る都度予想もしない展開続きで、一瞬たりとも飽きるということがありませんでした。時間さえあれば、上下巻一気に読了してしまったことでしょう。 さて、ストーリィの舞台は、下野北見藩二万石。 名君として信望を集めていた5代藩主=北見成興が突然死去したことにより、英明で美丈夫という評判の嫡男=重興が6代藩主の座に就きます。 しかし、その重興が家臣からの<押込>に遭い蟄居、従弟の尚正が7代藩主に就くという政変が起こります。 その原因は何かというと、重興が召し抱えて重用した伊東成孝の専横ぶりが批判の的になったというだけでなく、重興自身に度々精神的な錯乱が起きるという憂慮する状況があったらしい。 出戻りで、元作事方組頭の父親と隠居所で暮らしていた各務多紀は、父の死後、従弟の田島半十郎から請われ、ある場所へと向かいます。 そこは、重興の病状を見極め、何とか治癒をと願う元江戸家老の石野織部老人、藩医の次男である白田登らが重興と共に暮らす藩主別邸の<五香苑>だった。 一方、死者の魂と語る“御霊繰”という技を伝える出土村の住人が皆殺しにされるという惨劇が16年前に起きていたことが明らかになります。そのうえ、さらに・・・。 重興の不可解な病状の原因は、悪霊の仕業か? それとも精神的病なのか? いずれにせよ、それが起きた経緯は何なのか? 現代風に言えば、時代版“サイコ・ミステリ”という内容。 本作の面白さが、事実の見極め、謎の解明、重興に救いはもたされるのか、という点にあるのは勿論なのですが、もうひとつの魅力は登場人物たちにあると言って過言ではありません。 数多くの人物が次から次へと登場しますが、その殆どが善良で、一人一人魅力ある人物ばかりなのです。 その一方、邪でこの悲劇をもたらす原因となった人物は少数。それなのにその少数の人間が、実に多くの人を悲劇に落とし込んでいた、という事実。 そうした傾向は現実の世界においても言えることでしょう。その現実性が、宮部みゆき作品の奥深い力と思います。 本作の主人公は一応、各務多紀。その気丈さが事態を打開していくきっかけになるという点で魅力的な女性ですが、もう一人惹かれるのは五香苑の女中であるお鈴。大火で家族を失い、自身も大火傷し未だに顔と体にはその痕が残っている少女ですが、その健気な姿はとても愛おしい。「孤宿の人」に登場した少女ほうを連想されられ、ほうと並んで忘れ難い少女の一人となりました。 (上巻)1.押込/2.囚人/3.亡霊/4.呪縛/5.暗雲/6.因果/ (下巻)7.闇と光/8.解明/9.愛憎/終章.この世の春 |
| 「あやかし草紙−三島屋変調百物語 伍之続−」 ★★ | |
|
2020年05月
|
「三鬼」に続く、シリーズ第5巻。 相変わらず 570頁と分厚い一冊ですが、その分厚さが全く気にならない所が、本書の面白さを表しています。 むしろ、この面白さをたっぷり味わうためには、このくらいの厚さがあって当然、というべきなのでしょう。 おちかが川崎宿の実家から三島屋にやってきて早や3年。おちかももうすぐ20歳になろうとしています。 本巻では、「三鬼」で体の具合を悪くし奉公先から戻って来た伊兵衛とお民夫婦の次男である富次郎が、おちかと共に百物語の聞き手となります。 また、その富次郎と互いに美味いもの好き、甘いもの好きで意気投合した貸本屋<瓢箪古堂>の若主人である勘一が、折に触れ顔を出します。 「開かずの間」:飯屋を営む平吉が語った、塩断ちがきっかけとなって実家の両親・兄姉全員が死ぬに至った経緯とは。人間の底にある邪な心が絡んでいるからこそ、恐ろしい・・・。 「だんまり姫」:老女せいが若い頃に仕えた花兜城の姫君、何故か一言も口を利かず。ファンタジーで楽しさもある篇。 「面の家」:盗み、嘘と性分の悪いところがあるからこそ奉公人に向いていると言われ、お種が奉公した家の秘密は・・・。 「あやかし草紙」:今回の一番目の語り手は、瓢箪古堂の若主人である勘一。そこからどんな展開が生まれるのやら。 「金目の猫」:今回の語り手は、三島屋の長男である伊一郎。そして、聞き手は富次郎が務めます。2人がまだ10歳、 8歳だった頃の出来事。 そろそろかなぁと思っていましたが、そう来るかァと予想外の成り行きに舌を巻いたのは、宮部さんの語りの上手さ、と言う他ありません。 このシリーズもここで閉幕かと思っていたら、まだまだ続くようです(本当に百物語まで行くのかなぁ〜)。 とりあえずは、本巻がシリーズ第一期の完結篇とのこと。 序/1.開けずの間/2.だんまり姫/3.面の家/4.あやかし草紙/5.金目の猫 |
| 「昨日がなければ明日もない」 ★★ | |
|
2021年05月
|
“杉村三郎”シリーズ第5弾。 探偵事務所を開きれっきとした私立探偵となってから2作目。 流石に巧い! ストーリィ3篇とも何と達者なことか。今回も唸らされるばかりです。 3篇とも全く趣向の異なる事件。ですから贅沢に楽しめます。 そして肝心の杉村三郎、私立探偵としてのキャラが抜群に良い。 出しゃばらず、目立ち過ぎず、ストーリィの語り手かつ進行役としての役割を見事に果たしています。 この杉村三郎というキャラクターを生み出したことにつき、宮部さんにいつまでも拍手を送りたい。 ・「絶対零度」:結婚した娘と連絡が取れない、という母親の筥崎夫人からの依頼。娘が自殺未遂、そのため入院させた、原因は筥崎夫人との関係というのが、その夫の弁。娘との面会も許されず、病状も教えてもらえないという事情。 ちょっとした家庭内の揉め事かと思ったのですが、その裏にかくも陰惨な真相が隠されていたとは、絶句。 極悪非道な人物・・・こんな存在がいたら誰も被害から逃れようがないのではないか。凶悪な人物を書かせると、宮部さんの筆は本当に凄まじい。恐ろしさに震え上がる程です。 ・「華燭」:大家である竹中夫人からの依頼。中2の小崎加奈が従姉の結婚披露宴に出席するにつき、その付き添い仕事。 何ということもない筈でしたが、披露宴会場に着くと2組の披露宴が共に開宴遅れで大混乱の状態。一体何が? 結婚、結婚式という題材にしたドタバタ劇なのですが、実に現代的でありかつブラックユーモア的。 加奈の従姉である靜香に対する思い、靜香の決意にかかる言葉が共に印象的です。 ・「昨日がなければ明日もない」:まるで“モンスター女”と評すべきシングルマザー=朽田美姫(29歳)の強欲な動機による仕事依頼。 身勝手極まりない人物、これもまた現代社会的な存在。 たった一人そんな人物がいるだけで、善意の人物がとてつもなく苦しめられてしまう。その点は「絶対零度」と共通します。 絶対零度/華燭/昨日がなければ明日もない |
宮部みゆき作品ページ No.1 へ 宮部みゆき作品ページ No.2 へ
宮部みゆき作品ページ No.3 へ 宮部みゆき作品ページ No.5 へ