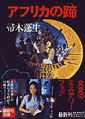|
|
|
|
|
2.十二年目の映像 3.カシスの舞い 4.空の色紙 5.賞の柩 6.三たびの海峡 7.アフリカの蹄 8.臓器農場 9.閉鎖病棟 10.総統の防具(文庫改題:ヒトラーの防具) |
|
|
|
|
移された顔、天に星地に花、悲素、受難、守教、襲来、沙林、花散る里の病棟 |
|
●「白い夏の墓標」● ★★ |
|
|
1983年01月
|
帚木さんのデビュー作。 パリの国際ウイルス会議に出席した佐伯教授が主人公。 |
|
●「十二年目の映像」● ★ |
|
|
1986年01月 2014年11月 1996/12/21 |
他の帚木作品とは、まるで趣の異なる作品です。そして、全体的に暗い。 |
|
●「カシスの舞い」● ★ |
|
|
1983年10月 1986年11月
1996/09/26 |
「臓器農場」の先駆作となっている作品です。 |
|
●「空の色紙」● ★ |
|
|
1985年02月 1997年12月
|
メディカル・フィクション中編3篇を収録した一冊。しかし、読んで面白かった、 という作品ではありませんでした。 「空の色紙」
1984年 「嘘の連続切符」
1977年 |
|
●「賞の柩」● ★★ 日本推理サスペンス大賞佳作 |
|
|
1996年02月 2013年11月 1996/02/25 |
長篇ミステリというには比較的短い作品ですが、良い作品でした。単にミステリというに留まらず、人が生きていく上で大切なものを謳いあげている点、ラブロマンスが明るい局面にて自然な形で
織り込まれている点。 ストーリィは、亡き清原教授の弟子である津田孝が、教授のエッセイに書かれた内容から、死の真相と真実を恩師の為に明らかにしようとするもの。悪事の暴露が目的ではなく、真実を明らかにすることが目的となっている点が、好印象。 ※本作品の紀子と「臓器農場」の規子は、帚木作品でもとくに私の好きな女性2人です。 |
|
●「三たびの海峡」● ★★★ 吉川英治文学新人賞 |
|
|
1995年08月
|
読み応えを感じ、感動した本ほど、感想を書くのは難しい。うまく自分の思いを書き表すことができないのではないか、という不安を感じるからです。また、書くべきことが多すぎて手に余るような 気がします。本書もそうした作品のひとつです。 太平洋戦争時、河時根は、17歳にして父親の代わりに朝鮮から日本へ強制徴用されます。日本に辿り着いて時根らが経験したことは、事前の話とは全く違った状況。九州の高辻炭坑にて、まさに監獄と同一の過酷な労働実態、そして食事も、幹部ら中間搾取するため酷い状況。 そして、逃亡、終戦、帰国とストーリィは展開していきますが、一度過酷な運命に落とされた河時根は、そう簡単に幸せを手に入れることはできません。この辺り、とくに切なさが嵩じ、耐え難い思いがします。 この作品で最も衝撃的であったことは、何故人間が同じ人間に対してこうも酷いことができるのか、ということ。この酷さ、リンチに発揮される凶暴さは何なのか。何故日本人は?と思わざるを得ません。 この物語の主人公は勿論河時根なのですが、その恋人となる日本人・千鶴の運命、辛苦については、河時根に対する以上に感動を覚えます。女性の強さをしっかり見せてくれる千鶴は、本作品にあって河時根以上に感動を呼び起こす人物です。 |
|
●「アフリカの蹄」● ★ |
|
|
1997年07月
|
題名の「アフリカの蹄」とは南アフリカ共和国のこと。アフリカ大陸を動物に模すと、ちょうど蹄の部分にあたるのだということです。本作品は、南アフリカ共和国へ留学している日本人医師が主人公。そこで彼が直面する事件と、その解決のために彼が自ら渦中に飛び来んでいくというストーリイです。 事件というより、大規模な犯罪というにふさわしい。 |
|
●「臓器農場」● ★★★ |
|
|
1996/08/17 |
読み甲斐のある作品でした。そして、帚木蓬生作品の中で、私が一番好きな作品。 ミステリー作家だと決め付けられているようですが、帚木作品は単にミステリーの形を取っているだけで、中身はかなりヒューマンティックな要素が強いと思います。本書の舞台は、九州のある山頂中腹にある新興の近代的病院。そこに新任看護婦として規子、優子の二人が配属されたところからストーリィは始まります。 このストーリィの中で、帚木さんは二つの問題提起を行っているのではないでしょうか。無脳症児への考え方、病院の看護婦に対する扱い方。 規子以外の、親友の優子、ケーブルカー運転手の藤野茂もまた、それぞれ個性的で存在感のある人たちでした。次の作品を読むのが楽しみになります。 |
|
●「閉鎖病棟」● ★★☆ 第8回山本周五郎賞 |
|
|
1996/09/08 |
感動的な作品でした。ミステリー作家という面影は全く感じません。 精神病院の中で生活する人々の姿。中に在って彼らを見るなら、個性的で少し偏屈というのとさして変らない。そんなところに、帚木さんの精神科医としての温かい愛情の眼を感じます。 ミステリー作家かどうかはどうでもいい、価値あり、感動する作品であればそれだけで十分、という気がします。 |
|
●「総統の防具」● ★★ |
|
|
1999年05月
|
第二次大戦の直前、ベルリンの陸軍武官事務所に赴任した日独混血の香田光彦中尉が戦争終結までベルリンにとどまって歴史の事実を見据える、というストーリイ。何故日本民族が戦争に巻き込まれたか、ということについては数々の作品が書かれていますので、いまさらどうのということはありませんが、海外の武官、それも最もドイツにひきずられた現場を知る、という部分には興味がひかれました。 ベルリンを訪れた「私」がその地の剣道道場を訪れた折、ドイツ人から古い剣道防具が保存されていることを聞く。現物を見に訪れた「私」はその防具が、対戦直前ヒトラーに贈呈されたものであること、それに添えられた日記のようなノートの存在を知る。本作品の中身はそのノートに綴られた内容、という形式です。 香田光彦、父ドイツ人、母日本人の混血。ドイツ語に堪能であることから、若くしてベルリン武官事務所に武官補佐官として赴任してくる。当時のドイツはヒトラー熱が高まっているところで、東郷駐独大使がナチ・ドイツに冷静、批判的なのに対し、大島武官はヒトラーの熱烈支持者だった。 帚木さんが光彦を借りて語り掛ける言葉は多いのですが、その中でも「真実は常に弱者の側にある」という言葉は印象的でした。 |
帚木蓬生作品のページ №2 へ 帚木蓬生作品のページ №3 へ