| 5 温泉の化学 5-6 アルカリ性泉 アルカリ性泉の魅力は、入浴したときに感じる滑らかな肌触りにあり、「美人の湯」としてとくに女性には絶大な人気があります。ガイド本などを読むと、つるつる湯になる原因を説明する文章には、「高アルカリ性だから」というのと、「重曹分が多いから」というのと二通りの説明があることに気付きます。どっちが本当でしょう? また、高アルカリ性の温泉だからさぞかし「つるつる」するだろうと期待して行ったのに、それほどでもなくてがっかりすることが往々にあります。どうしてでしょう? 何故につるつるか? つるつるの感触ができる原因はいろんな説明がされていますが、実はよく判っていないのが本当のところです。温泉の効能とはあまり関係がないので、本格的にとりくんだ研究例もないようです。そこで、似たような感触をもつセッケンとの類推で考えるとしましょう。手短にいうと、「アルカリ性の温泉では、皮脂とアルカリイオン(Na,K)が結合してセッケン状の物質をつくる」です。ここでアルカリという用語が2種類出てきますが、アルカリ性という場合はpHをさし(正しくは塩基性)、アルカリイオンという場合は周期表IA列のアルカリ金属元素(Li,Na,Kなど)のことをさします。 伝統的なセッケンの製法では、天然の動植物油脂(牛脂、やし油など)に、炭酸ソーダ(Na2CO3)や苛性ソーダ(NaOH)といった強アルカリ性物質を加えて加熱します。こうすると脂肪酸とナトリウムがくっついてセッケンとグリセリンに分解します。グリセリンはぬるぬるした滑性のある物質で、「ワセリン」としてお馴染みですね。 脂肪酸(R-COOH) + Na+ → Na-石鹸(R-COO-Na) + グリセリン このままではどろどろした液体ですが、これに塩水をまぜるとセッケンだけが分離してくるのでこれを固めて製品にします。ナトリウムの代わりにカリウム(K)を使ったカリ石鹸もありますが、温泉のカリウム含有量は少ないので、ナトリウムだけを考慮すればよいかと思います。温泉でもこれと似た作用で「皮脂石鹸」ができていそうですが、セッケンとグリセリンとがはっきり分離していないので、正確に言うと「石鹸のようなもの」です。つるつるの感触は、セッケンの界面活性作用(すべりやすくなること)で、ぬるぬるの感触のほうは、グリセリンが効いているのかもしれません。 また、脂肪とアルカリ性溶液は一般にあまり混じりあわないので、皮脂の溶け出しを助けるような働きを、重曹成分(NaHCO3)がしているようです。重曹は機械の洗浄にも使われるように、脱脂作用がとても強いのです。つまり、重曹成分が皮膚から脂肪をとりだし、アルカリ成分が石鹸に変えているという具合になっているものとみなしてよいかと思います。 温泉によっては重曹成分はとても少ないのに強いつるつる感があって不思議なことがありますが、似たような働きはメタ珪酸イオンやメタほう酸イオンでもしている可能性があります。ケイ酸ナトリウムやほう酸ナトリウム(硼砂)も、水に溶かすと強いぬるぬるの感触があります。 つるつるしないアルカリ性泉 高アルカリ性なのにつるつるしない温泉があるのは、2つの場合があります。 下図(5-6-3-1)では、縦軸に陽イオンのうちナトリウム対カルシウムの比率をNa/(Na+Ca)でとり、主成分型によって区分してみました。つるつるになる要因に重曹成分がはたらいてくるのは上に書いたとおりですが、アルカリ性泉のなかには塩化物泉や硫酸塩泉の組成をもつ泉質もけっこう多いことがわかります。これらの温泉はまた、Na/(Na+Ca)がかなり低くなっていて、ナトリウムの他にカルシウムも多く含んでくるのです。 以上をまとめると、つるつる温泉になるには3つの条件が揃う必要があるようです。 温泉の宣伝文のなかには、高アルカリ性という点だけに着目して「日本一の美人の湯」などと書いてあるのをよく見かけますが、成分のほうもちゃんと考慮しないと。「看板に偽りあり」ということになってしまいます。また、成分が希薄な高アルカリ性泉は、循環方式で使用すると、空気中の炭酸ガス(CO2)を大量に吸収してpHがどんどん低下していきます。最終的にはほぼ中性のふつうの地下水と変わらなくなってしまいます。 |
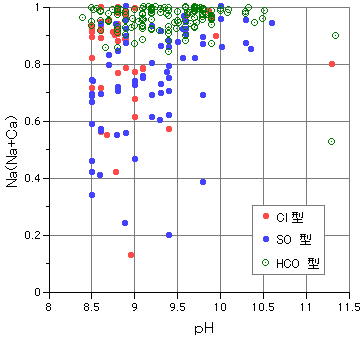
図5-6-3-1 ナトリウム比Na/(Na+Ca)と泉質
|
温泉分析表でみるつるつる温泉 上記のつるつる3条件を温泉分析表の数値から簡単にみることができます。下図(563-2)には、各地のつるつる温泉のナトリウムイオン(Na+)と炭酸イオン(CO32-)の関係をとってみました。縦軸に炭酸水素イオン(HCO3-)ではなく炭酸イオンをとったのは、高アルカリ性になると炭酸成分のうち炭酸イオンの比率が増えるからです(5-5-1章を参照)。 いろいろ入り比べてみると、図の右上になるほどつるつるの度合いが高くなっていきます。pHの高低を大まかに色分けで示していますが、意外にも高アルカリ性泉(赤色)の大部分は左下のほうになってしまい、つるつるの度合いは弱いほうになってしまいます。これはやはり成分が希薄だというのが最大のネックになっています。 |
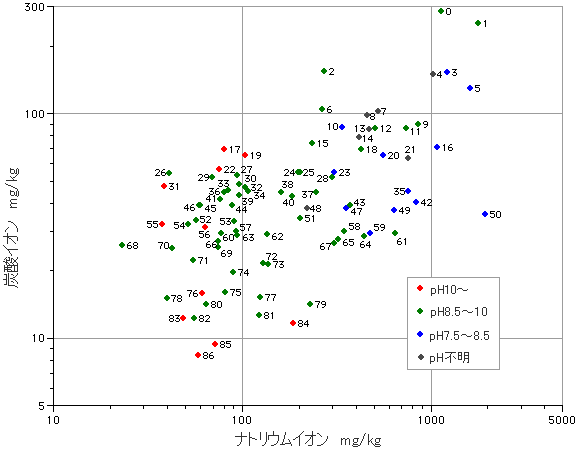
図5-6-3-2 ナトリウムイオンと炭酸イオンの関係
|
0:奥熊野(和歌山) 1:梅香丘(和歌山) 2:中山平星沼(宮城) 3:羽根沢(山形) 4:南紀田辺(和歌山) 5:上小野(和歌山) 6:中山平琢秀(宮城) 7:平戸(長崎) 8:塩入(香川) 9:鳴子ゆさや(宮城) 10:宍喰(徳島) 11:井川田代(静岡) 12:吉浦湯元(千葉) 13:嬉野(佐賀) 14:下津谷木(埼玉) 15:からつ(佐賀) 16:加賀八幡(石川) 17:松乃(東京) 18:大楠(神奈川) 19:大竜寺(埼玉) 20:新谷汲(岐阜) 21:美山(和歌山) 22:生津(長野) 23:泉崎堂花(福島) 24:愛宕(栃木) 25:井川赤石(静岡) 26:三ツ沢(東京) 27:三ヶ日(静岡) 28:津川(新潟) 29:四徳(長野) 30:松島乙女(栃木) 31:都幾川(埼玉) 32:矢吹いやさか(福島) 33:道後(愛媛) 34:昼神(長野) 35:中津川(岐阜) 36:天竜峡(長野) 37:帯広自由が丘(北海道) 38:帯広緑ヶ丘(北海道) 39:寸又峡(静岡) 40:味幸園(北海道) 41:天竜(長野) 42:黒鴨(山形) 43:小野上(群馬) 44:正徳寺(山梨) 45:観音(静岡) 46:丹波山(山梨) 47:波佐見(長崎) 48:奥香落淫(奈良) 49:白峰(石川) 50:戸沢野口(山形) 51:灰下(新潟) 52:玉川スプリング(埼玉) 53:白木川内(鹿児島) 54:泉崎さつき(福島) 55:真木(山梨) 56:下部湯沢(山梨) 57:柏原(鹿児島) 58:恩沢(栃木) 59:根尾川なべら(岐阜) 60:秩父満願(埼玉) 61:中標津マルエー(北海道) 62:女満別(北海道) 63:室賀(長野)64:信州平谷(長野) 65:越前厨(福井) 66:はやぶさ(山梨) 67:接阻峡(静岡) 68:ほったらかし(山梨) 69:日光和の代(栃木) 70:湯原(岡山) 71:天科(山梨) 72:帯広ボストン(北海道) 73:南郷(群馬) 74:七沢(神奈川) 75:雄琴(滋賀) 76:山中湖(山梨) 77:戸倉観世(長野) 78:川浦(山梨) 79:白山杉の子(石川) 80:名栗(埼玉) 81:飯田城(長野) 82:田沢(長野) 83:桃源天恵(山梨) 84:中川(神奈川) 85:下部(山梨) 86:白馬八方(長野) |