| 5 温泉の化学 5-3 水溶液の性質(2) pHってなに? 温泉の化学的性格付けをするときに、泉質名とともによく使われるのがpHです。 pHの数字が小さい(pHが低い)ものを酸性、pHの数字が大きい(pHが高い)ものをアルカリ性(塩基性)とよぶのはご存じのとおりです(2-1章)。酸性の温泉はすっぱい味がし、身体への強い刺激がとくに男性に好まれているようです、また、アルカリ性の温泉は肌がすべすべするものが多く、美肌の湯として女性に好まれています。 このように、pHの違いは直接に体感できる性格のものなので、分析表にごちゃごちゃ書いてある沢山の数値のなかでは、最もわかりやすい比較基準といえるでしょう。しかし、pHがいったいなにを表しているのか、ということを即座に答えられる人は、ベテランの温泉ファンでも意外に少ないようです。 高校の化学ではpHのことを「水素イオン濃度」として教わりました。でもはて? 温泉分析表には必ずpHの数字が書いてあるのに、水素イオン(H+)の値ってあんまり見かけませんよね。それに、どうしてPHとかPhって書いてはいけないんでしょう? この章では、pHの数値がもつ意味について考えていきましょう。そんなに難しいおはなしではありません(かな?)。 身近なもののpH はじめに、我々のまわりにある物のpHを示しておきます。pHメータがなくても、こういう物と比較してpHを記述することが可能です。たとえば、「○○温泉はリンゴよりは酸っぱかったけど、レモンほどじゃないから、pHは2.7くらいかな?」という具合です。ただし、アルカリ性のほうは、人間の舌で感じるようにはできてませんから、この方法で伝えるのは難しいですね。「セメントくらいのアルカリ度」といっても誰もわかってはくれないでしょう。これはむしろ、お肌のつるつる具合を言ったほうがわかりやすくなります。アルカリ度とお肌のつるつるの関係は、また別の章でおはなしします。 |
図5-2-1 身のまわりのpHいろいろ (HORIBA onine 「pHの話」より)
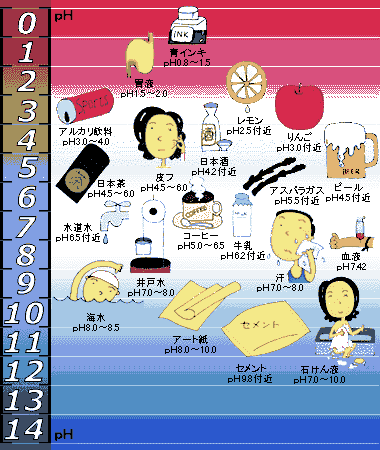
水は電気を通す? |
表5-2-2 pHと[H+]、[OH-]の関係
| pH | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| [H+] | 1 | 10-1 | 10-3 | 10-5 | 10-7 | 10-9 | 10-11 | 10-13 | 10-14 |
| [OH-] | 10-14 | 10-13 | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 10-5 | 10-3 | 10-1 | 1 |
| ゼーレンセンの定義からいうと、pHは「水素イオン濃度指数」または「水素指数」っていうのが正しいようです。じゃあ何て読むんでしょう? ゼーレンセン自身がなんて発音していたかはわかりませんが、日本にこの考えが導入されたときにはドイツ語の教科書が使われたので、ドイツ風に「ぺー・ハー」と読んでいました。これが最近まで普及し、かくいう私も「ペーハー」が頭に染み付いています。でも、国際的には英語読みで「ピーエイチ」というのが一般的なようです。今の高校ではどっちに教えているんでしょうね? でも実は、pH=水素イオン濃度として教えていることのほうが問題なのです。これを次におはなしします。 イオンの活量 温泉水のような濃い水溶液には、いろんな種類のイオンが多量に溶けていますが、これを化学で取り扱うときに意味をもってくるのは、じつはイオンの濃度ではなくて「活量」です。活量とは、化学表現で言い換えると「熱力学的に有効な濃度」ということですが、これではなんのことか解らないので、例え話で替えときます。 あなたが大切に乗っている愛車があるとしましょう。速度計には200km/hまで目盛りがあり、どうやらかなりスピードの出る高速車のようです。でもこれは、広いテストコースで走ったときの最高速度で、普段あなたはそんな高速走行をする機会はまず無いはずです。たいていは60km/h前後、高速道路でも100km/h前後でしょう。どうしていつも愛車の能力をフルに発揮できないのでしょうか? それは道路が混んでくると、そんなスピードでは危険なためですね。道路上に他の車が多ければ多いほど、あなたの車は速度を落として走らなくてはいけなくなります。 「活量」とはこういうことで、イオンの能力を100%発揮して化学反応に関係できるのは、希薄な溶液の中でだけ可能だ、ということです。イオンの濃度=活量となっている状態を「理想溶液」といいますが、まさしく現実は理想とは遠く、温泉水などの濃い溶液中では、イオンの能力の60〜80%くらいしか有効に働いていないのです。ミクロ的には、イオン量が増えると、互いの衝突でイオンの運動が制限されるために、こういうことが起こっていると考えられています。 濃度×活量係数(a)=活量 という関係になりますが、この活量係数(a)は計器で実測できない数値で、計算や実験によって推測するしか方法がありません(様々な推定法が提案されています)。このことが活量の取り扱いを難しくし、高校化学の授業で触れられない原因でしょう。だからといって全く無視するというのはどうでしょうか? 面倒な話ですが、温泉や地下水などの現実的な溶液化学についてもう一歩踏み込んでいこうと考えておられる方には、重要なことなので、触れておきました。 pHの理想と現実 pHを測る これまでおはなししてきた、水素イオン濃度[H+]からpHを求めるのは、じつは理想です。いつの場合も理想と現実の間には大きな隔たりがあるものです。現実の世界では、水素イオン(プロトン)の濃度を正確に測るのは非常に難しく、測定できるのは水素イオンの「活量 aH」だけです。活量を用いると、pHはつぎのように定義されます。 pH=-log(aH) ・・・(3) aH:水素イオンの活量 aH = [H+]・a a:活量係数 水素イオンの活量(aH)の大小は、電子の働きとして起電力に現れてきますので、pHメータで測定しているのは、ほんとうは2種の電極の間に生じる起電力(mV)です。この値を標準溶液のmVと比較して、pHを求めています。比較するには、なにか基準となるものが必要ですが、これには多少のことではpHが容易に変化しない、pH緩衝作用という性質をもつ標準溶液が用いられます。 JIS工業規格では、比較する標準溶液として、「0.05mol/lフタル酸塩水溶液を選び、このpHは15℃において、4.000と定義する。」というふうに定められています。つまり、pHの値は、具体的に1個2個と数えられるような絶対量ではなくて、物の長さのように、相対的な尺度として求められるものなのです。 秤や定規が規格に合っているかときどき検査しなければならないように、正確にpHを測定するためには、メータ内の目盛りがきちんと合っているかどうか、測定の度にチェックしておかなくてはなりません、これを「絞正こうせい」といっています。きちんと絞正されていないpHメータは、狂った秤と同じですので、意味のない値が出てくるだけです。 以下に、ちょっと煩雑ですが、JIS工業規格<Z 8802-1986>から抜粋しておきます。 【pHの目盛りの定義】 同温度の2種類の水溶液X及びSのそれぞれのpHを、pH(X)及びpH(S)で表わすと、それらのpHの差は、式(2)で定義される。 pH(X) - pH(S) = (Ex - Es) / (2.3026・R・T / F) ここに Ex:水溶液X中で、ガラス電極と比較電極とを組み合わせた電池の起電力。 Es:水溶液S中で、ガラス電極と比較電極とを組み合わせた電池の起電力。 R:ガス定数 8.3144J/℃・mol T:絶対温度 t℃+273.15 F:ファラデー定数 96495C/g-equiv |
2.3026RT/Fの値
| 温度℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2.3026RT/FmV | 54.19 | 55.19 | 56.18 | 57.17 | 58.16 | 59.15 | 60.15 | 61.14 | 62.13 | 63.12 |
| 温度℃ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2.3026RT/FmV | 64.11 | 65.11 | 66.10 | 67.09 | 68.08 | 69.07 | 70.07 | 71.06 | 72.05 | 73.04 |
| 温泉のpHを測る pH7は中性ではない? さて、25℃の純水が解離するときは、イオン積Kw= 1.01×10-14でした。ところが、水が解離する度合いは高温になるほど大きくなっていきます。したがって、中性([H+]=[OH-])のときの水素イオン濃度は温度によって変わります。ということは、ひとくちに中性といっても、そのpHは温度によってかなり違いがある、ということです(下表)。温泉の温度は様々ですから、それぞれのpH値を比べて高い低いといっても、全く意味のないことになってしまいます。 |
表5-2-3 中性の水がしめすpH
| 温度 | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 24℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 100℃ |
| pH | 7.47 | 7.27 | 7.08 | 7.00 | 6.91 | 6.76 | 6.63 | 6.51 | 6.13 |
| 温泉分析表に書かれているpHは、1) 源泉での実測pH値 2) 実測pH値を25℃に換算した補正pH値 3) 試験室で25℃にして測定した定温pH値 の3種があります。最近はほとんどデジタルpHメータで測定しており、pH値は自動的に25℃の数値に換算されて表示されてくるので、源泉pHとは2)のことです。 試験室でのpHは、採水してからやや時間が経っているので、溶存ガス成分などが変化して、源泉とはやや異なった数字になります。3)を表示する意味は、分析表の成分値を解釈するためにありますから、どちらかというとプロ向けの数字です。 さて、最近は温泉ファンのなかにも、pHこだわり派がいて、試験紙を使って温泉のpHを測定されている方がいます。これで得られる値(概略値ですが)は実測pHですので、高温の源泉で測ったときなど、とんでもない値が出てきて驚愕することがあります。温度補正をすればいいのですが、この計算はいささか面倒なので、手っ取り早いのは温泉を汲み置きして、25℃に冷ましてからあらためて測ってみることです。 温泉に行ったらpHを測ってみなくては気がすまない、っていう超こだわり派の方には、この際ですからデジタルpHメータを購入されることをお勧めします。pH試験紙は結構コスト的にばかになりませんし、最近はペン型の携帯用デジタルpHメータが7千円〜2万円程度で市販されていますから、そちらのほうがはるかにお得です。ただし、適用温度は0℃〜40℃までが普通ですから、注意しなくてはなりません。もともと河川の水質検査とか、食品のpHを測るようにつくられたものですから、温泉にはあまりむいてないのは当然です。 デジタルpHメータの原理については、代表的メーカーの堀場製作所のHPに詳しいので、そちらを参考にされて下さい。 http://global.horiba.com/index.htm [5-3章 参考図書・参考文献] 次回は日本の特徴的温泉ともいえる酸性泉について、いろいろの側面からつっこんでみます。 |