| 5 温泉の化学 5-4 酸性泉 いろんな泉質の温泉があるなかで、酸性泉はとても特殊な位置を占めています。この章では、酸性泉とほかの温泉はどう違っているのか、酸性泉はどうやって出来るのかに焦点を当てて見ていくことにします。 5-4-1 日本の温泉のpH まずは下の図をご覧下さい。これは全国2671カ所の温泉地について、pHを0.25ごとに区切ったときの温泉件数と総湧出量(棒グラフ)、平均温度(折れ線グラフ)を集計したものです。個々の源泉について集計したものではないので正確さの点では劣りますが、実態はかなり把握できているものと思います。 |
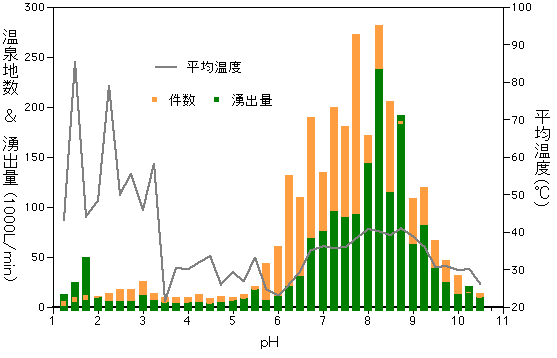
図5-4-1 pHを0.25毎に区分したときの温泉地件数・総湧出量・平均温度
温泉地の件数・湧出量ともに、大部分はpH6〜10の間にあって、pH8前後で最大になります。分布の山は中性(pH7)よりも大きくアルカリ(塩基)性の側によっていて、日本の温泉は中性〜弱アルカリ性のものが圧倒的に多いことがわかります。pH9以上の強アルカリ性泉は意外に数が多いですが、統計分布からは弱アルカリ性泉の特殊なものとみることができるようです。強アルカリ性泉の平均温度はかなり低くなっています。このあたりにアルカリ性が強くなる原因がありそうですが、これについてはまた別の章でとりあげます。 |
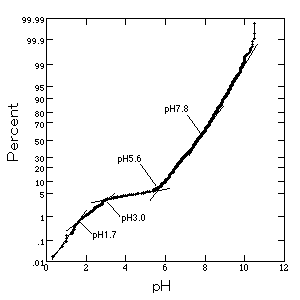
図5-4-2 pHの統計分布(確率分布)
| 泉質名とpHの関係 見慣れない図ばかり出て恐縮ですがもう一つ。 下図は各温泉につけられた泉質名を、pHごとにカウントしてみたものです。中〜弱アルカリ性には塩化物泉が多く、やや酸性になると炭酸水素塩泉(炭酸泉を含む)が支配的になり、酸性泉のほとんどが硫酸塩泉からできていることがわかります。 硫酸塩泉は酸性のものと、弱アルカリ性のものの2種類あるのが妙な感じですが、先にバラしますと、前者には硫酸水素イオン(HSO4-)が伴ってくるために酸性になっているのです。同様に、酸性領域にも塩化物泉が少し存在するのが見えますが、これは食塩泉ではなく、塩酸(HCl)による塩素イオンが多く含まれているためです。 (つづく) |