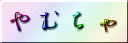 |
|---|
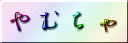 |
|---|
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板
| OUT |  |
|---|
2002年作品。日本映画。119分。配給=20世紀フォックス映画。監督=平山秀幸。原作=桐野夏生(「OUT」講談社刊)。脚本=鄭義信。撮影=柴崎幸三。照明=上田なりゆき。美術=中澤克巳。録音=田中靖志。編集=川島章正。音楽=安川午朗。香取雅子=原田美枝子、吾妻ヨシエ=倍賞美津子、城之内郁子=室井滋(むろい・しげる)、山本弥生=西田尚美(にしだなおみ)、十文字彬=香川照之、佐竹光義=間寛平、山本健司=大森南朋、吾妻千代子=千石規子
最後には、逃避行は4人連れでと感じるほど、女性たちの奇妙な友情に感染してしまっていた。ラストが、やや甘くなったのが残念。緊張の糸が切れる。知床のオーロラは「大人のおとぎ話」のような質感を狙ったのかもしれないが、深い闇に包まれた知床の凍てついた夜は、そのままみせてほしかった。現実からはOUTできない、EDGEがあるだけなのだから。
倍賞美津子、原田美枝子、室井滋、西田尚美という4人の絶妙ともいえるキャスティング。平凡な主婦というには華があり過ぎる個性的な名優ぞろいだが、それだけに屈折した人物像をくっきりと浮き上がらせていた。バラバラに見えながら緊張関係を保ち、やがて友情の深まりを見せる。若手の西田尚美は、3人の貫禄ある演技に対して、あっけらかんと軽く無責任に生きるキャラクターを際立たせて、別な意味で存在感十分。不思議に憎めなかった。男性陣では、香川照之が狂気をただよわせた良い味を出していた。間寛平も、新境地を開拓した。
| かわなかのぶひろVS.映像の新世代たち |
|---|
札幌のまるバ会館で、10月18-20日に「かわなかのぶひろVS.映像の新世代たち」と題した上映会が行われた。渋谷のシアター/シネマテーク・イメージフォーラムの創設者、そして映像作家もあるかわなかのぶひろ氏の作品と、東京の映像系大学・研究所から若い世代の作品が紹介された。
Bプロプログラムは、かわなか氏の「空の繪」と、イメージフォーラム付属映像研究所の女性監督の作品で構成。「空の繪」(16ミリ/30分)は、フイルムを持ってアメリカを回った1985年の記録フイルムを中心に、2000年に編集したもの。メカスらアメリカの友人たちが写し出される「旅の繪」といった感じの簡潔なフイルムと、自分史が重なる。無駄のないさり気ない映像が歴史的な厚みを持っている。素晴らしい。引用された寺山修司の詩の力にも、あらためて驚きを覚えた。
「ヨモヤマドレス、脱ぐ女」(寺島由紀/8ミリ/15分)は、ハッとするシーンはあるが、まとまりを感じない。「バンビの足はすぐ折れる」(大久保京子/8ミリ/8分)には、人形アニメの新しい世界。サイレントに才能を感じた。しかし、実は音声が出ていなかったことが判明。音声付きでは説明が多すぎて、イマイチの印象。説明などなくても映像だけで十分伝わっていたのに。「犬の棺」(清水好美/8ミリ/10分)は、詩の力を生かした作品。しかし殺してもいる。
「エミュ/amu」(神崎愛子/8ミリ/10分)は、衝撃的なファーストシーンに圧倒されたが、後が続かない。「絵空事セミモロジー」(佐川桂代/8ミリ/10分)は、蝉の抜け殻を食べるシーンが迫力ある。「エロティック・煩悩ガール」(山内洋子/ビデオ/20分)は、実写とイラストを併用し、ユーモアあふれる意外な展開に引き込まれた。しかし母親の死に移るとべたべたした映像に変わり、最後は「大きなお腹がエロティック」と、保守的な地点に着陸してしまった。残念。
Cプログラムは、かわなか氏と萩原朔美の共作ビデオ「映像書簡八」(28分)と、東京造形大学の女性たちの作品。「映像書簡八」は、等身大の日常的な風景を切り取った往復ビデオ書簡。かわなか氏の「人類共通の記憶」という持論が述べられる。自分の作品は一つの作品と言えると話した後、軽く語った「エンドマークがどこでつくかが、楽しみ」という言葉が印象に残った。
「口角」(荒井貴子/ビデオ/8分)は、いろいろな映像処理の魅力はあるが、まとまりに欠ける。「Family ties」(石井麻衣子/ビデオ/5分)は、テクニックは分かるが作品の力は弱い。「神様からの手紙」( 山崎美春/ビデオ/7分)は、おじいちゃんの死を契機に、作品が始まる歴史への問い。「polka dots」(鹿島さつき/ビデオ/10分)は、映像処理が魅力。「こめかみの轍」(島田奈々子/ビデオ/15分)は、アフガニスタンで、アメリカ同時多発テロ直前に撮影されたもの。個人的な映像が歴史的な映像に豹変する。「round-scape」(柳瀬千代美/ビデオ/10分)は、3分割の映像構成。「in two dimensions」(山口亮子/8ミリ/15分)は、執拗な映像処理に好感がもてた。
| クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイア |  |
|---|
2002年作品。アメリカ映画。102分。配給=ワーナー・ブラザース映画。監督=マイケル・ライマー(Michael Rymer)。製作=ジョージ・サラレギ。製作総指揮=スー・アームストロング、アンドリュー・メイソン。原作=アン・ライス(Anne Rice)「呪われし者の女王」。脚本=スコット・アボット、マイケル・ペルトローニ。撮影=イアン・ベイカー。編集=ダニー・クーパー。美術=グレイアム“グレイス”ウォーカー。音楽=リチャード・ギブズ、ジョナサン・デイビス。衣装=アンガス・ストレイシー。SFX=マネックス・ヴィジュアル・エフェクツ。レスタト・デ・ライオンコート(Lestat de Lioncourt)=スチュワート・タウンゼント(Stuart Townsend)、クイーン・アカーシャ=アリーヤ(Aaliyah)、マハレット=レナ・オリン(Lena Olin)、マリウス=ヴィンセント・ペレイズ(Vincent Perez)、ジェッセ・リーヴス=マルゲリート・モレー(Marguerite Moreau)、デヴィッド・タルボ=ポール・マクガン(Paul McGann)、パンドラ=クラウディア・ブラック(Claudia Black)、マウディ=メガン・ドーマン(Megan Dorman)
レスタト役のスチュワート・タウンゼントは、演技はイマイチながら官能的なので許そう。この作品が遺作となったアリーヤは、クイーン・アカーシャを好演していたものの、もっと出番がほしかった。魅力を出し切っていない。おそらく大多数の人が首をかしげるのが人間のヒロインの地味さ。派手好きのレスタトが、こういう女性にひかれるとは思えない。映像美は、楽しめたが、物語は最初から最後まで府に落ちないことばかりだった。
| なごり雪 |  |
|---|
2002年作品。日本映画。111分。配給=大映。監督=大林宣彦。プロデューサー=大林恭子、山崎輝道。詞・曲=伊勢正三。脚本=南柱根、大林宣彦。唄・ギター演奏=伊勢正三。映画音楽=学草太郎、山下康介(編曲・指揮)。撮影=加藤雄大。美術=竹内公一。照明=西表灯光。録音=内田誠。編集=大林宣彦。助監督=南柱根。制作担当=若山直樹。スクリプター=呉美保。ヘアー・メイク=岡野千江子。衣装=千代田圭介。装飾=河合良昭。梶村祐作(現在)=三浦友和、水田健一郎(現在)=ベンガル、園田雪子=須藤温子、梶村祐作(青年期)=細山田隆人、水田健一郎(青年期)=反田孝幸、菅井とし子=宝生舞。水田夏帆=長澤まさみ、杉田良一=田中幸太郎、新谷由梨絵=斉藤梨沙、梶村道子=左時枝、水田の母=津島恵子、槙弘美=日高真弓
過去と現代を行き来しながら、失われたものを静かに示し、50代の団塊の世代に生き方の再考を促すメッセージを込められている。映像のお遊びは控え、まっすぐな美しくて切ない青春映画に仕上げた。私は、フイルムと戯れ、はしゃいでいるような大林ワールドが好きだが、最近の大林作品は叙情に流れる傾向が強くなった。それも、悪くはないが「あの、夏の日」のような子供の感性でフイルムと遊ぶ作品も、また見せてほしい。
28年前の日本語を再現した会話が新鮮。会話の中に「なごり雪」の歌詞がそのまま取り入れられていることに驚く。かなりの冒険だ。主人公・梶村祐作役の三浦友和は、疲れた表情がいい。親友・水田健一郎役のベンガルとともに枯れた味を出している。ヒロイン園田雪子役の須藤温子は、新人らしい堅さがかえって昔の美少女らしかった。宝生舞の女子大生役も、はつらつとしていて印象に残った。
| 1996年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |