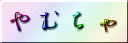 |
|---|
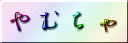 |
|---|
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板
| Tatsu Aoki 作品集 |  |
|---|
3月29日-31日にまるバ会館で、「Innocent Eyes and Lenses Tatsu Aoki 作品集」が上映された。シカゴ在住のフリージャズのミュージシャンとして有名なTatsu Aoki氏は、映像作家でもあり、今回来道を機に、本人トークも交えて、上映が行われた。心地よく変化する、これまで見たことのない映像に、感激した2時間。青木氏の軽妙な語りも印象的だった。
「Decade Passed」(ディケイド・パスド、2002年、16ミリ、18分)は、最新作。「10年経つ」という題名を持つ意味深長な日記映画は、日常的であると同時に抽象的。友人のジェフ・パーカーが曲をつけているが、映像が音楽に負けることなく、ダイレクトに魅力的なイメージを発している。
「Raputurou!s」(1984年、16ミリ、16分)、「Hallway」(1984年、16ミリ、15分)、「Souund in Sync」(1984年、16ミリ、19分)は、1980年代前半の作品で、それぞれに明確なコンセプトを持っているものの、あまり驚きはない。「Harmony」(1991年、16ミリ、12分)は、雑踏を撮った作品だが、なんと38重露光という処理をしている。羽衣のように流れる映像には、デジタルとは違った味わいの面白さがある。
「Free Hands Part 1」(1997年、16ミリ、10分)、「Puzzle」(2001年、16ミリ、20分)は、作品そのものの持つ喚起力に打ちのめされた。難しくなく、少しずつ変化する反復的な美しい映像に身をまかせる快感。甘美であり、恐怖でもある自在な映像。これまで体験したことのない映像の世界に引き込まれた。
伊藤隆介監督が聞き役となったトークも楽しかった。青木監督の語る横断表現的な芸術家論、生地の変化を基本にした映像論、持っているオリジナルの量が大切だというプロ論、分りやすく伝えようという芸人根性論は、とても共感する点が多かった。貴重な上映会だったと思う。
 Tatsu Aokiの映像論(Realaudio)
Tatsu Aokiの映像論(Realaudio)
| 地獄の黙示録・特別完全版 |  |
|---|
2001年作品。アメリカ映画。203分。配給=日本ヘラルド映画。監督=フランシス・フォード・コッポラ。脚本=ジョン・ミリアス。撮影監督=ヴィットリオ・ストラーロ。ナレーション=マイケル・ハー。「特別完全版」の製作者=キム・オーブリー。共同製作=フレッド・ロス、トム・スタンバーグ、ゲイリー・フレデリクソン。プロダクション・デザイン=ディーン・タボラリス。編集、音響=ウォルター・マーチ。音楽=カーマイン・コッポラ。ウィラード大尉=マーティン・シーン、カーツ大佐=マーロン・ブランド、キルゴア中尉=ロバート・デュバル、ルーカス大佐=ハリソン・フォード、フォト・ジャーナリスト=デニス・ホッパー、クリーン=ローレンス・フィッシュバーン、ランス=サム・ボトムズ
コッポラ監督が自ら語るように、この作品は「反欺瞞映画」だ。戦争の欺瞞性を、アメリカ自らが、ここまで真摯に告発した映画はない。その後に続いた戦争映画も、この作品の圧倒的な鋭さには、遠く及ばない。しかし、ラストを神話的な構図に収めたことで、その政治的な告発が、生かされなかったという側面もある。もっとも、作品としての射程は、人間存在そのものにまで、延びているのだが。
| ピアニスト |  |
|---|
2001年作品。フランス・オーストリア合作。132分。配給=日本ヘラルド映画。監督・脚本=ミヒャエル・ハネケ。原作=エルフリーデ・イェリネク(Elfride Jelinek)(鳥影社「ピアニスト」)。エグゼクティヴ・プロデューサー=ミヒャエル・カッツ、イヴォン・クレン。プロデューサー=ナタリー・クリュテール、クリスティーヌ・ゴズラン。撮影=クリスティアン・ベアガー。編集=モニカ・ウィッリ。音編集=ナディーヌ・ミューズ。音楽監修=マルティン・アッシェンバッハ。衣装=アンネッテ・ボーファイス。美術=クリストフ・カンター。エリカ・コユット=イザベル・ユペール、ワルター・クレメール=ブノワ・マジメル、母=アニー・ジラルド、ブロンスキー教授=ウド・ザーメル、ショーバー夫人=スザンネ・ローター、アンナ・ショーバー=アンナ・ジーガレヴィッチ
母親とともにピアニストになるために禁欲し続けてきた中年の女性が、教え子に愛を告白され、抑圧してきたマゾヒステックな欲望にほんろうされるというストーリー。つまりは、屈折した性欲の話だ。展開は冷静で、それでいて映像にねっとりとした質感がある。不思議な生々しさに包まれている。とりわけ、イザベル・ユペールが、驚くばかりの熱演をみせる。クラシックの華麗な演奏が繰り返されるので、後味の悪い結末に続く無音のエンドロールがかえって痛みを増幅させる。
ミヒャエル・ハネケ監督は「逃げ出すのが不可能になる形式を見つけ出そうと、私は試みているのです。状況をラディカルに尖鋭化させて、心理的個人的な鋳型を避けることで、観客自身を不安と攻撃の真っ只中に投げ込むことのできる形式を探し求めているのです。映画は気晴らしのための娯楽だと定義するつもりなら、私の映画は無意味です。私の映画は気晴らしも娯楽も与えませんから」と、挑発的に話している。なるほど。
| モンスターズ・インク |  |
|---|
2001年作品。アメリカ映画。92分。配給=ブエナビスタエンターテインメント(ジャパン)。監督=ピート・ドクター。共同監督=リー・アンクリッチ、デヴィッド・シルバーマン。製作=ダーラ・K.アンダーソン。製作総指揮=ジョン・ラセター、アンドリュー・スタントン。原案=ピート・ドクター、ジル・カルトン、ジェフ・ピジョン、ラルフ・エッグルストン。脚本=アンドリュー・スタントン、ダニエル・ガーソン。音楽=ランディ・ニューマン。ストーリー監修=ボブ・ピーターソン。編集=ジム・スチュワート。テクニカル監修=トーマス・ポーター。プロダクション・デザイナー=ハーレー・ジェサップ、ボブ・ポーリー。アート・ディレクター=ティア・W.クラッター、ドミニク・ルイス。アニメーション監修=グレン・マックィーン、リッチ・クエイド。ライティング監修=ジャン=クロード・J.カラシュ。レイアウト監修=ユーウィン・ジョンソン。シェーディング監修=リッチ・セイル。モデリング監修=イーブン・オストビー。セット装飾監修=ソフィー・ヴィンセレット。シミュレーション&効果監修=ギャリン・サスマン、マイケル・フォング。音響デザイナー=デイリー・リドストロム。サリー=ジョン・グッドマン、マイク=ビリー・クリスタル、ブー=メアリー・ギブス、ランドール=スティーブ・ブシェーミ、ウォー夕ーヌース=ジェームズ・コバーン、セリア=ジェニファー・ティリー、ロズ=ボブ・ピーターソン、イエティ=ジョン・ラッツェンバーガー、ファンガス=フランク・オズ、ニードルマン&スミティ=ダニエル・ガーソン、フリント=ボニー・ハント、ジョージ=サム・ブラック
ただ、エンドロールとともに始まる恒例のNG集は、今回も傑作。「トイ・ストーリー」からの隠れたカメオ出演が分ったり、うるさ型として登場していたおばさんが、ちゃめっ気を発揮していたりと、作品を観た直後の美味しい遊びが楽しめる。そして、モンスターズ社の社内劇まで披露されて、モンスターの世界をより身近に感じさせる。エンドロールが始まると、かなりの人たちが席を立つ。エンドロールの部分を含めて、楽しまないともったいない。
| 光の雨 |  |
|---|
2001年作品。日本映画。130分。配給=シネカノン。製作総指揮=高橋紀成 。製作=石川富康 。プロデューサー=青島武、森重晃 。監督=高橋伴明 。助監督=瀧本智行 。脚本=青島武 。原作=立松和平(『光の雨』新潮文庫刊) 。撮影=柴主高秀 。音楽=梅林茂 。美術=金勝浩一 。録音=福田伸 。照明=渡部嘉 。編集=菊池純一 。劇中短歌=福島泰樹 。筆文字パフォーマンス=軌保博光 。阿南満也(メイキングビデオの監督)=萩原聖人 、樽見省吾(映画監督)=大杉漣 、大山賢一(プロデューサー)=塩見三省 、玉井潔(指導部)=池内万作 、上杉和枝(指導部)=裕木奈江 、大沢守男(指導部)=松田直樹 、夏目洋太(指導部)=山中聡 、五十嵐俊哉(兵士)=近藤大介 、浦川秋子(兵士)=川越美和 、月田てるこ(兵士)=板谷由夏 、宇野咲子(兵士)=矢澤庸 、岡崎伸江(兵士)=関川侑希 、矢崎マリ(兵士)=玄覚悠子 、戸張真(兵士)=大柴邦彦 、戸張善二(兵士)=一條俊 、北川準(兵士)=蟹江一平 、谷口淳子(兵士)=西山繭子 、赤津利和(兵士)=佐藤貢三 、黒木利一(兵士)=鳥羽潤 、今村道子(兵士)=小嶺麗奈 、三橋信之(獄中の最高幹部)=金山一彦 、倉重鉄太郎(最高幹部)=山本太郎 、及川厚志(幹部)=大和屋ソセキ 、松村伸(幹部)=西守正樹 、高田ゆみ=高橋かおり 、森中広志(兵士)=三上大和 、田所良春(兵士)=恩田括 、河村哲也(兵士)=白石朋也 、新川次郎(兵士)=金子貴俊
あの事件の歴史的な意味は、まず若者が国家を超える理想を持つことに臆病になったということがあるだろう。人々が力を合わせて世界を変えることのリアリティが失われた。少なくとも、その傾向を決定的にした。なお変革を諦めなかった人たちは、深刻な方針転換を迫られ、人間の持つ弱さ、意識の変えがたさの認識から反差別の運動に移行したり、非日常性を求めるのではなく日常生活そのものを変えるという意図で、エコロジー的な運動が広まった。しかし、大きな理想が見えにくくなったのは事実で、オウム事件は、ある意味でその影響といえる。この作品を観て、若い人たちは「オウムみたい」と感じるだろうが、歴史が繰り返されているのではなく、「総括」にはなお時間がかかるということだ。
俳優では、裕木奈江のうまさがダントツに光る。知性と欲動の屈折を見事に演じている。山本太郎には、もう少し重い言動がほしい。次々と同志を殺していくシーンが「バトル・ロワイアル」(深作欣二監督)の延長に思えてしまう。萩原聖人は、とまどいながら映画と観客をつなぐ重要な役をそつなくこなしていた。映画の最後で、立松和平が語り手となって「あの時代に生きた子もみな普通の子どもだったよ。夢のとりこになって真剣だった」と述べる。ぶち壊しだ。この作品にただよう、自己満足さを増幅している。とはいえ、これから劇場公開される「突入せよ!あさま山荘事件」(原田眞人監督)の偽善性を照らし出す役割は、果たすことができるだろう。
| ロード・オブ・ザ・リング |  |
|---|
2001年作品。アメリカ映画。178分。配給=日本ヘラルド映画、松竹。監督=ピーター・ジャクソン(Peter Jackson)。脚本=フラン・ウォルシュ(Frances Walsh)、フィリッパ・ボウエン(Philippa Boyens)、ピーター・ジャクソン。原作=ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキン(J.R.R.Tolkien)「指輪物語」(1954年)。製作=バリー・M・オズボーン、ティム・サンダース、ピーター・ジャクソン。共同製作=フラン・ウォルシュ。製作総指揮=マーク・オデスキー、ボブ・ワインスタイン、ハーヴィー・ワインスタイン ロバート・シェイ マイケル・リン。撮影監督=アンドリュー・レスニー(Andrew Lesnie),A.C.S.。美術=グラント・メイジャー(Grant Major)。編集=ジョン・ギルバート(John Gilbert)。音楽=ハワード・ショア(Howard Shore)。衣装=ナイラ・ディクソン(Ngila Dickson)。スペシャル・メイクアップ/クリーチャー/ミニチュア/デジタルエフェクツ=WETA LTD.NZ。ビジュアル・エフェクツ・スーパーバイザー=ジム・リジール。フロド・バギンズ=イライジャ・ウッド(Elijah Wood)、ビルボ・バギンズ=イアン・ホルム(Ian Holm)、アラゴルン=ヴィゴ・モーテンセン(Viggo Mortensen)、サム=ショーン・アスティン(Sean Astin)、ピピン=ビリー・ボイド(Billy Boyd)、メリー=ドミニク・モナハン(Dominic Monaghan)、レゴラス=オーランド・ブルーム(Orlando Bloom)、ボロミア=ショーン・ビーン(Sean Bean)、ギムリ=ジョン・リス=デイヴィス(John Rhys-Davies)、ガンダルフ=イアン・マッケラン(Ian McKellen)、エルロンド=ヒューゴ・ウィービング(Hugo Weaving)、ガラドリエル=ケイト・ブランシェット(Cate Blanchett)、アルウェン=リブ・タイラー(Liv Tyler)、サルマン=クリストファー・リー(Christopher Lee)
ほぼ、3時間の大作。しかし、最後まで一時も飽きさせることなく、巧みに緩急をつけながら物語は進んでいく。心地よいクライマックスの連続。原作を忠実に再現した自然や建造物が素晴らしい。「指輪物語」の影響を色濃く受けている「スターウォーズ エピソード1」(ジョージ・ルーカス監督)の構想力を、しのいでいる。その美しい映像に見とれ、独創的な異世界に深く包み込まれた。数々のCGも、ハリウッドのレベルとそん色ない。ややもたつくシーンもあったが、むしろファンタジーとしての持ち味を引き出していた。キャスティングもめりはりがあって見事なものだ。中でも、ガンダルフ役のイアン・マッケランが、傑出していた。次作が、こんなに待ち遠しい作品はない。
20世紀までのファンタジーは、特定の個人や集団が、力の集中したものを巡って闘うという構図が目立った。物語の構造として、とても人々を引き付けた。しかし、今世紀は、この神話的な構造そのものを変える、それでいてリアルな物語を必要としている。
世界各地のひとり一人の試みが、離ればなれでいながら影響し合い世界を劇的に変えるというビジョン。その物語は、相互にリンクされた数千の断片によって構成する新しいスタイルになるだろう。そんなことまで、考えさせられた。
| カンダハール |  |
|---|
2001年作品。イラン=フランス合作。85分。配給=オフィスサンマルサン。監督・脚本・編集=モフセン・マフマルバフ。撮影=エブラヒム・ガフーリ。音楽=モハマド・レザ・ダルビシ。録音=ベルーズ・シャハマト、カーウェ・モインファール。助監督=M・ミルタルナスブ、カーウェ・モインファール。撮影助手=ハサン・アミニ、ハシェム・ゲラミ。スチール=M・R・シャリフイー。製作担当=シャマック・アラゲバンド。製作助手=アッバス・サグリサズ。製作=マフマルバフ・フイルム・ハウス(イラン)、バック・フィルムズ(フランス)。ナファス=ニルファー・パズイラ、タビブ・サビブ=ハッサン・タンタイ、少年ハク=サドユー・ティモリー、ハヤト=ハヤトラ・ハキミ
この作品は、女性差別などタリバンの抑圧性を強調している。ともするとアメリカによるアフガニスタン空爆を支持しているかのように見える。しかし、逆だろう。監督のまなざしは、そこに住む人々、歴史にほんろうされるひとり一人に向けられている。アフガニスタン空爆後に撮影されたとしたら、そこに暮らす人の視線で、アメリカの無神経さ、独善性を静かに告発したことだろう。
アフガニスタンで撮影できなかったのは、タリバンが映像そのものを禁止しているから。スタッフ、キャストの生命の危険を考慮して、撮影はイランで行われた。登場する人々は、ほとんどの人たちが俳優ではない。しかし生活感をたたえた見事な演技をしている。主人公ナファス役のニルファー・パズイラも、アフガニスタン出身のジャーナリスト。この作品は、彼女自身がカブールに住む友人からもらった「生きる希望を失ったので自殺する」という手紙が、もとになっている。
同時多発テロ以前に観ていたら、砂漠をはじめとした映像の美しさが、まず心に響いただろう。抑圧の象徴である衣装・ブルカが、とても美しく、複雑な気持ちになった。
そこで生きていかなければならない人々の、過酷な、しかしどこか滑稽なシーンやシュールな場面を通じて、アフガニスタンのおかれている現実を知ること。政治的にではなく、一人の人間として。監督は、それを願っているように思う。
| オーシャンズ11 |  |
|---|
2001年作品。アメリカ映画。117分。配給=ワーナー・ブラザース映画。監督=スティーブン。ソダーバーグ。共同制作=R・J・ルイス。製作総指揮=ジョン・ハーディー、スーザン・イーキンズ、ブルース・バーマン。制作=ジェリー・ワイントローブ。衣装=ジェフリー・クアランド。編集=スティーブン・ミリオン。美術=フィリップ・メシーナ。音楽=デイビッド・ホームズ。ダニー・オーシャン=ジョージ・クルーニー、ライナス=マット・デイモン、テリー・ベネディクト=アンディ・ガルシア、ラスティ=ブラッド・ピット、テス=ジュリア・ロバーツ、バージル・モロイ=ケイシー・アフレック、ターク・モロイ=スコット・カーン、バシャー=ドン・チードル、ルーベン=エリオット・グールド、フランク=バーニー・マック、ソール=カール・ライナー、リビングストン=エディー・ジェイミソン、イエン=シャオボー・クィン
ストーリーは、心地よく流れていく。意表をつく展開も、それほど驚かせるような演出をしない。飽きさせず、とても面白いのだが、あまりに自然に流れていくので、観終わった後に何も残らない。重い余韻を残した「トラフィック」とは、対照的。しかし、これはこれで見事な職人芸だと思う。ビッグスターの顔合わせにありがちな騒がしさもない。ジョージ・クルーニー、ジュリア・ロバーツらは、抑え気味の演技で、前に出過ぎないように配慮していた。
「オーシャンと11人の仲間」は観ていないが、今回オーシャン以外の強奪作戦メンバーは、10人しかいない。妻のテスを加えて11人なのだろうか。「オーシャンズ11」の場合は、オーシャンも含まれるのかな。
| コンセント |  |
|---|
2001年作品。日本映画。113分。配給=オフィス・シロウズ、メディアボックス。監督=中原俊。企画=佐々木史朗、見城徹。製作=鈴木孝之、宮下昌幸、升水惟雄、佐藤美由紀。プロデューサー=渡辺敦、東康彦、久保田傑。原作=田口ランディ『コンセント』。脚本=奥寺佐渡子。撮影=上野彰吾(J.S.C.)。照明=小野晃。録音=林大輔。音楽=大友良英。メインテーマ=メインテーマ=アディエマス『IMMRAMA〜ユキへ〜』(東芝EMI/Virgin)。美術=稲垣尚夫。衣裳デザイン=小川久美。編集=深野俊英。スクリプター=川野恵美。ビデオ・エンジニア=宇津野裕行。ヘア・メイク=小田多佳子。ユキ=市川実和子、木村=村上淳、律子=つみきみほ、ユキの兄=木下はうか、山岸=小市慢太郎、特殊清掃員=斎藤歩、葬儀社の男=不破万作、亜子=りりィ、アパートの大家=梅沢昌代、国貞=芥正彦、ユキの母=二木てるみ、ユキの父=夏八木勲
市川実和子の醒めた熱演も特筆すべきだが、シャーマニズムの研究をしている律子役つみきみほの奥の深い演技も見逃せない。トラウマを抱えながら、シャーマンにひかれつつシャーマンに頼らない自力での立ち直りを目指す律子の痛々しい姿に共感した。影が薄くなりがちな男たちの中では、腐乱死体の部屋を掃除する特殊清掃員役の斎藤歩が、生命力あふれる前向きの存在感があって清清しい。
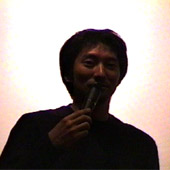


 中原俊監督のトーク
中原俊監督のトーク  質問に答える3人
質問に答える3人  田口ランディさんについて
田口ランディさんについて| 1996年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 |