|
 岡田健吉@zu5kokd1 岡田健吉@zu5kokd1
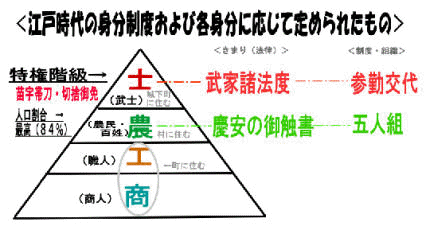
武家諸法度とは? (ネットより画像借用)
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・(
123 )
【
支折の言葉・・・20/
1 】・・・( 46 )
…という事になります。
江戸時代・初期/元禄(/1688年~1704年)の頃は…
まだ、<上方中心・・・天皇・公家の影響下の・・・日本文化・・・>
でしたが…
蕪村や一茶が活躍した、文化文政(ぶんかぶんせい/1804年~1830年)の頃になると、<日本の
文化は・・・江戸中心・・・>
に、移っていた、という事になります。
ええと…
先ほども、言ったように…
<江戸は・・・武家仕様の町/・・・消費専門都市・・・> で、その上に、争い事や武力が
封殺されていたわけです。武家のエネルギーは、武芸の鍛錬は当然のこととして、学問や
文化の方へも、押し出されて行ったわけですね。
ええ…
芭蕉が他界して、8年程後の事ですが…
この元禄年間/元禄14年に、人形浄瑠璃(にんぎょう・じょうるり)や歌舞伎の演目にもなった…
『仮名手本忠臣蔵』
の、<赤穂事件(あこう・じけん)>
が、起こっていますわ。
あの…
<江戸城/松の廊下の・・・刃傷事件(にんじょう・じけん)> で、抜刀したコトが、いかに異例
の大事件かが、私達にも伝わって来ます。幕府は、それほど、武威の暴発を禁じていたわ
けですね、」
「そあかあ…」マチコが、宙を見た。「でも、赤穂浪士の仇討ちは、容認しているわよね?」
「ええ…」響子が、強く、うなづいた。「そこは…
武家/征夷大将軍が取り仕切る、<武家諸法度(
/江戸時代初期の1615年に、江戸幕府が諸大名の
統制のために制定した基本法。)の・・・統治体制・・・>
だった、という事でしょうか、」
「ふーん…」マチコが、腕組し、コクリとうなづいた。
「はい…」支折が言った。「ええ…
話を進めましょうか。次は、<大和路> ですね…
 岡田健吉@zu5kokd1 岡田健吉@zu5kokd1
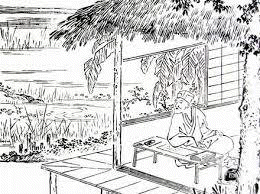 

1680年に、芭蕉は深川/芭蕉庵に転居します。 (ネットより画像借用)
<天和の火事/1683年1月25日>の際、芭蕉庵も焼失。 簡素な作りで、立て直すのも簡単だったのでしょうか?
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・(
122 )
【
支折の言葉・・・20/
1 】・・・( 45 )
ちなみに…
芭蕉がいた頃(/・・・元禄7年10月12日に、芭蕉は逝去(せいきょ/死ぬ、の尊敬語)しています。)…
元禄6年の、江戸の庶民人口は、約35万人ですね。プラス武士が50万人で、合計85万
人ほど、でしょうか。
現在/東京の人口が…
約1000万人として、その1/10以下ですよね。そして、幕府機関を中心として、消費する
だけの、世界的な巨大都市だった…
 岡田健吉@zu5kokd1 岡田健吉@zu5kokd1
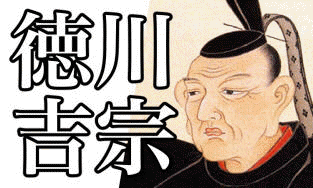 
第8代将軍/徳川吉宗 (ネットより画像借用)
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・(
121 )
【
支折の言葉・・・20/
1 】・・・( 44 )
< 1721年/享保6年には ・・・約50万人・・・>
1721年/享保6年には ・・・約50万人・・・>
…と推定されています。
これに…
<江戸の、武家人口の・・・約50万人・・・> を、加えると…
享保の頃…
<江戸時代・中期/・・・第8代将軍・吉宗の頃・・・> には…
<江戸の総人口は・・・約100万人・・・> に、達しています。
 岡田健吉@zu5kokd1 岡田健吉@zu5kokd1
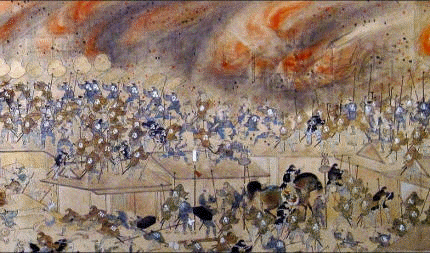
<明暦の大火
・・・明暦3年1月18日~20日
(1657年3月2日~4日)>
・・・江戸の大半を焼失した大火災です。
江戸・三大大火の筆頭で・・・外堀以内のほぼ全域の、天守を含む江戸城、多数の大名屋敷、市街地の大半を焼失
し、死者数については諸説あって、3万~10万人と記録されています。この大火で焼失した江戸城天守は、その後、
再建されることはありませんでした。
その後の <天和の大火・・・天和2年12月28日
(1683年1月25日)> の際は・・・芭蕉庵も焼失しています。
芭蕉自身は、六間堀に腰までつかって頭に苫(とま/スゲやカヤなどを粗く編んだムシロ。)をかぶり、時々は苫に水
をかけて、火を凌(しの)いだそうです。でも、大寒の季節ですよね。 (ネットより画像借用)
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・(
120 )
【
支折の言葉・・・20/
1 】・・・( 43 )
…必然的に、文化の中心地になりますわ。
ええ…
手元にあるデータによれば…
“
江戸の・・・町人人口の・・・推移
” は…
<関ヶ原の戦い/1600年> から…
34年後の…
< 1634年/寛永11年には・・・約15万人・・・>
1634年/寛永11年には・・・約15万人・・・>
< 1657年/明暦3年には ・・・約28万人・・・> (<明暦の大火>
・・・のあった年です。)
1657年/明暦3年には ・・・約28万人・・・> (<明暦の大火>
・・・のあった年です。)
< 1693年/元禄6年に約 ・・・約35万人・・・>
1693年/元禄6年に約 ・・・約35万人・・・>
|
 Twitter/2021・・・11月
Twitter/2021・・・11月 





