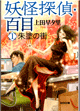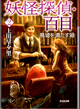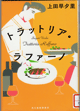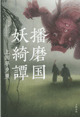| 10. | |
|
「妖怪探偵・百目<1>−朱塗の街−」 ★☆ |
|
|
|
妖怪と人間が共生する街<真朱の街>。ある事件をきっかけに帰る場所を失った相良邦雄は、この街の妖怪探偵=百目の元で探偵助手として暮すことになります。 その百目、スリットの深く入ったノースリーブのロングドレスを纏う絶世の美女ながら、実は全身に百の目を持つ妖怪=百目鬼。当然ながら百目の元に舞い込む事件はすべて妖怪絡みにしてその報酬はというと、依頼人の寿命。 それは邦雄も同様で、百目にこき使われる傍ら、時に百目の協力を得るため寿命を少しずつ吸い取られるという日々。 本書はそんな邦雄と百目コンビによる、真朱街を舞台にした妖怪探偵物語、という趣向の連作短篇集。「<1>」とあるので、今後シリーズ化されるようです。 “妖怪”というと昔はホラー、最近はファンタジーでしょうか。すぐ思い浮かぶのは畠中恵“しゃばけ”シリーズと荻原浩「愛しの座敷わらし」といったところ。 それらに対しSF作家である上田さんが妖怪ものを書くと、こうも違うものかと思います。まず説明が緻密かつ合理的楓。そしてさらに、科学進歩により異形の生物になったと言うべき人間は、もはやある点では妖怪に伍する存在となった、と説明されています。 本書は<SF+妖怪>要素が妙味。何が起きても不思議ないという前提が、この街の特殊な雰囲気と相まって、スリリングな香りを色濃く漂わせています。 主人公の邦雄、いつまでその寿命が持つのやらという気持ちもありますが、今後のシリーズ化が楽しみです。 ※本シリーズの第1篇「真朱の街」は短篇集「魚舟・獣舟」に収録。相良邦雄と百目との出会い、この街に住み付くこととなった経緯が語られていますが、本書中でも繰り返し語られていますので、第1篇を未読でも本書を楽しむのに何ら支障はありません。 なお、登場する妖怪に何となく親しみを感じてしまうのは、水木しげる「ゲゲゲの鬼太郎」のおかげでしょうか。(笑) 1.続・真朱の街(牛鬼篇)/2.神無しの社/3.晧歯/4.炎風/5.妖魔の敵 |