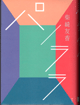|
部屋の更新料が支払えず困っていた主人公の田中真紀子28歳は、友人のイチローから勧められて、彼の家に間借りすることになります。
その家はコンクリート3階建の本館+黄色い木造2階建+鉄骨ガレージという奇妙な家。そして主人公が住むことになったのは、ガレージの上に乗っかった赤い小屋のような独立部屋。
家ばかりではなく住人も奇妙な人物ばかり。木村家の父親である将春は全裸で人前に現れるし、母親は脇役で人気の女優=志乃田みすず。イチローの姉=文、妹=絵波も一癖二癖あり、おまけに3人とも父親が違うのだという。
地味で平凡な主人公という設定はこれまでの柴崎作品と変わりありませんが、奇妙な家に奇妙な家族という設定は 400頁超という大部であることと合わせ、柴崎作品としては初めてと言って良いくらい珍しいもの。
しかし、読み進むうち、訳有りなのは何も木村一家の人々だけでなく、主人公自身の家族もかなり訳有りであることが、明らかになっていきます。
題名の「パノララ」とは、主人公がみすずから貰い受けたデジカメで時々写すパノラマ写真をもじったもののようです。
示唆された訳ではありませんが、本ストーリィを俯瞰して見ると本作品の内容が掴めてきます。
木村一家と田中一家を対照することができますし、ある意味で主人公とみすずは対極にある、と言えるでしょう。
居場所とは何か、自分の居場所はどうしたら見つけることができるのか、それらを問うたストーリィ。
そして結末はというと、完了形ではなく、現在進行形。
それは柴崎作品の現在および今後について語っているようで、これからの作品への期待心へと繋がります。
|