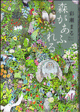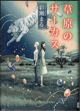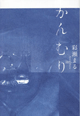| 「珠 玉」 ★★ | |
|
2022年11月
|
自分のブランドを立ち上げ、ファッションデザイナーとしての成功を夢見る真砂歩(あゆむ)。 しかし、歌姫として今も伝説的な存在である祖母・真砂リズに自分を比較し、容姿を含め自信が持てないままでいる。 そんな歩に愛想をつかし、ブランドのジュエリー分野でパートナーだった詩音についに見捨てられてしまう。 失意の歩が、芸能事務所を経営する義祖父・秀久のパーティで偶然出会ったのは、ハーフのイケメンである小暮ジョージ。 歩からすれば何でもできるだろうと思えるジョージでしたが、彼は彼なりに自信を失いかけていた。 勝手にという感じでジョージが歩の仕事に関わるようになったところから、それぞれ前に進めなかった歩とジョージが、お互いに関わり合いながら前にと踏み出していくストーリィ。 容姿に恵まれないこと、容姿だけ恵まれていること、それに引け目を感じてしまったらさぞ悩みは尽きないのでしょうねー。 しかし、それまで自分一人で悩みに向かい合っていた2人が、自分を見てくれる相手を得たことで、道が開けていく。 成長物語、確かにその通りなのですが、その一言で済ませてしまうのは余りに惜しい。 本作では、歩にしろジョージにしろ、等身大のキャラクターであるところが実にいい。 口下手でネクラな歩、手癖の悪いジョージ、それでも思い悩みながらなんとか前に進む糸口を掴もうとしている2人の姿は、とても愛おしい。 2人の物語と並行して祖母リズの物語も語られます。 また、リズのお守りだった真珠、今は歩のテディベアの片目となった真珠のキシも、人造真珠のカリンとの会話という形で、本ストーリィに加わります。 何といっても歩のキャラクター、歩とジョージの関わり具合が、好きです。 2人のこれからに心からエールを贈りたい。 |