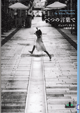|
|
|
|
1.停電の夜に 2.その名にちなんで 3.見知らぬ場所 4.低地 5.べつの言葉で 7.思い出すこと 8.翻訳する私 |
|
「停電の夜に」 ★★ |
|
|
2000年08月 2003年03月
|
いずれもインド系の人物を主人公とした9短篇。 原本の表題作は、O・ヘンリ賞を受賞した「病気の通訳」。O・ヘンリのようにユーモア、ペーソスが明瞭に現れている訳ではありませんが、自然とO・ヘンリを連想させる、同質の味わいを内包しています。端然とした文章の中にそれが隠れているという風で、噛み締めるほどに味わいがあります。 9篇の中で気に入ったのは、ユーモア度の高い「病気の通訳」、「神の恵みの家」。そして、見知らぬ2人が夫婦関係を築く過程を明るく描いた「三度目の最後の大陸」は、気持ちの良い作品です。また、表題作の「停電の夜に」は、読者の予想をはぐらかすような結末に、複雑な味わいがありました。 停電の夜に/ピルザダさんが食事に来た ころ/病気の通訳/本物の門番/セクシー/セン夫人の家/神の恵みの家/ビビ・ハルダーの治療/三度目で最後の 大陸 |
|
「その名にちなんで」 ★★☆ |
|
|
2004年07月 2007年11月 2004/08/22 |
アメリカで暮らすインド(ベンガル人)人夫婦、そしてその息子の人生を淡々と描いた、著者初の長篇作品。 ストーリィの始まりは1968年。出産を間近に控えたアシマ・ガングリーの登場から。アシマは、アメリカの大学院で働くアショケの元へカルカッタから嫁いできた女性。 不幸を描いたということではない。異国に暮らす、居付くということの姿を、母親とその息子を時に対比させながら、濃やかに描いているところが好ましい。 |
|
「見知らぬ場所」 ★★★ フランク・オコナー国際短篇賞 |
|
|
2008年08月
|
夫婦、家族、恋人等々と様々な愛の姿を描いた作品集ですが、さらりと読めてしまう割りに、噛み締めてみるといずれもしっかりとした、味わい深い作品ばかり。 前の「停電の夜に」「その名にちなんで」は、総じて異郷に暮らすベンガル人家族を描くという色彩が強かったのですが、本書でそれはかなり薄れています。意識しなければベンガル人の家族ということすら忘れてしまう程。それが先の2冊と違ってさらりと読めてしまう、という印象の理由かもしれません。 本書を読むと、愛情は決して一様なものではなく、お互いの愛情が微妙にすれ違うこともあれば、様々な関わり方、様々な現れ方をするものだなァと改めて感じさせられます。 第二部の「ヘーマとカウシク」は、3つの短篇を連ねて中編小説に仕立て上げるという趣向の作品。 インド系作家の中でも特に秀でたJ・ラヒリの最新刊。お薦めです。 (第一部)
見知らぬ場所/地獄・天国/今夜の泊まり/よいところだけ/関係ないこと |
| 4. | |
|
「低 地」 ★★☆ |
|
|
2014年08月
|
革命運動に身を投じて殺された弟=ウダヤン。米国に留学していた一つ違いの兄=スバシュは、ウダヤンの身重の妻=ガウリを救おうと、夫婦として生きていくことを決心して彼女を米国に連れ帰ります。 インドのカルカッタと米国ロードアイランドにまたがった、長い年月に亘る家族の物語。 470頁余と大部な一冊ですが、ストーリィ運びがうまいので、まるで重くなくすんなりと読み切ることができます。 ただし、同じように喪失感を抱えているといっても、スバシュ・ベラの2人とガウリの間には、違いがあるように感じます。 地味なストーリィですが、懐の大きな、そして作者の円熟を感じさせる好作品。お薦めです。 |
| 「べつの言葉で」 ★★☆ 原題:"In Altre Parole" 訳:中嶋浩郎 |
|
|
|
学生時代に妹とフィレンツェへ旅行したのが、著者とイタリア語との初めての出会いだったとのこと。その時にイタリア語に惹かれ、それから20年余イタリア語を学び、ついに家族と共にローマへ移住。 本書はその異国の地での暮らしを、苦労しつつもイタリア語で綴ったエッセイ&短編小説2篇。 残念なのは、翻訳で読むしかない我が身の故に、著者の苦労の程を文章から汲み取れないことです。 「べつの言葉で」という題名は、イタリア語で暮す日々と、イタリア語での執筆ということを併せて伝えているかのようです。 使用する言葉を変えるという行為によって、書くという行為が一旦リセットされたということなのでしょうか。本書の文章は平易で親しみ易く、共感できるものになっています。 イタリア語を身につけるには現地にて、という気持ちはよく分かります。イタリア語を使うことが自然な環境なのですから。 でもそれと同時に、いくらイタリア語に習得しても膚色のために外国人という視線から逃れられない(夫は妻よりイタリア語ができないというのに白人というだけでイタリア人と度々間違えられている)ということも筆者は感じさせられています。 それはイタリア語のみならず、米国における英語、故郷を訪れた際のベンガル語についても同様と言う。 言語については常に外国人という立ち位置。では自分がよりどころに出来る国は何処なのだろうかという疎外感も、イタリア語に奮闘する中ではっきりしてきた想いなのかもしれません。 とはいえ、小説でもなく、短いエッセイではありますが、極めて質の高い一冊。感じさせられることは頁数以上にあります。 ※短編小説は「取り違え」「薄暗がり」の2篇。 |
| 6. | |
|
「わたしのいるところ」 ★★☆ |
|
|
2019年08月
|
2012年から3年間にわたりローマで生活した著者が、自国語ではないイタリア語で書いた2冊目の著書、初の長篇小説。 |
| 7. | |
|
「思い出すこと」 ★★ |
|
|
2023年08月
|
本作は、詩集です。しかし、作者がラヒリであるからにはただの詩集ではありません。 作者がローマで住んだ家具付きアパート。そこにあった書斎机の引き出しの中から、作者は前の住人が残したらしいノートを見つけます。 中には手書き数十篇の詩が記されており、表紙には「ネリーナ」という名前。 そのネリーナという女性、祖父母の住まいや、過去に住んだことのある土地、家族の名前と、作者自身とよく似ている。 作者は、イタリアの詩を研究している親しい知人=ヴェルネ・マッジョ博士に詩の監修を依頼。マッジョ博士が詩をテーマ別に分類し、タイトルを付けて出来上がったのがこの一冊。 ラヒリ自身による<序>、ネリーナの詩、そしてマッジョ博士のによる<評論・注釈>という3つからなる構成。 ネリーナも、マッジョ博士も、実はラヒリによる架空の人物。つまり、全ては作者による創作なのです。 詩の内容はというと、日常生活のあれこれ。家族や旅、個人的な思い出等々。 収録されている詩のリズムが、実に良い、楽しく読めます。 複層構造により生まれる奥行き、読み応え、面白さに、いろいろな思いが交錯します。 こうした日常を、作者は心から愛しているのだろう、と感じられます。 そうした点から、詩という形式を用いているとはいえ、本作は本質的に小説ではないか、と思う次第です。 詩が好きな方、詩が苦手な方にも、お薦めしたい一冊です。 はじめに/伝記のための仮説/本文についての断り書き/ 窓辺/思い出すこと/語義/忘却/世代/考察/ 注 |
| 8. | |
|
「翻訳する私」 ★☆ |
|
|
2025年04月
|
久々の英語による著書、英語では初のエッセイ集とのこと。 内容は題名とおり、翻訳について著者が7年間にわたり考えたことまとめたものとのこと。 序文部分については、イタリア語に挑んだ理由が語られ、これまでの経緯を理解することができたのですが、肝心の本論部分、正直なところギブアップ。 内容がもう、翻訳に関する学術論文のようなもので、初めてイタリア語からの英訳に挑んだドメニコ・スタルノーネ「靴ひも」を除いては、全く知らないイタリア人作家の作品を取り上げての翻訳作業における課題等々を語ったもので、理解しきれず、読み切れず、といった始末。 ※イタリア「外国でのカルヴィーノ」は、作家イタロ・カルヴィーノに関するエッセイ。 なお、興味深かったのは、次の3点。 ・米国育ちで米国居住でしたから著者が英語で執筆するのは当然のことだと思っていましたが、そんな単純なことではなく、著者にとっては英語もまた翻訳作業の対象であったとのこと。 なるほど。英語では翻訳という行為が曖昧だったのでしょうけれど、イタリア語であれば翻訳であることは明瞭、だからこそイタリア語に挑戦したのかと得心した次第。 ・イタリア語で執筆した自作小説を自身で英訳する場合の問題、課題点。 ・著者については、小説家であり、翻訳はその傍らの作業と思っていたのですが、現在は既に、小説家であると同時に翻訳家であると認識すべきであるようです。 ※現在著者は、プリンストン大学の同僚である古典学科教授と、オウディウス「変身物語」のラテン語から英語への翻訳に共同で挑んでいるそうです。 同作が著者の訳書としてもし翻訳刊行されることがあったら、読んでみたい気がします。 本書については途中、読むのを止めて放り出したくもなりましたが、著者について知るという上では、貴重なものだったように感じています。 序文/1.なぜイタリア語なのか/2.容器−ドメニコ・スタルノーネ「靴ひも」の訳者序文/3.対置−ドメニコ・スタルノーネ「トリック」の訳者序文/4.エコー礼讃−翻訳の意味を考える/5.強力な希求法への頌歌−事象自称翻訳家の覚え書き/6.私のいるところ−自作の翻訳について/7.代替−ドメニコ・スタルノーネ「トラスト」への「あとがき」/8.普通の(普通ではない)翻訳・Traduzione(stra)ordinaria−グラムシについて/9.リングア・ランゲージ/10.外国でのカルヴィーノ/あとがき−変容を翻訳する オウィディウス |