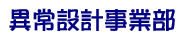
|
「らぴすらずりIII」は僕がロボット技術研究会の友人である片山君・中上君・篠原君と製作した
第6回かわさきロボット競技大会用マシンの名前です。
僕の1997年の「らぴすらずり」、 Meisterの1998年のマシン 「るびぃNT5」に続く、 巨大な腕をもつマシンの三代目として大会に参加しました。 |

|
「11条」と呼ばれるこの条文は、
- フィールド上の一点から別の一点までの走行試験
- 走行試験に失格したマシンの即時敗退
つまり歩行性能のないらぴすらずり(初代) のようなマシンには大会参加の道が閉ざされました。
そこで第6回大会に向けて設計を開始する際にはらぴすらずり(初代)同様の巨大アームと せっかく作るんだから人並み以上の歩行性能を備えたマシンを目指す事にしました。 この足回りの追加によって、 らぴすらずり(初代)では不可能だった、 旋回によって相手に照準を合わせる事も可能になります。
ただし、ICBE2に使用しているシャフトが曲がるのを防ぐために構造を変更しました。 らぴすらずり(初代)では両端が固定端であったため、 シャフトに曲がりが生じていたものを一端を回転対偶にし、 もう一端をダンパで支える事としました。
この改造によってシャフトが曲がる事がなくなり、ICBE2はより堅牢な 構造となりました。
その役目を果たしながら、以下の点で変更を加えました。
- らぴすらずり(初代)ではφ10mm、肉厚1mmのアルミパイプを使用していたものを 軽量化のため、φ10mmはそのままで肉厚を0.5mmに減少しました。
- らぴすらずり(初代)ではストラトリンクの一部に長さ1000mm以上のアルミパイプが使用されていました。 東急ハンズで注文するのですが、これが高価なのでパラメータを変更して 全てのアルミパイプが1000mm以下になるようにしました。
- パラメータの探索範囲を30倍に広げ、 35万パターンの中からある評価関数の値を最適化するように ogulinkを高速化改造し、検索を行いました。
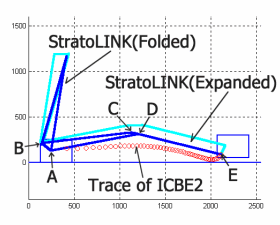
図1:ICBE2の軌跡とStratoLINK
| リンク名 | らぴすらずり(初代) | らぴすらずりIII |
| DA | 976 | 975 |
| AB | 164 | 130 |
| BC | 944 | 995 |
| CD | 92 | 75 |
| DE | 1044 | 935 |
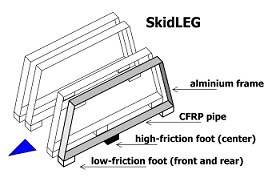
図2:SkidLEGと擬似12足歩行
|
完成したマシンらぴすらずりIIIは友人たちの尽力のおかげで、
当初の目的通りの巨大なアームによるアウトレンジ攻撃性能と
人並み以上の歩行性能を備えたマシンとなりました。
右に写真を示します。 この写真はらぴすらずりIIIを左側面から撮影したもので、 鳥のくちばしのように見えるICBE2の跳ね上げエッジ、 折り畳み時のアームの構造、箱型の足機構、 後部に集中して搭載されている電装品などが良く分かります。 一方残念ながらミラーチェビシェフ2機構は陰になってよく分かりません。 |
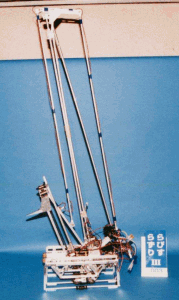
図3:らぴすらずりIII(1999年8月28日撮影) |
| 全長(スタート時) | 345mm |
| 全高(スタート時) |
1200mm
「るびぃNT5」「らぴすらずり」についで歴代3位 |
| 全長(展開終了時) |
2210mm
「らぴすらずり」「るびぃNT5」についで歴代3位 |
| 全幅(スタート時・展開終了時とも) | 245mm |
| 重量(バッテリー含む) | 3450g 重量制限は3500g |
| 電源 | 単三アルカリ乾電池10本(制御電源用4・足動力用6) |
| 動力 |
コンスタントフォーススプリング6
(アーム展開用2・相手跳ね上げ用4)・ 実委支給ギヤ・アーム巻戻し用モータ1・ エッジ展開トリガ用モータ1・ アーム展開用ソレノイド1 |
| 所要展開時間 | 約1秒
平均的マシンが自分の全長(およそ350mm)をすすむ時間の3分の2 |
| 歩行形式 | チェビシェフ近似直動機構によって駆動される4グループ12足歩行 |
| 歩行速度 | 約150mm/s |
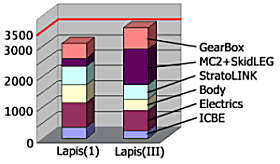
図4:重量配分
部品点数はらぴすらずり(初代)の約150点から320点強に増え、 そのほとんどが足機構の増強によるものです。 またストラトリンクとICBEは軽量化されましたが、 それは不十分で結果として重量制限をクリアするため、 多大な労力を費やす結果となりました。
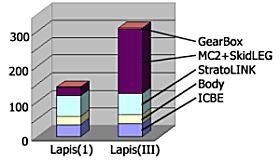
図5:部品点数(電装品は除かれています)
単純な形状の部品を組み合わせる事によって 複雑な機構を実現する設計方針は、製作が容易という利点を持ちます。
しかし一方でかわさきロボットの脚のような同形の部品を 大量に製作する場面では部品点数がうなぎ上りに増え、 また軽量化しようとした場合には小さな部品ばかりであるために どこを軽量化したらよいかわからないという欠点も持っているのです。
| 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 第1回戦 | model7-Antique | マシントラブルのため、引き分け2回のあと押え込み一本負け |
| 敗者復活1回戦 | PER-38 | 相手を転倒して当初想定の通り一本勝ち |
| 敗者復活2回戦 | RRW02 | 不戦勝 |
| 敗者復活3回戦 | ホイホイ | 相手が走行審査をクリアできず、一本勝ち |
| 敗者復活4回戦 | ひょっとこ | 相手を跳ね飛ばしたものの、押え込み一本負け |
| 特別戦 | 五六式メカトロ三等兵六三型丙 | 相手を転倒し一本勝ち |
| エスカフローネ弐号機 | 押え込み一本勝ち | |
| 高起動ロボット(GS99) | 相手が試合放棄 |
しかしここで問題となるのは、このマシンを製作する上で、 特に軽量化のため、 恐るべき労働力が使用されたという事です。 ロボット技術研究会の友人諸氏の協力がなければ、 このようなマシンの製作は不可能であったと考えられます。 今後は「らぴすらずり」また製作を完了せずに 出場辞退した1996年の「五里霧中」の設計方針に立ち返り 「より安く・より速く・より良く」を目指していきたいと考えています。
またこの年から異常設計事業部の設計スローガンに「ノーモア・ニクヌキ」が追加されました。
| 1998年12月 | 設計開始 |
| 1999年1月 | 足機構に「ミラーチェビシェフ2機構」の採用を決定 |
| 1999年4月 | 製作に着手 |
| 1999年8月 | 第6回かわさきロボットコンテスト予選・エキジビジョンマッチに出場 |
| 1999年11月 | 都立高専祭で開催されたバトルロボットコンテストに出場 |
| 2000年7月 | 足回りブロックを「らぴすらずりVI」で再利用。マシン解体 |
| ( 2001年8月 ) | 足回りブロックのみ「保守的らぴすらずり」にて再々利用 |
| ( 2002年6月 ) | NHK取材時に足回りブロックを破損。以降保管状態 |