|
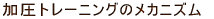
|
|
|
|
加圧トレーニングでは、運動時に筋血流が適度に阻害されるため、疲労物質である乳酸が発生して筋肉に蓄積します。その結果、負荷が小さな場合でも筋活動レベルが増大します。
そのため過酷な運動をしたときのように筋肉が酸素不足という情報が脳に伝わり、下垂体前葉で筋肉の合成に欠かせない、成長ホルモンが大量に分泌され、血流によって全身に運ばれます。
血流によって全身に運ばれた成長ホルモンは、ストレス状態にある筋肉に作用し、体脂肪を分解させたり筋肉を形成します。 体脂肪の分解や筋肉の形成のためには十分な量の成長ホルモンが必要になり、十分な量の成長ホルモンを出させるだけのストレス状態(乳酸濃度の上昇)を作り出すことが必要になります。
従来は、そのようなストレス状態に筋肉を追い込むには、ハードなトレーニングが必要でした。しかし、加圧トレーニングは、加圧を行うことによって、ハードなトレーニングによるストレス状態を擬似的に作り出しているのです。
|
|
|
|
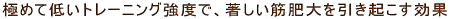 |
|
|
|
平均年齢60歳の女性を対象とし、肘屈筋に対し、平均110mmHgの加圧下で30〜50%
1RM×15回×3セットのトレーニングを週2回、4カ月間を行った結果、筋力、筋横断面積がともに平均20%増大した。
この結果は、80%1RMの負荷で加圧を伴わずに行った場合の効果よりやや大きい傾向があり、また、30〜50%1RMで加圧を伴わずに行った場合にはほとんど効果がなかった。
|
|
|
|
これらの結果から、加圧トレーニングは低負荷にもかかわらず、筋力増強と筋肥大に著しい効果があり、その効果は筋血流の制限そのものに関係していることが示された。
また、トレーニングを行わなかった上腕三頭筋にまで、著しい筋肥大がみられた。
|
|
|
|
一方、同様の低負荷の加圧トレーニングをトップアスリートの膝伸筋を対象に行った結果(圧は平均210mmHg)、膝伸展筋力で平均15%、膝伸展パワーで平均9%、筋横断面積で平均15%の増大が見られた。 さらに、50回の連続最大筋力発揮における疲労耐性に有為な向上が見られた。
このことは、筋肉のつきにくい高齢者の女性が、軽いダンベルカールの運動のみで、短期間で筋力、筋横断面積共に飛躍的に向上したことを示しています。また、直接トレーニングしていない拮抗筋まで著しい筋肥大の効果が及んでいることから、ケガからのリハビリにもさらに有効です。
アスリートの場合も、筋力と筋持久力が同時に増えるというトレーニングの原則を超えた結果が出ています。加圧トレーニングの場合は、軽い負荷でもトレーニングを開始すると早い段階で二種類(速筋、遅筋)の筋肉が活性化してきます。加圧をすることによって、血流量をコントロールすると筋肉が錯覚を起こすのです。その結果、筋肉を増強させ筋力と持久力の両方をアップさせることが可能になるのです。
高重量でトレーニングを行うと、どれほど注意しても、100%ケガから回避できるという保証はありません。さらに重いもの持ち上げると血圧が上昇し血管に何かしらの問題がある場合は、少なからず悪い影響を受けます。しかし、軽い重量で行う加圧トレーニングならば、関節が痛くても負担がかからず、ケガも血圧の上昇も心配ありません。安全にトレーニ
ングができます。
|
|
|
|
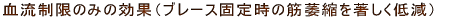
|
|
|
|
骨折して、ギブスをはめ、脚がまったく動かない状態であっても、トレーニングをせず、ただ加圧するだけで筋肉を維持することができます。
東京大学で行った実験では、骨折して脚が動かなくなったとき、加圧しないでおくと約20%筋肉が細くなったのに対し、1日数回加圧をするとそれが8%あまりですんだという結果がでています。
手術後や骨折、靭帯損傷、肉離れなど安静固定を必要とされる場合でも、早期リハビリとして加圧、除圧刺激を2〜3日目から開始することができ、筋萎縮を低減することが出来ます。
|
|
|
|
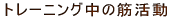
|
|
|
|
筋電図解析を用いた研究から、加圧筋力トレーニングでは、負荷強度が40%1RMと低い場合でも、筋中ほとんどすべての筋繊維が活動することがわかった。負荷が軽いにもかかわらず、筋としては、80%1RMの負荷がかかっている場合と同様に頑張らざるをえない状況に、即時に追いこまれることになる。
加圧トレーニングをした時には、負荷は軽くてもたくさんの筋線維が使われます。普通のトレーニングをしているとき、筋肉を目一杯使っているつもりでも、実はかなり余力を残しているのです。これは、イザという時の”火事場の馬鹿力”のために、体が無意識に制御をかけているからです。加圧をするといい意味で筋肉がだまされて、いつもより活発に働いてしまうのです。
|
|
|
|

|
|
|
|
大腿基部加圧をし、20%1RMという低強度(ほぼ日常レベルの筋力発揮)でレッグエクステンション、レッグカールを、それぞれ3セットずつ行うだけで、15分後には、血中の成長ホルモン濃度が安静時の300倍にも上昇した。
加圧トレーニングを行った後、成長ホルモンの血中濃度が著しく上昇することがわかってきました。この成長ホルモンの上昇を促すのが乳酸です、加圧トレーニング中には血液中の乳酸濃度も大きく上昇します。乳酸は筋肉が疲労する時にできる物質で、筋肉内にあるレセプター(受容体)を刺激して成長ホルモンを増やす働きをしています。
加圧時には腕や脚の血流が制限されているため、筋肉内の乳酸は血流によって出ていきにくくなります。そのため、筋肉内の乳酸の量が増え、レセプターが強く刺激されるので、大量の成長ホルモンの分泌が起こるのです。この成長ホルモン濃度の上昇が、筋肉の増強に影響を与えていると考えられています。
成長ホルモンの分泌促進により、体力強化、筋肉の増量、体脂肪の減少、肌に張りやつやがでる、免疫力の強化、コレステロールの減少、記憶力の回復、血圧安定、疲労回復が早くなる、更年期障害の改善、熟睡できる、視力改善、心肺機能改善、骨粗鬆症の予防、心臓病、脳卒中の予防、性的機能の改善、自然治癒力が高まる等、老化現象を遅らせるさまざまな効果が出ています。
また、加圧トレーニングを骨折や骨頭壊死のリハビリに取り入れた例では、筋肉の増強だけでなく、骨の修復速度が通常より速くなることがわかっています。この現象にも成長ホルモンの働きが関係しているのではないかと考えられます。
|
|
|
|
|
|
|
|
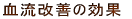 
|
|
|
|
加圧をして腕や脚へ流れる血流を制限すると、一時的に血液の循環が悪くなります。すると腕や脚の血管が少しでも多くの血液を取り入れようと、拡張する現象が起こります。
血管が拡張したところで加圧ベルトを外すと、多量の血液が一気に流れ込みます。この時、血管の内側では、それまで血流を妨げていた老廃物などが押し流されるのです。
(末梢抵抗(血液の流れにくさ)の指標は加圧前を1.0とすると、良好な加圧をかけているときは1,7ぐらいになり、1,7倍流れにくくなります。次にベルトをゆるめて圧を取り除くと、末梢抵抗の値がは0.6まで下がっています。これは加圧前に比べて血液が流れやすくなっていることを示しています。)
これを繰り返すことによって、血管の拡張、収縮の機能は高まり、血管の弾力性も増していきます。若い頃はほとんどの人が血管も弾力性に富んでいるため、心臓から送り出された血液を末梢まで送るべく、血管壁が十分に伸びます。
しかし、加齢と共に血管の弾力性は失われ硬くなります。その結果、血流に対する抵抗が大きくなり血圧は上昇するのです。つまり、高血圧になるということです。高血圧は、動脈硬化などの要因と考えられていますが、加圧を続けることで、血管は常に弾力性を保つことが可能になり血行がよくなるのです。
加圧トレーニングによって著しく血行が良くなると筋肉へ運ばれる酸素の量が増えます。そしてその結果、新陳代謝が活発になって筋肉が増大するのに適した環境ができます。
|
|
|
|

|
|
|
|
加圧の前後で血管が増えているのがレントゲン写真で確認さています。これが血液が流れやすくなるもうひとつの理由です。新しい血管ができて、より多くの血液が流れるようになるのです。
|
|
|
|
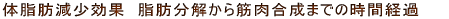
|
|
|
| |
加圧トレーニングをすると脳の下垂体で成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは筋肉をつくる上、体脂肪を脂肪酸とグリセロールという物質に分解する働きがあります。体内で実際に燃焼するのが脂肪酸です。
まず加圧トレーニングで脂肪を分解し、脂肪酸が血中に出てきた頃(成長ホルンモンの分泌後、約1時間で成長ホルモンによる脂肪分解が開始されます)に有酸素運動(エアロビクスや ランニング、ウォーキング)をすれば効率よく体脂肪を減らせます。
そして、約2時間後に成長ホルモンによる脂肪分解のピークを迎えます。筋肉合成は2〜3時間後に開始さ
れ1〜2日で完了されます。
(参考文献 加圧筋力トレーニングの理論と実践、加圧トレーニングの奇跡)
「極めて低いトレーニング強度で、著しい筋肥大を引き起こす効果」は、アメリカの権威ある研究誌「Jounal of Applide Physiology」の2000年1月号に掲載され、大きな話題となったばかりです。
2001年 第12回日本臨床スポーツ医学会で
加圧筋力トレーニング法のリハビリテーションへの応用 が井上医師により発表され大きな話題を集めました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|