|
5月14日
※無断転載を一切禁じます
◆◇◆Special Column◆◇◆
「スポーツと生きる日々」
4.ドイツで、スポーツとともに生きる
|
お知らせ
増島みどり著
シドニーへ
彼女たちの
42.195km
発売中
詳細はこちら

|
ミュンヘンで宿泊していたホテルの向かいにピザ屋があり、ちょっと覗いてみると、いかにもイタリア人という感じの親子がピザを焼き、惣菜を大皿に盛っていました。今ドイツは白アスパラガスの旬がやって来たところで、どこのレストランに入っても、アスパラだけのスペシャルメニューが、スープやオランダソース(マヨネーズに近いもの)がけといったメニューになって「おすすめ」で書かれています。
私は、どこに行っても日本食レストランには入ったことがなく、何でもそこの土地の食べ物ですばらしくおいしいと思うのですが、毎日同じような調理方法で食べていたものですからちょっと別のもの、と思って、この店に入ることにしました。
テニスのアンドレ・アガシに似た店員さんは、私が注文したマルガリータをテイクアウト用の箱に丁寧に詰めてくれます。見ると、箱にはイタリアの地図と主な都市の名前が書かれているのです。
洒落た箱を指して「どこの出身?」と聞くと、彼は箱の上からボールペンで「バリ」のところをなぞりました。中田英寿選手がペルージャに在籍してからというもの、私たちはみなバリまでゲーム取材で行っているわけですね。少し懐かしく、中田選手の取材で行った話をすると、彼は大喜びで、「この前のローマ、ユーべを見たか? あのシュートはすばらしかった。みんな言ってるよ」と笑いながら勢い良く話し出しました。
そうして、「もう一人日本の選手がいただろう、えーと……」親指を頭の横でパッチン、パッチンとさせながら、彼は名前を思い出そうと必死になっていました。私が「な……」と言いかけたところで「ナナミ!」と声を上げるのです。
彼は日本人プレーヤーが好きなのだそうです。表情を変えず、淡々と試合をし、痛がって大げさなポーズもしなければ、ハメを外すような大喜びもしない。プレーに集中しているように見える姿が「ほかのセリエの選手や、僕たちイタリア人とは全然違うから」と2人を追っていた理由を教えてくれました。
私がいるのはドイツのミュンヘンで、しかもピザ屋です。以前にも、欧州でこうした経験、つまり、他国でプレーする日本選手のおかげで思わぬ会話ができることがある、と感じた話をしたことがあったと思います。
さて、終盤になってバイエルンミュンヘンが逆転Vに大手をかけ熾烈な優勝争いをしているブンデスリーガ。「TSVミュンヘン1860」は(現在11位)、ミュンヘン市内にあって、バイエルンとは言わずと知れた「ダービー」を戦う間柄であります。今回、丸一日かけて1860の取材をしました。バイエルンが、現在多額の資金からキラ星のようなスターを連れてきてチャンピンズリーグに王手をかけているわけですが、一方ではミュンヘンの人々の中には「バイエルン(州の名前)は馴染みのない選手ばかりで退屈だ」という、たとえるならば「読売ジャイアンツ化」への反発もあるそうです。強豪クラブにはつきものの話ですが、両クラブには明確なカラーの違いが存在しているようです。
1860は一時アマチュア、日本でいえば「地域リーグ」まで落ちた歴史があります。クラブのマネジャーの話では、その際も、1人10マルクの会員費用を支払って「永久会員」になったメンバーらは、まず、市内に持っていた土地、テニスコートを売り資金を捻出したそうです。また、会員数がそこから右上がりに増えたということです。
そんな話を聞きながら4面あるピッチ(ひとつは温熱ヒーターの入った人工芝です)を見ていると、日本人コーチの姿がありました。西村岳生さんはこのクラブで3年目を向かえるキャリアを持つ、16歳以下のチームのコーチです。中京大を卒業後、単身、ドイツのケルン体育大学でサッカー研修コースを学んで、3年前、ドイツでもう少しキャリアをと願書を公募のあったクラブに送ったところ、1860から採用されたとのことです。
印象的なシーンだったのは、彼が練習後、一人の少年とボールを挟んで長い時間話していたことでした。彼はボールをいじっているのですが、顔を上げないのです。それでも西村コーチと時々笑顔を見せながら話を続け、20分くらいしたところでコーチは彼の肩をたたいて送り出しました。監督もいるのですが、監督とはこうした交流はしないようにしているのだそうです。「うちのクラブ」と西村コーチは自然にそう言います。
「うちのクラブは、やはりプロのサッカークラブですから毎年、今頃の季節になると、上のクラスに行けない子供たちはプロは諦めざるを得ない。でもサッカーは続けていける、ということを話してやらねばなりません。これはとても辛いです」
話していた選手は、今スランプが続いていて、学校や家で何か悩みはないか、そういったことを雑談しながら話していたそうです。ドイツの子供たちは自己主張が強く、日本の子供たちのように「先生に言われればとりあえず、ハイ、というようなことが全くない」(西村コーチ)ため、やはり理論立てて、子供が間違っていても正しくても「納得」をできるように話す、これが難しいのだと笑っていました。
練習を終え、取材を終えてクラブハウスに戻ったとき、コーチ陣や練習を見に来ていた親たちが、このクラブのスポンサーでもあるビールの「レーベンブロイ」を飲み交わす輪に、西村コーチは練習着のまま挨拶に寄り、彼らと楽しそうに話していました。
その実に自然な、堂々とし、普通の人々の信頼を得ながら仕事に打ち込む姿を、私はとても「不思議な感覚」で眺めていました。
「こちらに着て、日本のサッカーの良さ、独自の方法といったものにも以前よりも遥かに目を向けるようになりましたね。日本の選手たちはすばらしいですし、事実、こちらのプロコーチたちもみなそう評価している。力を出すために外に出て欲しいですね」
西村コーチに最近、来年も契約を更新して欲しいとのオファーが1860から出されたそうです。まだサインはしていないとのことですが、心の中は決まっているようです。
夢は、「今の経験を強い土台にして、ドイツで学んだ良さやシステムを生かして、日本サッカー界で人を育てたいと思います」と言い、私たちは握手をして別れました。
|
お知らせ
増島みどり著
ゴールキーパー論
発売中
詳細はこちら

|
以前このHPに、また私の新刊『ゴールキーパー論』にも登場していただいたハンドボールのGK橋本行弘選手も、フランクフルトでプロ生活2年目のシーズンを終えようとしていました。ミュンヘンから乗り継ぎのためにフランクフルトに寄ることを電話で伝えると、彼は空港に迎えに来てくれました。
夜のフライトまで、彼のご自宅に伺い、奥様、3人のお子さんとランチをして、小さな街のアイスクリーム屋で、これもまた旬の、大盛りイチゴパフェを食べ、素敵な午後を過ごしました。ドイツは一年でもっとも美しい緑の季節で、特にバイエルンなどの南ドイツでは「新年は5月から始まる」と言われるんだそうです。家の庭には、クリスマスツリーのように「5月の木」というのを植え、「新しく、輝く季節」を祝う習慣を教えてもらいました。
彼は本田技研鈴鹿から一昨年、ブンデスリーガのクラブに移籍しました。クラブはドイツ代表GKがいるため、出場チャンスは少なく、その下部組織から現在は2部リーグでプレーをし、ちょうど、シーズン最終戦を終えたところでした。
「ドイツ語でお別れの挨拶、なんていわれてほんのちょっとだけ話しましたが、恥ずかしいですね。あっという間でした。練習の方法、チーム作り、彼らの習慣、スポーツとの関係、文化としてのスポーツ、さまざまなことをこれだけ凝縮して体験できたことは幸せでした」
実は今月末には、帰国し本田に戻るそうです。伺ったご自宅は、すでに第一陣の荷物出しが終わっていて、国際宅急便のダンボールがたてかけてありました。リビングからは緑に囲まれた庭の木々や花がすばらしく映えておて、そのぶん、スペースの大きな部屋がなんだか寂しそうでもありました。
「実感がわかなくて……」奥様は本当にこの土地を離れるのが辛いと言います。
「はじめは右も左もわからなかったんですが、近所の方によくしてもらって、私もこの地域のスポーツクラブに入ったんです。毎日、毎日送別会で、みなさんとのお別れはちょっと辛いです」
横から橋本選手が、「ぼくよりも送別会がはるかに多いんですよ」と笑いました。
奥様もハンドボールのGKでした。もちろん元選手で腕はプロ級ですから、クラブの奥様ハンドボールチームにするととんでもない「助っ人」が加入したことになります。控え目な奥様はあまり競技経歴のことは話さなかったそうですが、試合をするとやはりGKですからね、チームの勝利を左右する。お母さんのハンドを見守るお父さん、子供たちのスタンドからは「あのクラブはあんなうまい中国人を入れてずるい!」と野次も飛んでいたんだと、笑って教えてくれました。
日本人学校に通う小学生のお嬢さんと、現地の幼稚園に行くお嬢さん、そして元気一杯の3歳の男の子を見ながら、それでも地域のスポーツクラブで様々な行事やグループに加わりながら、日本ではできなかったハンドボールを再び仲間と続けたことは、彼女にとってどんな意味を持ったものか、想像できます。
35歳と、周囲には遅いと思われるかもしれないチャンスにかけた橋本選手も、まったく言葉がわからない中でプロとして戦い、2年のシーズンを終えてドイツ語で挨拶をしたのです。
慣れないうちにたくさん使ったのでしょう。広々とした部屋に張られた街の地図を見ながら、私はやはり「不思議な感覚」に包まれていました。
サッカーやMLBの日本選手たちの活躍を見るのとほとんど同じような、それは憧れや夢を実現することへの羨望でもあり、立ちはだかる様々な困難に克って、自分の成果を手にすることへの敬意であり、何よりも、彼らを通してちょっとした自慢というものを自分の心の中に抱く感覚だと思います。中田や名波のすばらしいプレーに胸打たれるのと同じように、私は、見知らぬ土地で子供たちの将来に責任を担ってプロとして生活する西村コーチや、決して目立つことはありませんでしたが、日本人としてブンデスリーガの1部リーグでプレーをし、家族ともども2年をドイツで暮らし、地域に溶け込んだ橋本選手に胸を打たれました。彼ら指導者の立場になる人間の活躍をこのドイツで実際に目にできたことは、大変な収穫でありました。
さて、フランクフルト空港に再び送り届けてもらうことになり、すずらん、ライラック、チューリップ、すべてがいっぺんに咲いている花壇をバックに奥様、子供たちとお別れをしました。私の「大リーグ養成パソコン」(しかも海外には2台持って出ますからね)を入れたバックをありがたくも橋本選手に持ってもらい、ゲートまで送ってくれました。
海外の空港ですからここはカッコよく、握手をして別れようというとき、ご自宅で預かってもらったジャケットを置き忘れてきたことに気がつきました。
それほどいい天気で、それほど楽しかったのだと告げて、そのジャケットを送ってもらわずに日本で渡してもらうことにしました。
また会うために。
イングランドではロンドン、郊外で公園の充実した施設、市民のために100面を取ったサッカーグラウンド、イングランド代表の拠点でもある五輪センター、ドイツでは、橋本選手の奥さまが加わっていたような地域の小さなクラブから、「シューレ」と言われる地域の学校体育、生涯スポーツ、身障者スポーツの拠点とするような施設、またオリンピック選手を養成するような五輪センターまで幅広く取材することができました。
このレポートでもわかるように、恵まれ、日本から見ればある意味の理想の実現とも言われている欧州のスポーツの現場さえ、大きな転換期にあることがわかります。
収穫は、日本のやり方、独自の方法にも将来があるかもしれないということです。「日本型スポーツ」における夢の実現は、一人一人のスポーツマインドにかかっているのかもしれません。その財源をトトによって確保しようとしている関係者の責任と義務はとてつもなく大きなものだということを、ここで指摘しておきたいと思います。
この原稿は飛行機の中で書いています。
晴れ渡ったドイツの上空は、芝のグランウンドや競技場も本当にたくさん見ることができます。今回、テレビ東京系の夏の番組のための取材でしたが、非常にいい勉強をさせてもらいました。みなさんに御礼を申し上げます。
みなさんも、一億円が当たった時にうろたえないためにも、ぜひ、何に使うかを真剣に、日ごろから検討しておくのはいかがですか。
車、マンション、ローンの返済……、数え切れない夢の中に、ほんのひとつだけでも、「スポーツ」のために、何かを加えてみるのも手です。
日本に戻り、そのまま出張です。また日ごろの生活に戻りますが、今回の出張で見たものはそう簡単に忘れはしないでしょう。
ではみなさん、随分と濃い連載になってしまいましたが、読んでいただいてありがとうございました。お体をどうぞ大切に。スタジアムで会いしましょう。
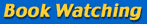
読者のみなさまへ
スポーツライブラリー建設へのご協力のお願い
|
![]()

