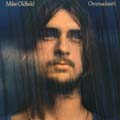
Ommadawn/Mike Oldfield
ろくでもない毎日とうんざりする日常に訣別できる日ははたして来るのだろうか。寿命が尽きる前にそんな日が来て欲しいものだが、儚い夢なのか。過去へ過去へと遡っていくような指向と収束。民族色というかウェールズ・トラッド色が比較的強いソロ三作目にして最高作との評価も高い秀作。ラストに歌曲を配したことにより長曲の構成展開の瑕疵も目立たない。前半の終り、あのなんとも驚異的なギターソロはピック使わないで右手の指を総動員している。後半は民謡大会で最後は子供の舌足らずな合唱で終わるが、まぁ、繊細な自意識のストレートな発露として完成度の高いリリカルな牧歌組曲に仕上がっている。
「馬の背(Horseback)」
ビールも好きだしチーズも好きだよ
偏西風の匂いも捨てがたい
でも、そんなもろもろのことよりも
ただ馬の背で揺られているのが好きだ
「さぁ、向うへいこう
野を越え、雪原を越えて
ビーズのような目と眉毛、眠たげな茶色の面
宇宙を飛ぶよりもお前といっしょがいいな」
雷も好きだし雨もいいな
もし頭のなかで雷鳴がとどろき
紅蓮の炎が火蓋を切るならば
馬の背にのっているのがいいな
街が好きな人もいれば、騒音が恋しい人もいる
車を造ったり、他にもいろんなおもちゃが作られてる
でももし選ぶことができるなら
馬の背に乗っていることを選びたい
「〃」
不思議なところだという人がいる
知らないところなどあるはずのない小さな惑星なのに
そんな畏怖に満ちたところで
馬の背に乗っているすばらしさ
ちびもいればのっぽもいる
壁に頭を打ちつけている奴もいる
でもそんなことはすべてにおいて本質じゃない
馬の背に乗ってればいいのに
「〃」
もしあなたがふさぎ込んでいるならば
あなたもここ(Hergest Ridge)へ来て
夏も冬も、雨の日も晴の日も
馬の背で揺られていればいいんだよ
「〃」
当然のことながら、訳は適当だからあまり信用しないように。しかしながら、こういった指向性には惹きつけるものがあって恐いなぁ。踏み切ってしまえばそれはそれで気にすることもないのだろうが、戻り道はないだろう。後は野となれ山となれ教に帰依しそう。
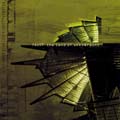
The land of Ukko & Rauni/Faust
新作のようです。2CDで2枚目はヘルシンキでのライブらしい。相変らず著しく一般性には欠けるけど、かなり最近のお気に入り。今でもこういうの買う人いるのだろうか? 今一つ不思議です。徹底的にはずし続ける逆説としての音。パピエ・コレ的な要素は薄れてきたけど、ノイズとアンビエントの饗宴はそれはそれで極めて愉しい。曲調はSFファンタジィ風ですが、この不思議な郷愁はなんだろう。三万光年の異郷でウミウシに出会ったような異質さと炭素野郎としての同類意識。いやゾウリムシの方が合ってるか。スリーブのアートワークもめちゃくちゃ格好良くて絶賛です。色といいモチーフといい、ところでウコとラウニって何よ? ウニとタラコじゃないって。(後注;古代北欧神話の神らしい)
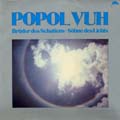
Bruder des Schattens-Sohne des Lichts/Popol Vuh
『ノスフェラトゥ』(ヘルツォークのね)のサウンドトラック。映画と同タイトルのCDもあるようですが、そのあたりの経緯は不詳です。音楽はもちろん映画の出来も秀逸にして感嘆。吸血鬼ものとしては異色で絶品でしょう。ひたすら静謐で美しくてついでに全然怖くない。冒頭からいきなり延々とアンビエントで悲痛なフレーズのロングショットが続いて、ススッと引き込まれてしまう。ストーリは他愛ないですが、イザベル・アジャーニの圧倒的なまでの美しさにはお手上げ。派手でも煌びやかでもないけれど、本質的に美しい。まるで人間のように美しい。
そして鼠。これでもかこれでもかとあたり一面の鼠。ペストに絶望した街の人が棺桶の山に埋れながら、飲んで食って踊って狂って死期を待つ蒼い光景の中を彷うアジャーニは水中を泳ぐ魚のよう。ノスフェラトゥならペストに感染しないという二律背反だったのか。
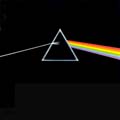
東芝音楽工業
OP-80778
The dark side of the moon/Pink Floyd
実質50分全1曲のトータル・アルバムという形ですが、最後の2曲の間のアナログ・ムーグのソロにかぶさる“lunatic”の笑い声が心底ぞっとするほど美しくて心臓が止りそうだ(った)。捉え方はいろいろあろうが、確固たるものがいつも確固としてあるわけじゃないことを知った小僧は、その後の道を少しづつ踏外していくことになるのだった。もう2年、生れたのが遅いか早いかしていれば、きっとまったく違った道が見えたのでしょう。でも、正直言って一番良い時期(素直だったのね)に巡り会えたことに、その偶然と必然に、何よりも感謝しております。前作までの胡乱な不明解さが一掃されて、良きにつけ悪しきにつけ直截でわかりやすい音になった。構成やバリエーションのコンセプトとしては『Body』の発展系、音響的にはアラン・パーソンズ等スタジオ・エンジニアの貢献が目を引くがトータルな完成度の高さゆえ、当時の音楽全般に与えた影響は計り知れない。
そぅ、月は地球に近過ぎて自転できない(公転周期【恒星月で27.32日、朔望月で29.53日】と自転周期が強い潮汐力で一致しているためそう見える)のです。だから私達が見ている月は影で姿形は変るけれど常に同じ面なわけです。太古の昔から人は月を見てきたけれど、その“dark side”を見たのはほんの30年ほど前のこと。向こう側へ行ってしまったシド・バレットへのオマージュというかラブレターというか決別の免罪符なのだろうが、結局のところ、少なくともここ25年ほど、いろいろなところで顕在化する“月の光が人を狂わせる”というフレーズの出所はこれだと思う。“lunatic”を辞書で引いてマーカーで印を付けたあの頃が懐かしい。
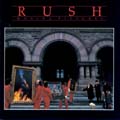
Moving pictures/Rush
トリオの割には音が厚くて緻密。かなり凝った作りだが、あまりその辺を感じさせないノリの良さと軽快で時代に合ったセンスが特徴だろう。硬くてタイトな変拍子が気持良くて、最近の仕事の友にも最適か。一般的には変拍子なんて受けないのだろうが、病みつきになるよなぁ。普通の8ビートとか聴いてるともう少し工夫できねぇかぁ? などと思うようになるのは必然。というか、リズムに対する感覚というか、パーカッションの面白みみたいなものをもっとまじめに突詰めて欲しいなと思ってしまう。有ればいいってもんじゃないでしょ。
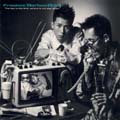
Freebee/Barbee Boys
紆余曲折と裏切りと悔恨の痕跡かもしれない。開けてはならぬパンドーラの箱ならぬ玉手箱か。今更ながら酷いことよ。今更ながら残ってしまった痕跡を辿ることは無常? それとも自虐? 許されることではないのか許すことではないのか今となってはすべては闇の奥。いまみちともたかの作る歌は素気なくて媚びない。さりげなく暖かくて、少し淋しいけれど、すんなりと近づいて来ていつも隣にあるような、いるような、手を伸ばせば届くような……。もう、「もとどおりにランデヴー」することも、「チャンス到来」することもありえないこと。あってはいけないし、記憶はそのままの形で封印されなければならないし、もちろん忘れることはないし、忘れられることもないだろう。デュエットするのが面白いと思った面もあるのだけど、意味深な歌詞と似合わないほどキャッチィなメロディが楽しいのだなぁ。とても素直に聴けるというか、変に造り込まないところも好感なポップ。
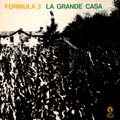
La Grande Casa/Formula 3
モノクロジャケの内側は見事なまでの見開きカラー写真で黄色の花畑を前景に館がちんまりと建っています。内容に関しては何も言うことはないでしょう。70年代前半のイタリアもの(プログ+カンタウトーレ)の中でも決して他に劣ることはない素晴らしい出来というか、代表的な逸品であり、バティスティ門下生として到達しえた境地でもあるだろう。とても暖かな土臭い雰囲気で、前作の怜悧な曲調とは少し違う歌物としての味わいも捨て難い。個人的には(やりたいことを素直にやってるような)自然な感じが好みなもので、こういったしみじみとした「歌」には弱い。研ぎ澄まされた一音一音に滲み出てくる心意気と後に残る余韻が素晴らしくも切ない。

Please/Pet Shop Boys
おや、懐かしい。この頃は外向的に積極的だったのでこういう巡り会わせもあったのかもしれない。もっとも、貪欲に外部のものを吸収できる時期には、後で考えると自分とは思えないことをしていたりして少し恥かしい。(後にリリースされる『ディスコ』は明解で良いのだが)2作目以降の受け狙い世間に迎合路線にはついていけないけれど、これはまだまだ未完成というか、それなりに瑞々しくて清々しい。エレ・ポップとしての中身自体に新味はないにしても、晴れ後小雨、遅くなって曇か晴れといったイングランドの天気のような移り気な表情の変化は愉しめるかもしれない。PVの全盛時代でMTVの常連的な露出度の多いデュオでしたが、少しヨーロッパ大陸風のエレガンスが感じられるのは気のせいか。

日本コロムビア
COCY-6801
Heaven or Las Vegas/Cocteau Twins
フルカラーの万華鏡。円熟しています。エリザベス・フレイザーの声はいつになく力強い。9月だったか。買ってきたその晩、今何故ないのか非常に不満なのだが、このところまったく見かけない“Fino”の“Tio Pepe(スペイン、ゴンザレス社のドライ・シェリィだな)”を開けて、一晩中少し涼しくなった部屋で窓を全開にして、虫の音と一緒にエンドレスで聞いていた。決めなきゃいけないことや、やらなきゃいけない事が山積みで酷く疲れていたけれど、頭はどうしようもなく冴え渡っていてバランスが狂いまくって放心していた。そんな腐れ脳髄をヒタヒタと沁みわたるように浸食していく、包むような、包まれるような仄かに匂うような音でした。中身はまぁ、そこはそれ、要は書くことがないわけで、もともと解釈を必要とするわけではないし、書くべきじゃないしってこともあるし。聴くことが唯一なのだろう。
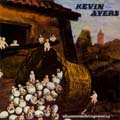
whatevershebringswesing/Kevin Ayers
1999年のデジタル・リマスター盤。この辺のものは最近1,000円ちょっとくらいで手に入るのでとても嬉しい。彼女と川で水遊びがしたいがために仕事をおっ放り出してしまうようですが、まぁ、いいんでないの。中身は外面とは裏腹に非常にシリアスでデリケート。とはいっても根が陽性だから暗くはならない。才気は迸ってますが嫌味じゃないし、実にほのぼの。詰めが甘いというか、その甘さが多分このふわっとした暖かさを醸し出しているのだろう。相変らずオールドフィールドは小僧のくせにギターもベースもめちゃくちゃ巧いし、ベドフォード(David Bedford)のアレンジもヒクヒクするくらい斬新で鮮烈だ。なんだかみんなで伸び伸びと楽しそう。
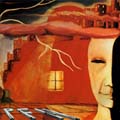
Storia di un minuto/Premiata Forneria Marconi
後に世界進出を果たしイタリアで最も成功したといわれるP.F.M.のイタリアでの1stアルバム。もちろん、74年に英語盤が出るまでは存在すら知らなかった。存在を知ったとしても、当時のイタリア盤なんぞプレミア付きでとてもじゃないが子供の小遣で買える値段じゃなかった。もっとも今はうっかりすると海外では手に入らないようなものが国内向け商品として国内で販売されているのだけど、いかんせん高過ぎるので状況が変わったわけではないと思っている。総体的なアレンジはこの原盤の方が土臭くて、少し古臭い。それを味としてみるか否かで評価は分かれるだろう。楽曲の完成度はシンフィールド(Pete Sinfield)の英詩とプロデュースが光る英語盤に負ける。モコッとした感じで録音があまり良くないのだが、イタリア語の響きがとても心温まる情景を描いてます。
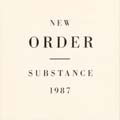
Substance/New Order
どっかで1986年と書いたかな、まちがいまちがい。2CDによる集大成というか総決算。これじゃ終わりだなと誰もが思ったはず。内容が悪いのではなくて、いや、中身はとても良い。実際当時の状況のなかでは、やることをやり尽くしたという意味で終わっていたような気がするということ。個人的に、車のお供としてコクトー・ツインズ(Cocteau Twins)と交代でよく聴いたなぁ(変な趣味だね)。「Thieves like us」とか「Perfect kiss」、「Bizarre love triangle」はもちろん「True faith」と「1963」がめちゃめちゃ好きで四六時中流していた気がします。当時全盛だったプロモビデオも斬新だった。今は亡きFactoryレーベルのやたらと簡素で途方もなく素っ気無いスリーブデザインもスカッと気持良いものでした。全編に渡って文句の付けようが無い一つの時代の証し。

Phaedra/Tangerine Dream
アナログ・シーケンサが楽器として使えるようになったのはこの頃かな? 今でも非常に斬新というか目を開かれる感がある、英ヴァージン移籍第一弾にして通算五作目出世作。ひんやりと冷たいシャーベットのような触感がスルスルと細胞の隙間に入り込んでくるようなヒタヒタ感。メロディやリズムといった規制から解放されていながら曲として聞かせてしまうみたいな力量には恐れ入る。メロディになることを徹底して拒絶するラストのメロトロンの凍るような冷たさ。身を切られるような辛さ。(見えないけれど)内ジャケの有機シアニンブルーの清冽な印象を表象するような刹那さ。ここまで冷徹に見切った即興的論理性は稀有でしょう。似たような、聴きやすくてついでにもっとメジャーなものはたくさんあるけれど、本質的に違う。
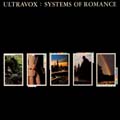
Systems of rommance/Ultravox
フォクス(John Foxx)時代の終りを告げた三作目にして逸品。パンク風の部分が薄れてエレクトロニクスになってきた。フォクスの声はあまりにも悲痛で痛々しい。
「ほんの一瞬(Just for a moment)」
暮れていく窓辺で話そう
私は自分の声が壊れていくのを聞いた
ほんの一瞬
暮れていく窓辺で話そう
私は大地が海原に変わりゆくのを
感じた
ずっとここにいよう…
永遠にここにとどまろうよ
街が寝静まったら
その静寂の中に歩み出そう
夜の兆しを耳が捉える
私は脳裏から部屋を消し去る
ほんの一瞬
木陰で座りながら
私は大地が海原に変わりゆくのを
感じた
ずっとここにいよう…
永遠にここにとどまろうよ
街が寝静まったら
その静寂の中に歩み出そう
機械が奏でる音を聞きながら
私は心臓の鼓動を止める
ほんの一瞬
機械が奏でる音を聞きながら
私は大地が海原に変わりゆくのを
感じた
ずっとここにいよう…
永遠にここにとどまろうよ
街が寝静まったら
その静寂の中に歩み出そう
シャープで研ぎ澄まされた緊張感は少し息苦しいかもしれない。冷え冷えとした雰囲気がやたらとカッコ良くて「今度のUVは凄いぞ」と触れ回っても誰も相手にはしてくれなかったけどねぇ。さすがにそれから20年以上経って、ことに音楽に関しては人に触れて回ろうなどという気はすっかりなくなった。実際、「聴いてみないとわからない」っていうのは情報収集において実にとんでもなく非効率な手段だし、結果的には現代における最高の贅沢かもしれない。折返し点はとっくの前に過ぎているわけだから、残すものもないわけだし、きちんと使いきったろか。
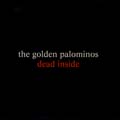
Dead inside/Golden Palominos
うぅ、なんでこんなの持っているのかわからん。秋頃、サボって新宿のHMV(だったかな)で買った記憶がある。そのまま会社で何度か聴いて、そのまま忘れて行方知らずで、会社辞めちゃったもんだからコリャダメかと思って諦めていたら、ひょっこり最近巡り巡って戻って来たという不思議な遍歴。重低音の打ち込みループを背景に、官能的でありながらもフラットな女性ボイスが散文詩の朗読をするような構成。昔はもう少し歌らしい歌が乗っていた記憶があるが、蒐気迫る非尋常さが冷え冷えと横たわる。うむむ、けっこう、おっかなくって好みです。というか、もーの凄く暗い。耳元で囁くような扇情的なボーカルとしゃきっとした暗黒リズムのアンビバレンツ(二股裂き)さがうるうると心地良い。

Larks' tongues in aspic/King Crimson
一人になったロバート・フリップ(Robert Fripp)主導の下に、かき集めた人材で再編された第二期クリムゾンの一作目。通算6作目。完成度からいえば初作に勝るとも劣らない力作かつ代表作でもある。全編が硬質な美学に貫き通された繊細で剛毅な二律背反の上に成り立つ。無名ながらも特筆すべき構成員は、スコットランド人で仏教信者であるミューア(Jamie Muir)の驚異的なまでに前衛的なパーカッション、リリカルさとシニカルさを併せ持つ作詞担当のパーマー・ジェイムズ(Richard Palmer-James)か。
続く2作『Starless and Bible black』、『Red』込みで3部作と解釈してもよい。もっとも3部作の場合、後になるほどネタ切れで質が落ちるのはこの頃からの特徴です。単純にいえば繊細を担っていた人間の切り捨て離脱とアレンジを放棄し即興に傾倒したことが『Red』の剛直を生んだだけともいえる。
“aspic”は小型の毒蛇を表す古詩語、ないしは肉料理や野菜の型として使われる、肉ないしは魚ベースのブイヨンを元にした風味の良いゼリーのことらしい。前者の意味は中辞典以上でないと記載がないせいか、雲雀舌先肉壷挿入といった卑近な意味に取るのが一般的なようだ。語源はラテン語の“aspis”。一方、ドイツ語だと“aspik”で肉ゼリーとしての意味しかないが、フランス語では同じ綴りで第一義が“蝮、毒蛇”、第二義が“肉ゼリー”、第三義に“ラベンダーの一種”と一般性が増す。“毒蛇”の拡張で“... avoir une langue d'aspic”といった成句では“毒舌をふるう”とか“意地が悪い”といった意味をなす。上品で知的な雰囲気を出すためにフランス語の単語を散りばめるというのはイギリスではよくある手法だし、ミドル以上なら必須教養だから“毒舌のなかの軽いおしゃべり”ぐらいの意味であってもおかしくはないだろう。