
Exit/Museo Rosenbach
なんとムゼオ・ローゼンバッハ、ほとんど30年ぶりの新盤です。もちろん30年の歳月はこういう世界ではあまりにも長過ぎるわけです。私が最初に聴いたのは25年前のことですが、その頃大好きだった女の子に再会した気分でしょうか。お互いにすっかり変ってしまったけれど、話しているうちにすっかり意気投合してしまうような、どんどん時間が若返っていくような、それでいて今更どうしようもない無力感と哀惜感を同時に味わっているような。困るよなぁ。いろんな意味で昔と同じものを求めてはいけないんだろうけど昔好きだったならば、同じように聴けるんじゃないでしょうか。
オリジナル・メンバーはバッテリアのジャンカルロ・ゴルツィ(Giancarlo Golzi)とバッソのアルベルト・モレーノ(Alberto Moreno)だけ。ゴルツィとマティア・バザールで組んでいたセルジオ・コッス(Sergio Cossu)がタスティエーレで加わっています。いろいろなものを通過してきた年輪の重みというか、歌ものであって歌ものでない、時代に迎合しない質と意気が心から羨ましい。

WEA/Manticore
P-8444M
The world became the world/Premiata Forneria Marconi
いろいろな意味でP.F.M.が世に名を知られるきっかけとなった英語盤。ちなみにこの英語盤のイタリア語バージョン(同じジャケデザインで緑のもの)もあります。タイトル曲の「甦る世界」はもともとイタリア盤では「9月の印象」というタイトルで、とてもしっとりした質感のある佳曲。カラカラに乾燥した夏が終わって、9月のすがすがしい大気の中で、雨に洗われてしっとりと濡れた緑が美しい、といった情景を歌っています。美しいだけで一曲できちゃうなんて短歌や俳句や五言絶句の世界だ。
ジャケットはいわゆる変形ジャケットで、中央の島の部分が繰り抜きになっていて、最初は島の平面図(取り外して山形の立体細工にする)がついている。それを外すと繰り抜き部分から内スリーブが見えるという仕掛け。内スリーブの裏はこの写真なのだが説明がなくて意味不明。
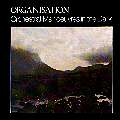
Organisation/Orchestral Manoeuvres in the Dark
「エノラ・ゲイ」は今の時代に生きている人ならばたぶんほとんど誰でも聞いたことがあるでしょう。ニュース番組のBGMにもなっていたし、ほとんどスタンダードです。もっとも、個人的にはOMDの場合はもっとスローな曲が持味だとは思う。所謂エレ・ポップの走りですがとても上品で端正。2作目だと思いましたがなかなか完成度も高い。ポップな乗りというよりもこの頃はむしろほの暗い。黄昏時にふっと忍び寄る影のような端正で曖昧で不可思議な音に包まれていると、とても幸せな気分に包まれる。この浮遊感はちょっと危ないかもしれない。
「Enola Gay」
エノラ・ゲイ、昨日は基地にいるべきだった
この感情も、おまえが嘘をついたやりかたも
とても書きとめることはできない
おまえの演じたこのゲーム
いつの日か涙をもってそのすべてを終えるだろう
だがエノラ・ゲイ、こんな方法で終わらせるべきではなかっただろう
8時15分、それがその時間だ かつてのその時からずっと
無線で受け取ったメッセージ、「異常なし、帰投する」
エノラ・ゲイ、今日おまえは“リトル・ボーイ”を誇りに思う母機
おまえのしでかしたことは、決して忘れ去れないことだ
エノラ・ゲイ、こんな方法で終わらせるべきではなかっただろう
エノラ・ゲイ、それは我々の夢を消し去ったのだろう
8時15分、それがその時間だ かつてその時からずっと
無線で受け取ったメッセージ、「異常なし、帰投する」
エノラ・ゲイ、今日おまえは“リトル・ボーイ”を誇りに思う母機
おまえのしでかしたことは、未来永劫消え去らないことだ
エノラ・ゲイ(Enora Gay)はテニアン島(サイパンの南隣)から飛び立った陸軍航空隊B-29戦略爆撃機につけられていた名称。機長の母親の名前らしい。リトル・ボーイ(Little Boy)はTNT火薬換算15キロトンのU(92/235)ガンバレル方式(前後に二分割した20%程度の濃縮金属ウラン235 各11kg程度以上を火薬で一体化させて臨界に達するタイプ)の熱核爆弾。原理は単純で工作精度も必要としないが、自重4トンとあまり小さくはない。

Reale accademia di musica/Reale Accademia di Musica
ちょっとリバーブがかかった流れるようなソロだったり、怒涛の連弾だったり、アコースティック・ピアノがとても印象的なイタリアの歌もの系RAMの唯一作。歌入りですがイコライザ掛っていたりして、カンツォーネ風のねちっこい歌い方とはまた違ったかなり線が細い感触です。経験的に類似の例を知らないオリジナリティを感じさせてくれますが、一方で、安心できる巧さというか職人風の手堅さというかプロっぽさというか、奇を衒うとこがまったくなくてサラッと淡々と演じている不思議さが見事。RAM自体はこの1枚のアルバムを残して消えてしまうのですが、春の夜の一夜の夢というか沈丁花が匂い立つような、儚くも柔らかい上質な空気感が素晴らしい。

(独盤)
KLINGKLANG
CDP 564-7 46132 2

(英盤)
EMI 0777 7
46474 2 7
Radio-Aktivität/Radio-activity/Kraftwerk
ガイガーカウンタの反応音をイントロに「放射能、キュリー夫人によって発見された……」と淡々と歌う声に衝撃を受けました。タイトルは「放射能」という意味と「電波+活動」を引っ掛けていると思われます。この時代はまだテクノの創世期。ガチガチにならない工夫は随所に見て取れますが、未だポップのかけらもありません。この理工系的世界にはなかなか親近感を感じますが、今や原子力関系はすっかり継子扱いされるようになってしまいました。所謂テクノ・ポップ的な展開は次作以降顕著になるわけで、モノクロームでマッシブで武骨で暗幕の隙間から射す光で実験流しの陶器の色だけがやたらと白く映える理科の実験室みたいだ。
ドイツ語盤の内ジャケには電波ごっこしているテクノカットの御仁が四人。う~む、この時代からこんなことしていたんですねぇ。

Substance/Joy Division
1977年から1980年にかけてのアルバム未収録集。「Blue Monday」から8年後、ニュー・オーダーの『Substance』が出た2年後、ニュー・オーダーによって編集されてリリースされました。86年の『Substance』がニュー・オーダーにとってのひとつの集大成であり終りであったように、これはニュー・オーダーのジョイ・ディビジョンに対する決別でしょう。わずか3年の軌跡ですが変貌の凄さというか、後々まで語り継がれることになる、ある時代のある音の集大成ではありましょう。
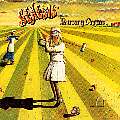
Nursery cryme/Genesis
こういう音楽はコンピュータやラジカセのちんけなスピーカ、アンプで聴くものではありません。周波数特性のフラットな再生ダイナミックレンジの広い環境が必要でしょう。音の小さな部分と大きな部分の落差が激しいからといって音に合わせてボリュームを絞ったり上げたりしては本末転倒。荒っぽいところはあるけれど全盛期ジェネシスの始りを告げる秀作です。いろいろ思い入れもありますが、1曲目「Musical box」のミノカサゴみたいな被り物で成りきって歌う役者根性と、密度の高さと余韻が繰り広げる緊張感に溢れた音には心底圧倒されるものがある。
この曲には長い前振りがある。これを読まないとさっぱり意味がわからない。趣味が良いのか悪いのか不思議な歌だ。
ヘンリー・ハミルトン-スマイス君(8歳)がブレイズ-ウィリアム家のシンシア・ジェイン嬢(9歳)とクロケットで遊んでいたときのことです。うっとりするような微笑を浮かべたシンシアちゃんはクロケットの槌を高く振り上げて、優雅な一振りでヘンリー君の頭部を叩き落としてしまいました。
その二週間後、ヘンリー君の子供部屋でシンシアちゃんは彼が宝物にしていたオルゴールを見つけ出しました。一生懸命になってその蓋をこじ開けると“オールド・キング・コール”のメロディが流れ始めました。するとなんと、小さな精霊が現れたのです。それはヘンリー君でした。しかしすぐに、彼がオルゴールから出て部屋に起ち上がるや否や、ヘンリー君は中身は子供のまま、体だけが急速に大人に成りはじめたのです。一生涯の欲望が彼の中で燃えあがりました。
でも不幸なことに、シンシア・ジェインちゃんを口説いて熱い想いを遂げようとする企ては、その不思議な音を聞きつけて部屋を覗いた彼の乳母によって未遂に終わりました。本能的に危険を感じた乳母はオルゴールをそこにいた髭のある子供に投げつけたのです。すると、両方とも粉々になってしまいました。
「The musical box」
“オールド・キング・コール”をかけておくれ
きみと一つになれるから
今や、きみのこころはぼくから遠く離れているよう
事態は困難を極めているようだ
乳母はきみに嘘を語るだろう
あの空の向うに王国があるだなんて
一方、ぼくはこの半分の世界のなかですらきみを失うのか
今や事態は困難を極めているようだ
ぼくの歌をかけておくれ
そうすれば再びここに来れる
ぼくの歌をかけておくれ
そうすれば再びここに来れる
ほんの一欠片
ほんの一欠片の時間
ぼくの人生にはそれしか残されていない
ぼくの歌をかけておくれ
そうすれば再びここに来れる
ぼくの歌をかけておくれ
そうすれば再びここに来れる
“オールド・キング・コール”は陽気なひと
陽気なひとといえば彼のことだ
だから、彼はパイプを求めたし
雁首を必要としたのだ
だから彼は三人のペテン師と呼ばれた
その時計、チクタクと時を刻む
そこのマントルピースの上で
ぼくは欲し
感じた
ぼくは理解して
その壁に触れる
彼女は淑女で、彼女には時間がある
髪をとかして、ぼくにその顔を見せておくれ
彼女は淑女で、彼女はぼくのものだ
髪をとかして、ぼくにその躰をおくれ
ぼくはここで長い間待っていた
ぼくの傍らをどんどん時間が通り過ぎた
それはもう過ぎた問題だ
でも、きみは固い表情でそこに立ちつくして
ぼくが言わずにはいられないすべてを疑っている
どうしてぼくに触れてもくれないのだい?
どうしてぼくに触れてもくれないのだい?
さぁ、いますぐに、さぁ、さぁ、さぁ
ちなみに、“オールド・キング・コール”とはナット・キング・コール(Nat King Cole)という1950年代から60年代にかけてのアメリカの黒人ジャズピアニスト、兼シンガーのことと思われる。「昔のキング・コール」という感じでしょうか。第六節の部分はひと、パイプ、雁首(葉煙草を詰るところ)という三つがすべて凹型を表して、ペテン師というのが凸型を表している? と思うのですが寓意がわからん。凝っております。

Obscured by clouds/Pink Floyd
『谷(La vallée)』というフランス映画のサウンドトラックですが、映画は西洋的な優越感が端々にみえて特に面白くもなかった記憶がある。『Meddle』と『Dark side of the moon』に挟まれて、たいして話題にすらならなかったと思いますが、つまらないわけではありません。既に終わってしまったその歴史を俯瞰してみれば頂点は『Meddle』とするか本作とするか迷うところだ。ギルモアの腕が上がるにつれ全体のバランスがとれて、ちょっと野趣に富んだ、くったりと惚れ込んでしまうような魅力が出てきた。VCS3シンセを含めた機材の使い方も実験的ではあるが意欲的。コンセプチュアルな制約がないせいか、比較的ブルーズ色も薄くて演歌にならない曲が多いところも良い。『Meddle』と共に、内容的にも音響的にもロン・ギーシンが絡んでいない最も“らしい”アルバムだろうと思う。

Saw delight/Can
エスニック風のリズムはより研ぎ澄まされてひとつの頂点に達した。決して薄っぺらな感じではなくて重量級なところも良い線を突いてくる。時代の波に翻弄されて、70年代前半の薄暮の昏さがどっかへ行ってしまったのは残念だ。もっともこのアルバムの最大の焦点は「Future days」の技術的完成とも云える15分におよぶ長曲「Animal waves」にある。カンの真骨頂はやはり無限に縦横無尽に反復されるリズムと浮遊する音による夢幻なのだから。
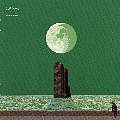
Virgin
7243 8 49380 24
Crises/Mike Oldfield
80年代ものとしては秀作の部類でしょうか。中くらいの曲がいくつかと短いのがいくつか。「Crises」で“監視者と塔”が刻々と何を“待っている”のかはわかりませんが、長曲のわりにはなかなか緊張感に溢れたテンポのいい曲だと思います。以前に比べると歌ものが増えたのが目立ちますが、不自然な感じはない。シングルヒットとしてはおそらく最初で最後と思われる、マギー・ライリィが蕩けそうな声で歌う「Moonlight Shadow」に関してはもう何も云うことはないです。生きていてよかった。
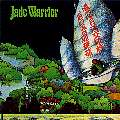
Jade Warrior/Jade Warrior
妙に東洋的なリズムが印象的なジェイド・ウォリア(翡翠の戦士)の1stです。とは言ってもしゃきっとタイトというよりは民族太鼓のノリ。総体的に洗練とは無縁なので、アプローチがかなりミニマルでプリミティブだし、今風に云えばむしろアンビエント寄りかもしれない。荒削りだけど独特の主体音と環境音が唐突に絡み合うような、形容し難い世界ができあがっています。巷では「はっけよいサウンド」と云うそうですが、云い得て妙だ。取組み前の長い立ち合いと仕切り直しを背景に相撲甚句が流れているような気がしないでもない。
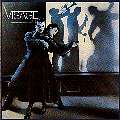
Visage/Visage
ビザージュの1st。ほとんどの曲をミッジ・ユール(Midge Ure)が書いているせいもあるけれど、音楽的には80年代ウルトラヴォクスそのもの。それなりにヒットもしたはずの「Fade to grey」は名前と裏腹にちっとも色褪せない新鮮さを保っています。冷ややかな質感とフランス語の鼻母音が透明に美しく響きます。視覚的な面においても、ビデオ(LD)版では実際肌の色が色褪せて“grey”になっていく様がとても美しく描写されていて目が眩むようだ。一応、ビザージュの顔であるストレインジ(Steve Strange)は本来もう少し奔放な気もするのだが、全体的に内省的でクールなおとなしい感じでまとめられています。
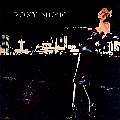
For your pleasure/Roxy music
このジャケット、黒ずくめの美人(注;後に男であることが発覚)が黒豹を連れて散歩しているところ。よーく見るとね。薄ぼんやりした輪郭に眼と口だけが光っていてそうとわかる。いろんな意味でイーノの(楽器は弾けないけれど)音に対するセンスが光る極度に人工的な二作目。細部にまで配慮が行き届いた繊細なまでの感覚と、それを感じさせないダンディさのバランスが面白い。前作でちょっと浮いてとっぱずれた感じだったフェリィのボーカルも実に音の中にうまく埋め込まれて嵌っている。全体のスケール感もひとまわり大きくなった。B面の組曲風の3曲など最早ポップやロックの領域を完全に凌駕しています。

Six/Soft Machine
庇を貸すと母屋を乗っ取られるのかどうかは知りませんが、前作『Fifth』で加わったジョン・マーシャルに加えカール・ジェンキンズがエルトン・ディーン(Elton Dean)の代りに加わり、フリー・ジャズからちょっとダイナミックなミニマル・フュージョン風に変化しています。ジェンキンズが主導権を握るのは次作以降ですが、その片鱗はすでに現れています。キーボードによる延々と反復されるリフの上を管楽器が駆巡る独特の浮遊感と緊張感。しかしまぁ、ここまで受けないのは、音楽の持つエモーショナルなダイナミズムみたいな部分を極力排除した極度に理知的な音に聞こえてしまうからなのだろうか? ソフト・マシンが大好きですという人には会ったことがない。
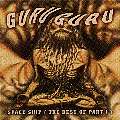
Space ship (The best of part 1)/Guru Guru
グルグルと云えばすっかりゲテモノというか極物扱いされていたけれど、プレイボタンを押して出てくる音は至極まともである。マニ・ノイマイヤー導師が異常な顔して太鼓叩いてるイメージが先行していたのでしょうか。確かにお近づきにはなりたくないか。これはアメリカで編集されたベスト盤ですが1枚目は71~74年頃のもの。混沌とした宇宙といんちき宗教のちゃんこ鍋という感じでしょうか。あぁ、“Guru”とは“グル”なのか。気がつかなかったわい。「教師」だか「教祖」だか知らんが漢字が違うような気がするぞ。
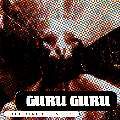
Purple pyramid (Best of Guru Guru part 2)/Guru Guru
同上と一緒に紙ケースに括られていた第ニ集は75~81年のベスト盤。リズムが多様化して少ししゃっきり、タイトになってきました。御詠歌みたいなけったいさと途方もないリズムと轟音、ボイス・チェンジャーを掛けまくったグルのご神託でいっぱい。もっとも今聴くとそんなに異様じゃないのは耳が腐れたせいだろか。比較的重めに暗めに攻めて来ますが、実は本質的にはお茶目なので笑えるフレーズも結構あるんですね。どのみち一般性には著しく欠けるんで一人でほくそ笑みながら聴くのが最高。ひゃっひゃぁ。