
To our childrens childrens children/The Moody Blues
当時も地味だったけどそれなりに知られていたのが、本当にいつの間にか忘れ去られてしまいました。実は今でも! やっているみたいですが、多分聴かない方が良いのでしょう。本国ではアルバムを出せばNo.1というビッグネームでしたが、日本ではそうでもなかったのはこの独特の「甘さ」故かもしれません。当時斬新とは思えなかった(わけでもないんだけど)ものは、逆相的に今でもあまり古臭く感じないので最近愛聴しております。まぁ、時間は関係ないというか、時間を超えて訴えてくるレベルに仕上った秀作には違いがない。
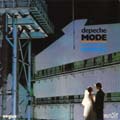
Some great reward/Depeche Mode
最近のものはちょっとご無沙汰しているので一概には言えないけれど、これが一番好みか。曲もすばらしいし、何といっても「Blasphemous rumours」のドツボな暗さには打ちのめされました。これは宗教的な理由により本国で放送禁止歌になったそう。
「Blasphemous Rumours(冒涜的な噂)」
彼女は16
前途は洋々
でも手首を切った
ただ退屈して
それが失敗に終わったことは
主に感謝
そのちっぽけな慈悲に
涙をこらえて
母親は再びノートを繰る
胸に16本のキャンドルを灯し
自分を責めている
いつものように
娘の枕元にひざまずき
そして祈る
私は望みません
どんな冒涜的な噂も
でも私が思うには
神様のユーモアのセンスは少し悪趣味
私が死ぬときも
笑っているような気がするわ
少女は18になり
あらゆるものを恋し
神と共に歩む道をみつけた
でも車に撥ねられて
結局…
機械に繋がれて生きることになる
そんな夏の日
少女が帰らぬ人となった時
ただ鳥がさえずっていた
晴渡った空の下で
通り雨がやってきて
また鳥の鳴声が戻ってくると
一筋の涙が
母親の頬をつたった
私は望みません
どんな冒涜的な噂も
でも私が思うには
神様のユーモアのセンスは少し悪趣味
私が死ぬときも
笑っているような気がするわ
楽器でない金物叩いて音出す(すまん、何ていうんだっけ? 忘れたわ)のもこの辺で終りなのかもしれない。端的に丁度このあたりがエレ・ポップ路線の頂点に違いないと思う。そういえば実際この頃まではアイドル風の外面でちょっと一歩引いてしまうところもあった。今となっては信じられないけれど。

June 1,1974/Kevin Ayers-John Cale-Eno-Nico
なんともむさい組合せで御通夜かと思いましたが、おやおやビックリ、結構ノリノリのライブです。ていうかなぁ、ちょっと組合せが無謀ですねぇ。ニコが死にそうな声で「The end」歌ってますが、おかげでエヤーズのお馬鹿な陽気さが浮きあがってます。イーノも奇矯な陽気さが特徴ですが不思議とニコに合っていて恐ろしい。一応の脱落カンタベリィ系とニューヨーク・アンダーグラウンドの同窓会みたいな雰囲気で蒐気迫る陽気さと陰気さで一杯です。
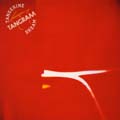
Tangram/Tangerine Dream
76年の『Stratosfear』以降陳腐化の道を辿り、結果的に今のところこれが私にとっての最後のタンジェリン・ドリームになっています。とても綺麗で聴き易いけれど昔の意気込みはどこへ行ったんだろう? BGMとこき下ろすまで酷くはないけれど、一般的な市場としてのシンセサイザー・ミュージックなるジャンルが確立されたのもこのあたりでしょうか。他のBGMは意識して聴いた事がないんで知りませんが、これ以降すっかり一般化していくのはご存知の通り。ちなみにタンジェリン・ドリームというかエドガー・フローゼ、今でもやってるんですが怖いもの見たさに聴いてみようかな。
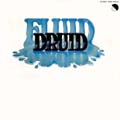
Fluid druid/Druid
グレートブリテン島のキリスト教化以前のケルト土俗宗教の僧というか魔術師をドゥルイドというらしいが、中身はこれと云って暗いイメージとは無縁。とてもクリアな明るさと時代のわりにはタイトで乾いた重いリズムが印象的な音作り。これは二作目で多分最後のアルバムになったような気がする。良く考えてなかなか丁寧に作り込まれていて好感がもてます。男なんだけどやたらと可愛いくて、ちょっとウェットで、高めの前に出てくるボーカルがとっても綺麗で良いのではないでしょうか。

(the rest of)New Order/New Order
残り物と題されたニュー・オーダーの残滓。リミックス。2CDで2枚目は『Blue Monday-95』と題されて「Blue Monday」の変形バージョンだけがたくさん入ってます。これの1年前に『(The best of)NewOrder』というコンピ盤が出ていて、一応それと対になっているようだ。まぁ、好きだから何でも良きに計らえば良し。さすがにこれで終止符を打ったのかと思いきや、今年になって新作が出るという話がある。えぇ! 8月にまじで出るらしい。せっかく終わったと思って気持の整理をつけたのに気まぐれだな。出たらやっぱり買うんだろうな。(後注:買いました)

Rock puzzle/Atoll
好き嫌いで評価が激しく割れるアトールですが、私ゃこれが一番好き。一応四作目なんでしょうがオリジナル・アトールとしては最後で最高ですね。タイトな現代性とパワフルな叙情性が同居して溢れんばかりのセンスで力ずくでまとめましたという感じが痺れるなぁ。中身はちっともプログレッシッブじゃないのに形式だけがプログみたいなものを称賛する感覚が嫌いなので、良い意味で期待を裏切りつづけ、常に変遷を重ねるアトールのシニカルな捻じ曲がり根性が実に好みなのだった。音の方も本当にこけおどしでなく巧さが滲み出るようになってきた。
ちなみにこれは当時購入したLPで、最近のCDに入っているらしいボーナスはもちろんない。どういう構成でのテイクかしらないが、解散後のウェットン・ボーカル? なんて紛い物以外の何ものでもないだろう。

Vienna/Ultravox
フロントマンがフォクス(John Foxx)からユール(Midge Ure)に入れ替って、時代の流れに乗って一世を風靡したエレクトロニック・ポップの秀作というのが世間的な評価でしょうか。ちょっと構え過ぎ(気取りすぎ)かという気もしますがおおむね的を得た評価でしょう。コニー・プランクによるエンジニアリングも非常に効果的で、最先端の技術とセンスが生きている。「New Europians」とか「Vienna」とか結構ヒットしてました。「Vienna」はクリスマス・ソングだし「NE」なんかCMソングになってTVから流れていたものだ。フォクス時代に比してなんだか隔世の感を感じた憶えがあります。フォクスのクール過ぎるセンスに対してUreの民族性はちょっと親しみやすい。
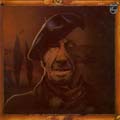
Emile Jacotey/Ange
何でこんなフランスの片田舎(現フランス領ストラスブール)にこんなものが転がっているのだ。日本でいうならエトロフとか魚釣島とか竹島みたいなところじゃないか。個人的には間違いなくオリジナル・アンジュの頂点だと思う。フルパワー全開で走る馬車馬のような武骨さには、ほとんどリリシズムすら感じられる。センスも洗練も技巧も何もありゃしない。「Sur la trace des fées」みたいな曲が作れるなら(聞けるなら)もう思い残す事などはないはずです。
ジャケットのベレー帽はWW2時のフランス陸軍装でしょう。この老人、エミール・ジャコティ(デカンの親戚らしい)の語る昔話が曲間の挿話になっているトータル・アルバム。アルバム四作目。

Mummer/XTC
「Wonderland」がすばらしい。主人公はもちろんアリス。プロモ・ビデオも見たけれど刈り込まれた方形の櫟(いちい)の迷路。作庭者が趣向を凝らし、庭師がその美意識で刈り込んだ巨大な自然の迷路。英国式庭園といえば櫟の迷路というほど有名ですが、私の場合マーサ・グライムズの「跳ね鹿亭のひそかな誘惑」(本だからね)に惚れ込んでるせいもあって、どっちが先かは憶えてないが鮮烈な印象が残っているのです。泡坂妻夫の「乱れからくり」(これも本だからね)にも凄い迷宮があったっけ。迷路の中心は逢ってはいけない人と人とが出会う場所。この世ではない夢幻なのか。

Forse le lucciole non si amano più/Locanda delle Fate
ひたすらリリカルに叙情で押し捲るが、時代は既に動いていたのだ。イタリアのロカンダ・デッレ・ファーテ、70年代末期の1stアルバム。楽団名は「妖精の宿」、あるいは「仙女の安ホテル」の意。非常に質は高いが売れなかったでしょう。タイトなリズムと土臭い声にいろんな楽器が万華鏡のように絡み合い、これでもかこれでもかとドラマチックに盛上げてきます。全編を駆巡るグランドピアノの音が華麗で美しい。かなり難しいフレーズを苦もなく流れるように弾きまくる。ダブル・キーボードにダブル・ギターに専任ボーカル、計7人の大所帯ですがそれなりの音の厚みが迫力を持って襲いかかり、あるいは繊細に忍び寄る。
『たぶん蛍はもう愛し合わない』というタイトルは何を表象してるんでしょうか。1999年の復活新作は歌ものですが負けず劣らず良い出来です。
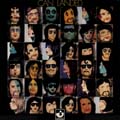
Landed/Can
前作『Babaluma』の黄昏にこもった半陰陽木魚はすっかり失せて自前で歌も歌ってたりします。生音がまったくないというか、極度に加工された音の複雑怪奇でありながら冷徹な構成は、さながら音響製造工場のラインからぱっくり生まれた機能美と性能に優れた工業製品のようだ。英ヴァージンへ移籍した世界進出盤でもあるが評判は極めて悪かったと記憶している。リズムとメロディの先鋭さ加減が、過去を期待した人にとっても、同時代性を求めた人にとってもズレたということだろう。音が縦横無尽に疾走してるものなぁ。おちゃらけた諧謔と既成を愚弄しているような感覚が楽しい。A面ラストの「Vernal equinox(春分)」における独楽鼠のようなループとリズムに翻弄されて、ラスト13分の「Unfinished(未完成)」は後の「Animal wave」に繋がるアンビエント怪作。

Black moon/Emerson,Lake&Palmer
昔から今一つ洗練からは程遠かったですが相変らず。『脳味噌サラダ』以降の意図不明な諸作は聴いていませんが、これも90年代風のリズムを導入して若ぶってはいるものの身体がついていかないって感じですねぇ。個人的には弄りまわしたこてこてのキーボードよりも、さらっと弾けるエマーソンの生ピアノが好みなもんで、あんまり重くてズンズンしてるのは格好悪いなとしか思えない。個人個人はとても上手いのに3人揃うと文殊の知恵ならぬ、何だか逆にイモっぽくなってしまうのはなぜなのだろう。

Sabotage/Black Sabbath
前作を更に発展させて技巧に走った6作目。確かにちょっとやり過ぎですが決して悪くはない。そういう時代でもあったわけだし。アレンジに凝固まってのびのびした自然さは薄れたけれど、それを補ってあり余る魅力はあるだろう。基本的な路線は若干色気づいてはいるけど本質的なところは変っていないし、情勢に合わせて変えられるほど器用でもない。構築的で凝った曲調は個人的には大歓迎です。しかし、このジャケットはあまりにもセンス悪過ぎで困ったもんだなぁ。知らなければとてもじゃないが怖くて買えない。
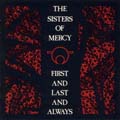
First and last and always/The Sisters of Mercy
意味深なタイトルはそのまま楽団として1stアルバムでありながらラスト・アルバムになってしまったことを示しているのだろうか。1stアルバムを出す前が長かったせいもあるし、既に評価は出来上がっていたのだろうが、エルドリッチ(Andrew Eldrich)とハッセイ(Wayne Hussey)は陽子と反陽子のように出会った瞬間に光となって崩壊してしまった。暗黒の宇宙に生じた一瞬の光彩みたいなものか。夜の王国でのたうつ冷たくて美しいメロディ。すべての言葉は不要でしょう。悶絶してください。

Phantasmagoria/Curved Air
秀才バイオリン弾きのダリル・ウェイと渋々で何でも屋のフランシス・モンクマン、やたらと色っぽいというか艶っぽい声のソーニャ・クリスティナが目立っていた最高作との評価も高いカーブド・エア三作目。結局、B級の枠からは出れなかった気もするが、それなりに個性的で愛着の残る音作りをしてました。今一つしゃきっとしないのは、ウェイのバイオリンがポップ系には全然向いていないからでしょう。ビバルディを弾かせればサスガって感じなのだがなぁ。ファンタジックな曲調とふんわりした柔らかさと霞みのようにおぼろげな輪郭が美しくも儚い。前作以前にみられた実験的な部分は極力消化した優美で女性的な手触りで、次作のライブ以降はロック色が強まる。