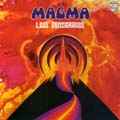
1001°centigrades/Magma
後のザオ組を抱えるジャズ色の強い二作目。マグマの諸作のなかでは、総帥ヴァンデール以外の意志と意図が見えてしまう異色作でもある。それは、言うなればセファー、カーン、ラズリーらによる洗練されたシャープで透明感溢れるジャズ・ロックであり、浮遊するエレピのソロに導かれるリリカルな叙情であったりするわけだ。もちろん、その一方で、リズムは変化に富んで、喇叭も元気だし、強迫的にぐいぐい押してくるド迫力のパーカッションも健在で、リフを刻むピアノの尋常でないところが実に格好良くもマグマであることに何ら異論はない。
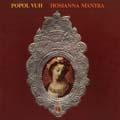
Pilz
20 29143-1
Hosianna Mantra/Popol Vuh
路線変更した一般的には初期の名作と言われている三作目。現代の賛美歌というよりは神秘主義的ハイブリット。正統から観れば異端に違いない。朝鮮系の女性のでしゃばらない少し掠れたソプラノの至高というか至福の余韻と相まって、宗教的な高みにまで昇りつめた安寧と美学。所謂リズム・セクションは存在しないが、音の繋がりが不思議に緻密で飽きさせません。きらきらと輝くようなギターのファイト(Conny Veit)以外は電気を使っていないせいもあるかもしれないが、数百年ほど遡った中世趣味も感じられる。もっともマントラは独鈷を握り、振り回しながら真言坊主が唱えるものです。

Carrington/Michael Nyman
けっこう最近の映画のサウンド・トラックですが聞いたこともない映画だ。キャリントン(Dora Carrington;1893-1932)という実在の女性画家の半生というか頭の痛くなるような人間関係を描いたものらしいですが、なかなか良さそうな映画です。と探してみたがDVDはないようだ。例によってナイマンの音楽はたおやかです。どこがどうだとは言えないんですがこの人の音楽はすぐわかる。ごく普通の編成の楽団(いつものマイケル・ナイマン・バンド)だし、奇を衒うこともないのだが、独特の展開なのか変調の仕方なのか理論はわからんが、非常に“耳につく”のです。
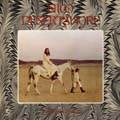
Desert shore/Nico
少し前に一斉に再発CDがリリースされました。そんな歳じゃないはずだが、もう10年以上前に亡くなってます。生きているときから生ける屍のような人だったからそれを知ったときには妙な感慨がありました。この人の場合は歌うというよりは詠唱。抑揚があるのかないのか。ベルベッツ時代の庇護者、ケイル(John Cale)の全面的なバックアップのもとに作られていますが、なかなか絶望的な荒涼さをうまく表現していると思います。一曲、息子(4,5才? アラン・ドロンの子でもある)が歌っている(「小さな騎士」)小品がありますが余計暗くなるなぁ。
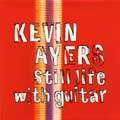
Still life with guitar/Kevin Ayers
スペインのマジョルカ島に居ついて20年くらい経つんでしょうか、思い切り脱力してます。アイディアも枯れて来たから、もうそんなに曲も作れないとのたまったそうですが、正直な人でもあるよう。個人全集みたいなCDが出ていたので、死んだかと思いましたが、そういう訳ではないみたい。マジョルカかイビサあたりで安いシェリーでも飲みながら、日がな一日ごろごろしてる雰囲気が濃厚です。才気迸るといった切れ味はすっかり影を顰めてしまいましたが、気の抜けたサイダーみたいなものだとしても、どうにも愛着があるのです。
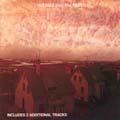
Hatfield and the North/Hatfield and the North
いろんな要素を特有のウィットでくるんで非常に高い次元でまとめあげたカンタベリィ系の一つの完成型。ちょっと文句のつけどころがない。曲の完成度は2枚目の方が更に高いけれど、流れるような全体の構成と、それぞれの曲の密度の高さはまさに絶品と言って良いでしょう。全編を通してちょっと涼しい曇り日みたいな穏やかな冷ややかさが底の方に沈殿していています。音の成り立ちの良さというか気品というものを再認識させられる一枚ですが、そのせいか? ちっとも売れなかったようです。日本では結構、根強い隠れ人気があるみたいで本国よりも売れるらしい。日本の聞いたこともない演歌やTVドラマが東アジア以外のエジプトとかトルコで大人気になったり絶賛されるのと似てるけど、不思議なものだ。
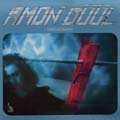
Vive la trance/Amon Düül II
一応、オリジナル・デュールIIの六作目。タイトルは「Vive la France」のもじりか。フランス人が演説の最後に必ず叫ぶ「フランス万歳」なるフレーズです。音の方は前作の延長線上でいっそうポップ、アクの強さも薄まった。ほの暗いどろどろした部分がコミカルで道化っぽい、というかおちゃらけたお馬鹿っぽい雰囲気に置き換わった。個人的には当時最初に手に入れたアモン・デュール・ツヴァイトということで感慨深いし、こういう(一見ポップな)方向性も悪くないと思います。
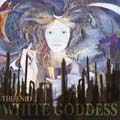
White Goddess/The Enid
再編第二作。ゴドフリィ(Robert John Godfrey)以外のメンバーはオリジナルと違いますが、音はそのままと言っていいでしょう。もともと非クラシック系の人がオーケストラを使う時にそのスコアを書いたり、アレンジするのが仕事だったようですが、人のためじゃなくて自分でやり始めたのがEnidってとこですか。当然技術的には申し分のないプロフェッショナルなわけで、とても完成度の高い音です。今風に展開も凝っていて、結構びっくりするほど変化に富んでいて長いけど飽きずに楽しめます。

Country life/Roxy Music
好きだねぇと言われりゃ、その通り。自分でもどこがどのように良いのかと問われてもわからないんだが、ロクシーは同時代の同系ポップのなかでも抜きん出ていたというか異形だった。前後作の評価が非常に高くて埋没してる? 四作目ですが、イングランドの田舎とこういうお姉さんの関係性は不詳である。田舎の明るい日差しの下でお姉さんと遊んだというならとても良く理解できる。とてもゆったりとした余裕すら感じられる音ですが、『田舎暮らし』というタイトルにはかなり語弊が合ってやっぱり都会的な極度に先鋭的なセンスだよなぁ。リズムの扱いが少し変わってきたところがあって、一段とキレが良くなってきた。左のモデルはカンのジャキ・リーベツァイトの妹らしい。右のお姉さんは透けて見えてはいけないものが見えて当時は大きな話題になっていた。
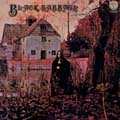
Black sabbath/Black Sabbath
降りしきる雨と雷のなか教会の鐘が時を告げるというイントロで始まるデビュー作。雨の音がやたらとベチャベチャした感じで生々と暑苦しい。非常に渋い構成でシンプルだけど勘どころはきちんと押さえられていて、完成度はかなり高い。ライブでは黒魔術っぽい演出等してたそうですが、音だけでも十分それなりのレベルにあると思います。所々に先を感じさせる要素がちりばめられていて、元々ただのブルーズ楽団ではない。ギターのアイオミの影で目立たないけどベースが重くてなかなか新鮮だ。

As far as dreams can go/Dave Stewart & Barbara Gaskin
オーバーグラウンドでヒットしたおそらく唯一のカンタベリィ系でしょうか。これはヒットしちゃったシングルを中心にした編集盤ですが、昔のヒット曲のカバー物が数曲にオリジナル数曲という構成でゆったり聴けます。なかなかカチっとまとまったポップな作りで、やれば何でも、あるいはどうとでもできちゃう余裕まで感じられる。やりたいことをやると凄いものができるのだけれどちっとも売れなくて、売れるように作ればそれなりに売れちゃうというのは、結局どこの世界でも同じなのだろうけど、そういうものか。生まれて母親に褒められたことが二度あるそうで、最初はどこかのパブリック・スクールに特待生で入学したとき、二度目がこのガスキンと組んだ曲で全英No.1ヒットを取ったときだそうだ。どこかでステュワートがとても嬉しそうに語っていた話がとても印象に残っている。

Flowmotion/Can
『Landed』の方が先だったかな。前作から英ヴァージン(Virgin)に移籍して一応国際進出という形になるんでしょうか。結果的に賛否は大きく割れることになったような気がした。ちょっとエスニックなリズムなども導入されて、それなりに明るい作りになったかもしれない。もともとエンジニアとしてのチュカイ(Holger Czukay)の存在のおかげで、現代でもまったく遜色のない先鋭的な音作りですが、一時のほの暗い浮遊感は影を顰めてしまいました。
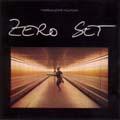
Zero set/Moebius-Plank-Neumeier
そっち(つまりテクノ系?)方面ではかなり有名なかつ名盤らしい。知らなかった。クラスター(Cluster)のメビウス(Dieter Möbius)と泣く子も黙る偉大なプロデューサ+エンジニア、プランク(Conny Plank)とあぁ、やっぱりぐるぐる教祖のノイマイヤー(Mani Neumeier)の単発ユニットのようです。同じテクノでも冷っこ綺麗系ではなくてモノリシック(Monorithic)というか“ぐるぐる”ですね。音の塊がずがーんとあってぐるぐるドラムがぐるぐるなわけさ。人間の感情とか感覚とかを良い意味で超越しているだろうから、無機物になったようで気持ちいい。
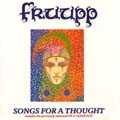
Song for a thought/Fruupp
70年代中頃のベストものに92年の未収録曲を加えた編集盤。ぶつ切りにされるとちょっと興醒めな部分は否めない。昔はアイリッシュだと思っていましたが、どうも北アイルランドのアイリッシュみたいですね。どちらかといえば古典的でトラッドやクラシックの要素を巧く取り込んで料理した音という感じ。ジェネシスなんかに比べるとずっと湿っぽくて暖かくて優しい感触。都会的な先鋭さの正反対、いや正に牧歌的というべきかな。

Screamadelica/Primal Scream
アシッドってどういうのと云われてもこういうの? なんでしょうか。最近のジャンル分けにはお歳柄全然ついていけないんですが、まぁ気にしない気にしない。詳しい事は何も知らないのだけれど、最近のものも良いけれど初期のものも良いですね。黒人風コーラス入るのはちょっとパスって雰囲気ですが、数曲だから許そう。今みたいに蹴散らすというよりは、所々かったるそうだったり、かわいかったりもして聴き返してみるとなかなか新鮮ですね。うう、世間的には90年代を代表する名盤だそうですが、なにも知らなくてごめんなさいね。
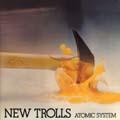
N.T.Atomic system/New Trolls
分厚くて力強い音。前へ前へとたたみかけるような肯定的な明るさと優しさ。ニュー・トロルスは時期によっていろいろと方向性に変化が多くて掴み難い感触が強いが、この分裂後のアルバムはとても安定感ある力強い歌謡曲。個人的には『UT』あたりの透明で冴えたセンスがいちばん好みですが、この手の「歌もの」に近いものも円熟味が出ていて良いと思うのです。歌が上手いとどうしても歌に寄り掛りがちだけど、音の方も実に堅実というかしっかりしていて安心できます。