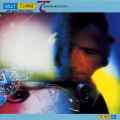
No Speak 005
Transportation/Billy Currie
買った当時はやたらに散漫で、印象薄くて、つまんねぇな、とそれ以来たいして聴いた記憶もなかったのだが、何故か今聴くと全部憶えがある曲な上にとてもツボに嵌る音作りだ。ヒットしてラジオで掛っていたとか、何かのBGMで使われてたのでしょうか? (反語のつもり)。ウルトラヴォクスのキーボードの人だから音楽的にはその延長線上で、それなりにクールで美麗なセンス溢れる曲作りです。ほとんどの曲でハウ(イエスのSteve Howe)がギターを弾いているのもオツと感じるべきでしょうか。冷たい抜けの良さが病み付きになるほど気持ち良い。NO SPEAKレーベルという歌無しレコードをリリースしていたところから出ている(いた)のですが、確かにそういうものが流行っていた時代も瞬間的にあったかもしれない。ビリー・カリー氏は、最近とうとう(無謀にも、という意味を込めている)第3期ウルトラヴォクスを再編しちゃったみたいですねぇ。
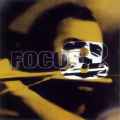
Focus III/Focus
オランダでまとめて再発されたようで、このところ入手性が宜しいようでありがたいことです。三作目ですが、昔のLPから録音したカセットテープしか手元に見当たらず、ずっと探していたものです。もっとも、漸く手に入ったと思ったらLP2枚組を強引に1CDにしたようで最後の1曲が欠けています。他のに混じってるんかいな? 1000円ちょっとだからLP持っているものも全部買ってしまってもよいのだが。比較的クラシック趣味が薄くジャズ色の濃い逸品ですが、私にとってはリアルタイムで初めて聴いたフォーカスでもあるわけで、なかなか感慨深いものがあります。「シルビア(Sylvia)」や「Focus III」などギター少年達にとっての名曲揃いでもあるしなぁ。
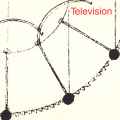
Television/Television
なんともやる気の感じられないタイトルだが、これは80年代初頭に二作残して解散後、事情は知らないが何故か突然再結成されてリリースされたもの。中身はすべてオリジナルで新作だが、長続きすることはなく、これをもってテレヴィジョンは終焉した。曲の出来は以前よりも骨太なダイナミズムが強調されて、その分先鋭感や繊細さは失われた。ベルレーヌを詩吟した肺病文学青年も世間の荒波に揉まれたということか。
首領であるヴァーレイン(Tom Verlaine)のソロもいくつか出ているはずですが、すっかり見かけない。再発待ちなんでしょうか。昔、どうにも余裕がなくて手が廻らなかったので、まとめて面倒見たるから早く再発してください。世間的にブレイクするような内容ではないだろうが、それなりに評価も定まった人たちだから市場に忘れ去られるというのも寂しいものだ。
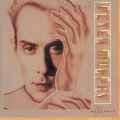
Love hysteria/Peter Murphy
ポスト・パンクの落し子、元バウハウスの歌手のソロ2作目。バウハウス時代からずるずると引き摺っていた神経症的暗鬱趣味も控え目でずいぶん明るく健康的になった。ちょっとインテリゲンチャして気取っていたイギリスものは、吹っ切れて地が覗くとブルーズやロックの下地が露わになって幻滅することが多いのだが、この人の場合はそういった過去のしがらみをきちんと処理しきれているところが好感である。エレクトロニクスと打ち込みへの傾倒は時代の要請だろう。ちょっとエスニックな雰囲気なども漂わせていますが、全然媚びない。

Columbia
CK 32858
Secret treaties/Blue Öyster Cult
懐かしくて探したら思わず売っていて買ってしまったではないか。「Me262」のスタジオテイクが聴きたくて、テープを探していたのだが見つからなくて面倒だから買った。メッサーシュミットMe262は世界最初の実戦配備されてそれなりの戦果を挙げたジェット機です。機首の4門の30mm機関砲は一連射で鬼畜米英の重爆撃機を叩き落としたそうですが、曲の中でもそんな風に歌ってます。空中では敵なしだったでしょうが、いかんせん物量には勝てなかったということですか。
「Me262」
フライブルクからゲーリングの電話
「ヴィリィ、おあつらえ向きの仕事だ」
ベルリンからはヒトラー総統までが
「君をスターにしよう」という
フォン・オンディーネ機長、次の哨戒任務だ
イギリスの爆撃機の編隊が運河を越えた
昼過ぎにはここまでやって来る
出番だ
奴らは大空にぶら下がったカモだ
たわわに実った果実のように
爆撃機はしこたま爆弾を抱え込み、爆撃準備も万全だ
イギリス野郎が生き残れば、我等が死す
彼等が生き残ることは自らの死を意味するのだ
上昇時の高加速の重力で
ときおり意識を失い、方向感覚を喪失する
失敗に褒賞はない。死あるのみ
バックミラーに自らを見出し、機体の横滑りに耐える
レーダーに機影を確認、失敗などありえない
大口径の銀色の砲弾は獲物を渇望している
敗北などあり得ない、いつなんどきも
25機の熟れきった爆撃機を前に
奴らは大空にぶら下がったカモだ
たわわに実った果実のように
爆撃機はしこたま爆弾を抱え込み、爆撃準備も万全だ
イギリス野郎が生き残れば、我等が死す
彼等が生き残ることは自らの死を意味するのだ
Me-262、ターボジェットの貴公子、吼えるユンカース・ユモ004ジェットエンジン
機首のR4Mの四重奏が炸裂する
一撃でイギリス機が炸裂する
今や空を赤々と染め上げていくのを目の当たりにし
空飛ぶ要塞はそれを最後に逃げ帰っていく
1945年4月、ヴェストファリアは闇に沈んだ
奴らは大空にぶら下がったカモだ
たわわに実った果実のように
爆撃機はしこたま爆弾を抱え込み、爆撃準備も万全だ
イギリス野郎が生き残れば、我等が死す
彼等が生き残ることは自らの死を意味するのだ
イギリス野郎が生き残れば、我等が死す
ユンカース・ユモ004ジェットエンジンが吼える
12時の方向上空、敵機
訳注;ゲーリングは空軍大臣。ヴィリィはヴィルヘルムの略称だろうがドイツ人がそういうかは不詳。R4Mは実際には翼下の発射装置に吊られた計24発の空対空ロケット弾を指す。機首の4連装30mm機関砲はMk-108。ヴェストファリアはドイツ西部の州名。
元々、サンディ・パールマンという業界人によるプロデュースが楽団の生い立ちでもあって、ラブクラフトあたりの影響下にあるオカルト風で文学的な歌詞などもパールマンのコンセプトに基づくものらしい。個人的にはBÖCといえば本作であり、なかでもラストの「Astronomy(天文学)」は秀逸にして名曲の誉れ高く、愛着を禁じえないのだが、どうも歌詞の意味がわからん。で、冥府からの使者なのでしょうか? このいかにも微妙にマーキングを消した“絵”が如何にもアメリカというか、某民族マネーが牛耳る音楽業界で逆鱗に触れず許される限界なのだろう。

Faust/Minstrel
いやはや、ファウストの『Minstrel』だと思ったら逆だって。新しいし、イタリア盤のようだし、おかしいなとは思っていたのだが最近注意力極度に散漫。まぁ、災い転じて福を為すというか結果的にはひさびさの“当たり”です。ゲーテの「Faust」のオペラのよう(雰囲気ね、イタリア語わからんし)です。ミラノ出のようであまりイタリア臭くなくてサラっとした感触。最後のFaustとMargheritaの掛け合いがぐぐっと良さげですが、意味わからんから辞書買ってこようかな。
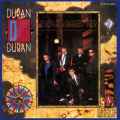
Seven and the ragged tiger/Duran Duran
文句なしの最高作でしょう。この後分裂して今でもやってるみたいですが最近のものは全く知りません。今でも現役なのに最高作などと言っては失礼でしょうが、やはり人には“盛り”というものがあるのではないかと。前作の『Rio』も素晴らしかったけれど、それに変幻自在な華麗さを加えて出てくる音がキラキラと煌めいていた。当時としてはかなり衝撃的で会社でがんがん聴きながら、へろへろ踊って仕事していたら「ウルセーぞ! ぼけ」とか怒られた記憶があります。もったりしていたリズムがファンクし始める世相の中で、先鋭的であった故。実際、綺羅綺羅うるさいけど。

Minstrel in the Gallery/Jethro Tull
笛吹き爺さんイアン・アンダーソン(Ian Anderson)のワンマン楽団です。現代のどさ回りの旅役者というか吟遊詩人というか実にプロフェッショナルな方々。日本で言えば自作自演の演歌の大御所って感じでしょうか。なんだか、やたらに長きに渡って膨大な量のレコードがリリースされているし、敢えて年代順に並べて神妙な顔で聴いたこともないですが、基本的にやっていることもあまり変わらないところも驚異的です。非常に灰汁が強い強烈なオリジナリティが滴り爛熟して発散されておりまする。慣れてしまえば快感かも。

Psalm 69/Ministry
インダストリアル・メタルというのか? ジャンルわからん。フェイツ・ウォーニング等とまとめて手に入れた憶えがあるか。結構重めにぐんぐん迫って来るのだが個人的にはリズムがもう少し複雑な方が良いと思う。まぁ、この手の非技巧的な単調さはアメリカものだから仕方ないか(マシな方?)。ほの暗くてセンスいいんだけど新しい割には録音が良くないというか、音が引っ込んじゃうというか、音の粒立ちが悪くてとても損してる気がします。それともこういうもんなのだろうか、スラッシュ系はたいして聴いたことないんでわからんよ。
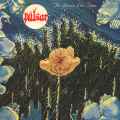
The strands of the future/Pulsar
アンジュやモナリザの演劇系とは正反対の、夢見てうるうる系ピュルサーの二作目。カルプ・ディアンのアプローチがジャズなのに対し、こちらは音響系というべきか、アンビエントを思わせる音空間の醸成に意欲的である。ゆるゆる淡々と曲が続いていくので、弛れそうになるのを類い稀な情緒性が救っているように思う。前半はタイトル曲でもある長曲で、前作の曲間英詩朗読を受けたようなSF風叙事詩。構成力は遥かな進歩を遂げており、抒情的だがあまりウェットな感触はない。音に全部イコライザが掛っているような柔らかな半透明感と、淡く青みがかった水のイメージが美しくも儚い。後半は小品でSEや不協和音が巧みに挿入されて斬新な切り口を垣間見せてくれる。かなり技巧的だがテクを感じさせない、あくまで包み込む世界観で勝負という基本線も良いと思う。個人的には短い曲のほうが華やかで良いかな。

The Dream Academy/The Dream Academy
ネオ・アコブームに乗って登場したちょっと中流趣味というかスノッブなトリオ。ポップで明るい都会的な洗練と、見映えを考えた戦略がそれなりに受けていた記憶がある。プロデュースがデビッド・ギルモア(David Gilmour)というせいもあるのか、デビュー作とは思えない音の良さです。比較的生っぽい音使いが得意みたいですが、なかなか初々しいというかさわやかというか、お上品な雰囲気はあるかも。おねえさんも育ちの良さげな美人だし。
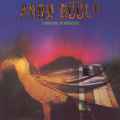
Carnival in Babylon/Amon Düül II
シングルLPになって古代メソポタミア風中近東趣味に傾倒した4作目。前作までのカオスは薄れ、レナーテ・クナウプ・クレーテンシュバンツ嬢のゲザングも結構前に出てきます。短い曲が増えて端的にいえばポップな味わいが増したのですが、音楽としての完成度はかなり上がってきた。一つの曲に5曲分くらいのアイディアが凝縮されていて、ローテク故かどうかは知らないが、がんがん展開されていくみたいなとこは圧巻です。勿体無い気もするが、そこは素人集団、全然気にしてません。こういうエネルギーはいいなぁ。

It'll end in tears/This Mortal Coil
インディ・レーベル、4ADの社長アイヴォ-ウォッツ・ラッセル(Ivo-Watts Russell)によるプロジェクト第一作。この後、同じようなかたちで3作目まで作られています。カバー物とオリジナルを適当に混ぜて、制作者としてのアイヴォの趣味で固められていますが、ここまで耽美的な叙情性みたいなのもちょっと珍しい。ちなみにスリーブはこのシリーズのビデオ版である『Lonely is an eyesore』に含まれる「Acid, bitter and sad」の一部でしょう。月明かりの湖中? で浮遊する美女(生きてるのか?)ですね。芸術至上主義的な趣味の良さと美しいものをとことん愛でていたいという独占欲に貫かれた逸品です。
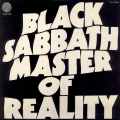
Master of reality/Black Sabbath
北イングランドの元祖ヘビメタ(といわれると非常に違和感があるのだが)、ブラック・サバスの三作目。HMというジャンルが存在しなかった当時、そのサバトだか黒ミサ風のステージが話題になって、かなり風変わりでアンダーグラウンドなハードロックと捉えられていたと思う。ゼペリンが華やかで陽ならば、正に内にこもって陰々滅々、その淫蕩なまでの邪神崇拝に心惹かれたものだ。
この3作目は4、5作につながる大きな路線転換が行われ、当時は一般的に不評でした。アルバム全体の構成を考えた曲作りや展開が見出せるのもこの頃で、「Embryo」や「Solitude」といった一服の清涼材の使い方は以後の典範となるもの。ひときわスケールアップした非常にバランスの良いうねりとリフが気持ち良い。
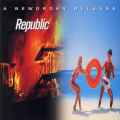
Republic/New Order
前作から4年ぶり、最終作です(後注;その後再編新作が出ている)。すっかり円熟して大人の音を出しています。お世辞にも上手いとは言えなかったサムナーのボーカルも嘘のように余裕しゃくしゃくです。もっとも明るい曲調とは裏腹に底の方にはうろうろと訣別感だけが流れているような感触が拭えません。Joy Divisionを含めて個人的にとても思い入れが深かったので、複雑な心境です。変にずるずる引き摺るよりはスパッと切れてよいけれど。
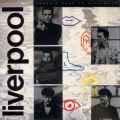
Liverpool/Frankie Goes To Hollywood
ZTTレーベルの寵児、FGtHの2ndアルバムにして最終作。それほど突っ込んで聴いたわけではないのですが、日陰に咲いた隠花植物のようで実はかなり好みです。当時の売られ方は今思えば全然しっくりこないもので、オルタナだかゲイだか知らないが、結果的に敬遠させられていたようなところがあって今思えば残念です。非常に洗練された重厚さみたいなものが心地良いのですが、ZTTとはあまり合わなかったかも。やたら人工的な音の中にふわっと漂うかなり頼りない情感が絶妙な世界観を作っています。