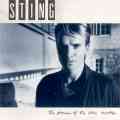
The dream of the blue turtles/Sting
「Russians」一曲のために買った記憶がある。前にも後にもこの先も接点はそこだけですが、元パンク・ロッカー(ポリスだったかな? 違ったらすまぬ。後注:パンクからポストパンク・レゲエ・ニューウェイブへの移行だったらしいわ)にして熱帯雨林保護活動家が金満日本の、それもこともあろうに拝金リゾート施設のTVCMに出演なさっておったのには時の流れと価値の変動をまざまざと見せ付けてくれた憶えがあります。そういえばそのCMのスポンサーでもある愚の骨頂として一ツ葉浜海岸の十万本の松を伐採して屹立していた三セクは会社更生法を申請しました(今は外資なのかな)が、間抜けにも逃げ遅れた人は夢見た分の辛酸を舐めたのでしょう、かね? 税金だから関係ないか。
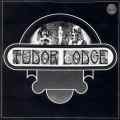
Si Wan Records
SRMC 0028
Tudor Lodge/Tudor Lodge
それなりに著名なイングランドのフォーク。全編を覆う伝統的で比較的上品な感触は18世紀室内楽の庶民版を思わせるが、可憐で瑞々しい声を披露するアン・スチュアート(Ann Steuart)はアメリカ人。そのあたりの特質かどうか、イングランド・トラッドの重苦しさは感じられず、爽やかで洗練された曲調が気持ち良く響く。軽やかで流麗な曲調は正に琴線に触れる極上の出来栄えを誇る。タイトルにもなっているテューダー朝(1485-1603)はヨーク対ランカスター、すなわち薔薇戦争終結の結果即位したランカスターのヘンリー7世以降の治世を指す。シェイクスピアの「リチャード三世」あたりが有名だが、実際の史実は大きく異なって後書きの改竄された歴史を堪能できる。
80年代に復活した後のことは不詳。デモ音源に加え99年には新作がリリースされているようですがこちらは未聴。
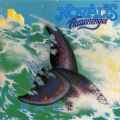
Flossenengel/Novalis
80年代後半、バブルを象徴するような下らないTVドラマ(金妻)にテーマの部分が使われていて、爆笑した記憶が残ってます。不倫が発覚したりすると高らかにテーマが鳴っちゃったりするのだ。その選曲のセンスはそれなりに凄いとは思うが、おかげでヒットしたとかいう記憶もないので、TV放送会社お得意のせこい剽窃だったのでしょう。音の方は昔のほにゃっとへなちょこな部分が影を潜めリズムもタイトで力強くなった。らしいような、らしくないようなちょっと複雑な気持ちです。SE?で挿入される鯨の鳴き声が懐かしい。邦題は確か『凍てついた天使』だったと思いますが(“l”と“r”を取り違えて)間違ってない?

Something wicked this way comes/Enid
このタイトルはなんだかブラッドベリみたいだな。比較的短めの曲でわかりやすくてなかなか力強いリズムとメロディが特徴の歌入りの小品集。リリース当時の受けは最悪だったと記憶している。重厚長大を期待した向きを裏切ったわけだ。もちろんイーニドとしてのオリジナリティは完璧に健在です。時代がどう流れようとも、なにも変わらない。数年前(1997頃)に再結成されて新作Dがリリースされていますが、そこでも同じだから正に堂に入った真性といえるでしょう。極めて少数みたいですがフリークもいるみたいだし。

Should the world fail to fall apart/Peter Murphy
バウハウス(BAUHAUS)が行き詰まってソロになった一作目。居場所がなくなったというのが正解か。そういえばこの頃か。もにょもにょしたゾウリムシとかミドリムシの模様が流行ってた時期もありましたね。ほの暗い空気感と見通しの効かない曖昧模糊とした霧中のような不安感が交錯してます。影を引きずった音の粒を紡ぎ出すような絶望感はほんとに救いがない。
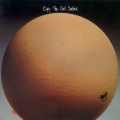
The civil surface/Egg
エッグは70年初頭に2作のアルバムを出して、一度ぽしゃっているのでこれは再結成ものにして本当の最終作。相変わらず感情移入は断固として拒絶的な音と曲で攻めまくっていますが、慣れると快感になるんで怖いですね。しかし、まぁ、よくもこう難しいことをやるもんだ。やけくそというか反骨か? ここまでできればそりゃ楽しいだろう。もっとも、ちょっと明るくなったような気もするし、聖歌隊のノーセッツも参加してるし、ゲストも多い。バーバラ・ガスキンはビール飲んでるけど残りのお二人のノーセッツの方、なんか普段着の奥さんって感じで楽しそう。
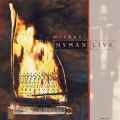
Live/Michael Nyman
現音ミニマルの人、マイケル・ナイマンのスペインでのライブ。この人のライブは典型的なクラシックという趣ではないのでおもしろい。ビオラの隣で電気ベースギターを弾いていたり、クラリネットを顔が真っ赤になって熱演したり等の見た目以外にも、けっこう乗れる曲、リリカルな曲と演出構成も楽しい。客は間違いなく体が動いてます。もっとも日本では現音といえども完璧にクラシック扱いなので真似をすると思いっきり顰蹙を買うので注意しましょう。葡萄酒酒場とか麦酒処でやってくれないかなぁ。

Rough Trade
ALCB-241
Greatest hits/Throbbing Gristles
なんか痛々しいのです。幸か不幸か知らないが、その血まみれのパフォーマンスは未見です。「痛みを通した悦楽」という線がこたえられない向きにはたまらんでしょうが、個人的には苦手ですな。今更不得意科目の克服という歳でもないんでわかりたくもないですが、最近怖いもの見たさにときどき聴いてます。いやはや。結構かわいっぽい音もあるんだけどな。
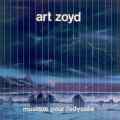
Atem 7002
Musique pour l'Odyssée/Art Zoyd
ユニヴェール・ゼロの兄弟か親戚か、暗澹とドツボを張り合うアール・ゾワの初期二作目。フランドル地方の現音室内楽で、弦楽器と金管楽器がぐいぐいと神経症的に迫り、不安を煽るような弦楽器の音が延々とワンコードで繰り返されて、電気ベースの重低音がぐんぐん、呪術のような掛け声の揃い踏み。ただし、演奏にはかなり向上の余地がある。
編成は以下。この時点の主要人物、コンポーザはヴィオラのジェラール・ウルブットのようだ。
Frank Cardon : Violon(ヴァイオリン)
Gérard Hourbette : Alto(ヴィオラ)
Thierry Zaboitzeff : Violoncelle, basse, vocal(チェロ、ベース、声)
Jean-Pierre Soarez : Trompette si B.(B面のトランペット)
Michel Thomas : Saxes(サックス)
Michel Berckmans : Hautbois, basoon(オーボエ、バスーン)
Daniel Denis : Percussions(打楽器)
ダニエル・ドゥニの名前が見えるが、ドラムセットは不使用。 タイトル曲「オデュセイアのための音楽」はLP A面すべてを使った組曲。呪術的な木管金管のリフと通奏低音のヴィオラ、躍動する電気ベースが暗く神経症的な地平を描写して、静と動の明確な抑揚が切迫した緊張感を強調する。オデュセイアはホメロスの叙事詩。
「Bruit, silense - bruit, repos(静の音、空の音)」は無調だが軽やかなメロディが奏でられるも、弦楽器の変拍子上をベースと金管が駆け抜けるループを構成し、急転直下ユニゾン連発。ラストは再び無調で冷たい弦楽器がテーマを奏でる協奏曲。
「Trio 《Lettre d'automne》(三重奏:秋の手紙)」は蜩(ヒグラシ)が鳴いているような弦楽三重奏。メシアンを思わせるクールな不協和音と焦燥を煽る悲痛なメロディが聴きどころ。アナログ盤ですが音質はクラシックほどではないがこの時代のものとしては良い方でしょう。正規メンバーとしてベルクモンとドゥニの名前がある通り、ユニヴェール・ゼロへの献辞付き。
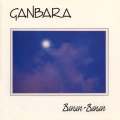
Banan-banan/Ganbara
バスク・フォーク、ガンバラの2ndアルバム。結構今風の音使いですが、しっとりとした特有のノスタルジィがふつふつと沸き上がる切ないまでのリリカルさが特徴です。歌詞は孤立言語であるバスク語。中央アジア、グルジア語に類似しているそうですが、非常に独特な文法と語彙を持っているようです。もちろん、おかげで内容はさっぱりわからんわけですが、とても穏やかな、あるいは牧歌的というか、時間の流れ方が違うんでしょう。枯れ具合が実に見事。背伸びしないで自分達の特質をわきまえているみたいなところも好感です。
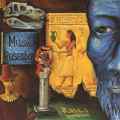
Rare items/Museo Rosenbach
濃厚なイタリア色とリリカルな泣きのダイナミズムで一世を風靡したムゼオ・ローゼンバッハの未発表・デモ・ライブ曲集。基本的に入れ込まないようにしているのでブートは買わないのですが、こりゃどうみても音質的にはブート以下。元々、(70年代には)オリジナル・アルバムはたったの一枚しか出てない上に、その一枚は持っているわけだし。ならばそれ以外はすべてブートである! という理屈がするっと滑り落ちた瞬間があったらしい。中身は正規盤「ツァラトストゥラ」の別バージョンと若干のライブ音源。メロウの発掘盤ですが、音は非常に悪く残念至極。
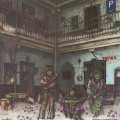
El Patio/Triana
哀愁のエスパーニャはアンダルシア(現スペイン南部地方。元はムスリムがイベリア半島をアンダルスと呼んでいたところから)、セビージャ(セビリア)の出、トリアナの1stアルバム。タイトルは『中庭』の意。泣きのメロディのロック・フラメンコ。カスタネットがカタカタ鳴ってます。リズム、曲の展開がどうにもこうにもフラメンコになっちゃうという、正に業というか血が薫る。演歌で言う小節みたいなものでしょうか。くせだらけですが好きな人にはたまらないでしょう。ちなみに演歌の節回はアラビア系の間では非常に高雅だそうで、あちらの一流ホテルのロビーやクラブではよく演歌がかかってるそうです。
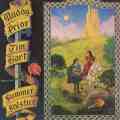
Summer solstice/Maddy Prior & Tim Hart
題名通り『夏至』だからそれほど暗くないイングランドのフォークです。デュオの片割れ、マディ・プライア(Maddy Prior)は電化フォーク、スティールアイ・スパン(Steeleye Span)を率いるフォーク界の重鎮ですが、日本でいえば民謡界のトップシンガーといったところでしょう(そんなのいるんかいな)。最近100円ショップの「日本の民謡」シリーズを集めていますが、「いいよっ!」って人に薦めても何故か白い目で見られてとても悲しく思っております。音楽は風土や伝統と切っても切れないと思うがの。

Yeti/Amon Düül II
2作目にしてLP2枚組み。1枚目は比較的タイトに音楽っぽくまとまったドロドロサイケ。リフを刻むカーレルさん(Chris Karrer)のシャキシャキ・ギターが気持ちよい。2枚目はカオスな即興演奏が延々と繰り広げられて脳味噌がぐるぐるです。ちなみに『Yeti』はヒマラヤの雪男ですが、なんか「おぞましいもの」みたいな感じで捉えられているのかな。シュールで美しいジャケットにも惹かれるものがある。

Real world/Peter Gabriel
ロンドンのミレニアム・ドームのこけら落しのショウだそうです。音の方はともかくとしてショウはサーカスと演劇を足して5で割ったようなものらしい。一応、音楽監督と作曲をしているのでしょう。中身は所謂イベントもので、歳のせいかこの手のものにに惑わされることもすっかりなくなりました。ドームの方はその後ちっとも客が入らなくて早々に取り壊しになったそうで。さぁすがアングロ・サクソン、手も速いが逃げ足も速い。

Melos/Cervello
この年はなにか異常だな。コンピュータ化以前としては逸材がゴロゴロしてた年です。オザンナの弟分です。オザンナほどの暗い陰惨さは感じられないですが喩えようのない無常感に満ちあふれている。マカロニおじさんに無常がわかるのか、かなり疑問ではありますが。重密度高充填の破滅寸前の真美。言葉では説明しがたい。チェルベロ唯一のレコードですが、ここまで作ってしまうと次は作れないよなぁ。
オザンナのダニーロ・ルスティチの弟、コラード・ルスティチがでろでろとよく泣くギターを弾いていますが、当時15歳だそうです。だから「おじさん」ではなくて「子供」ですね。児童福祉法違反じゃないのかな?