
Exterminator/Primal Scream
スランプ5、6cmの超固練りコンクリートの塊が雨あられと降り注ぐ、ようだ。非常に高密度で鋭角で嵐の通り過ぎた後には荒野しか残らないというか、荒んでいます。思わずガックリした余所行き風のめかし込んでいたスタイルも、すっかり元に戻って良かった良かった。なんだか人間の本能の妙なところを突くような、CADでお絵書きとかしているとマウスぶち切ってキーボード乱打しまくりませんか? あんまり流行ってなさそうで良かった。
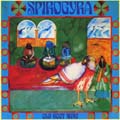
Old boot wine/Spirogyra
いやぁ、感激です。ちょっと前に弟のところからかっぱらってきたやつですが、期待していなかったので。年代物だから録音はあまり良くないですが、比較的シンプルで躍動感のあるエレクトリック・トラッドです。とても透明感のあるリリカルですばらしい曲を作っています。若き日のバーバラ・ガスキン(Barbara Gaskin)が歌っていますが、後に彼女はカンタベリィとは切っても切れない聖歌隊になったり歌姫になったりするわけだ。これは2ndアルバムですが、これ以外に正規盤前後作とデモ、未発表音源(ライブ)が出ているようです。
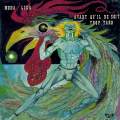
Avant qu'il ne soit trop tard/Mona Lisa
モナ・リザ絶頂期の4作目。テアトラルで類い稀な表現力を持ったボーカルと変幻自在なリズムが疾走しています。カチッと決まった全体構成がとても美しく、正にフランス庭園のような様式美が確立されたといって良いでしょう。足すことも引くこともできず、冗長な部分はまったくないですが、デリケートで角の丸い女性的なしなやかさみたいなところはけっこう感じられる。

Static and silence/The Sundays
巨大な月の写真を目にするや否や、速攻で購入してしまう私でした。前作からしばらく間隔が空きましたが、昔のようなちょっとエキセントリックな部分は影を潜めてすっかり大人の音になっていた三作目。この幸せそうな安定感はなんだ? ハリエット・ウィラーはどちらかというと細めのあの声で淡々と歌っています。タイトルにもなっている「Monochrome」の7月の午前4時の月、その水の底のような儚くも美しい情景にはゾクゾクきます。
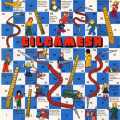
Gilgamesh/Gilgamesh
ハットフィールズの弟分ギルガメッシュの1stアルバム。後に足して1.5で割ってヘルス(National Health)に昇格する。ちなみに母親はキャラヴァン(Caravan)で長男はエッグ(Egg)で離婚したオヤジはソフト・マシン(Soft Machine)といったところでしょうか。親戚も多いなぁ、数え切れないあたりが狭い範囲で人脈が錯綜するカンタベリィの風土。で、このギルガメッシュ、紛れもないカンタベリィ系の音楽ですが兄貴分と比べるとより内向的で、繊細で、ウェットな気がします。それはそのままエレピのアラン・ゴーウェン(Alan Gowen)の特質なのだろうが、ジャズ色の強い優美なトーンは唯一無二だろう。歌える人がいないのでハットフィールズから聖歌隊を借りてきているようですが、むさ苦しい通好みの一歩手前で踏み留まった親しみ易さと心に響くメロディも持ち合わせている。

Souvenir/Matia Bazar
これは日本での編集盤です。CMソングにもよく使われていたから聴けばあれかぁとわかる人も多いかも。アントネッラ・ルッジェーロという女性カンツォーネ歌手に、形骸化して時代に見捨てられていたJ.E.T.とMuseoのメンバーを加えて出来たらしい。驚異的なバカテクだから質的には文句のつけどころはなくて、あとはいかにもイタリア的(とはいってもミラノだけど)な肺活量の大きそうな歌い方が好みの別れめか。それほどアクは強くなくポップな美しいメロディが特徴で、演歌だと思えば間違いはない。
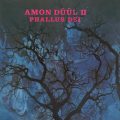
Phallus Dei/Amon Düül II
IIとしての一作目。タイトル『神の陰茎』は著名なミサ曲「Agnus Dei(神の子羊)」を愚弄しているものと思われる。昔はお神輿を担いでいるような掛け声で騒いでいる尋常でない小品が好みだったが、最近は歳のせいか長いのでも全然平気。あの妙ちきりんな独特の雰囲気はこの頃から既にあって、素人集団ではあるがオリジナリティは完璧だ。混沌としたエネルギーが制御できなくてあちこちからフツフツと湧き出てるような原初性が、今聴くと実はとても新鮮だったりもする。

Supper's ready/Another serving from the musical box
ジェネシスのカバー曲集。取上げられた原曲はすべて聴き憶えがあるが、演者でパッと見、知っているのはルネサンスのハズラム(Annie Haslam)、キャラヴァンのシンクレア(Richard Sinclair)ぐらいか。ジェネシスもとうとうスタンダードというか古典扱いされるとなると何とも感慨深いものがある。もっとも私が知っているのは78年くらいまでで80年代以降に関してはまったく不詳。当時はとても地味なイメージがあったけれど、英国滋味に溢れた良い曲を作っていました。それなりに賢く巧かったし。
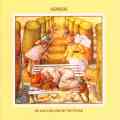
Virgin Japan
VJCP-23117
Selling England by the pound/Genesis
せっかくだから原盤も取上げてしまおう。ジェネシスのスタジオ盤5作目にして、個人的にはジェネシスの最高傑作と考える『ポンド何ぼで、お国を売っちゃるで』。ここまで完璧なまでに緻密に構成され、尚且つその特質を余すところなく表現したアルバムはないだろう。前作までのホワイトヘッドのジャケ画に代えて、これまた英国趣味に溢れたスワンウィック(Betty Swanwick)の「The Dream」が採用されたあたりも興味深い。各曲の微妙に角が取れた儚い色使いや、ふわっとフェイドアウトで終わっていく展開なども含めて、統合されたイメージの創出にこだわりが見えるし、初のヒットチャート曲であり、アルバム中で唯一、毛色が違う2曲目「I know what I like」は正にこの絵そのものであり、ポイントというか解読(笑)のキーワードは「君の姿を見るよりも、君のワードローブの中がシアワセ」と歌うグータラ芝刈り男が夢見る変態フェティッシュな歌にある。
ハンバーガーチェーンのWimpyと買い物クーポンのGreen Shield Stamps(固有名詞)を引き合いに出して、斜陽に喘ぐ当時の社会状況を皮肉った「月影の騎士」、「エピングの森の戦い」はロンドン北郊の町Eppingの東にある森で当時実際に起こった事件の新聞記事を脚色したもので、「cinema show」はエリオットの「荒地」からの引用。冒頭と同じメロディに回帰するラストはスーパーの安売り広告だったりと、中身は悪意に満ちたユーモア、皮肉と隠喩、歴史参照と現代時事であり、含められた意図を思い遣るならば、おそらく英語圏の住人ですら100%の寓意を愉しむことは難しいように思う。訳注と引用だらけになってもいいので、できれば古典に秀でた英国文学者に決定訳をお願いしたいものだ。したがって、残念ながらこの時期のジェネシス人気が今ひとつというのは実に正しい現象ではあるのだろう。
演奏技術も格段に上がり 録音の音質も前作に比べ飛躍的に改善されている。

Lonely is an eyesore/4AD
インディ・レーベル、4ADのオムニバス。ビデオ版もあってなかなかそれっぽい耽美な雰囲気でまとまっています。「Acid,bitter and sad」を見て迷わず買いました。月明かりに照らされた夜の湖の水中で聞こえてきそうな音。曲によって勿論傾向は全く違うのだけれど、こうやって並べられると確かに4ADなわけで、仕掛け人(レーベル・オーナーだな、つまり)アイヴォ(Ivo)の力量がよくわかります。
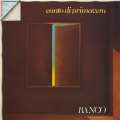
Canto di primavera/Banco
ま、春だから「春の唄」ですね。日本の春は花曇りだけど彼の地の春は雨季が終わって光の季節なんだろうか。ジャコモおじさんの巨大な腹から振り絞られた美声は脳天を貫通して朗々と響き渡るのだった。70年代初頭のカンツォーネっぽい部分は少し薄れたか。コンパクトでタイトになって、題名の通り明るい春の陽光のもと暖か味に溢れた人間臭い音です。

The mix/Kraftwerk
焼き直しというかRemixです。かつての有名どころは入ってますね。「このボタン押せば音楽奏でる」と発声してるのは知らなかったけれど。個人的には「Radioactivity」の頃のアナログ? で一所懸命やっていた、とてもモノクロームで無機質な陰気さが好みなのですが。ライブで4人直立不動でポケコンの端末叩いてた(本当は人形だった?)のはぜひ見たかった。しかしドイツ人はそんなに金属とか機械とかが好きなのだろうか?

Flowermouth/No-man
2nd。とても表情豊かで耽美的な音です。かなり冷やっこい感じでクールにさりげなく目まぐるしく展開していきます。技巧的であることは間違いないけれど、それを感じさせないセンスは見事。箱庭室内楽みたいに枠からはみ出さないわけでもなくて、新鮮なフレーズも結構あったりして、なかなか油断できません。ちょっと妖しい雰囲気もあるんだけれど。
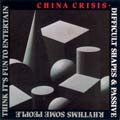
Difficult shapes & passive rhythms,some people think it's fun to entertain/China Crisis
軽妙なリズムと妙ちきりんな明るさが心地よい。ビートルズ風のハーモニーがとても憶え易くて印象的なメロディと相まって不思議な郷愁を誘います。結構手の込んだ技巧的なPOPなんだけど、どこか牧歌的で素朴な民謡みたい。これは1枚目みたいだけど(今ちょっと調べた)どういう状況で買ったのか全然憶えてないわぁ。

Ciclos/Canarios
ビバルディの「四季」のスパニッシュ・エレクトロニック版大作ですかな。グレゴリオ聖歌風とか修道院ローカルとかかなり宗教がかってるところもありますが、あまり本筋ではないかな。まぁ、時代が時代だからアナログシンセでコズミックしてますが原曲にあまりこだわってないとこがかえっていいようです。もともと原曲が好きなせいもあるけれど、長い割には時間を感じさせません。
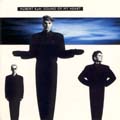
Sound of my heart/Hubert Kah
85年の前作に比べすっかり昏さが薄れてさわやかに力強くなってしまった3作目です。プロデュースと一部の曲を書いているのは後のEnigmaのCretuさんみたいですね。(たった今まで知らんかったわ)こちらは時代的にもエレクトロニック・ポップって感じですが、曲の感じとかアレンジとか最近のEnigmaあたりにびっくりするほど似てますなぁ。