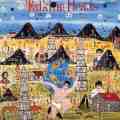
Little creatures/Talking heads
なんだかとてもかわいいトーキング・ヘッズです。シンプルで暖かくてキャピキャピしてます。思ったより伝統的な感覚が見え隠れするけれど、しれっとしたかったるそうな歌と結構ファンキーな音が妙に醒めた現実を思い起こさせる。良くも悪くもアメリカ的ということなんだろうけど、実はその辺りを逆手に取って先鋭感や斬新性を売りにしていたのだろう。国内ではとても評論家受けしていたように思うが、結果的にはインテリ臭くてなかなか無国籍に仕上っているところ等、ワイアに似ているものを感じさせる。
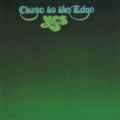
Electra/Rhino
R2 73790
Close to the edge/Yes
初めて聴いたイエス、確か。実はその頃まだほんの子供でしたが(友達の兄貴のお薦めだった)。最近のガキと違って英語が敵性言語という時代なわけで、ひたすら内ジャケのロジャー・ディーン(Roger Dean)の絵に圧倒されておりました。表も含めてこういうデザインって目にする機会がまだまだ限られていた時代だったしなぁ。当時は「And you and I」の優しげな響きに憧れてましたが、今はやっぱりタイトル曲の結構タイトな展開とボーカルのコラボレーションですかね。このリズムにこのメロディを乗せるのか! みたいな構造的にスリリングなところは正に感動モノですね。変拍子にしてもポリリズムにしても、昔はわからなかったがスクワイアのベースの独創性と鮮烈さは真似ができない。中身は売れない芥川賞作家の敬虔な哲学談義みたいですが、後半へ突入していく部分の上昇感みたいなものは、なんだかズズッと精神が高揚しちゃいます。いやぁ、凄い凄い、うっかりしてると感激しちゃいます。
2003年のライブでは「Close to the edge」はやらなかったけれど、「And you and I」は感激ものでした。ほぼレコード通りのアレンジでしたが中間部の圧倒的なまでの高揚感には参った。ありとあらゆる記憶がぼろぼろと零れ落ちてきて涙が止まらなかったな。ま、そういう歳か。
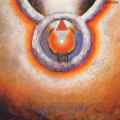
Gone to Earth/David Sylvian
「Silver moon」のプロモーションビデオがとても印象に残っていて、あぁ、これかと手を出してみた。おそらくスコットランドあたりの荒れ野で撮影されたものだろう。海、山、石、川、野、草、空と微妙に追憶を刺激する、笑い、逃げて、佇んで、臥せて、踊り、開き、まどろむ女の人の柔らかい肌色が陽光にきらめいて、雨に濡れて、風に吹かれて、躍動していたり静止していたり、目くるめく美しさ。当時も今も死ぬ前に是が非でもここに行きたいと思っている。当時はバブル真っ盛り。現実ではいろいろなことに追いまくられて、落ち着いて音楽を聴いてる余裕も無かったし、そういったわけでそれ以外のことは過去も含めてよく知らない。
「銀の月(Silver Moon)」
見渡す限りの曠野に
土砂降りの雨が降る
通り過ぎていく二人の高まりに逆らって
僕等はもういちどシーツを引き上げる
君がここに抱えている数々の疑惑は
自ら出口を探して消え去るだろう
君が望むなら、僕は二人の隠れ家を作ろう
さぁ、僕の手を取って、歩こう
立ち塞がる山々の高みを越えて
その内に深く切れ込む川に橋を架けよう
君を導く意志があれば
君の心はもう誰も必要としない
あの日々は既に過去のものだ
出口なんてそんな簡単に見つかるものじゃない
君を導くはずの夢の内側に取り込まれた君
出口なんてそんな簡単に見つかるものじゃない
もうまもなく道標の月光も消えてしまう
二人の潮の弱まりに伴って
海の波も鎮まって
同じやり方で罰せられる
天が大きく広がれば、
あらゆる岸辺を月光が照らし
サイレンの歌がすべての言葉
“誰も信じてはいけない”
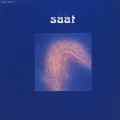
Saat/Emtidi
詳細不明。茸マークのピルツ・レーベルから出ていたという意味では伯林コズミック同志だったのだろう。びっくりしたことに意外に有名で、極東日本ではCDが出ていたらしい。中身はギターとソプラノボイスによるドラムレス電気コラボレーションって感じですか。アシュ・ラ・テンペルほどぶっ飛んだところはありませんが、モジュレータでごにょごにょとかはやっています。男女ボーカルと思いきったリリカルな曲調、メロトロンとアコースティックな味わいとのバランスが美しくも儚い。ドイツものですが歌詞は英語だし、フォークを基調にした柔らかい曲調がメインで薄明に漂う女性的な印象が特徴です。スリーブデザインも柔らかく華やかな麦の穂。
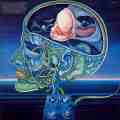
Clearlight Symphony/Clearlight Symphony
実にフランス的に冷湿に流れるようなクリアライト長編第一作。この時点では“Symphony”が付いておりますが、次作以降は単にクリアライトと称するようです。2枚目の若干コケティッシュなイメージはまだなくて、ひたすら穏やかで地味、或いは派手派手ではない流麗さというか。淡々と流れるグランドピアノの音色がエレガントで冷やっこい。
これを聴いていると、どうもコレット(Sidonie Gabrielle Colette 1873-1954)の「青い麦(Le Blé en Herbe)」を思い出してしまって、バカンスなのに曇りと雨で湿気た空気が体に纒わりついて、脳の奥の方が刺激されるような妙に疼くような感覚を思い起こさせてくれる。シリーユ・ブルドー(Cyrille Verdeaux)という元クラシック畑で、トリオ時代の初期ZNRの一人でもあった人のユニットですが、GONGのメンバーとか掻き集めてやってます。しかしVirginも昔はこういうの出してたんだよなぁ、と感慨深いものがある。
ちなみに、CDはLPと曲順が逆になっております。なぜだろう?
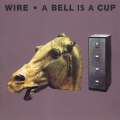
A bell is a cup...until it is struck/Wire
第2期ワイアの2枚目です。この後は“ダガダガ”にのめっていくんで何か真っ当にやった最後のCDといったら言い過ぎか。もうパンクでもポストパンクでも全然ないわけですが、熟練したいい味が出てるような気がします。辛辣な歌とはずした音は結局インテリの証し。かなりタイトなリズムとメロディアスな曲で完成度は結構良い線行っているような気がします。ずろずろっと引き摺るようなリリカルさが堪らない。

Sabbath bloody sabbath/Black Sabbath
五作目ですが個人的にはブラック・サバスの最高傑作と認識している。マイナー・コードを多用した非常に陰にこもった重い曲調と単なる流行りもののHM/HRを超えた展開の圧倒的な技巧と流れには今聴いても惚れ込んでしまう。比較的テクはあるが、ひけらかしに走らない泰然としたところも好感です。実はけっこうキーボードとシンセサイザ(Rick Wakemanだそう)の比重が高まって音に広がりが出てきた。曲中あるいは曲として間奏的に挟まれるアコースティックな音の響きも絶妙で、雲間に一瞬差し込んだ光のように煌いている。基本的な部分は前作と同じ構成ですが、更にこなれて円熟した。冒頭の「Sabbath bloody sabbath」一曲で頭が真っ白になるほどの衝撃を受けたものだ。明るくて健全だった子供心へ鈍い鉛色の世界を垣間見せてくれた。うんうん、マイナー好みはこのへんからだ。

Musea
FGBG 4055.AR
Flesh that understands/Masque
スウェーデンのマスク、CDアルバムとしてはデビュー作。北欧風の妙に伸びやかではあるが虚ろな明るさと凝った曲調、タイトで独特なメロディが特徴です。複雑なリズムをこなすテクニックはあるし、イコライザが掛かったような硬質なボーカルも独特、クリアなトーンのギターもツボを押えた仕上りで、不思議なコード進行と技巧的な曲展開が斬新だ。緩めにチューンされたスネアで叩かれる変拍子と重く曖昧に響くベースのトーンも全体を引き締めているのか弛緩させているのかどうも捉えどころがない摩訶不思議な感触だ。決して派手ではないが非常に惹きつけられる芯を持っている。歌詞、表記は全曲英語。取っ掛かりとしてはある意味とてもありがたい。
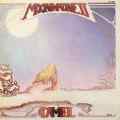
Moonmadness/Camel
月の光を浴びていると“気がふれる”というのは西洋では比較的良く聞く話みたいですが、私が思い起こすのはやはり「うさぎ」とか「だんご」とか「かぐや姫」とか「雁」とか実におやぢ好みで柔らかいものばかりですねぇ。というか日本の文化ではマイナスイメージのものを探すのは難しいでしょう。一方、西洋では二元論的な世界観とも相まって、月はあくまで陰のイメージであることが多いようです。前作の『白雁』がかなり好意的に評価(当時としては重厚長大、長編大作ならなんでも高評価だった)されていたのに比べ、ぱっとした評価のなかった四作目。しかし、内容的には身の丈にあった路線に戻り、どっちつかずの方向性も定まって、ようやくキャメル独自の音楽性が定着したといえると思います。ジャケ絵通りの儚くも美しい世界観は正に冷たく冴え渡る月夜。とても細やかで上品な隅々まで行き届いた丁寧さが印象的です。ストリングシンセが作り出す奥行きのある空気感が恐ろしく冷やっこくて気持ち良い。
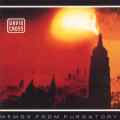
Memos from Purgatory/David Cross
70年代の第二期クリムゾンのバイオリン奏者、デビッド・クロスの初ソロアルバム。引退後はずっとバイオリンの先生をしてたそうですが、かつての栄光が忘れられなかったのか、隠居の手遊びなのかは知らないが、このCDけっこう楽しそうに弾いております。まぁ、最初期を除いてクリムゾンは実質的にロバート・フリップ(Robert Fripp)とイコールだから、クリムゾン・フォロワーを期待するのはお門違いだとは思います。リズムがつまらないとか鈍臭いなどと言っても仕方のないことでしょう。元クリムゾン系みたいな感じで追っかける趣味はないのであまり深入りはしていませんが、欧州的で黄昏た雰囲気は巧く醸し出されているようです。学究的な線の細さも相変わらず。
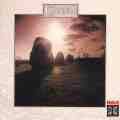
Magical ring/Clannad
アイルランドのベテラン・グループ、クラナド中期7作目くらい。60年代末期、最もケルト色が濃い西岸のサケの町ドネゴールで結成された。初期は別として、アイリッシュものの中ではそれほどトラッド色は強くない、比較的新しいことを積極的に取り込んでいる気がします。ゲール語で歌っているものもあるので、こだわりがないわけでもないようですが基本はポップです。中庸で穏やか、年季の入ったとても大人っぽい和める音が気持ち良い。女の人の声がちょっと寂しげですが確かにそんな風土です。人口が少ない上に町に寄り添うように集中して住んでいるので中間部には実に何もない。西部は特に石の荒地ばかりで風と声が実によく通る。ジャケはあちこちにごろごろしているドルメン(Dolmen)といわれる巨石墳。

Meddle/Pink floyd
まだ鼻垂れ小僧だった頃、(前述の)友達の兄ちゃんに《これもいいよ》と聞かされた。そのときはなんだかなぁと思った記憶がありますが、鼻垂れが止まった最近(25年以上前だけど)では結構良いではないかと思ったりもするし、ピンク・フロイドとしての頂点だとも思う。湿ったブルーズが基本なんですが、(多分私にも)いろんな可能性があった時代なんですよね。大作「Echoes」も良いですが、前半のアコースティックでブルーズな小品の出来が素晴らしい。こんなに上手かったっけ? 「Fearless」でSE処理されるイングランドのサッカー応援歌もおもしろい。夕暮れの箱根で「Echoes」のイントロの「ぴっ」を聴いて感涙した世代ではないですが、たまぁに明け方の白み始めた空を見ながら聴いちゃったりするとやっぱり泣けますか。
ジャケットは耳の穴と水面の波紋の合成写真。アルバムタイトルは『干渉』のほうがしっくりくるなぁ。

Seventh Records
A1/A2
Offering I-II/Christian Vander
マグマの総帥クリスティアン・ヴァンデール(Christian Vander)は“コルトレーン命”であることは有名な話ですが、いつのまにやらこんなのを出してました。コルトレーンに奉げられた“供物”です。もっとも70分を越える全9曲は静謐で壮厳、マグマとは別の緻密な世界を垣間見せてくれる。聴くのも買うのも物好きとしか言いようがないが、こちらの方がロック色が薄くて気持ち良いかもしれない。実は『IV』で終わらずに『V』まで出ています。
ステラ・ヴァンデールが歌うオペラ調のスキャットで幕が開くが、変拍子と変態コーラスに、R & Bからソウル色までを感じさせるボーカル・ワークが極めて多彩にして興味深い。アンサンブルはピアノをメインにすっきりとしたもの。マグマのように暑苦しくドカドカ迫って来るところはないですが、変わらずマグマ以外の何ものでもないところはさすが。

Seventh Records
A5/A6
Offering III-IV/Christian Vander
コルトレーン(John Coltrane 1926~1967)はアメリカの黒人サックス奏者でジャズの人。20世紀初頭、ルイジアナ州ニュー・オーリンズ(フランス植民地時代はヌーベル・オルレアン(Nouvelle Orléans))に発祥したジャズは、ミシシッピを北上して、マイルス・デイビスとコルトレーンによってモダン・ジャズとして大成されるのだが、詳しいことは他をあたりましょう。コルトレーンは晩年、フランスでも活躍したようですが、ヴァンデールとの接点はその辺なんでしょうか、全然知りません。
『III』と『IV』をどう区分するのかよくわからないのだが、44分の長曲に小曲が2曲。前作よりもコンパクトになった。ジャズ色も一層濃くなって、歌詞のあるようなないような掛け合いもジャズボーカルやソウルを髣髴とさせる空気感が見事だ。ラスト「Offering (2)」は『I』の導入と対になっているようだ。ステラ・ヴァンデールの夕闇に消えていくようなスキャットが深い余韻を残す。
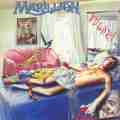
Fugazi/Marillion
ジェネシスそっくりなどと誹謗されたこともあるマリリオンですが、確かにいろいろ似ているところもある。もっともジェネシスの上流英国滋味とは本質的に差があるし、フィッシュ(Fish)はどちらかというと野蛮にしか見えない。物語するところは似てるけど演劇にはならないしなぁ。もっとも“ポンプ”というムーブメントを知らないからその位置付けでの評価は不詳です。
信じられないほど完成度が高い三部作の二作目。曲もタイトで緊張感に溢れたものばかり、というと誉め過ぎか。本国ではたいそう人気だったらしいですが、ジェネシスと同じで言葉がわからんと興趣も半減ってところですか。ライブで「Jigsaw」が始まったりするともう騒然としたらしいですが。
「Jigsaw」
僕らは枠の外周に沿って並べられたジグソーのピース
間を繋ぐ一駒があればうまく噛み合うのかも
僕らは「溜め息の橋」の下で停滞してるルネサンスの子供のようだ
永遠に、石造りの橋に松明の火を投げ続ける
僕らは心だけが繋がったシャム双生児
かつての法廷闘争という手術から血を流し続けている
震える唇に言葉というメスをくわえたまま
「まっすぐ立つんだ
その目で僕を見据えて、さよならを言うんだ
まっすぐ立つんだ
僕らは何故か真っ当でないところまできてしまった
昨日が明日始まり、明日が今日始まるような
問題はいつもそんな浮ついた状況にありながら、繋ぎの一ピースを探していることかもしれない
その繰り返し」
血の色のような日没に溺れ、深夜便で密航する
恋の逃亡者は現実からの避難所を求めている
めちゃくちゃな周波数で苦悩のシグナルを緊急発信しても
いつも犯罪者のように早朝便で強制送還
僕らは汗みどろでコースを維持しようとしてる、熱にうかされたパイロット
お定まりの最終協議と変わり映えのしない朝飯時の離婚話に向けて
休戦を叫び、雪崩地帯で雪盲目になりながらも
「〃」
僕らは幸せなまま引き金を引ける?
待合室でのロシアン・ルーレット
空っぽの部屋が結末を包み込む
混迷した見通しはトレビの月を映す泉のさざ波のように揺れ動く
夢のコインは泉に投げられるのか、それとも君の眼を覆うのか
僕らは滑稽さを通り越して発火点に達したようだ
地平線に煙が立ち上るのが見えるだろ
君は僕が逃げようとしてることを知っていたんだろう
「〃」
でも僕は繰り返し、再び君に出会うのだろうな
その時に君は残りの一駒を見せてくれるのかな
僕は繰り返し、やっぱり君に出会うのだろう
そこでも問題は相変わらずだけど。その繰り返し
う~ん、メロドラマはわからんですね。we は「私と妻」と「私と妻でない女」とどちらでもとれないことはない。3節目の「お定まり」と「変わり映えのしない」は「別のもう一人との」の方が自然だからなぁ。ricochet も口語だともっと端的な意味があるんだろうか。どちらにしてもあまり明るい内容じゃない。ちなみにトレビの泉で左の肩ごしにコインを投げいれると、二人の関係は昔に還るそうで、目をコインで覆うのは死人だそうです。

Electronic/Electronic
名前ほど特にエレクトロニックではないのですが、それはそこ、功利主義のお膝元、イングランドの特質でもあり、まぁ、そう感じさせないところが大人なのか。音としてはちょっと柔らかくて薄いけどニュー・オーダーそのもの。基本的にはニュー・オーダーのバーナード・サムナー(Bernard Sumner)とスミスのジョニィ・マー(Johnny Marr)のユニットですが、Petshopboysのような感じもするか。結構流行ってたからなぁ。メロディアスなトーンと綺麗でノリノリのサビが印象的な90年代初頭エレポップ。