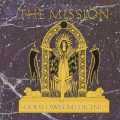
God own medicine/Mission
分裂したシスターズ オブ マーシィ(Sisters of Mercy)の片割れミッションの一応正規1stアルバム。こちらはシスターズほどは暗くはないから、あの暗さはエルドリッチ(A. Eldritch)の個性でしょう。曲は元々、ウェイン・ハッセイ(Wayne Hussey)が書いてたようなので、まったくそのものだけれど、鬱屈した陰惨さは随分と軽減されて開放的に、伸びやかになったかもしれない。いちばん印象が違うのはドラムが人間になったことだったりするのもおもしろい。しかし通奏低音のようにじわじわと滲み出てくるこの暗さは何だろう。風土か?
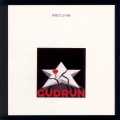
Gudrun/Pierrot Lunaire
イタリアのピエロ・ルネーレの二作目。アヴァン・ガルドで硬質、前作で若干みられたポップな要素は欠片もなくなりました。アルテュロ・スタルテリ(Arturo Stalteri)+ガイオ・チョッチョ(Gaio Chiocchio)にダービィ(Jacqueline Darby)というソプラノ・オペラ歌手を加えたトリオ編成。なんと評せばよいことやら、形容詞が思いつかない。多分形式とかジャンルとかそんなものとは全く無縁です。音の粒立ちが良いというか、とても感覚的だけれど非常に緻密、構成も展開もすばらしく非凡です。非常にシンプルで地味に感じるけれど音の無い部分までもが音楽の一部であることを認識させてくれるような余韻に満ちた世界です。中身はトータル・アルバムで、グードルーンは北欧の英雄神話の登場人物名(スカンジナビア語名)だそうだ。ちなみに女性の名前です。

Saturn ascension experiments/Union Wireless
ジャンルに関しては極めて不案内ですがヒップホップというらしい。サンプリング音源としては70年代のCANとか。既成の音源を編集というかRemixすることで思い入れを排した純粋な形を目指していたとかいないとか。というか、DJなパフォーマンスと一体のものらしいので、やっぱりおやぢはお呼びじゃないんだろうな。まぁ、個人的にコンポーズとリミックスは本質的に別物だと思うし、単なるパフォーマはそれとはまた次元が別だとしか言いようがない。創造や芸術とクリエイトやアートは相入れない別世界の事象なのだろう。
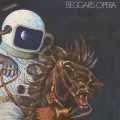
Pathfinder/Beggars Opera
ちょっとドタドタ、モタモタした感は否めないものの、グランド・ピアノの音が気持ち良く響き渡る三作目。マーティン・グリフィス(Martin Griffiths)の歌も珍しいことに歌謡曲か童謡歌手みたいな歌い方で、とても上手いし暖かみのある声だ。3枚目ということでカチッとまとまってきたポップな部分はあるけれど、いかにもヴァーティゴ(Vertigo)・レーベルみたいな鈍臭い手作り感が微笑ましい。当時のジャケは6面折り特殊変形。名前の元は「Beggar's Opera」であり、1728年にロンドンで初演され、空前の成功を収めたジョン・ゲイ作の諷刺喜劇『乞食オペラ(The Beggar's Opera)』。後にクルト・ヴァイルが『三文オペラ』としてリメイクしていたりする。
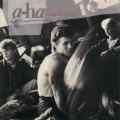
Hunting high and low/A-ha
途方もないヒットを飛ばしていたノルウェイのポップ・ロックだが、歌詞はすべて英語。MTVやビデオクリップ等視覚メディアが民生用として流行り始めたころで、露出度最大、PVを嫌というほど見せられた記憶が残っている。よくあるアイドルっぽい親近感での販促が計られており、どうにも、お人形さん臭が抜けない胡散臭さが丸出しだったが、バイキングの末裔のような骨太のあんちゃんが“いい男”で、“俺たちだってそんなことはわかってるさ”みたいな雰囲気を醸し出しているのが救いになっていたように思う。タイトルは『根こそぎ獲りつくす』の意。あんちゃんのファルセットが朗々と響く名曲であるが、個人的にはスケトウダラなんぞを底引き網で一網打尽にして、腹かっさばいてタラコ取り出して、ハァハァといった情景のほうが性に合う。
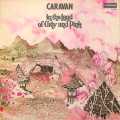
In the land of grey and pink/Caravan
キャラバンの中ではかなりポップで明るめ、アレンジで聞かせる初期三作目のアルバム。比較的アコースティックな雰囲気が前面に出ていて、トラッド・フォークと得意のウィットに富んだ上品なポップのブレンドが英国南部特有の香りを醸し出しているよう。リチャード・シンクレアのボーカルも朗々とすっきり歌いまくっている。お約束の長尺曲は後半の組曲だけですが、これも初期を代表する出来映えだ。ちょっと奇矯で不思議な明るさみたいな部分が不気味ですが、相変わらずカンタベリィ系としてはまったく申し分なく斬新でかつ巧い。一応、ソフト・マシンと共に当時のカンタベリィを代表する楽団ですが、キャラバンのほうがずっと保守的で、職人的。
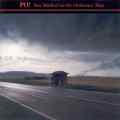
Not marked on the ordnance map/Po!
とてもシンプルでたおやかなルツ・ミラー(Ruth Miller)の声と生っぽいトラッド風POPな音です。Prefab SproutやSundaysに似た感じもするけれどもっと若くてシンプル。うむうむ、良い意味でとても田舎っぽい。こういう暖かみのある生ドラムの音って久しぶりかも。ちょっとほっとします。残念ながら他の音源があるのかないのか、至って不明。雨に打たれたうら寂しくも美しいイングランドの田園風景の彼方にたなびく煙は沸騰水型軽水炉原子力発電所の蒸気タービンの排気です。
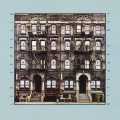
East West Japan
32P2-2739/2740
Physical Graffiti/Led Zeppelin
発売時は2枚組LPだった6作目。目指したものはこれをもって、ほぼ完成したと考えられる。表現手法の基盤はブルーズ・ロックだが、ありとあらゆる要素が分解されて再構築され、70年代ロックの到達点として提示されているといえよう。 前半は 後半はその時点までのアウトテイク集 重量級。押し潰されそうだ。ひたすら前に突進していくようなイメージで語られることも多かったですが、けっこう意識的にいろいろ実験的な音作りをしていたと思っています。曲作りにおいてもなんとなくこうなってしまったというよりも、すべて計算されつくした構成、展開、アレンジの絶妙さが光っていたと思う。「Kashmir」とか「The Rover」とか、渋いし、メロトロンが絶品です。

東芝EMI
CP35-3172
Parade/Spandau Ballet
とっても控えめな気がしていたけれどそうでもないのか。会社勤めをしてた頃、二つぐらい下の京大出の新人君に「まぁさか、スパンダ・バレヱとかデュラン2とか聴いてんじゃないでしょうね」と諭された記憶がありますが、何でかな? 結局意味はわからなかったんだけれど、いい歳こいて…ということだったのか。あまり評価も人気もないけれど歌も上手いし、曲も良いし、ノリも良いと三拍子揃って高質なニュー・ロマンティックスの一翼です。透明度の高いセンスの良さ、上品さは同類の中でもピカ一でしょう。
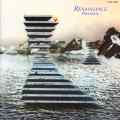
Prologue/Renaissance
最近また新作が出ているようですがこれは第二期の一枚目です。冒頭、インスト曲(スキャット入りだけど)から入るあたり意気込みを感じます。アニー・ハズラムのソプラノを得て一気に浮上したみたいなところはありますが、地味だけど良い曲を作っていると思います。「Kiev」とか。斬新さというよりは良識溢れる丁寧さというか崩れない、期待を裏切らない安心感がこの頃からあります。このクラシカル・トラッド路線は第一期のヤードバーズ組であるキース・レルフ+マカーティ(及びその弟子の第二期の主役ダンフォード)に依るもので、第一期ルネサンスと同じコンセプトです。掻き集められた演者達が一人立ちするのは三作目くらいから。
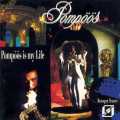
Pompöös is my life/Pompöös
おぉ、どっかにも書いたけどバロック・トランスだそうで。そういえばこの当時結構流行っていた。もちろんバロックじゃなくてトランスが。ハラルド・グレックラ(Harald Glöckler)とディータ・シュロツ(Dieter Schroth)なる中年のババリアのお二方のユニットみたいですが、音楽的にはニコライ・ドチェク(Nikolei Dotzek)なるスラブ人キーボード兼プログラマが仕切っているようです。おそらく黒人と思われる女性が情感たっぷりに歌ったりはしないところがセンス煌めいています。バロック風の室内楽的なところもかなり聞かせますが、全編を通して流れる厭世的で黄昏たメロディと妙に覚醒感に溢れたリズムが実に気持ちいい。グレックラとシュロツは服飾デザイナが本職のようで「ポンプース(Pompöös=豪奢、けばけば)」なる店でバロック風やロココ風のけばい服やアクセサリを売っているらしい。わかりやすく言えば、江戸小物とか呉服を扱う店の中年親父が目から鼻に抜けるような中国人スタジオプログラマと組んでディスコで踊れる歌舞伎を作ったようなもんだ。そんでもって「どうだい? このけばさこそ我がファッション、我がスタイル、我が人生」とおっしゃっているわけであります。美しくも儚い曲の出来もさることながら、そのたおやかなやわらかさと淫靡な輝きに正直言って感動しました。
Pompöös is my fashion, is my style

You/Tuxedomoon
安部公房の『箱男』をモチーフに据えた後期の作。英訳で朗読しています。新しいような古いようなとても不思議な演劇的な音ですが、わざと外してる様な奇怪なリズムと1930年代風の喇叭が売りなんだわなぁ。本質は現代音楽寄りのチェンバーですが、レイニンガー(Blaine L. Reininger)がいなくなって若干明るくおおらかになった。昏く胡乱なペシミズムは影を顰めてしまいました。当初はアメリカ西海岸で産声を上げたユニットですが、チェンバーの本場ベルギーに移住して現在も活動しています。
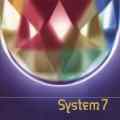
System7/System7
アンビエント・ハウスというものらしい。ヒレッジ(Steve Hillage)とかオーブ(The ORB)とかYouthとかまぁ、その辺の関係のコラボレーションというかユニットのようですね。ヒレッジと云えばゴング、ゴングといえばヒレッジというほどその最盛期に貢献した人ですが、当時を鑑みればこういう方向性もわからないではないか。で、ヒレッジ爺さん、今作だけですがとても伸び伸びと気持ちよさそうに弾いています。う~ん、格好良い。どうでもいいけど黒人風のファンクっぽい声も入ってますがあんまりエモーショナルでもソウルフルでもなくて、まぁ許容限度内か。
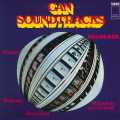
Soundtracks/CAN
その名の通り数本の映画のサウンド・トラック集です。この時代、若くてちょっと面白げな人達にサウンド・トラックを作らせるのが流行ってたようで、他にもけっこう例はあります。もっとも使い方はかなりイモっぽかったようですが。実質CANの2枚目ですが、鈴木ケンジとマルコム・ムーニィが半々、やる気なさそうに歌っています。サウンド・トラックということもあるだろうが、比較的ポップでメロディアス、短い曲が多いので聴き易い。

Crypto
ZAL 6403
Cueille le jour/Carpe Diem
ラテン語の楽団名がそのままフランス語訳になってタイトルになっている。と思ったが、これは1stが売れなかった場合によくあるパターンで、タイトルはあくまで『Carpe Diem』なのだろう。ジャケ表にのみ、そのフランス語訳が表示されていると解釈すべきようだ。成句“Cueille le jour sans te soucier du lendemain”で“明日の心配をせず、その日を充分に味わえ”の意。元ネタはポンペイの遺跡から発掘された日時計の石板に刻まれていた文字から。酒池肉林の享楽に溺れ、欲望の限りを尽くした古代ローマ人の座右の銘「今を愉しめ」。(注:←ウロオボエ)
LP-A面は小曲5曲、うち歌入り1曲。前作の疾走感というか、ちょっと元気なところはなくなって、全体的にゆるゆると流れるようなとても地味で淡々とした音使い。フランス風の演劇的なシニカルさは薄く、どちらかと言えばおっとりとした柔らかい湿っぽさみたいなものが感じられる。けっこう珍しい部類。ジャズ風の繊細で上品なアプローチもさることながら、特異なキーボードの音とソプラノ・サックスのアンサンブルがとても視覚的なイメージを喚起する。前半の小曲では珍しく歌入りの曲があったりして興趣に富んでおるが、やはり後半の「色」をテーマにした大曲が衆目を集めるところでしょう。
後半は5部、黒:最初の一歩、橙:砂漠縦断、緑:次の村…最初の雪、紫:遭遇、白:沈黙の扉の5部構成をとる組曲「色彩」。描き出されたモザイク模様の妙のように、精緻でテクニカルなアンサンブルが堪能できる。ちなみに当時のLPと今のCDでは曲順に加え曲名まで異なるという混乱ぶり。少なくともオリジナルLPにおいては以下の通り。拙訳は歌詞がどこを探してもなくて真偽の程は不明。
A-1:Naissance 誕生
A-2:Laure ロール(女の子の名)
A-3:Le miracle de la Saint-Gaston サン=ガストンの奇跡
A-4:Tramontane 北風(アルプス、又はピレネーから吹き降ろす季節風)
A-5:Divertimento (伊語)嬉遊曲
B-1:Couleurs 色彩
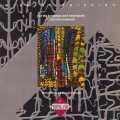
Wishful Thinking/Propaganda
『A Secret Wish』のリミックス盤。ダンスバージョンということらしい。もっともプロパガンダの場合ビートを強調すると余計陰気臭くて踊るというよりドツボって感じだけどなぁ。アンチ・ダンスバージョンということなのかな? 能書きが少なくてわかりません。もっとも初作『秘密の願い』→『希望的観測』というタイトルの変遷をみる限りにおいては、彼等のイギリスにおける挫折と絶望がこめられていることには間違いはなさそうだ。そういえば「P machinery」ってパチンコ屋とかの有線でよくかかってたけれど出るのかなぁ?