
Tubular bells III/Mike Oldfield
うむ~っ。20年後ではなくて2年後に出ていたようだ。この頃は買わない時期だからまったく世情に疎くて知らないわけ。『II』は原曲にかなり忠実にリアレンジして今風にまとめたものという内容に対して、好意的にみれば、『III』は今ならこういう風に作るけど…、という感じなのか。かの有名な楽器が変りながら同じコードを弾いていくパートもないし、「Moonlight shadow」風の曲が突然挿入されたりと、イメージをけっこう裏切ってくれます。まぁ、漸く足枷がとれたということなのだろうが、ならば敢えて『Tubular bells』という呼称を使うべきではないだろう。(#なんだなんだ、『Millenium Bells』ってのも出てんの? ネタ切れ?)
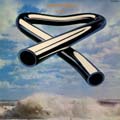
日本コロムビア
YQ-7005-VR
Tubular bells/Mike Oldfield
まとめてかたをつけてしまおう。曲のイントロフレーズの一部が映画「エクソシスト」のサウンドトラックに使われて一躍、時の人になったソロデビュー作。映画は初冬、地方都市の場末の映画館に見に行った記憶がありますが、キリスト教とは全く無縁な私には何が恐いのかさっぱりわからなかった。ちょっと気色悪いだけじゃんと(貴重な資金をつまらないものに使ってしまったなという)惨澹たる思い出だけが残ってますが、20Hzを下まわるような低周波でウーハが震えてるけど耳には聴こえない音(CDじゃわからんが)? とかチュブラー・ベルがガンガン鳴り響くところのアンサンブルには正に圧倒されました。楽曲としては全体的にとても地味で、暗鬱で安寧な部分と民俗調の鮮烈な抒情が巧く融合されて新しいかたちを作り出していると云えるだろう。個人的にはBBCかなんかのライブ映像でかつての師匠達が総出でバックアップしてるのを見て感激しました。「エクソシスト」の方は実はサブリミナル効果をかなり取り入れていた事が発覚して、最近ちょっと話題になってました。

O espirito da paz/Madredeus
「和の心(平和の精神かな)」と題された4枚目(だと思う)。ポルトガルのとても地味でローカルなトラッド。と書くとかなり語弊がありそう。そう聴くのは簡単だけどイージー・リスニングでもヒーリングでもないです。アコーディオンとか生ギターとかチェロとか使ってますが、それほど民族色が強いわけではなく、女の人の声もとても穏やかです。自分の国の言葉や音楽を正確に捉えて、安直な劣化コピーに堕せず新しいものを作り上げていく姿勢みたいなものはとても新鮮(?!)です。

Virgin
VJCP-2535
To keep from crying/Comus
ちょっと異様で、リリカルでとても美しいトラッド・ポップ。病的なほどの奇妙な陽気さと、その裏返しにべったりと貼り付いているような狂気が絶品です。ワトソン(Bobbie Watson)の予定調和をぶち壊す裏返った異様に甲高いソプラノが脳髄をギコギコ掻き毟るように不安感を煽る。初期ヴァージンの同類項、ゴングとかヘンリィ・カウにエスペラントに至るまで絡んでるんで、比較的その辺の影響もあってシニカルな内容になっていると思われる。コーマスとしては比較的音が華やかになった二作目ですが、この後は消息不明。

Vol.4/Black Sabbath
この世のものとは思えない悩ましいイントロに打ちのめされた四枚目。って、今どき誰も知らないか。トニー・アイオミがこういう形でメロディを弾いたのは初めてなのではないだろうか。すべてを語りすべてを否定する圧倒的な表現力。ヘビメタの元祖的に扱われることが多いようですが、それは後付け。まったく本質を外しているとしか思えない。基本的にはブルーズですが、アレンジの比重が高い非常に重く粘った音と、不思議なほどクリアなアコースティクの対比が勘所のような気がします。まぁ、名前通り明るくて健康的でないことは間違いない。所謂HR/HMなアルバムとしては珍しく、曲の寄せ集めでなく全体を通してきちんと聴ける(その必然性のある)完成度の高さは見事です。

Rockbottom/Robert Wyatt
車椅子の人になってしまったワイアット(Robert Wyatt)の復帰第一作です。ドラムは叩けなくなりましたがピアノも弾けるし歌も歌えるし、なんといってもすばらしい曲を作れるのが凄いところ。叩けないことによってむしろ才能が開花してしまったみたいなとこもあるかも。全編を通じて湿った冷たい底流が流れているような不思議な音です。そうそう、「Seasong」とか人の声の持つ力を再認識するようなところもあります。
「海の歌(Sea song)」
おまえはやって来るたびに違って見える
潮水に泡立つ冠毛
おまえの皮膚は月夜に柔らかく輝く
一部は魚、一部はネズミイルカ、一部は幼いマッコウクジラ
仲間に入れてくれるのかい? 遊んでくれるのかい?
冗談ではなしに、酔っ払っているおまえはすごい
とてもご機嫌な、深夜のおまえは実にいかしている
でも、朝のおまえの変わり様は理解できない
そのときはしばらくの間、笑いかけてまでくれて人間を演じてくれる
春にはまた姿が変わってしまうことはわかっている
おまえは潮間に漂うヒトデのように季節で姿を変える動物
だから次の満月が来て、その血が騒ぐまで
おまえの狂気は心地良いほどわたしにぴったりだ
おまえの狂気はわたし自身の狂気にきっちりと合う
だから、ぼくらは孤独じゃない
プロデュースはピンク・フロイドのニック・メイスン(Nick Mason)。おそらく契約上の問題でJamesとだけ表記されているドラムもメイスンと思われます。同志アルフリーダ・ベンジ(Alfreda Benge)の鉛筆画の絵もイメージを広げます。夏なのに妙にうすら寒い白っぽい日、ひんやりとした濡れた砂といつもより塩辛い潮。
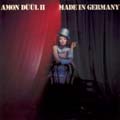
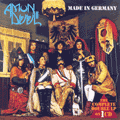
完全盤2LP→1CD
Made in Germany/Amon Düül II
混沌さが薄れてポップになった駄作と評されることが多いようですが、個人的にはとても好きなスタジオ盤8作目。リアルタイムで購入したのはアメリカ盤の廉価版シングルLP。実際の本国仕様は豪華ダブルLPだったらしい。もともとババリア風の民謡と中近東趣味が混じって、巧くはないけどサイケで混沌とした音世界を創っていましたが、これは素朴な部分が薄くてまったりと濃厚、中欧風の華麗なバロック乃至はロココ趣味にあふれた作り込んだ構成になっています。なんだか上手いんだか下手なんだかよくわからない、浮上がったキッチュな安っぽさが良いですねぇ。カーレル(Chris Karrer)の出番が少なくてちょっと残念ですが、ババリア・フォークがロックンロールになってしまう「Mr. Kraut's jinx」の荒唐無稽な展開はまさに真骨頂。

Flesh+Blood/Roxy Music
この頃になるともう何も言うことはない。完全に完成された音。とても安心して聴けるセンスの良い良質な楽曲になっている。一流ホテルのディナー・ショウで聞いても全くおかしくないような優れて洗練されたエンターテイメント。これこそがロクシィが求め登りつめた音楽だろう。前作『Manifesto』の迷いみたいな曖昧さが払拭されて、タイトで流れるように美しくも力強いメロディが燦然と煌いている。

Seven/Soft Machine
あまりにも巧過ぎて、あるいは完璧過ぎて感情移入ができない典型になってしまった七作目。ほとんどの曲をカール・ジェンキンズ(Karl Jenkins)が書いており、とてもタイトで明晰なジャズ・フュージョン。人力ループを多用した短い曲が多いのでちょっと印象が変わって、聴き易くなった部分はあります。なんだかディジタルっぽいイメージのジャケですが、今考えると意外に中身を上手く表していると思う。
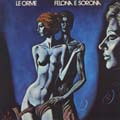
Felona e Sorona/Le Orme
不幸な星フェローナ(Felona)と幸福の星ソローナ(Sorona)の物語(逆かもしれん、織姫と牽牛みたいな話だっけかな、もう忘れたわ)。英語版が出たという意味ではオルメで最も有名な一枚。それに加え、所謂イタリア臭い部分が比較的薄いのだけれど、逆に洗練されてるともいいがたい不思議なバランスに載った作品。ちょっともたもたした部分もあるけれど、元々、テクよりも曲作りとアンサンブルで聴かせるタイプです。トータルで一曲ですが歌が意外に少なくて、オルメにしては少し冷やっこい印象はあるでしょう。トリオという最小編成ですが、メロトロン乃至はストリング・シンセの使い方がけっこう好みである。これはイタリア語バージョンのCDですが、ピーター・ハミル(Peter Hammill)による英訳の英語バージョンもあります。
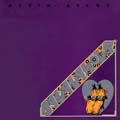
Bananamour/Kevin Ayers
バナナでチェスしても駒の区別がつかんがのぅ。(中ジャケの話)まぁ、楽しそうでなによりなにより。すばらしいアイディアとセンスが凝縮されたソロ四作目のアルバム。個人的にはエヤーズのベストといってもいいかも。様々な音が万華鏡のように華麗に変幻自在に展開されていく。楽曲も非常に凝ってはいるがそれを感じさせない構成が素晴らしい。アンダーグラウンド系のフリーク扱いされることが多いようですが、出てくる音は極めてポップで明るい。ふとしたはずみに尋常でない妙な落差を感じることはあるにしても。「Interview」ではマイク・ラトリッジ(Mike Ratledge)の18番、空間を縦横無尽に掛け巡るオルガン・ソロが聴けます。
ワンコインで購入した2003年のリマスターは英国国内盤がCDDA、EU向け盤はCCCDです。CDのスリーブはLPの裏ジャケに載っていた歌詞は割愛されているが、エヤーズにインタビューした曲目解説のテープ起こしや、没写真が満載。「Decadence」のマーレーンはニコのことだとか、「Oh! wot a dream」はシド・バレットのスタイルだとか。チェスの中写真は太平洋のどこかを航走する船の船室で撮られたそうだ。古いマホガニーがふんだんに使われ、どこに向かってるのかは知らない……もっとシャンペン持って来い! って言っておりますが真偽のほどは不詳。
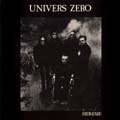
Hérésie/Univers Zéro
現代の『異端』は中世の異端審問官とは異なり「無」を背負ってるらしい。弦楽四重奏の低音側の楽器をベースとパーカッションに置き換えたような構成でひたすら攻めて来るユニヴェール・ゼロ二作目。前作『1313』の現代音楽に若干リズム感が加味されて、壮絶なまでの暗黒が溢れんばかりになみなみと注がれた無限の容器から、今まさにそのエッジを越えようとする刹那感と緊張感がない交ぜになって、黒くて冷たい塊のようなものが喉を塞いで息も吐けないような悪寒が忍び寄る。人相悪いし、寒そうだし、湿地みたいだし、そんなところに車椅子でやって来て写真撮るなよ、と云いたくなる辛気臭さ。同じチェンバー・ミュージックのアール・ゾワに見られる素っ頓狂で躁な部分もないので、かなり強迫で重量級。暗黒です。

B-sides・Seasides & freerides/Ocean colour scene
突然、全然毛色が違って浮き上がりそうですが、ネオ・アコースティックというのだろうか。トラッド風弾き語りにビートルズ風(カバーもしてるし)と、いろいろありますが内容はけっこう辛辣なようだ。今風のアレンジとアコースティックなとても暖かみのある音と、とてもメロディアスで内省的な歌が印象的です。タイトルからするとシングルのB面集とミニアルバムのカップリングなのだろうか。ロック色の強いアルバムに比べるとメロディが儚くも美しい。

津軽三味線・高橋竹山の世界/高橋竹山
生い立ちとかはあちこちで書かれているから詳しくはそちらを参照してもらえば良いとしても、境遇やそれをもたらした風土は今からは想像もつかないものだったのでしょう。和楽器というものもすっかり馴染みのないものになってしまいましたが、これは学校教育の所為だろう。大昔の経験を今に援用できるかどうかは疑問だが、少なくとも三味線に初めて触ったのは高校生のときでした。三味線の奏法? を如何に革新したのかは不勉強でわかりませんが、歌無しの独奏が極めて珍しいのは確かなことだろう。歌が入るとバック(!)の演奏の音量が小さくなるのが極めて一般的なこの国の音楽の姿だから。

Chromium echoes/Neuronium
スペインのシンセ・アンサンブル、ニューロニウムの五作目。カタルーニャ人、ミケール・ウィゲン(Michel Huygen)を中心とするユニットで77年アルバム・デビュー。今作はヘビメタ風のダサいロゴとやっぱりスペインなセンスの欠片も感じられない田舎臭いデザインでちょっと気後れしそうですが、なんのなんの、音の方は聴いてびっくり“およよ”ってところです。後半の厭世的で人工的なボーカルが入るところなぞ、震えが立つほど格好良い。この頃は二人組のようですが、比較的湿っぽいセンチメンタルなメロディが日本人好みでしょう。タンジェリン・ドリーム(Tangerine Dream)あたりの影響はかなりありそうですが、それに比して遥かに南国的で情緒的。こういう方向性もそれなりに面白いと思う。

Polydor/EG
2302 071
Before and after science/Brian Eno
すっかり現代音楽の大御所になってしまったイーノですが、ロクシィを辞めてソロになって四作目ぐらいのソロアルバム。ちょうどドイツでハルモニア、クラスターあたりと盛んにコラボレイトしている頃で、その成果が早速取り入れられていることがわかります。タイトルの“以前・以後”というのは音楽的な性質を表わしているのだろうか。前半は主として以前の陽気なボーカルポップ、後半は明らかに質感と肌触りが変わって黄昏た儚さが全開のアンビエント。気持ちの良さに卒倒しそうだ。
「14枚の絵」という副題が付いたこのアルバムは10曲と4枚の水彩画(本当にカバーに入って添付されている)で構成されている。見た目も含めたちょっと感覚的に奇矯なところ、その乾いた明るさみたいな部分がイーノの特徴ですが、音階がズレてるような、もう少しで届きそうで届かないもどかしさみたいなものを感じさせてくれる。その奇矯さはやがてアンビエントな空気感へ遷移していくわけですが、Win95のデフォルトの起動音とかも作っていました。